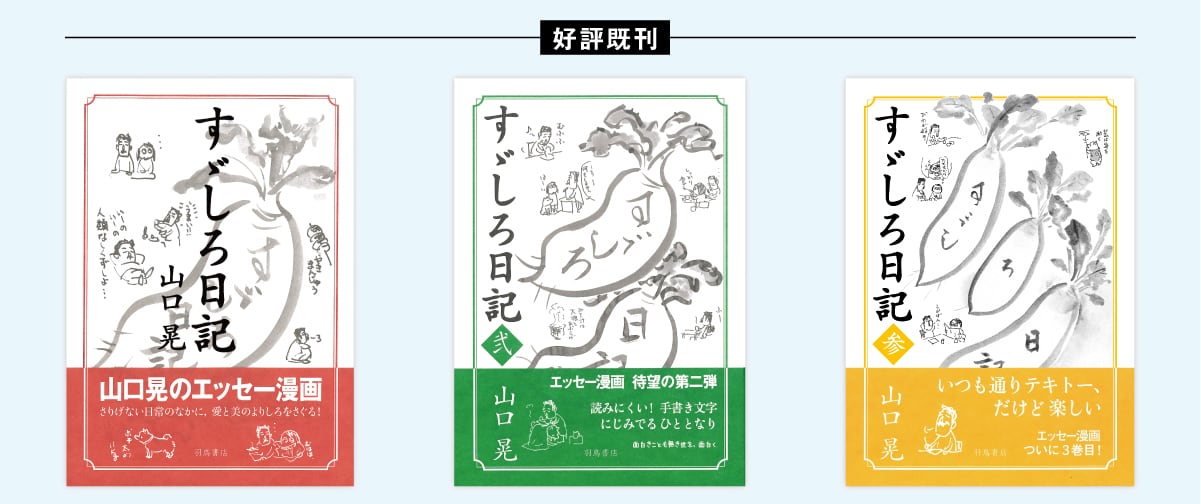NEWS
◉パブリシティ情報
高田宏臣さん(一社 地球守・有機土木協会代表理事、安房大神宮の森コモンプロジェクト主宰)を1年取材した番組が放送されます。
NHK Eテレ『こころの時代』 「地面の下に宇宙があった 自然再生家・高田宏臣」
2026年2月14日(土)午後1時~2時
*1週間、NHKプラスでネット配信。
*本放送2/8の予定がオリンピック中継により延期となりました。
TOPICS
BOOKS
-


有機土木ライブラリー 1『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 高田宏臣・小倉沙央里[著]
¥2,200
◉全国送料無料 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A4判(横組)・並製・56頁 ISBN 978-4-904702-93-2 C2051 本体価格2,000円+税 発行:地球守・有機土木協会 発売:羽鳥書店 印刷・製本:大日本法令印刷 本文デザイン:羽鳥書店 表紙デザイン:村上亜沙美 *英訳併記、オールカラー、図版40点 ▼概要 一般社団法人地球守・有機土木協会が発行するシリーズ「有機土木ライブラリー」の第1弾。2025年6月に、代表理事・高田宏臣と、協会のフェローであり世界の伝統知の研究者である小倉沙央里(マサチューセッツ大学アマースト校ポスドク研究員)が共同発表した国際コモンズ学会カンファレンスでの報告を書籍化したもの。 房総半島最南端の「安房大神宮の森」をもとに、地域の環境上の要となる場所がどのように守られ、これからどのように守りつないでいく必要があるか、土中環境の視点と有機土木の技と知恵を紹介する。 森と海の関係、御神体としての磐座の意義、山の尾根筋から水源をとる仕組み等、古の人の造作や工夫を知り、コモンズ(共有財産)をつなぐ方法を探る。平易な語りに英訳を併記、オールカラー、図版40点。 ▼目次 はじめに 安房大神宮の森──先祖代々受け継がれてきた神聖な場所 太平洋に面した半島先端──人びとや文化の交流地点 土地の豊かさをもたらす海と森──暖流と寒流が交わる地 山の中の巨石「磐座」──豊かな山や森を護る御神体 先人たちが守り育ててきた水の源、いのちの源としての大神宮の森──山の上に水源をつくる智恵 現代の土木と先人たちのかつての土木──土地を潤し、いのちを養う水への視点の違いから 伝統技術に基づいた有機土木──自然の素材(有機物)を利用する 有機土木の実践──かつての視点を現代の土木に活かしてゆく 大神宮の森から学ぶ古の技──コモンズを再生し未来へ渡す あとがき ▼著者紹介 高田宏臣(たかだ ひろおみ) 1969年生まれ。株式会社高田造園設計事務所代表取締役、一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事。東京農工大学農学部林学科卒業。国内外での造園・土木設計施工ののち、現在は土中環境の健全化、水と空気の健全な循環の視点から住宅地、里山、奥山、保安林などの環境改善と再生の手法を提案、指導する。大地の通気浸透性に配慮した伝統的な暮らしの知恵や土木造作の意義を広める活動を各地で行っている。著書に、『これからの雑木の庭』、『土中環境──忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』、『よく分かる土中環境』など。 小倉沙央里 (おぐら さおり) 米マサチューセッツ大学アマースト校のNSF Center for Braiding Indigenous Knowledges and Scienceにおいてポスドク研究員、及び、東北大学 統合日本学センター客員助教。学習院⼤学法学部卒業。米レズリー⼤学⼤学院、カリフォルニア⼤学バークレー校環境デザイン⼤学院終了(修⼠)。ブリティッシュ・コロンビア⼤学(カナダ)にて博⼠号取得。ニコンサロン写真選にて三⽊淳賞奨励賞受賞(2017年)。 2011年より、自然と共生した伝統的な知恵を世界各地の先住民や地域の人々から学ぶ。研究者として、伝統知を次世代につなぐ活動を行うと共に、アートを通して研究からの学びを広く共有し、対話の場を創出している。また、2023年に世界各地で在来作物の種と知恵を守っている人々を繋ぐプロジェクト、Growing Millet Together! を立ち上げ、伝統知と雑穀栽培を未来に繋ぐ活動を行っている。 ▼発行元 一般社団法人 地球守・有機土木協会 https://organiccivilengineering.org/ 2024年設立。代表理事・高田宏臣。有機土木とは、土地環境を傷めずに安定させてきた、伝統的な民間土木の知恵を継承し、自然の自律的な働きと調和するインフラを構築する視点と工法。現代土木の抱えている多くの問題を解決する工法として、社会への周知、職業としての確立、普及・啓発を目指す団体。 ▼関連書籍 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]『大神宮の森へ 1 』2025秋冬 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 『大神宮の森へ 1 』と創刊セット販売【送料無料】 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122336294 ---------------------------------------------- Reviving the Commons in Japan: Restoring the land-human relationship for a climate-resilient future Hiroomi Takada, Saori Ogura Organic Civil Engineering Assosiation (Foreward) This publication is based on the presentation titled: “Reviving the Commons in Japan: Restoring land-human relationship for climate-resilient future”, presented at the International Association of the Study of the Commons Conference (IASC 2025), hosted by the International Association of the Study of the Commons, at the University of Massachusetts, Amherst, U.S.A., on 16 June 2025, co-presented by Hiroomi Takada (online) and Saori Ogura (in-person). Captions and partial editorial revisions have been added for publishing this work from the original transcript. Hiroomi Takada: Founder & Director of the Organic Civil Engineering Association Founder & Director of Takada Zouen Sekkei Jimusho [Takada Landscape and Construction Company] Saori Ogura: A Transdisciplinary scholar on Traditional Ecological Knowledge Research fellow at the Organic Civil Engineering Association Postdoctoral Research Associate at the NSF Center for Indigenous Knowledges and Science, University of Massachusetts, Amherst Visiting Assistant Professor at the Center for Integrated Japanese Studies, Tohoku University
MORE -


■地球守・有機土木協会会員限定 10冊以上購入割引■ 有機土木ライブラリー 1『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 高田宏臣・小倉沙央里[著]
¥17,600
【注意事項】 ・地球守・有機土木協会会員(NPO法人地球守も含めた、正会員・賛助会員・メーリングリスト登録会員)限定の割引販売ページです。 ・ご注文の際は、登録のメールアドレスをお使いください。 ・10冊以上購入で20%OFFとなるセット販売です(送料無料)。 ・10冊1セット(税込17,600円)に、オプションで端数を追加して購入冊数を調整してください。 ・50冊以上購入の場合は25%OFFとしますので、希望の方は問合せよりご連絡ください。 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A4判(横組)・並製・56頁 ISBN 978-4-904702-93-2 C2051 本体価格2,000円+税 発行:地球守・有機土木協会 発売:羽鳥書店 印刷・製本:大日本法令印刷 本文デザイン:羽鳥書店 表紙デザイン:村上亜沙美 *日英併記、オールカラー、図版40点 ▼概要 一般社団法人地球守・有機土木協会が発行するシリーズ「有機土木ライブラリー」の第1弾。2025年6月に、代表理事・高田宏臣と、協会のフェローであり世界の伝統知の研究者である小倉沙央里(マサチューセッツ大学アマースト校ポスドク研究員)が共同発表した国際コモンズ学会カンファレンスでの報告を書籍化したもの。 房総半島最南端の「安房大神宮の森」をもとに、地域の環境上の要となる場所がどのように守られ、これからどのように守りつないでいく必要があるか、土中環境の視点と有機土木の技と知恵を紹介する。 森と海の関係、御神体としての磐座の意義、山の尾根筋から水源をとる仕組み等、古の人の造作や工夫を知り、コモンズ(共有財産)をつなぐ方法を探る。平易な語りに英訳を併記、オールカラー、図版40点。 ▼目次 はじめに 安房大神宮の森──先祖代々受け継がれてきた神聖な場所 太平洋に面した半島先端──人びとや文化の交流地点 土地の豊かさをもたらす海と森──暖流と寒流が交わる地 山の中の巨石「磐座」──豊かな山や森を護る御神体 先人たちが守り育ててきた水の源、いのちの源としての大神宮の森──山の上に水源をつくる智恵 現代の土木と先人たちのかつての土木──土地を潤し、いのちを養う水への視点の違いから 伝統技術に基づいた有機土木──自然の素材(有機物)を利用する 有機土木の実践──かつての視点を現代の土木に活かしてゆく 大神宮の森から学ぶ古の技──コモンズを再生し未来へ渡す あとがき ▼著者紹介 高田宏臣(たかだ ひろおみ) 1969年生まれ。株式会社高田造園設計事務所代表取締役、一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事。東京農工大学農学部林学科卒業。国内外での造園・土木設計施工ののち、現在は土中環境の健全化、水と空気の健全な循環の視点から住宅地、里山、奥山、保安林などの環境改善と再生の手法を提案、指導する。大地の通気浸透性に配慮した伝統的な暮らしの知恵や土木造作の意義を広める活動を各地で行っている。著書に、『これからの雑木の庭』、『土中環境──忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』、『よく分かる土中環境』など。 小倉沙央里 (おぐら さおり) 米マサチューセッツ大学アマースト校のNSF Center for Braiding Indigenous Knowledges and Scienceにおいてポスドク研究員、及び、東北大学 統合日本学センター客員助教。学習院⼤学法学部卒業。米レズリー⼤学⼤学院、カリフォルニア⼤学バークレー校環境デザイン⼤学院終了(修⼠)。ブリティッシュ・コロンビア⼤学(カナダ)にて博⼠号取得。ニコンサロン写真選にて三⽊淳賞奨励賞受賞(2017年)。 2011年より、自然と共生した伝統的な知恵を世界各地の先住民や地域の人々から学ぶ。研究者として、伝統知を次世代につなぐ活動を行うと共に、アートを通して研究からの学びを広く共有し、対話の場を創出している。また、2023年に世界各地で在来作物の種と知恵を守っている人々を繋ぐプロジェクト、Growing Millet Together! を立ち上げ、伝統知と雑穀栽培を未来に繋ぐ活動を行っている。 ▼発行元 一般社団法人 地球守・有機土木協会 https://organiccivilengineering.org/ 2024年設立。代表理事・高田宏臣。有機土木とは、土地環境を傷めずに安定させてきた、伝統的な民間土木の知恵を継承し、自然の自律的な働きと調和するインフラを構築する視点と工法。現代土木の抱えている多くの問題を解決する工法として、社会への周知、職業としての確立、普及・啓発を目指す団体。 ▼関連書籍 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]『大神宮の森へ 1 』2025秋冬 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 ---------------------------------------------- Reviving the Commons in Japan: Restoring the land-human relationship for a climate-resilient future Hiroomi Takada, Saori Ogura Organic Civil Engineering Assosiation (Foreward) This publication is based on the presentation titled: “Reviving the Commons in Japan: Restoring land-human relationship for climate-resilient future”, presented at the International Association of the Study of the Commons Conference (IASC 2025), hosted by the International Association of the Study of the Commons, at the University of Massachusetts, Amherst, U.S.A., on 16 June 2025, co-presented by Hiroomi Takada (online) and Saori Ogura (in-person). Captions and partial editorial revisions have been added for publishing this work from the original transcript. Hiroomi Takada: Founder & Director of the Organic Civil Engineering Association Founder & Director of Takada Zouen Sekkei Jimusho [Takada Landscape and Construction Company] Saori Ogura: A Transdisciplinary scholar on Traditional Ecological Knowledge Research fellow at the Organic Civil Engineering Association Postdoctoral Research Associate at the NSF Center for Indigenous Knowledges and Science, University of Massachusetts, Amherst Visiting Assistant Professor at the Center for Integrated Japanese Studies, Tohoku University
MORE -


『大神宮の森へ 1 』 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]
¥2,750
土地に根ざした暮らしのための雑誌 [2025年秋冬]創刊第1号(年2回発行) ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A5判(縦組)・並製・168頁(カラー) ISBN 978-4-904702-94-9 C0051 本体価格2,500円+税 印刷・製本:大日本法令印刷 ブックデザイン:村上亜沙美 *本体価格の内1,000円は安房大神宮の森コモンプロジェクトの活動支援に充てられます。 ★地球守・有機土木協会の会員には機関誌として1冊進呈 ★『大神宮の森へ』Instagram公式アカウント @daijingu_forest_magazine ▼概要 房総半島最南端にある55haの「安房大神宮の森」を整備し再生する活動の紹介を柱とし、さまざまな分野の執筆者による多彩な文章を収録。古の人の営みの知恵を知り、森や海、土や木や水とともに生きる楽しさと面白さを発掘する。 一般社団法人地球守・有機土木協会(代表理事・高田宏臣)の広報誌も兼ね、地域の環境上の要となる場所(コモンズ)の守り方や、継いでいくために大事な「土中環境」の視点と、具体的な方法である「有機土木」も紹介する。 ▼内容構成 以下の5つの章より構成。 安房大神宮の森の整備活動のことや古の暮らしの名残や技の発見、森の未来像を長期的に紹介する「安房大神宮の森へ」、森を介してさまざまな人と場所とをつないでいく「焚き火をかこんで」、土中環境の視点と有機土木の活動とそこから広がる多様なテーマを伝える「生きものとしての土木」、土中環境の視点を通して目に留まった書物から文章を紹介する「書を捨てよ森へゆこう」、房総半島南端の人々の声を聞く「半島の海街から」。 ▼目次 有機土木と「安房大神宮の森コモンプロジェクト」 高田宏臣 安房大神宮の森へ 安房大神宮の森コモンプロジェクトの歩み1 房総半島最南端の森──整備の始動と縄文小屋づくり 高田宏臣 [コラム]沖ノ島の台風被害 〈大神宮の森〉と「生きものとしての土木」 中村桂子 小川誠さんの「稲の多年草化栽培」 高田宏臣 安房の歴史と〈大神宮の森〉 愛沢伸雄 館山まるごと博物館1 逆さ地図の視点で地域を見てみよう 池田恵美子 [コラム]布良という聖地──画家に愛された神話の漁村 池田恵美子 焚き火をかこんで コモンズは人間だけがメンバーではない 中島岳志 ことばの森1 こんもり 佐藤良明 風景から人へ、人から風景へ 小森はるか 想像力 鴻池朋子 生きものとしての土木 土中環境から見た「土葬」 高田宏臣 うんこも死体も土に還そう──有機物を循環させる 伊沢正名×高田宏臣 山岳エリア大規模工事のリスクと潜在水脈の重要性 ──長崎県の高規格道路計画における「土中環境」調査より 高田宏臣 書を捨てよ森にゆこう 書物からの引用アンソロジー マザーツリーからウミガメまで 半島の海街から アルカディアに住む 込山敏郎 [コラム]房州のヒト・コト・モノ1 沖箱 前田宣明 房州に根ざして枝葉を伸ばす1 「きすがうら」のこと──小泉丹と滴水居 前田宣明 [コラム]布良のウミガメ ▼編者紹介 安房大神宮の森コモンプロジェクト 房総半島最南端に位置する55haの「安房大神宮の森」を整備し再生する活動を進めるプロジェクト(2024年発足)。森をコモンズ(共有財産)として未来につないでいくことを目的としている。土中環境の視点から自然を傷めない伝統的な工法を使う「有機土木」を提唱し実践する高田宏臣(一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事)が主宰をつとめ、協会や高田造園設計事務所のスタッフをはじめ、地域の内外から多くの協力者が参加し、推進している。サポーターの一員である羽鳥書店編集部の矢吹有鼓が雑誌編集人を担当。 ▼緒言より 太平洋に張り出した千葉県の房総半島最南端、安房国一の宮である安房神社の周辺は古くは大神宮村と呼び、そして今でも館山市大神宮という地名で呼ばれています。2023年末、大神宮の約55ヘクタールの山域を、私は仲間とともに融資を受けて取得しました。奇跡的に一人の所有者によって守られてきた土地が手放され、誰の手にわたるか知れない状態だったのです。大神宮一帯は起伏豊かな森に覆われており、この山域を私たちはいつしか「安房大神宮の森」と呼ぶようになりました。 安房大神宮の森はもともとは安房神社の御神域です。この森は、地域の大切な水源であり、川や海にいたる豊かさの源であり、安房神社に関係する方々を起源として、子孫代々が暮らし、守ってきた山域でした。近年は人の手が入らず台風で荒れたままの状態でしたが、数千年にわたる営みは、山中に埋もれた古道や水路堀や田畑の痕跡、土葬墓跡などから推しはかることができます。 豊かな命の営みを支え続けてきた大神宮の森を守り、未来につなぎたい。そんな思いでこの広大な土地を購入しました。「購入」したと言えども、私たちにはこの土地を「自分たちのものとして所有する」という考えは全くありません。「いっときだけ預かり、育み、そして未来に手渡す」ために、土地取得と同時にこうした環境上大切な地を守りつなぐための新たなコモンの仕組みを模索するべく、「安房大神宮の森コモンプロジェクト」を立ち上げました。(...) ──「有機土木と「安房大神宮の森コモンプロジェクト」」(高田宏臣/一般社団法人 地球守・有機土木協会代表理事) ▼関連書籍 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122335317 有機土木ライブラリー 1 と創刊セット販売【送料無料】 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122336294
MORE -


『大神宮の森へ 1 』+ 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』セット
¥4,950
創刊2冊をセットでご購入いただけます【送料無料】 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き 『大神宮の森へ 1 』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122335317
MORE -


山口晃『すゞしろ日記 四』
¥3,960
B5判 並製 184頁(カラー24頁) 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-92-5 C1071 2025年7月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画第4弾。約7年ぶりとなる4巻目刊行。「UP版すゞしろ日記」をたっぷりといつもの1.5倍にあたる76回分(151~225回+番外編)、「やがて悲しき私的ラジオ生活」(初出『BRUTUS』)、「START はじまり~」(初出『UOMO』)の他、東京パラリンピック公式アートポスター《馬からやヲ射る》原画、ポスターについて綴った作品《当世 壁の落書き 五輪パラ輪》も全編収録し、ボリューム満点の1冊に。 ▼目次 端書き I すゞしろ日記風 やがて悲しき 私的ラジオ生活 当世 壁の落書き 五輪パラ輪 馬からやヲ射る START はじまり~ II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第151回~第225回 あとがき 収録作品一覧 ▼プロフィール 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2018年「Resonating Surfaces」(Daiwa Foun- dation Japan House Gallery、ロンドン)の後、横浜能楽堂、ZENBI-鍵善良房(京都)で個展、2023年にはアーティゾン美術館(東京)で「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」展が開かれた。パブリックアートも多数手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。2019年、NHK大河ドラマ「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」のオープニングタイトルバック画を担当、東京2020パラリンピック公式アートポスターを制作するなど、ますます意欲的な創作活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 『すゞしろ日記 参』(羽鳥書店、2018年) 『山口晃 親鸞 全挿画集』(青幻舎、2019年) 『CHRONIQUES D’UN JAPON MERVEILLEUX』 (Les Éditions de la Cerise、フランス、2023年) 『趣都』(講談社、2025年、近刊) 2025年7月7日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行
MORE -
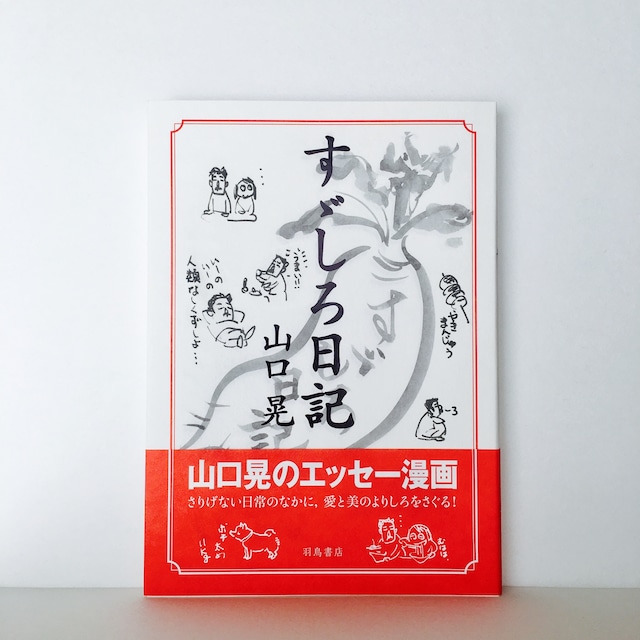
山口晃『すゞしろ日記』
¥3,300
★2025年7月の重版分から価格を以下のように改定させていただきます。 本体2,500円→本体3,000円 B5判 並製 160頁 本体価格 3,000円+税 ISBN 978-4-904702-00-0 C1071 2009年7月刊行 ブックデザイン 佐々木由美・岩橋香月(タウハウス) 印刷 サンエムカラー 製本 新生製本 ▼書評・記事 『朝日新聞』2009年8月30日 「人気画家の“うまい”マンガ」[評者]南信長(マンガ解説者) http://book.asahi.com/comic/TKY200909020204.html 『毎日新聞』2009年9月1日(夕刊)「人気画家が漫画エッセー」岸桂子 『読売新聞』2009年9月13日 編集T氏 『神戸新聞』2009年9月27日 「後悔、反省、居直りの日々」文化生活部・新開真理 『公明新聞』2009年10月12日 「注目の出版社から”現代の絵師”の日記」」編集者・小島直樹 〈紹介ブログ〉 弐代目・青い日記帳 ~山口晃「すゞしろ日記」 http://bluediary2.jugem.jp/?eid=1830 フクヘン。 ~山口晃『すゞしろ日記』羽鳥書店刊 http://fukuhen.lammfromm.jp/?p=973 白 の 余 白 ~「すゞしろ日記」山口 晃 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ Zkarohisia bakana Y. ~時折発症するマジメな文体病 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ ▼概要 山口晃のエッセー漫画 月に1度の楽しみがついにまとめて読める。東京大学出版会PR誌『UP』に好評連載中の「UP版すゞしろ日記」の第1回~第50回までを収録。元祖すゞしろ日記〈描き下ろし解説付〉をはじめ、各バージョン──美術手帖版・プリンツ21版・OH!ヤマザキ版・さて、大山崎版──のすゞしろ日記が大集合。白州探訪乃記、アトリエ探訪/仕事場リアル探訪、私的ラジオ生活、大相撲観戦乃記、藝術カフェー乃圖、モーニング25周年表紙原画など、カラー作品も多数おさめる。斗米庵双六には、オリジナル駒とサイコロのおまけ付。 [目次] 端書き Ⅰ 元祖すゞしろ日記 すゞしろ日記 斗米庵双六 ザッツマイウェー すゞしろ日記洋行編 元祖すゞしろ日記 解説 元祖すゞしろ日記洋行編 解説 白州探訪乃記 当世絵かき気質(とうせいえかきかたぎ) 仕事場リアル探訪 アトリエ探訪 美術手帖版すゞしろ日記──光悦についてかけってゆーからかくけど、詳しくないから知らないわよーの巻 仏像の歴史──ブルータス「仏像特集」の為の描きおろし 仏教公伝/慶派台頭 私的ラジオ生活 プリンツ21版すゞしろ日記 Ⅱ UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第1回~第50回 ラグランジュポイント Ⅲ すゞしろ日記大山崎編プラス OH!ヤマザキ版すゞしろ日記 さて、大山崎版すゞしろ日記 人に会う/人と会う2/自転車隊がゆく/鬼くすべ/勝手に大山崎 大相撲観戦乃記──和樂 大相撲特集の為の原画 蕭白エピソード集──藝術新潮 蕭白特集の為の原画 乞食、梅をほころばすの事/蕭白 虹をかけるの事 御使僧 追い返されるの事/探幽ときいてたちたるムカッ腹の事 藝術カフェー乃圖 モーニング25周年表紙原画 作品一覧/作家略歴 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ、群馬県桐生市育ち。1996年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。 会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、個展「山口晃展 今度は武者絵だ!」(練馬区立美術館)。2008年12月から2009年3月にかけては、関西初となる個展「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を開催。近年、活動の幅は多岐にわたり、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線「西早稲田駅」のパブリックアートや、読売新聞ドナルド・キーン著「私と20世紀のクロニクル」の挿絵、三浦しをん著『風が強く吹いている』の装画(単行本・文庫)につづき、2008年9月から始まった五木寛之氏による新聞小説「親鸞」(東京新聞、中日新聞、京都新聞など全国の主要26紙にて連載)でも挿画を担当するなど、幅広い制作活動を展開中。 [作品集] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009) ▼関連書籍 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行
MORE -
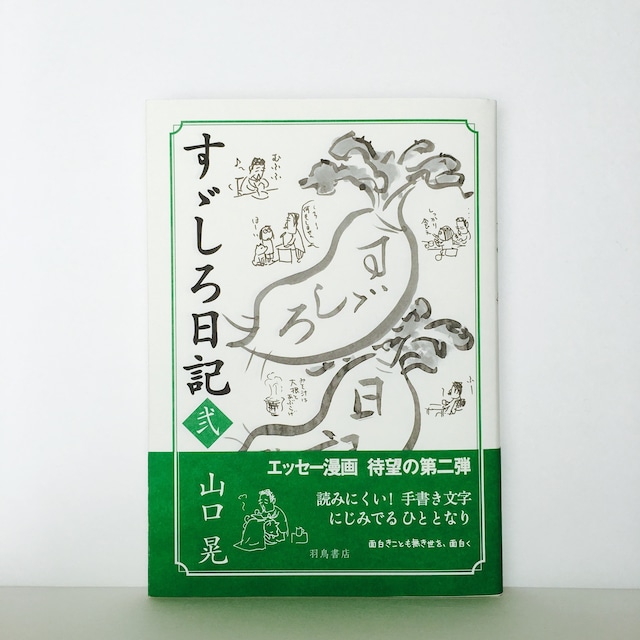
山口晃『すゞしろ日記 弐』
¥2,420
B5判 並製 136頁(カラー24頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-43-7 C1071 2013年11月刊行 著者自装 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『読売新聞』2014年1月12日書評 「一話完結全五十回、読めばスカッと憂さも晴れる!(中略)山口晃画伯の“エッセー漫画”が、面白すぎて困ります。(中略)とまあ手放しで絶賛してしまうわけだが、きっとこれも画伯のお人柄のなせるわざに違いありません」(評・平松洋子/エッセイスト) 『すこやか健保』2014年2月号 『美術手帖』2014年3月号 ▼概要 エッセー漫画 待望の第二弾 面白きことも無き世を、面白く! 画家・山口晃の“どーでもいいけど楽しげなこと”満載 各地での個展開催、小林秀雄賞受賞とますます大活躍の画家・山口晃のエッセー漫画第2弾。「UP版すゞしろ日記」第51~100回を中心に、各バージョンもたっぷり。「美術の窓版すゞしろ日記」(美術の窓)、「冷泉 家の起こり」(芸術新潮)、「当世養生訓」「当世夫婦道行」「当世おくの細道」「青春物忘れ」「当世胸算用」(文藝春秋SPECIAL)、「当世お伊勢参り」(産経新聞)、「セザンヌ紀行」(BRUTUS)、「美術手帖版すゞしろ日記②」(美術手帖)、「私的 谷根千マップ」(和楽)、「スターウォーズ 帝国兵半生之記」(朝日新聞)を収録。カラー原画はカラーで再現。 [目次] I すゞしろ日記風 美術の窓版すゞしろ日記 或る日の駄洒落──浮かんじゃったものはしょーがない 冷泉 家の起こり 当世養生訓 お気楽養生/腰はたいせつ/雲古あれこれ… 当世夫婦道行(めをとのみちゆき) 当世胸算用──凡夫死ヲ想フ 当世おくの細道──歌枕 さがしあぐねて 草まくら の巻 青春物忘れ セザンヌ紀行──エクスアンプロヴァンス 行くさ!プロざんす 美術手帖版すゞしろ日記②──利休翁2枚の肖像画のこと 当世お伊勢参り 花より団子/夏越の大祓 私的 谷根千マップ スターウォーズ 帝国兵半生之記 II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第51回~第100回 作品一覧 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、2008年には関西初となる「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を催し、以降、各地で展覧会が開かれている。2012年、メゾンエルメス銀座「望郷 TOKIORE(I)MIX」展。同年11月には平等院養林庵書院に襖絵を奉納し、特別公開された。2013年、地元群馬の県立館林美術館で、「山口晃展 画業ほぼ総──お絵描きから現在まで」を開催。近年、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線のパブリックアートなどを手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年に刊行した『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。ますます意欲的な創作活動を展開中。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 2013年11月30日 初版 2013年12月20日 第2刷 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行
MORE -
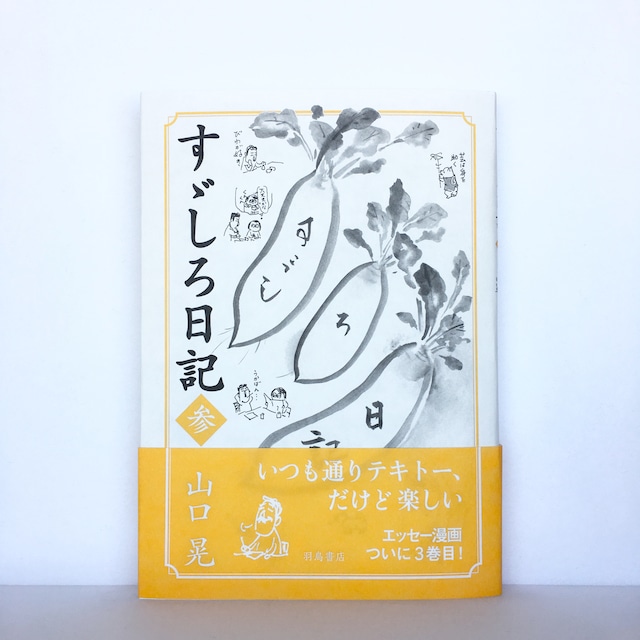
山口晃『すゞしろ日記 参』
¥2,530
B5判 並製 152頁(カラー24頁) 本体価格 2,300円+税 ISBN 978-4-904702-69-7 C1071 2018年2月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2018年3月18日書評 「(前略)帯の売り文句に「エッセー漫画」とあるけれど、むしろ音楽で言うラップとDJの掛け合いが近い。手書きの譜面と言ってもいい。実験精神に寄せて言えばさしずめ図形楽譜か。(後略)」(評・椹木野衣/美術批評家) 『銀座百点』2018年5月号 「大根もすゞしろと書けば印象は違う。本書も味気ない日常を賑やかす絵日記。」「飄々として狷介とは真逆の人柄。展覧会も押すな押すなの盛況だ。性は清白(すゞしろ)、客はすゞなり。」(評・伊藤豊/銀座 教文館) 『月刊アートコレクターズ』2018年3月号 BOOK GUIDE 『北日本新聞』2018年4月1日「県内書店 注目のコミック」 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画、第三弾。連載12年を超えた「UP版すゞしろ日記」第101〜150回を中心に、すゞしろ日記風作品を収録。日々の““どーでもいいけど楽しげなこと”を、まるごと一冊に。 【収録作品】「 UP版すゞしろ日記」第101~150回(『UP』)、「当卋 銀座探訪」(『銀座百点』)、「暁斎絵日記風」(『美術手帖』)、「今月の野菜」(NHK 趣味の園芸『やさいの時間』)、「ラヂオの現場 見学記」「私的 愛しのスターウォーズ」「それ行け! オランジュリー パリー美術紀行」(『BRUTUS』)、「姫路城 見学記 ただ今工事中」(『婦人画報』)、「ワンだふるアートワールド」(『SPUR』)。 [目次] 端書き I すゞしろ日記風 当世 銀座探訪 暁斎絵日記風 やさいの時間 ラヂオの現場 見学記 それ行け! オランジュリー パリー美術紀行 姫路城 見学記 ただ今工事中 ワンだふるアートワールド 私的 愛しのスターウォーズ II UP版すゞしろ日記 101〜150回 ▼プロフィール 山口晃(やまぐちあきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2011年「Bye Bye Kitty!!!展」(ジャパンソサエティ、NY)、2012年「望郷TOKIORE(I)MIX展」(銀座メゾンエルメス)。2012年から13年にかけて「山口晃展」が3都市を巡回し、地元群馬の県立館林美術館で「山口晃展 画業ほぼ総覧─お絵描きから現在まで」が開催される。2015年から16年にかけては、水戸芸術館現代美術ギャラリー、霧島アートの森、馬の博物館、愛媛県道後地区、ミヅマアートギャラリーで個展が相次いで開かれた。成田国際空港、副都心線西早稲田駅や大分駅のパブリックアート、山梨県富士山世界遺産センターのシンボル絵画を手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年刊行の『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。2017年には群馬県桐生市初の藝術大使に就任し、ますます意欲的な活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 2018年2月5日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行
MORE -

鴻池朋子『メディシン・インフラ・マップ』(委託販売品)
¥1,650
★青森県立美術館で2024年7月13日~9月29日に行われた「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」カタログ。 本体価格1,500円+税 仕様:両面フルカラー印刷、16折加工 サイズ:w985 x h600 mm(広げたサイズ) w110 x h224mm(折りたたんだサイズ) 編集:鴻池朋子 執筆:鴻池朋子、奥脇嵩大(青森県立美術館学芸員) デザイン:小川順子 発行:青森県立美術館(鴻池朋子展実行委員会)2024年9月30日 ▶︎概要 「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」の記録であり、同時進行して美術館外部、東北を中心に各地で展開中の鴻池のプロジェクトの数々を、ポケットサイズにドキュメントとしてまとめたもの。アートを通して同時代を生きのび、旅する人々のための地図であり、新たな記録の持ち方として提案された、軽く折りたたまれた美術館の記憶装置。 文章、図版多数収録。ある程度の耐水仕様。 (青森県立美術館ミュージアムショップの紹介文より一部引用) ▶︎鴻池朋子展 メディシン・インフラ https://www.aomori-museum.jp/schedule/13464/
MORE -
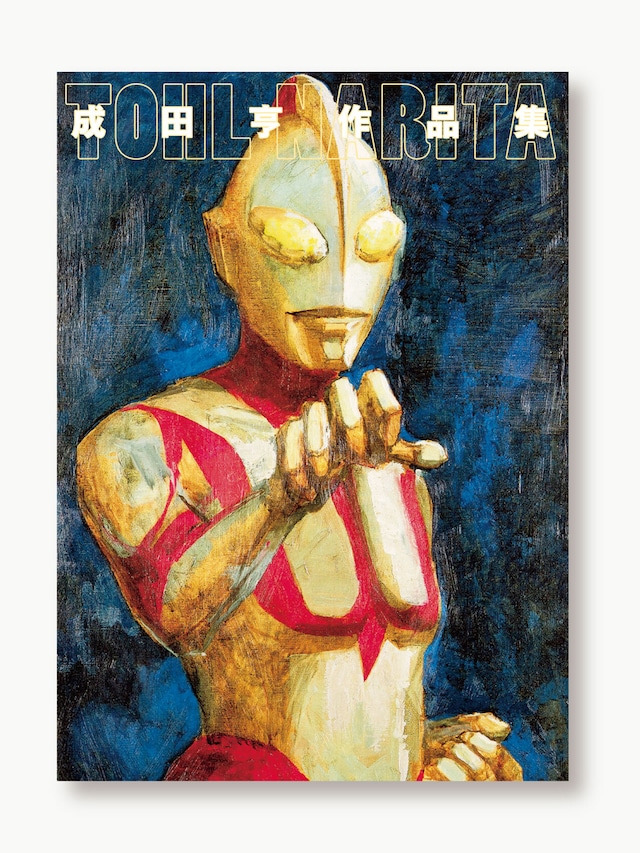
成田亨『成田亨作品集』
¥8,800
決定版作品集 ★当サイトでご購入の方には、特典「ヒューマンサイン[復刻版]」をお付けします。 「ヒューマンサイン[復刻版]」は「成田亨 美術/特撮/怪獣」展(2014年)開催時に会場での購入特典として作成したものです。 B5判変型 並製 400頁(カラー312頁) 本体価格 8,000円+税 ISBN 978-4-904702-46-8 C1071 2014年7月刊行 装丁・デザイン 大西隆介(direction Q) レイアウト 山口潤(direction Q) *2021年の重版に伴い、本体価格5000円から8000円に改訂、カバー帯を新装 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣 2014年7月19日 初版 2014年9月10日 第2刷 2021年8月9日 第3刷 ▼『成田亨作品集』 is available for purchase in the United States, Singapore, Thailand, and Taiwan. For more information, please access the links below. ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF AMERICA CO.,LTD. Email: [email protected] https://usa.kinokuniya.com/stores-kinokuniya ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF SINGAPORE PTE. LTD. https://kinokuniya.com.sg/stores/ Enquiry: https://kinokuniya.com.sg/corporate-information/feedback/ ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF (Thailand) CO., LTD. Email: [email protected] https://thailand.kinokuniya.com/store ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF TAIWAN CO, LTD. Email: [email protected] https://www.kinokuniya.com.tw/artical.php?page_id=65&ch_id=57 ▼概要 ウルトラの原点。決定版作品集! ウルトラ、マイティジャック、ヒューマン、バンキッドから、モンスター大図鑑、特撮美術、後年の絵画・彫刻まで。未発表作品、実現しなかった幻の企画案も含む、全515点一挙収録。 成田亨の仕事は、「芸術って何だ」という根源的な問いに肉薄する! ── 村上隆(アーティスト) 「成田亨 美術/特撮/怪獣」展 オフィシャル・カタログ (展示700点のうち、515点を収録) 富山県立近代美術館 2014年7月19日~8月31日 福岡市美術館 2015年1月6日~2月11日 青森県立美術館 2015年4月11日~5月31日 [寄稿] 椹木野衣(美術批評家) 「成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで」 三木敬介(富山県立近代美術館学芸員) 「〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨」 山口洋三(福岡市美術館学芸員) 「四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?)」 工藤健志(青森県立美術館学芸員) 「成田亨が残したもの」「試論 成田亨と鬼、あるいは〈芸能〉を継ぐ者」 田中聡(映像作家) 「他界の扉」 [目次] 成田亨プロフィール 成田亨のこと 成田流里 感謝の言葉 成田カイリ 序にかえて──「成田亨 美術/特撮/怪獣」展の開催に至る、およそ15年の経緯 工藤健志 成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで 椹木野衣 成田亨が残したもの 工藤健志 1 |初期作品 1950-60年代 2 |ウルトラ 1965-67年 2-1|ウルトラQ 特撮美術の作業 成田 亨 2-2|ウルトラマン ウルトラマンの頃 成田 亨 メカニズム・デザインについて 成田 亨 2-3|ウルトラセブン 3 |マイティジャック 1968年 4 |ヒューマン 1972年 ヒューマン怪獣──風船獣の闘い 成田 亨 5 |バンキッド 1976年 6 |マヤラー/ Uジン 実現しなかった企画案1 1970-80年代 7 |未発表怪獣 1984-87年頃 天空獣のデザインの発想 成田 亨 8 |モンスター大図鑑 1985-86年 9 |日本・東洋のモンスター 1980-90年代 10| MU /ネクスト 実現しなかった企画案2 1989年+1990年代 11|1970-90年代の絵画・彫刻 阿部合成先生の思い出 成田 亨 12|特撮美術 原爆を撮る 成田 亨 〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨 三木敬介 四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?) 山口洋三 試論 成田亨と鬼、あるいは「芸能」を継ぐ者 工藤健志 他界の扉 田中 聡 成田亨 略年譜 成田亨 著作物および関連文献目録 作品一覧 ▼プロフィール 成田 亨(なりた とおる) 1929(昭和4)| 9月3日神戸市に生まれる。1930年4月青森県に転居後、囲炉裏の炭をつかんで左手火傷。小中学校時代を再び兵庫県で過ごし、空襲に遭遇。青森県で終戦を迎える。県立青森高等学校卒業後、画家・阿部合成、彫刻家・小坂圭二の指導を受ける。 1950(昭和25)| 武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。3年次に彫刻科に転科し清水多嘉示に師事。 1954(昭和29)| アルバイトで東宝映画「ゴジラ」の撮影現場の手伝いをしたことをきっかけに、映画美術の世界に入り、彫刻家として新制作展(1955[昭和30]年の第19回展から1971[昭和46]年の第35回展まで)に出品を続けながら、映画の特撮シーンを数多く手がける。 1960(昭和35)| 東映で特撮美術監督。1962(昭和37)年第26回新制作展で《八咫》が新作家賞受賞、協友となる。 1965(昭和40)| 円谷特技プロダクションと契約、「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「マイティジャック」の怪獣、宇宙人、メカニックのデザインのほか、特技全般を手がける。 1968(昭和43)| 円谷プロを離れる。以後、ディスプレイデザイン、舞台、テレビ、映画の特撮を数多く担当。 1969(昭和44)| (株)モ・ブルを設立。 1970(昭和45)| 日本万国博覧会の岡本太郎作《太陽の塔》の内部に《生命の樹》をデザイン。 1972(昭和47)| 「突撃 ! ヒューマン !!」のキャラクターデザイン他特技全般を担当。 1983(昭和58)| 六本木アネックスで個展。朝日ソノラマより画集出版。 1990(平成2)| 京都府大江町(現・福知山市)に《鬼モニュメント》を制作。 1991(平成3)| 東京・銀座に「ギャラリー宇輪」開設(1992年まで)。 1994(平成6)| 北上市立鬼の館のためにレリーフ《鬼幻影》を制作。 1996(平成8)| フィルムアート社より『特撮と怪獣 わが造形美術』、『特撮美術』刊行。 1999(平成11)| 水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された椹木野衣企画の「日本ゼロ年」に出品。同年青森県が、ウルトラ関係のデザイン原画189点を購入。2006(平成18)年開館の青森県立美術館の所蔵品となった。 2002(平成14)| 2月26日、多発性脳梗塞のため永眠。享年72歳。 ▼書評・記事 『毎日新聞』2014年9月21日 「「ウルトラマン」など特撮作品のデザインや美術を手がけた著者の集大成」 『読売新聞』2014年9月28日書評 「ウルトラマンやその怪獣をデザインしたことで知られる成田亨。本書は、そのデザイン原画だけでなく、特撮美術、彫刻、絵画まで、氏の全活動にわたる全515点を収録した決定版作品集だ(後略)」(評・青木淳) 『朝日新聞』2015年2月15日書評 「成田亨──という名前になじみがなくても、〈ウルトラマン〉〈カネゴン〉〈バルタン星人〉と聞けば、「ああウルトラ怪獣!」とすぐに思い出せるだろう。(そう、彼こそは、ウルトラマンやウルトラセブン、そしてウルトラ怪獣たちの生みの親。伝説の怪獣デザイナー、いや、「アーティスト」である。(後略)」(評・原田マハ)
MORE -
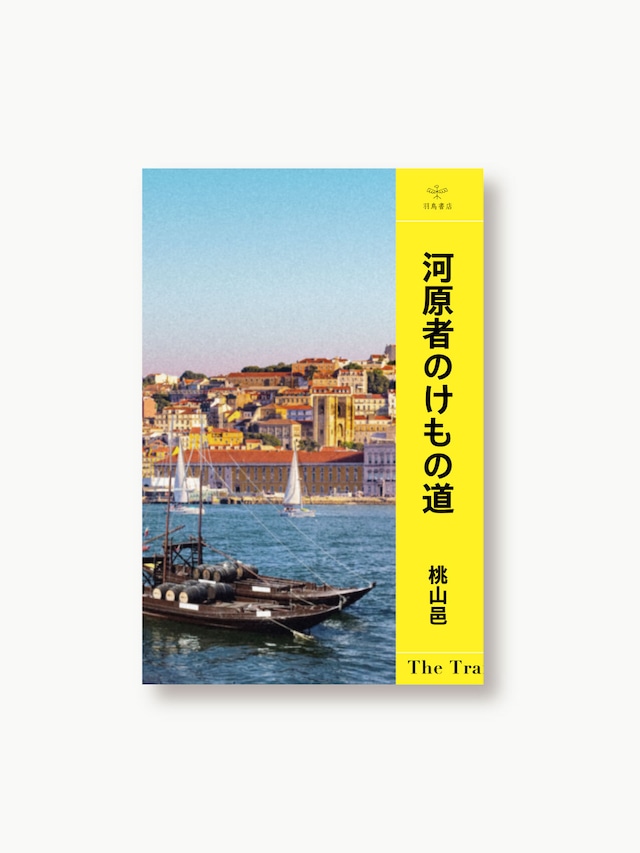
桃山邑『河原者のけもの道』
¥2,420
▼書籍概要 B6判変型 並製 400頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-91-8 C0074 2023年6月刊行 装幀 近藤ちはる 野戦攻城の幟の下、自らの手で野外に仮設劇場を建て、35年にわたり芝居をつづけてきた水族館劇場の座長、桃山邑最期のメッセージ。エッセイ、台本のほか、自らを赤裸々に語った8時間インタビューも収録する。 [主要内容] こんなふうに芝居の獣道を歩いてきた(インタビュー) 綯交の世界(エッセイ) おわかれだね/日雇下層労働の変容と山谷玉三郎の死 朱もどろの海の彼方から/ぼくの作劇法―座付き作者の使命 こんな音楽で舞台をいろどってきた 出雲阿國航海記(2022年公演台本) 水族館劇場 上演年表 寄稿:桑田光平・矢吹有鼓・佐藤良明・千代次 ▼著者プロフィール 桃山邑 (ももやま ゆう) 1957年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。1987年、水族館劇場として一座創設。以降35年にわたり寺社境内を漂流しながら人の縁を結んでゆく。2022年10月、銀河の涯へと旅立つ。桃山邑編『水族館劇場のほうへ』(2013年、羽鳥書店)。
MORE -
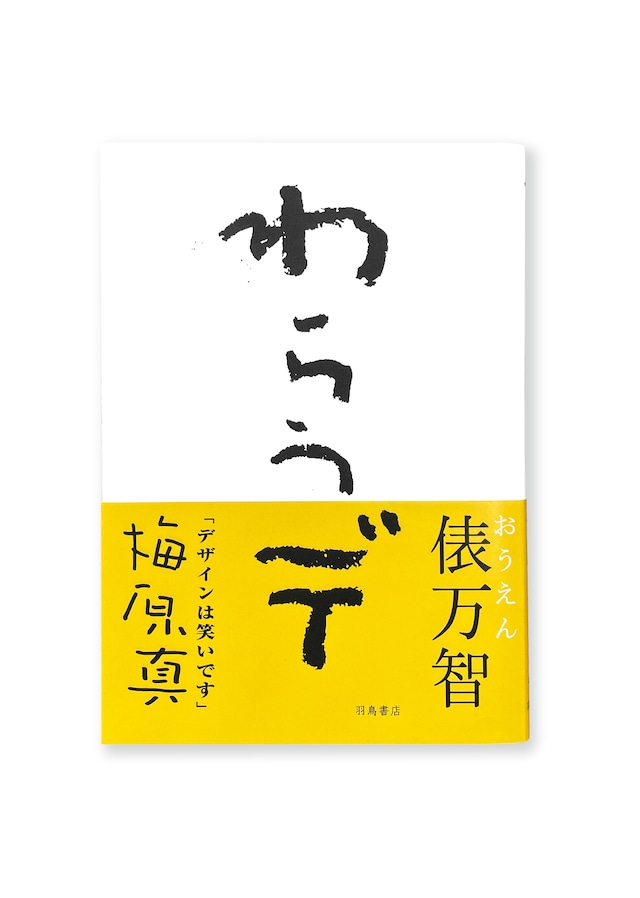
梅原真『わらうデ』
¥2,530
『わらうデ』刊行記念 梅原真×原研哉トークイベント「デザインは笑い」 2023年8月25日(金) 19:00~20:30 会場 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE *下記サイトよりご予約ください。 https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/34706-1412290706.html ▼書籍概要 A5判 並製 270頁 オールカラー 本体価格2,300円+税 ISBN 978-4-904702-90-1 C0070 2023年5月刊行 ブックデザイン 梅原デザイン事務所 「デザインは“笑い”です」 高知在住のデザイナー、梅原真の最新刊。オールカラー。 ローカルから世界へ発信するデザイナー梅原真が、43の仕事をショートショート・エッセイで紹介する。 [目次] みてる/良心市/スウェーデン/あきたびじょん/あうんアールグレイ/パリの野本くん/フタガミ/のんでます。/小布施見にマラソン/サトウとカトウ/鶴の湯/しまんと新聞ばっぐ/you no suke/犬も歩けば赤岡町/ゆずの村/ひがしやま/サキホコレ/ないものはない/ジグリフレンズ/いりこのやまくに瀬戸内際/砂浜美術館/マイナス×マイナス/ダニエラ・グレジス/おの肛門科/小布施ッション/マイトイレ14/げんぱつにげんこつ/とんかつソース/くんてきさん/1人より3人/こころのふしぎ/四万十川図鑑/男と女の石鹸/大阪だし/ひのき風呂/みつばち先生/ビッグデータ・とさのかぜ/いのうえ農場/図工・デ/重塑日本風景/B案/しまんと分校/しまんと流域農業 【関連書】 梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4873255 梅原真『おいしいデ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/12014680
MORE -
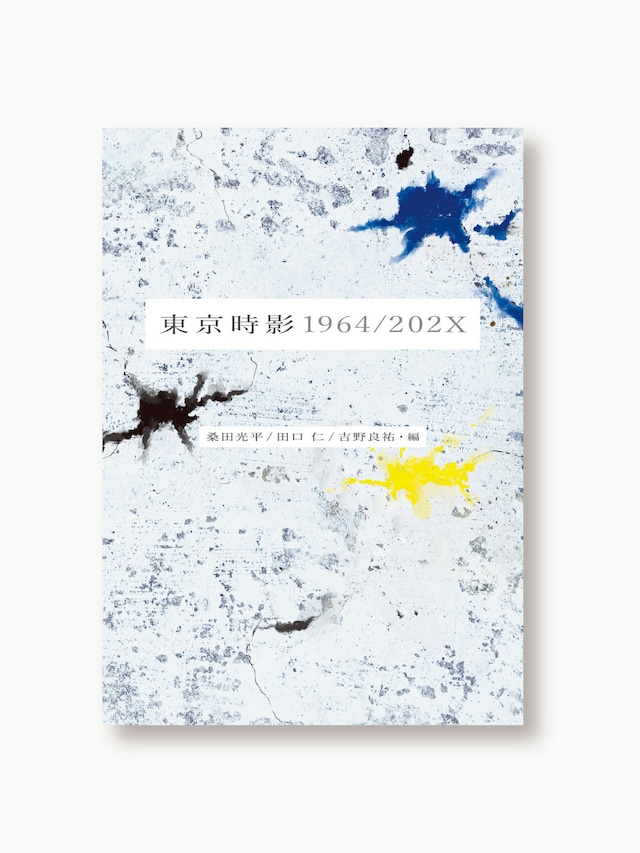
桑田光平・田口仁・吉野良祐[編]『東京時影 1964/202X』
¥3,520
▼書籍概要 A5判 並製 354頁 本体価格3,200円+税 ISBN 978-4-904702-89-5 C3010 2023年4月刊行 ブックデザイン 大西隆介・沼本明希子(direction Q) パンデミックで揺れ、変貌しつづける東京を歴史の地層から掘り起し、錯綜するイメージを切り取る。表象文化論からの果敢なアプローチ。 東京大学大学院総合文化研究科桑田ゼミにおけるリサーチを基礎に企画し、漫画、音楽、映画、文学、建築、美術──1964 年の東京、コロナ禍と五輪を経た現在の東京、両者を比較する表象分析の論考とエッセイ13 本を収録する。 [主要目次] 宙吊りの時間を記録する 桑田光平 序──「東京と」 田口仁 Part I/動 歩くこと──「人間の尺度」の回復 桑田光平 われら内なる動物たち──寺山修司、ダナ・ハラウェイ、AKI INOMATA 田口仁 Part II/時 Waves From A Seaside City in 1964──サーフィン、GS、City Pop 田口仁 都市のレイヤーを描く──マンガの中の東京、その地下 陰山涼 半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について 高部遼 「壁」景から「窓」景へ──写真表現における東京を見る人の表象をめぐって 西川ゆきえ 無柱のメカニクス/かたちのポピュリズム──フラー・山田守・坪井善勝・丹下健三 吉野良祐 東京肉体拾遺──ボクシング、ミステリー、水 伊澤拓人 失踪者のための回路──都市における失踪表現の変遷 小林紗由里 Part III/標 赤瀬川原平の楕円幻想 桑田光平 ガールたちの無自覚な反乱──源氏鶏太と愛とBG 平居香子 ジオラマ都市のカタストロフ──ゴジラが去ったそのあとに 吉野良祐 Part X/夢 捏造のランデブー──樺美智子と土方巽 平居香子 あとがき 吉野良祐 人名索引/事項索引/図版一覧/執筆者紹介
MORE -
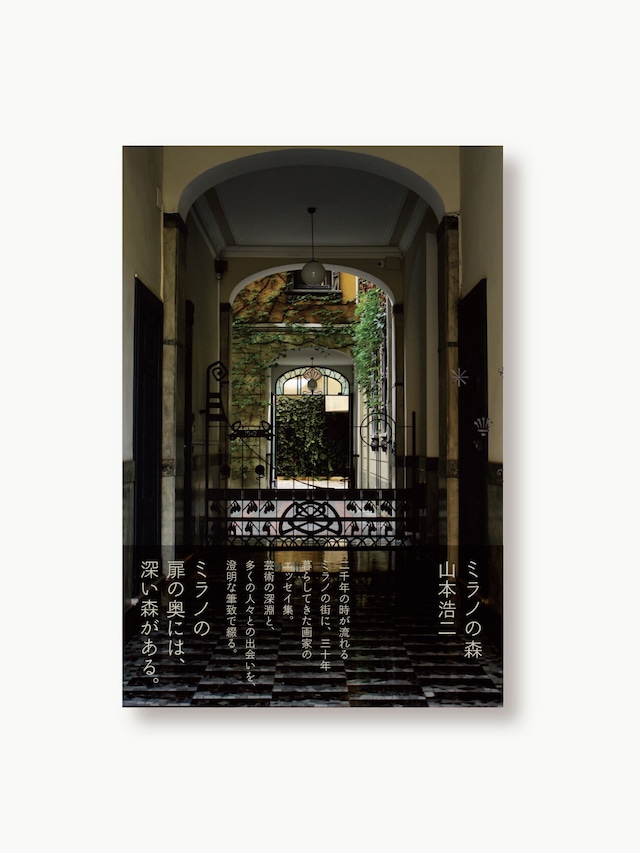
山本浩二『ミラノの森』
¥2,640
★刊行記念トークイベント★ 第2弾【終了】 出版記念対談「美の真実」 菅谷富夫(大阪中之島美術館館長)×山本浩二(画家) ミラノデザインを通して考える建築・プロダクトの意味と、古典と現代美術を俯瞰することで見えて来る芸術の深奥。広範な知識と経験から日本とヨーロッパ・地中海文明に横たわる美の真実を語り合います。 日時 2023年4月8日(土) 14:30〜16:30(開場14:00) 会場:大阪中之島美術館 1階ホール ・入場券のみ1500円(税込) ・書籍付入場券3700円(税込) 【申込】羽鳥書店 mail@hatorishoten.co.jp (@を半角@に変更してください) *下記HP問合せページからも送信できます。 https://thebase.in/inquiry/hatorishoten-official-ec *大阪中之島美術館 アクセス https://nakka-art.jp/visit/access/ ★刊行記念トークイベント★ 書籍先行発売【終了】 2022年8月12日(金) 19時〜(会場・オンライン同時開催) 会場:銀座 蔦屋書店 BOOK EVENT SPACE 山本浩二(画家)×古谷誠章(建築家) https://store.tsite.jp/ginza/event/architectural-design/27605-1241110704.html ▼書籍概要 四六判 上製 242頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-88-8 C0095 2022年9月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 ミラノの森──ミラノの街では、通りに⾯した建物の⾨扉は5mもの⾼さがあり、さまざまな時代のデザインが施され、扉の奥には鬱蒼とした森が広がっている。その奥深さはまた、⼈であり、歴史でもある。 ミラノの通り名がつけられた10 の章からなる、画家のエッセイ。ミラノを拠点に活躍する著者が、⽼舗画廊や書店とどう関係を築き上げていったか、また、その中で出会ったかけがえのない⼈々との交流を、⽂化的・歴史的背景を細やかに探りながら、澄明な⽂章でつづる。 ▼目次 サンタ・マリア・フルコリーナ通り Via Santa Maria Fulcorina ── ブルーノ・ダネーゼとジャクリーヌ・ヴォドツ チョヴァッソ通り Via Ciovasso ── 指揮者カルロ・マリア・ジュリーニと建築家フランチェスコ・ジュリーニ ヴェネツィア門 Porta Venezia ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(1) マンゾーニ通り Via Manzoni ── ナヴィリオ画廊とレナート・カルダッツォ ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレII世 Galleria Vittorio Emanuele II ── ボッカ書店と、社主ジャコモ・ロデッティ ピアーヴェ通り Viale Piave ── 路面電車(トラム)9番の並木道 ラッザーロ・パラッツィ通り Via Lazzaro Palazzi ── 編集者ジェラルド・マストゥルッロ ヴィスコンティ・ディ・モドローネ通り Via Uberto Visconti di Modrone ── 映画監督ルキーノ・ヴィスコンティとジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ ブエノス・アイレス大通り 2番地 Corso Buenos Aires 2 ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(2) ガリバルディ通り Corso Garibaldi ── ファッションデザイナー ナンニ・ストラーダ ▼著者プロフィール 山本浩二(やまもと こうじ) 画家 1951年生まれ。日本における抽象画の代表的作家の一人で、イタリア・ミラノを拠点に国際的に活躍する。2011年、内田樹氏の合気道場「凱風館」の能舞台に、抽象画による「老松」を制作し話題となる。ミラノでは、ボッカ書店に天井壁画を常設し、詩画集・随筆を出版、ロレンツェッリ・アルテで個展を開催。日本でも、銀座・永井画廊を中心に各地で活動。 画集『もうひとつの自然×生きている老松』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4874155
MORE -

鶴見明世・藤村龍生『スピリチュアル・コード──鶴見明世のシャーマン世界』
¥2,420
四六判 並製 220頁(カラー20頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-87-1 C0010 装幀 白井敬尚(アートワーク:山本理乃) 2022年3月刊行 ▼概要 卓越したタロット・リーダー、稀代のシャーマン、鶴見明世が視るヴィジョン。 知覚器官のようにしてタロットを「読む」力をもち、臨死体験をへて大きく覚醒したシャーマンとして活動する鶴見が、哲学者・藤村龍生との対談を通して、独自のスピリチュアルな次元を初めて語る。 〈スピリチュアル〉──それは、精神的、霊的、神秘的であり、またエネルギー的かつ情報的である。いま危機的な地球を生きる人類が、多元的な時空に存在する一人ひとりの自分を知り、未来を見据えるために、新しいスピリチュアルの扉が開かれる。 ▼主要目次 I 鶴見明世の原点──独学でタロットを学ぶ II 臨死体験、そして四神の世界へ III ヒーリング、世界を舞台として ▼著者紹介 鶴見明世(つるみ あきよ) 1962年生まれ、横浜市出身。タロット・リーダー、シャーマン、ヒーラー、スピリチュアル・アーティスト。2005 年、ドイツ国際ヒーリング協会から日本人で唯一のOutstanding-Healer 認定を受ける。2010年、NPO 法人IAOH-JAPAN 理事長就任。2011 年、ドイツ・スイスインターナショナルホリスティック協会ボードメンバー就任。2020 年、スピリチュアルな事象全般に対応するため、OfficeNIJI(オフィス虹)を設立。明解なリーディング、ハートフルなヒーリングを求めて訪れる人々の数は年間約1 千人、トータルで3 万人を超える。 Office NIJI https://office-niji.com/ 藤村龍生(ふじむら たつお) 1950年生まれ、東京都出身。哲学者・神秘思想研究家
MORE -
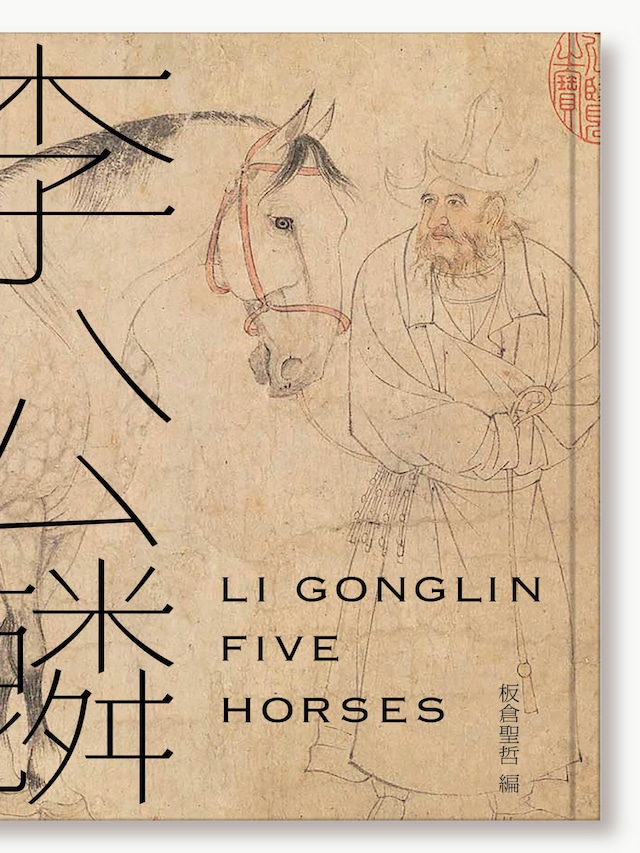
板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』Li Gonglin 'Wuma-tu’ (Li Gonglin’s Five Horses)
¥30,800
★編者による画集紹介 UTokyo BiblioPlazaより 日本語:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/E_00218.html English:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/en/E_00218.html 板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』 A3判 上製 84頁 スリーブケース入り 本体28,000円+税 ISBN 978-4-904702-75-8 C1071 撮影:城野誠治 ブックデザイン:原研哉+大橋香菜子 画集【特設サイト】 http://www.hatorishoten-articles.com/fivehorses.html ---------- 幻の神品、現る。 北宋時代、李公麟(りこうりん。1049?~1106)によって描かれ、中国の歴代王朝で愛蔵された「五馬図」を、原寸で紹介する、唯一無二の画集。 ▶︎内容構成 ・図版 李公麟筆「五馬図巻」 原寸・縮尺全図・拡大部分図 ・論文 板倉聖哲「李公麟筆「五馬図巻」の史的位置」 *年表・主要関連文献・中国語対訳(繁体字)・英文サマリー付 ▶︎編者プロフィール 板倉聖哲(いたくら まさあき) 1965年、千葉県生まれ。1988年、東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻、博士後期課程中退。大和文華館学芸部部員、東京大学東洋文化研究所助教授を経て、現在、同教授。研究領域は中国を中心とした東アジア絵画史。 [編著]『南宋絵画 才情雅致の世界』展図録(監修・共著)根津美術館、『講座日本美術史 第2巻 形態の伝承』(編・共著)『中国絵画総合図録三編 第1~5巻』(共編)『描かれた都─開封・杭州・京都・江戸』(共著)東京大学出版会、『日本美術全集第6巻 東アジアの中の日本美術』小学館、他。
MORE -

名雪晶子『コン・アニマ 魂を込めて、生き生きと』(写真集)
¥3,300
【終了】富士フイルムフォトサロン若手写真家応援プロジェクト【写真家たちの新しい物語】 名雪晶子 写真展「コン・アニマ ─ 魂を込めて、生き生きと」 会期:2021年4月2日(金)~4月15日(木) 会場:FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)内 富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3 https://fujifilmsquare.jp/photosalon/tokyo/s3/21040205.html B5判変型 並製 84頁 本体価格3,000円+税 ISBN 978-4-904702-86-4 C0072 2021年4月下旬刊行 アートディレクション・ブックデザイン:長尾敦子 ▶︎概要 水の変幻自在なあり方に魅了され、そのさまざまな姿を撮り続けている写真家による、初の写真集。「柔らかいかと思えば、時には鉱石のように硬く見えることもあり、まわりの世界の色を溶かして輝く様はひとつの生命体のよう」。生き生きとした力がはじけて音楽がきこえてくる、そんな水の姿を、魂を込めて(con anima)映しとる。 ▶︎写真家プロフィール 名雪晶子 NAYUKI Shoko 1992年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。 祖母、両親が音楽家という環境に生まれ、音楽や美術に親しんで育った。大学時代、写真家で教授の上田義彦氏の授業をきっかけに真剣に写真と向き合い始める。幼い頃から抱いていた水の流れへの興味を昇華させようと、作品を作り続けている。 公式HP https://nayukishoko.com FAVORRIC(フェイバリック)のアーティストサイト https://favorric.com/artist/shoko_nayuki
MORE -
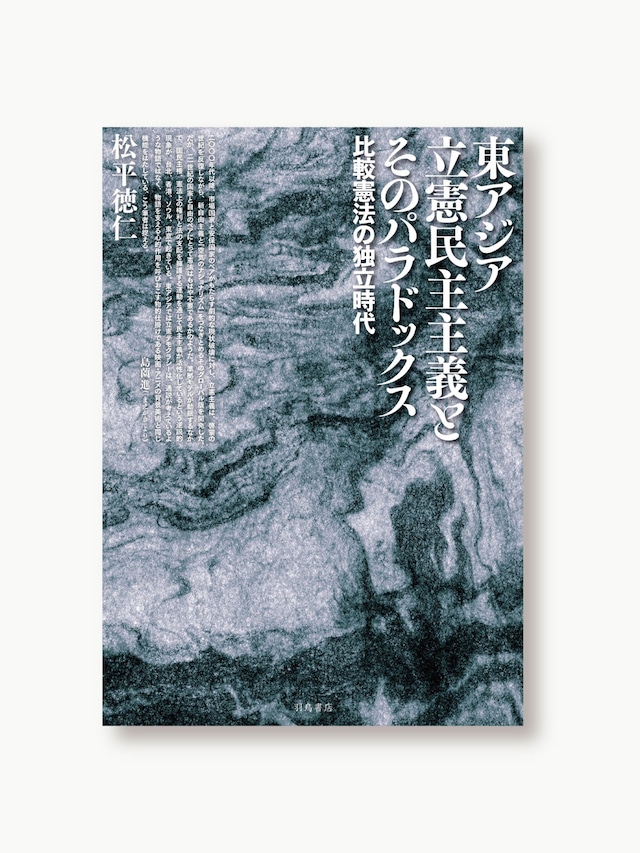
松平徳仁『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス──比較憲法の独立時代』
¥6,600
A5判 上製 336頁 本体価格6,000円+税 ISBN 978-4-904702-85-7 C3032 2021年3月中旬刊行 ブックデザイン:鈴木一誌+吉見友希 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス』 正誤表(2021年2月25日) https://www.hatorishoten-articles.com/uploads/9/7/4/1/97413020/teisei_higashiasia_20210225.pdf ▶︎概要 セカイ系立憲主義から東アジアの憲法状況を展望する。ジャック・ランシエール、エドワード・ヤン、「セカイ系」アニメから比較憲法と表象文化の接点を見いだす、境界領域を超えるしぶとく力強い憲法論。 ▶︎目次 まえがき 比較文明的視野をもった新たな憲法論 島薗進 序章 「儒者の困惑」──問題・主義・イメージ 第1部 文化的パラドックス──立憲主義、ナショナルかつコロニアルな 第1章 立憲主義による植民地主義──その償還責任 第2章 「仁義なき戦い」の憲法学──東アジアにおける「権威主義対立憲主義」の深層 第3章 憲法というゴールデン・ドリーム──「日本の衝撃」と、中華民国憲法でつなぐ中国と台湾 第4章 ワイマール憲法学で中国を読む──シュ・ダウリンの実践 第5章 押しつけ憲法による人民自決?──李登輝の「特殊二国論」 第2部 制度的パラドックス──「セカイ系立憲主義」の展開 第6章 立憲主義の濫用を防ぐ「憲法工学」 第7章 原子力緊急事態で考える国家理性と避難 第8章 自粛と日本型共同体主義 第9章 民主憲政のはざまで──市場国家と安保国家に抗して 第10 章 「集団的自衛権」をめぐる憲法政治と国際政治 第11 章 戦力・軍事裁判・立憲主義──台湾を素材として 第3部 「セカイ系立憲主義」の動揺──アメリカの憲法政治 第12 章 国家理性、憲法感情と司法審査──二〇一二年の医療保険制度改革法連邦最高裁判決 第13 章 権力者の自己言及──オバマとトランプ 第14 章 国家像をめぐる法廷闘争──入国禁止令違憲訴訟 あとがき/人名索引 ▶︎著者プロフィール 松平徳仁(まつだいら とくじん) 神奈川大学法学部教授。憲法学、比較憲法学専攻。1969年、台湾・台北市生まれ。1998年、東京大学法学部卒業。ワシントン大学ロースクール修了(法学修士)、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。共著に『憲法の尊厳』(日本評論社、2017)、翻訳にサンフォード・レヴィンソン「立憲民主主義国にとってストレスの多い時期」法時1150号(2020)など。
MORE -
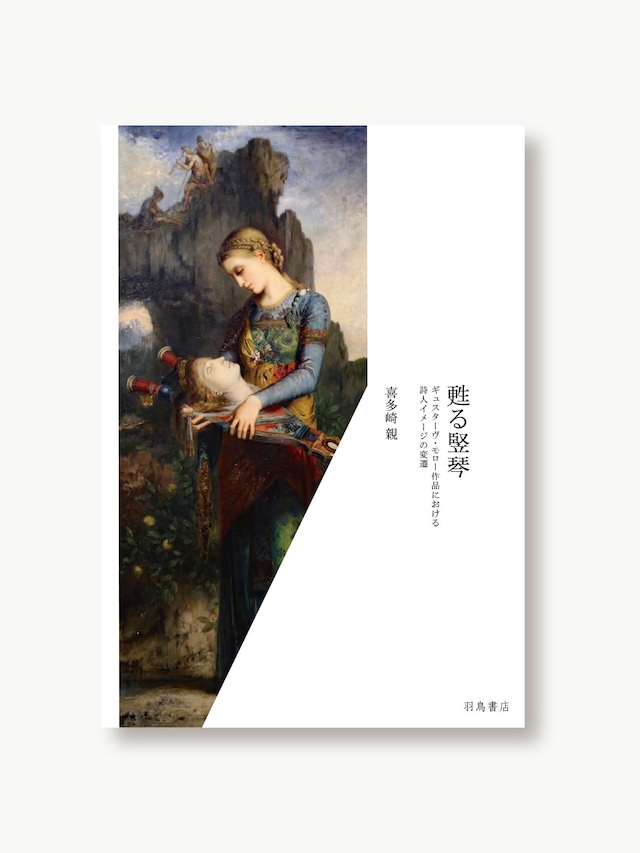
喜多崎親『甦る竪琴──ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』
¥4,620
A5判 上製 288頁(口絵8頁) 本体価格4,200円+税 ISBN 978-4-904702-84-0 C3070 2021年2月中旬刊行 ブックデザイン:原研哉+矢崎花 ▶︎概要 画家が生涯描きつづけた詩人の主題。そこに託したメッセージとは何か。 ギュスターヴ・モロー(1826-98)が、1860年代から晩年にかけて制作した6つの作品を対象に生成過程を分析し、詩人イメージがいかに形成され変容していったかを明らかにする。19世紀後半、新しい芸術の担い手たちが次々に登場する時代、新しい歴史画を模索したモローは、独自の図像を生み出していった。 ▶︎目次 序論 第一章 インスピレーションの寓意──「ヘシオドス」テーマの変奏 第二章 哀悼の神話──新しい神話画としての《オルフェウス》 第三章 オリエント幻想──《聖なる象》の異国趣味 第四章 詩想の喪失──《人類の生》の二つのヴァージョン 第五章 浄化と再生──《ユピテルとセメレ》の逸脱 第六章 甦る竪琴──《死せる竪琴》と終末のヴィジョン 結論 あとがき 文献一覧/図版一覧/作品名索引/人名索引 ▶︎著者プロフィール 喜多崎親(きたざき ちかし) 成城大学文芸学部教授。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。博士(文学)。国立西洋美術館主任研究官、一橋大学大学院教授などを経て現職。専門は19 世紀フランス美術史、特に近代の宗教画や象徴主義。著書に『聖性の転位――九世紀フランスに於ける宗教画の変貌』(三元社、2011)、編著に『岩波 西洋美術用語辞典』(益田朋幸と共編著、岩波書店、2005)、『近代の都市と芸術1 パリI 』(竹林舎、2014)、『前ラファエッロ主義――過去による19世紀美術の革新』(三元社、2018)など。
MORE -
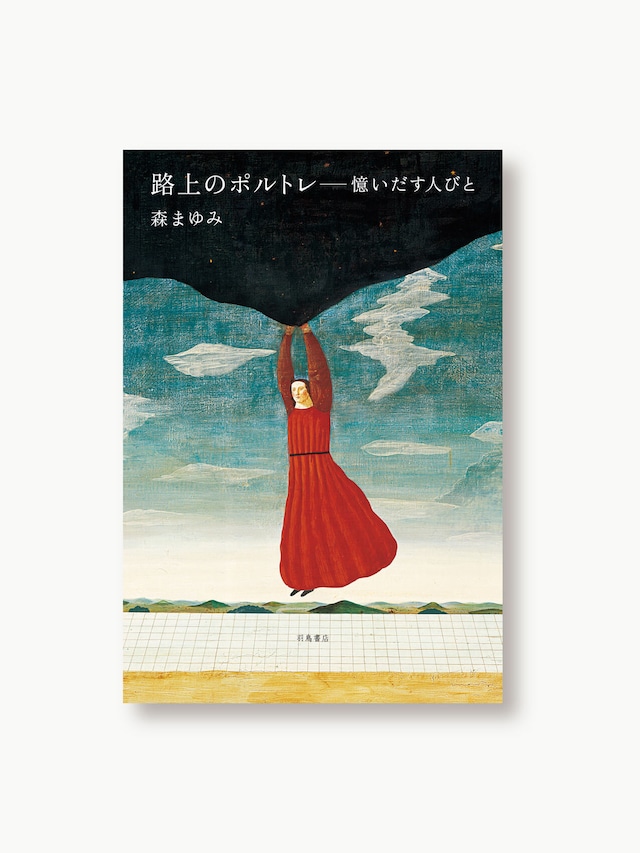
森まゆみ『路上のポルトレ── 憶いだす人びと』
¥2,420
四六判 上製 336頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-83-3 C0095 2020年11月下旬刊行 編集:南陀楼綾繁 カバー画:有元利夫 ブックデザイン:大西隆介(direction Q) ▶︎概要 忘れ得ぬ人の記憶をたなごころですくい、 そっと温めるように書いておきたい── 地域雑誌『谷中・根津・千駄木』から出発し、評伝をはじめ多彩な活動を続けてきた著者が出会った人びとを回想するエッセイ集成。 作家、思想家、詩人、映画監督、芸人、そして市井に生きる人……。およそ100人が織りなす星座のような人間模様。 ▶︎目次 はじめに Ⅰ こぼれ落ちる記憶 もう一人のモリマユミ ──西井一夫 朝の電話 ──藤田省三ほか アメリカのセイゴさん 羽黒洞のおやじさん ──木村東介 ひらひらした指 震災でおもいだしたこと ──吉村昭 衿子さんの家で ──岸田衿子 センチメンタル・ジャーニー ──目賀田先生 狐につままれた話 本郷の畸人のこと ──品川力 「根津の甚八」伝説 いっそままよのボンカレー ──岡本文弥 大地堂の一筆 ──浅田良助 故郷忘じがたし ──沈壽官 海の切れはし ──森家の人びと 谷中墓地で会った方たち ──萩原延壽ほか 背中を流す バーの止まり木 ──種村季弘 Ⅱ 町で出会った人 木下順二さんのこと 谷中で戦争を語りつぐ会 弥生町の青木誠さん 町の兄い 岩崎寛彌さんのこと 建築史・門前の小僧 ──村松貞次郎ほか 元倉眞琴さんのこと 宇沢弘文先生の最後の言葉 横浜のお兄さん 北澤猛 サイデンステッカー先生の不忍池 解剖坂のKさん ゆっくり知りあう ──小林顕一 高田爬虫類研究所 ──高田栄一 やっぱりオモシロイ平岡正明 集まってきた本たち なくなったお店三つ(泰平軒、鳥ぎん、蛇の目寿司) 母の日によせて ヤマサキという人 ──山﨑範子 Ⅲ 陰になり ひなたになり 粕谷一希さんの支え 鶴見俊輔さんの遺言 温かい手のやわらかさ ──瀬戸内寂聴師 杉浦明平さんに聞く 風太郎大人との至福の時間 ──山田風太郎 『彷書月刊』のあの頃 ──田村治芳ほか すゞやかな文人 ──高田宏 倉本四郎の庭 きっとですよ ──大村彦次郎 信濃追分を愛した人 ──近藤富枝 花のような人 ──木村由花 Ⅳ 出会うことの幸福 上を向いて歩こう ──永六輔 活字遊びと恋の転々 ──岡本文弥 吉原に愛された人 ──吉村平吉 自主独立農民 佐藤忠吉 阪神間のお嬢さま ──脇田晴子 河合隼雄長官の冗談 わたしの知ってる矢川澄子さん 黒岩比佐子さんを惜しむ 旅の仕方を教わった人 ──紅山雪夫 古い友だち 佐藤真 同僚教員の村木良彦さん ゆふいん文化・記録映画祭 ──土本典昭ほか neoneo坐で会った萩野靖乃さん 松井秀喜選手とちょっとだけ立ち話 ジュリーのいた日々 ──沢田研二 樹木希林さんとの接近遭遇 九代目市川團十郎丈のギャラン バングラディシュのマクブールさん 北上へ行ったジョン君 中村哲さんのたたずまい わたしの病気を発見してくれた人 ──原田永之助 おわりに 初出一覧 人名索引 ▶︎著者プロフィール 森まゆみ 1954 年東京生まれ。作家。大学卒業後、PR 会社、出版社を経て、1984 年に仲間と地域雑誌『谷中・根津・千駄木』を創刊、2009 年の終刊まで編集人を務めた。 歴史的建造物の保存活動にも取り組み、日本建築学会文化賞、サントリー地域文化賞を受賞。 『鷗外の坂』で芸術選奨文部大臣新人賞、『「即興詩人」のイタリア』でJTB 紀行文学大賞、『「青鞜」の冒険』で紫式部文学賞を受賞。他の著書に『彰義隊遺聞』『暗い時代の人々』『子規の音』など。
MORE -
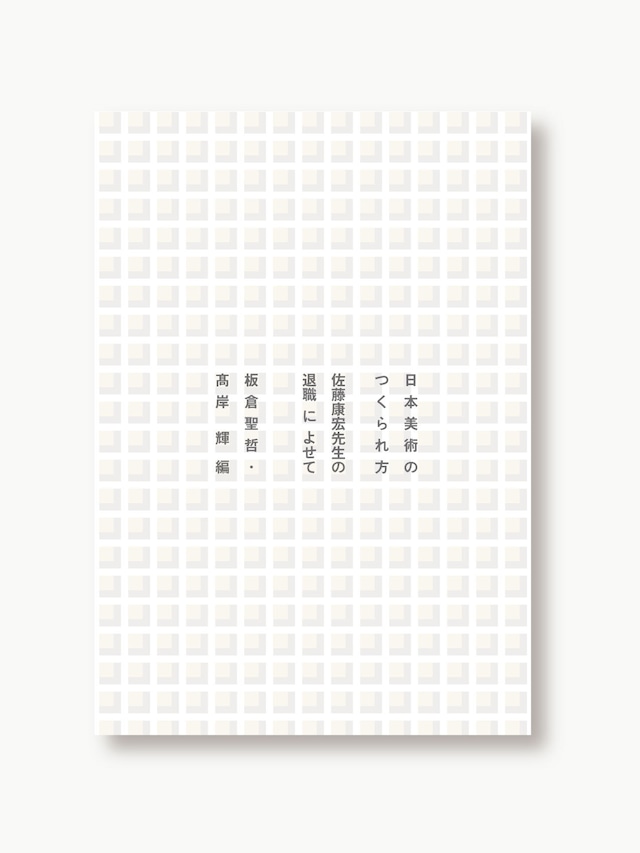
板倉聖哲・髙岸 輝[編]『日本美術のつくられ方──佐藤康宏先生の退職によせて』
¥13,200
A5判 上製 800頁 本体価格12,000円+税 ISBN 978-4-904702-82-6 C3071 2020年12月刊行 ブックデザイン:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 今、日本美術史研究で何が起き、どこに射程が広がっているのか? 若冲研究の第一人者である佐藤康宏教授(東京大学大学院人文社会系研究科・文学部)の退職によせた論考集成。第一線で活躍する学芸員・研究者31名が拓く、最先端の読みの試み。 ▶︎主要目次 Ⅰ 絵のすがた、像のかたち──古代・中世 Ⅱ ひろがる世界、つながる絵画──近世〔1〕 Ⅲ 社会のなかの絵師たち──近世〔2〕 Ⅳ 日本美術の今を創る──近代・現代 ▶︎執筆者[登場順] 増記隆介(神戸大学)/佐々木守俊(清泉女子大学)/佐藤有希子(奈良女子大学)/伊藤大輔(名古屋大学)/五月女晴恵(北九州市立大学)/髙岸輝(東京大学)/荏開津通彦(山口県立美術館)/板倉聖哲(東京大学)/三戸信惠(山種美術館)/鷲頭桂(東京国立博物館)/五十嵐公一(大阪芸術大学)/野田麻美(静岡県立美術館)/野口剛(根津美術館)/田中英二(うげやん)/伊藤紫織(尚美学園大学)/門脇むつみ(大阪大学)/池田芙美(サントリー美術館)/馬渕美帆(神戸市外国語大学)/横尾拓真(名古屋市博物館)/森道彦(京都国立博物館)/曽田めぐみ(東京国立博物館)/山際真穂(すみだ北斎美術館)/中田宏明(群馬県立近代美術館)/中谷有里(高知県立美術館)/岡島奈音(文化学園大学)/中村麗子(東京国立近代美術館)/植田彩芳子(京都文化博物館)/吉田暁子(目黒区美術館)/村田梨沙(秋田市立千秋美術館)/廣瀬就久(岡山県立美術館)/片岡香(川崎市岡本太郎美術館)
MORE -
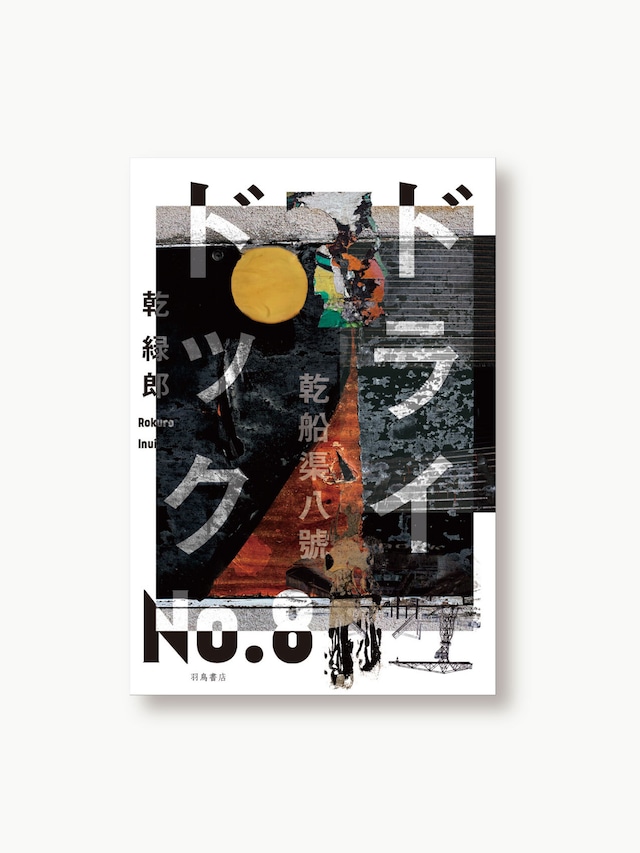
乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』(戯曲集)
¥2,420
★水族館劇場 花園神社公演(4/10–19)は中止となりました。 四六判 並製 248頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-81-9 C0074 2020年4月中旬刊行 装幀:近藤ちはる ▶︎概要 「機巧のイヴ」シリーズなどで新たなSF伝奇小説を開拓する小説家・乾緑郎、初の戯曲集。野外に巨大な仮設劇場を建てる芝居集団〈水族館劇場〉の新宿花園神社公演(2020年4月10日〜19日)のために書下ろされた新作「ドライドックNo.8 乾船渠八號」に、劇作家協会新人戯曲賞最終候補作「ソリテュード」を併録。 有人砲弾、月へ! 造船と紡績でにぎわう架空都市「横濱」。ヴェルヌの「月世界旅行」が史実として持てはやされる港町で、月へ向け、有人砲弾の打ち上げ計画がはじまった。 横濱に建設された巨大なドックに、カンカン虫と呼ばれる下層労働者が船の錆落としのために打ちおろす槌(ハンマー)の音が鳴り響く。月世界旅行にあこがれる少年ワタルと糸繰り工女の虹子。持たざる者たちは、カイウサギの投機ブームに翻弄されながら、陰謀うずまく国家事業にのみこまれてゆく。 ▶︎収録作品 「ドライドックNo.8 乾船渠八號」 「ソリテュード」 ▶︎著者プロフィール 乾 緑郎(いぬい ろくろう) 1971年、東京生まれ。小説家・劇作家。2010年『完全なる首長竜の日』(宝島社)で第9回「このミステリーがすごい!大賞」を、『忍び外伝』(朝日新聞出版)で第2回朝日時代小説大賞を受賞しデビュー。2013年『忍び秘伝(文庫化タイトル:塞ノ巫女)』で第15回大藪春彦賞候補。近年は作品の英訳版が発売され、中国のSF雑誌にも掲載されるなど、海外での評価も高い。『機巧のイヴ』シリーズ(新潮社)、『見返り検校』(新潮社)『僕たちのアラル』(KADOKAWA)、『ツキノネ』(祥伝社)、『ねなしぐさ 平賀源内の殺人』(宝島社)など、著書多数。 ▶︎水族館劇場 2020年 新宿花園神社公演 「乾船渠八號 DRY DOCK NO.8」 作 乾緑郎 演出 桃山邑 2020年4月10日〜19日(10日間連続公演)19時より 会場:新宿 花園神社 境内特設野外舞台 http://suizokukangekijou.com/information/
MORE -
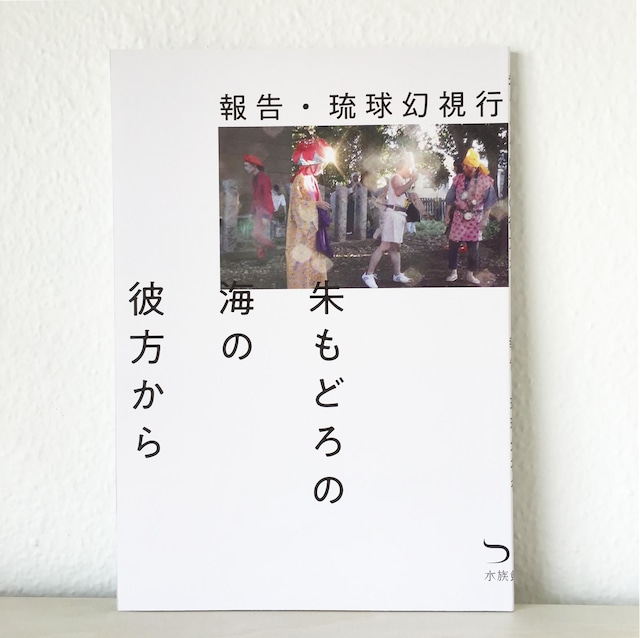
水族館劇場『朱もどろの海の彼方から──報告・琉球幻視行』(委託販売品)
¥1,650
B5判 並製 100頁 本体価格1500円+税 装幀:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2019年12月 ▶︎概要 水族館劇場は、「さすらい姉妹」興行として2019年「風車(かじまやー)の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」へ参加し、5月に東京上野で、七月には沖縄で『陸奥(みちのおく)のの運玉義留(んたまぎるー)』(作演出 翠羅臼)を上演した。10月、沖縄というテーマを引き継いで、水族館劇場座長の桃山邑によって新たな台本「GO! GO! チンボーラ」が書かれ、東京世田谷の太子堂八幡神社で奉納芝居として上演された。 本書は、二つの台本(★)を収録するとともに、沖縄公演から、沖縄をめぐる新たな芝居上演にいたる記録として編んだものである。 『陸奥の運玉義留』(作演出 翠羅臼)★ 「風車の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」参加 東京 上野 水上音楽堂 5月31日 沖縄 辺野古 キャンプシュワブゲート前テント 7月12日 那覇 新都心公園 天幕渋さ 特設ステージ 7月13日 「赤い森の彼方へ──沖縄のアンダーグラウンド」(水族館劇場主催) 東京 新大久保EARTHDOM 7月5日 『GO! GO! チンボーラ~ 満月篇』(作演出 桃山邑) 東京 三軒茶屋 太子堂八幡神社境内 例祭奉納芝居 10月13日 『海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり』(作演出 桃山邑)★ 東京 新大久保EARTHDOM 12月13日 ▶︎目次 沖縄から世界へ。世界から沖縄へ。──移民、貧困、歴史。希望なき社会の希望 桃山 邑 陸奥の運玉義留(作演出 翠羅臼) ボンヤリ沖縄行き 千代次 冬のかんげーぐと 居原田 遥 来訪と放浪─さすらい姉妹の旅の夏 梅山いつき 沖縄報告(辺野古─高江─安部海岸─読谷村)──2016年暮れ 秋浜 立 海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり(作演出 桃山邑) ▶︎関連書 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』2017&2018 http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150539 乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/26902335
MORE -
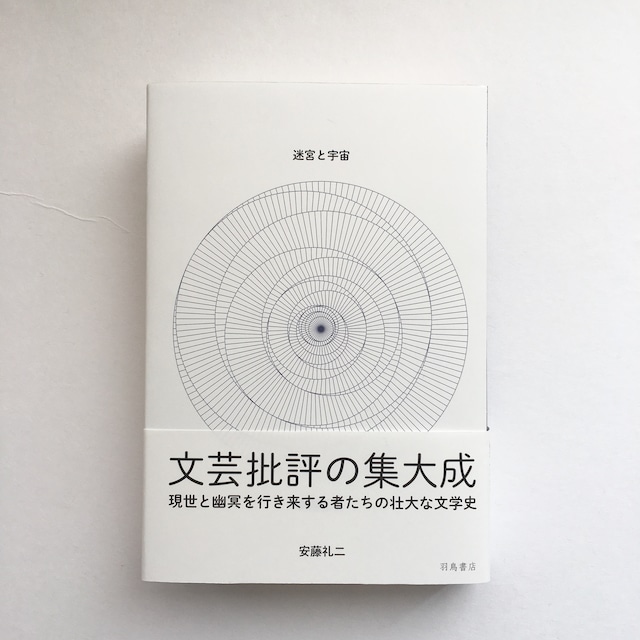
安藤礼二『迷宮と宇宙』
¥3,080
四六判 上製 320頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-80-2 C0090 2019年11月刊行 装幀:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 文芸批評の集大成 現世と幽冥を行き来する者たちの、壮大な文学史 平田篤胤とエドガー・アラン・ポーをめぐる「二つの『死者の書』」から始まり、鏡花、谷崎、土方、乱歩、三島、澁澤へと論が展開する「I 迷宮と宇宙」6編。折口を通底におきながら、賢治と久作を手繰りよせる「II 胎児の夢」2編。最後に、ポーからボードレールに及ぶ1編「III 批評とは何か」で、「解釈」(翻訳)そして「創作」について分析し、批評の世界を切り拓く。 終了イベント 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 2019/11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎目次 Ⅰ 迷宮と宇宙 二つの『死者の書』――平田篤胤とエドガー・アラン・ポー 輪舞するオブジェ――泉鏡花『草迷宮』をめぐって 人魚の嘆き――谷崎潤一郎の「母」 肉体の叛乱――土方巽と江戸川乱歩 夢の織物――三島由紀夫『豊饒の海』の起源 未生の卵――澁澤龍彦『高丘親王航海記』の彼方へ Ⅱ 胎児の夢 多様なるものの一元論――ラフカディオ・ハーンと折口信夫 胎児の夢――宮沢賢治と夢野久作 Ⅲ 批評とは何か 批評とは何か――照応と類似 後記/人名索引/文献一覧 ▶︎著者プロフィール 1967年、東京都生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。 [主要著書]『神々の闘争 折口信夫論』(講談社)芸術選奨文部科学大臣賞、『近代論 危機の時代のアルシーヴ』(NTT出版)、『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社)大江健三郎賞・伊藤整文学賞、『霊獣「死者の書」完結篇』(新潮社)、『場所と産霊近代日本思想史』(講談社)、『たそがれの国』(筑摩書房)、『祝祭の書物 表現のゼロをめぐって』(文藝春秋)、『折口信夫』(講談社)角川財団学芸賞・サントリー学芸賞、『大拙』(講談社)、近刊に『列島祝祭論』(作品社)。
MORE -

長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』
¥3,080
四六判 上製 312頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-79-6 C1032 2019年11月刊行 ブックデザイン:原研哉+稲垣小雪 ▶︎概要 自由な思惟のエッセンス 2017年1月から2019年3月まで羽鳥書店Webで連載された「憲法学の虫眼鏡」(第一部に収録)を中心に、書下ろしを含め、『UP』連載「法の森から」など35篇を収録した最新エッセイ集。憲法学者のヴィヴィッドな思索に触れる。 ▶︎目次 はしがき 第一部 憲法学の虫眼鏡 1 森林法違憲判決 2 法律の誠実な執行 3 カール・シュミット『政治的ロマン主義』 4 ThickかThinか 5 緊急事態に予めどこまで備えるべきなのか 6 有権解釈とは何なのか 7 八月革命の「革命」性 8 内閣による自由な解散権? 9 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 10 英語で原稿を書く 11 プロイセン憲法争議 12 「ユダヤ的国家」万歳 13 適切な距離のとり方について 14 最悪の政治体制、民主主義 15 意思と理由 16 ポワッソンのパラドックス 17 法人は実在するか? それを問うことに意味はあるか? 18 統治権力の自己目的化と濫用 19 クリスティン・コースガードの手続的正義 20 相互授権の可能性? 第二部 法の森から 1 ルソーのloiは法律か? 2 戦う合衆国大統領 3 フランソワ・ミッテラン暗殺未遂事件 4 英米型刑事司法の生成 5 フォークランド諸島 一九八二年五月二五日 6 巡洋艦ベルグラーノ撃沈 一九八二年五月二日 7 バーリンの見た日本 8 国際紛争を解決する手段としての戦争 9 アメリカがフィリピンで学んだこと 第三部 比較できないこと 1 比較できないこと 2 サリンジャーと出会う 3 人としていかに生きるか──カズオ・イシグロの世界 4 自己欺瞞と偽善の間──「狂気の皇帝」カリグラ 5 奥平康弘『萬世一系の研究(上)』解説 6 変えるべきか変えざるべきか ▶︎著者プロフィール 長谷部恭男 (はせべやすお) 1956年広島生まれ。早稲田大学大学院法務研究科教授。 [主要著書]『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991)、『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004)、『憲法とは何か』(岩波新書、2006)、『Interactive憲法』 『続・Interactive憲法』(有斐閣、2006、2011)、『憲法の境界』(羽鳥書店、2009)、『憲法入門』(羽鳥書店、2010)、『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)、『憲法の理性 増補新装版』(東京大学出版会、2016)、『憲法の論理』(有斐閣、2017)、『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論 増補新装版』(東京大学出版会、2018)、『憲法 第七版』(新世社、2018)、『憲法の良識──「国のかたち」を壊さない仕組み』(朝日新書、2018)
MORE -
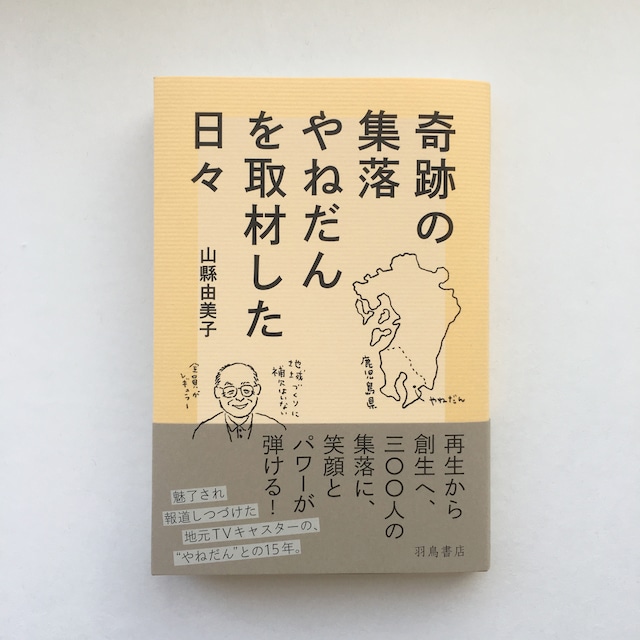
山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』
¥2,200
四六判 並製 208頁 本体価格2,000円+税 ISBN 978-4-904702-78-9 C0095 2019年10月刊行 イラスト:なかむらるみ ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 再生から創生へ、300人の集落には、笑顔とパワーが弾ける リーダーの豊重哲郎さんを中心に、行政に頼らない地域再生を果たし、全国から注目される鹿児島県鹿屋市柳谷(やなぎだに)集落、通称やねだん。元TVキャスター(現九州大学理事)の著者が、アイデアと工夫、結束力あふれる集落の人びとを表情豊かに綴る。山縣がディレクターを務めたドキュメンタリー番組「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」(南日本放送)は、ギャラクシー賞テレビ部門選奨、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、など数々の賞を受賞。 ▶︎主要目次 プロローグ やねだんの地域再生はこう始まった 年々増える自主財源 全世帯にボーナス! 豊重さん、なぜそんなにがんばるのですか? 逆境からつかんだ“感動”の手法 やねだんの新しい風 アーティストがやってきた! すべてを分かち合う集落 ドキュメンタリー番組『やねだん』に込めた思い 国境も越えて広がった連帯 取材できない 奇跡は手の届くところに あとがき やねだん再生と取材の年譜 【コラム】 手づくり〈わくわく運動遊園〉の完成 ヒット商品〈焼酎やねだん〉を生み出した畑 自治公民館長・豊重哲郎さんの履歴書 集落を象徴する〈焼酎やねだん〉 第1号の移住アーティスト 人生初めての似顔絵 おちゃめな中尾ミエさん 海をわたった“やねだん” 広がる韓国との交流 ▶︎著者プロフィール 山縣由美子(やまがた ゆみこ) 九州大学理事。元TVキャスター。1981年九州大学文学部を卒業後、南日本放送にアナウンサーとして入社。「MBC6時こちら報道」で鹿児島初の女性ニュースキャスターとなる。1989年フリーとなり、NHK福岡放送局やFBS福岡放送でキャスターに。1997年南日本放送に復帰。キャスター業とドキュメンタリー番組制作を続け、「小さな町の大きな挑戦~ダイオキシンと向き合った川辺町の6年~」で文化庁芸術祭賞など、「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」で早稲田ジャーナリズム大賞など様々な賞を受賞。2014年10月、九州大学理事に就任。大学と社会をつなぐスポークスパーソンの役割を担い、広報改革などを指揮。 ▶︎柳谷集落(やねだん)公式サイト http://www.yanedan.com/ ▶︎MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』DVD販売 DVD単品 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 書籍とのセット販売 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875741
MORE -
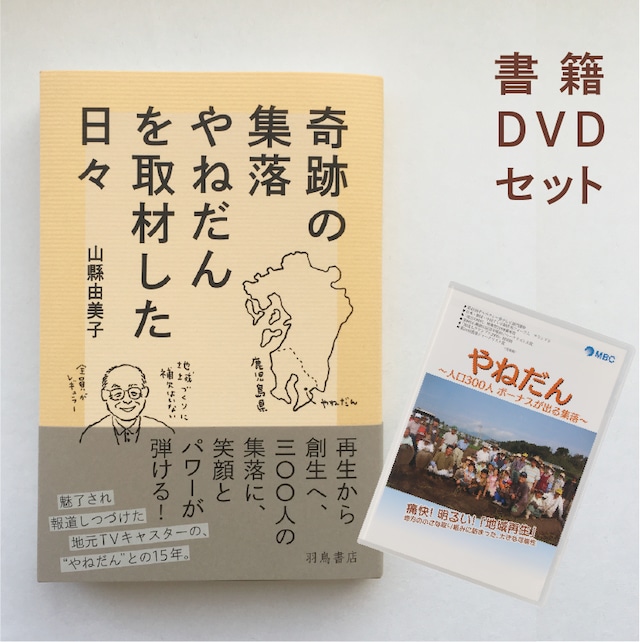
やねだん 書籍&DVDセット
¥5,200
山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』(書籍)税込2,200円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458 MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)税込3,000円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 *DVDは単品の場合に送料200円をいただきますが、セットの場合は、送料無料です。
MORE -
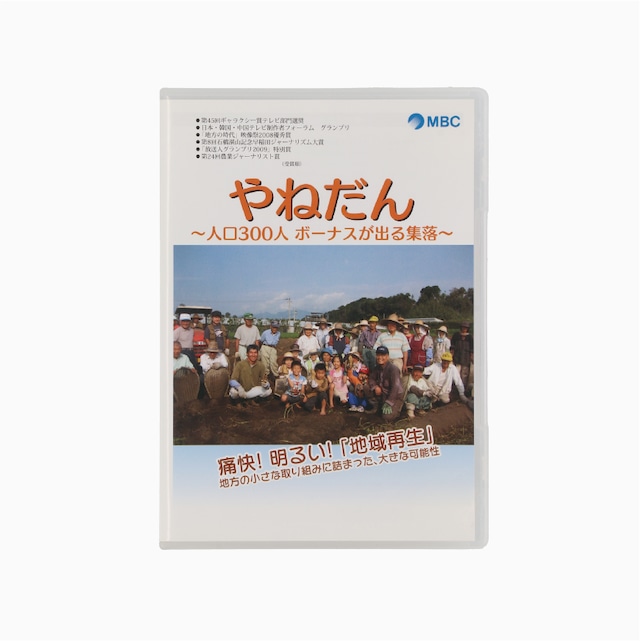
MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)
¥3,200
*本商品は、羽鳥書店刊行の山縣由美子著『奇跡の集落やねだんを取材した日々』の関連商品として、本サイトで委託販売を行なっています。 ドキュメンタリー番組 『やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落=』 南日本放送、2008年5月29日放送 (DVD:2009年3月発売) 定価:税込3000円 *本サイトでは送料200円を頂戴します。 アイデアと工夫、そして集落をあげた結束で、「限界集落」「過疎・高齢化」などの逆境をはねのけ続ける「やねだん」の、笑いと感動の12年をつづった番組。 ディレクター・ナレーション=山縣由美子 撮影=福留正倫 [受賞歴]ギャラクシー賞テレビ部門選奨、日韓中テレビ制作者フォーラム、番組コンクールグランプリ「地方の時代」映像祭優秀賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、放送人グランプリ特別賞 【公式ショップサイト】 南日本放送 MBCショップサイト https://www.mbc.co.jp/tokusen/yanedan/ -------------------------------------------------------------------- 山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458
MORE -

工藤庸子『女たちの声』
¥2,640
B6判 上製 200頁 本体価格2,400円+税 ISBN 978-4-904702-77-2 C0095 2019年6月刊行 ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 〈言語環境〉に潜む、性差の力学を問う。スタール夫人、ラーエル・ファルンハーゲン、ハンナ・アレント、ボーヴォワール、マルグリット・デュラス、コレット、ヴァージニア・ウルフ──。羽鳥書店HPで連載された「人文学の遠めがね」15編と、書下ろし100枚、「〈声〉と〈書くこと〉をめぐって」を収録。 工藤庸子 字幕監修 映画『コレット』5月17日より全国ロードショー *コレット『シェリ』『シェリの最後』『牝猫』(岩波文庫、工藤庸子訳)が復刊! https://colette-movie.jp/ ▶︎目次 人文学の遠めがね I ベンジャミン・フランクリンの恋文 その一 II ベンジャミン・フランクリンの恋文 その二(KYのメモ) III 二本のネクタイ あるいは男女格差について Ⅳ 性差のゆらぎ Ⅴ 両性具有──排除的分類ではなく VI わたしたちの社会的アイデンティティを剥奪しないでください──選択的夫婦別姓 VII 女たちの声 VIII 続・女たちの声──六七年の記憶 IX 「性愛」と「おっぱい」 X 元祖は皇帝ナポレオン? XI 大江健三郎と女性(一)── contemporaineであるということ XII 大江健三郎と女性(二)── 政治少年のéjaculation XIII 大江健三郎と女性(三)──「全小説」とfictionとしての「小説家」 XⅣ 女のエクリチュール XⅤ ゼラニウムの微かに淫靡な匂い──続・女のエクリチュール 〈声〉と〈書くこと〉をめぐって──デリダ/スタール夫人/アレント 何を、どんなふうに語ればよいのか…… 〈女のエクリチュール〉とは?──デュラスの方へ 〈エクリチュール〉は女?──デリダの〈尖筆〉とフローベールの手紙 サロンの会話とスタール夫人の〈声〉──〈公共圏/親密圏〉の二元論に抗して (Auto)biography を書く──アレント『ラーエル・ファルンファーゲン』 アレントの〈言論(スピーチ)〉とは?──『人間の条件』 「あとがき」にかえて ▶︎プロフィール 工藤庸子(くどうようこ) フランス文学、ヨーロッパ地域文化研究。東京大学名誉教授。著書に、『ヨーロッパ文明批判序説──植民地・共和国・オリエンタリズム』『近代ヨーロッパ宗教文化論──姦通小説・ナポレオン法典・政教分離』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ──フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母』(いずれも東京大学出版会)、『政治に口出しする女はお嫌いですか?──スタール夫人の言論vs.ナポレオンの独裁』(勁草書房)。訳書に、『いま読むペロー「昔話」』訳・解説(羽鳥書店)、コレット『シェリ』(岩波文庫)。編著に『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)、共著に『〈淫靡さ〉について』(蓮實重彥、羽鳥書店)。他、多数。 ▶︎担当者より http://www.hatorishoten-articles.com/hatoripress-news/6340884 ▶︎他のオンラインストアでご購入の方 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904702772
MORE -
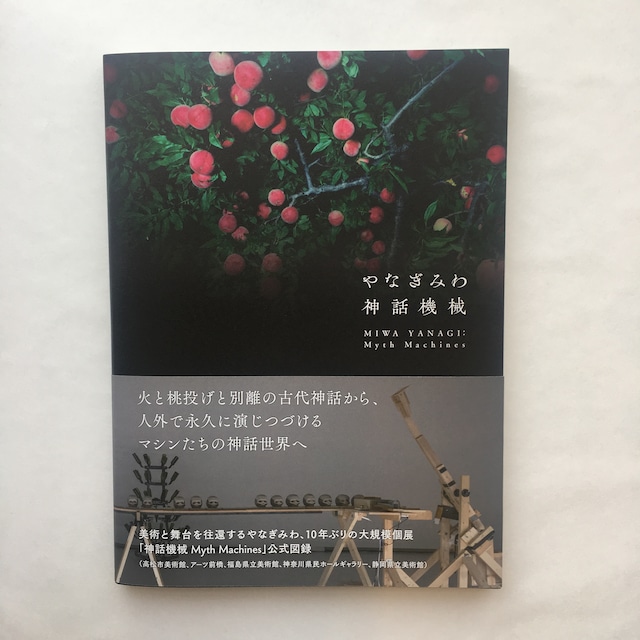
やなぎみわ『神話機械』
¥3,080
「やなぎみわ展 神話機械」 高松市美術館 2019年2月2日〜3月24日 アーツ前橋 2019年4月19日〜6月23日 福島県立美術館 2019年7月6日〜9月1日 神奈川県民ホールギャラリー 2019年10月20日〜12月1日 https://www.kanakengallery.com/detail?id=36191 静岡県立美術館 2019年12月20日〜2020年2月24日 http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/detail/57 ★公式図録 A4判変型 並製 128頁 本体2,800円+税 ISBN 978-4-904702-76-5 C1071 2019年3月刊行 ブックデザイン:木村三晴 【終了イベント】 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎概要 火と桃投げと別離の古代神話から、人外で永久に演じつづけるマシンたちの神話世界へ。 美術と舞台を往還するやなぎみわ、10 年ぶりの大規模個展「神話機械 Myth Machines」公式図録(高松市美術館、アーツ前橋、福島県立美術館、神奈川県⺠ホールギャラリー、静岡県立美術館)。 福島の桃を撮影した新作シリーズ〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉や、自動で演じつづけるマシン4機がつくりあげる演劇空間《神話機械》の会場写真を中心に、これまでの代表作や演劇アーカイブなどの資料も充実。 ▶︎目次 作品 Works 演劇アーカイブ Theatrical Archives 作品一覧 List of Works テキスト 「乗り入れの箱」毛利直子(高松市美術館学芸員) 「桃と境界をめぐって」荒木康子(福島県立美術館学芸員) 「折口信夫、中上健次、やなぎみわ──「うつほ」の共振」安藤礼二(文芸評論) 「遊行する機械──やなぎみわのステージトレーリング計画」高山 宏(視覚文化論) 略歴 Biography 主要文献目録 Bibliography ▶︎プロフィール やなぎみわ 1967年神戸市生まれ。1991年京都市立芸術大学大学院(工芸専攻)修了。1990年代半ばより、若い女性をモチーフにCGや特殊メークを駆使した写真作品を発表し、とりわけ、制服を身につけた案内嬢たちが商業施設空間に佇む〈エレベーター・ガール〉、2000 年より女性が空想する半世紀後の自分を写真で再現した〈マイ・グランドマザーズ〉、少女と老婆が登場する物語を題材にした〈フェアリー・テール〉シリーズ等により世界的な評価を受ける。2009年第53回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表、2010年より演劇プロジェクトを始動。大正期の日本を舞台に新興芸術運動の揺籃を描いた『1924』三部作(2011–2012)を美術館と劇場双方で上演し話題を集めた。あいちトリエンナーレ2013にて上演した『ゼロ・アワー 東京ローズ最後のテープ』は2015年アメリカ・カナダ数か所を巡回した。ヨコハマトリエンナーレ2014を皮切りにステージトレーラー・プロジェクトが立ち上がり、2016年には野外劇『日輪の翼』(原作:中上健次)となって横浜・新宮・高松・大阪・京都への移動公演を行った。2018年高雄市立美術館(台湾)の国際企画展に招待され、新作写真〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉等を発表した。
MORE -

岡口基一『裁判官は劣化しているのか』
¥1,980
四六判 並製 168頁 本体1,800円+税 ISBN 978-4-904702-74-1 ブックデザイン:小川順子 装画:鈴木ゴウ ▶︎パブリシティ 『週刊プレイボーイ』2019年3月18日(no.13)「"本"人襲撃 BOOK」 『週刊文春』2019年4月25日号 評者:唐澤貴洋(弁護士) 「少数者の権利が多数決の専横から守られる社会であるために、司法制度がどうあるべきか、我々は考えていく必要があるはずだ。著者の情報発信が今必要とされている。」 https://bunshun.jp/articles/-/11561 『週刊ポスト』2019年4月26日号 評者:岩瀬達哉(ノンフィクション作家) 「岡口基一判事が綴る裁判所の統制と萎縮」 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190420-00000015-pseven-life 『ハイローヤー』2019年6月号 ブックレビュー 「日本の裁判所について、この上なく真面目に論じた本である」「法曹を目指す者としては、要件事実の入門書としても読める」 『月刊税理』2019年5月号 ブックレビュー 『AERA』2019年5月20日号 評者:野上由人(リブロ) 「裁判官教育制度の問題点をするどく指摘」 『月刊税理』2019年6月号 岡口基一「ゼロからマスターする要件事実」第42回「裁判官は劣化しているのか」 『法学セミナー』2019年7月号 新刊ガイド 「司法を愛するがゆえのダメ出し」 ▶︎レビュー https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214068935542044&set=a.4454305320370&type=3 http://www.fben.jp/bookcolumn/2019/03/post_5717.html https://ameblo.jp/ivorygrin/entry-12444212490.html ▶︎概要 裁判所の内部で何が起こっているのか? 現役判事による異色のエッセイ。裁判官の「智」を支えるシステムを、自らの経験をもとに解説。国民が知るべき裁判所・裁判官の世界を分かりやすく紹介する。 ▶︎目次 プロローグ 1章 思い出話を通じて昔の裁判所を知ろう 寺子屋と要件事実マニュアル/25年前の裁判所/対照的であった東京地裁と1人支部/ホームページと要件事実マニュアル/刑事裁判官から家事裁判官へ/人気サイトの閉鎖の理由/基督において一つになる 2章 昔の裁判官の「智」を支えたシステムを知ろう 請求権の物語/主張しなければ負けというルール/学界と実務界との間にある「ものすごく深い溝」/「智」の結集/ガラパゴス要件事実/司法研修所の要件事実/要件事実教育 3章 裁判官を劣化させる要因を知ろう 裁判官の劣化が疑われている/飲みニケーションの消滅/旧様式判決から新様式判決へ/「要件事実」教育/議論が苦手なコピペ裁判官/ハマキョウレックス判決の衝撃/ようやく動き出した裁判所当局 4章 裁判官を劣化させない方策を考えよう 全てを背負わされた裁判長/何も教わっていない裁判官もいる/司法修習中に勉強しておくしかない/司法の本質論・役割論を裁判官に理解させる あとがき ▶︎著者プロフィール 岡口基一(おかぐち きいち) 1966年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事を経て、現在、東京高等裁判所判事。 著書に、『要件事実入門』(創耕舎、2014年)、『民事訴訟マニュアル──書式のポイントと実務 第2版(上下)』(ぎょうせい、2015年)、『要件事実問題集[第4版]』(商事法務、2016年)、『要件事実マニュアル 第5版 全5巻』(ぎょうせい、2016-2017年) 、『裁判官! 当職そこが知りたかったのです。──民事訴訟がはかどる本』(中村真との共著、学陽書房、2017年)、『要件事実入門(初級者編) 第2版』(創耕舎、2018年)。
MORE -
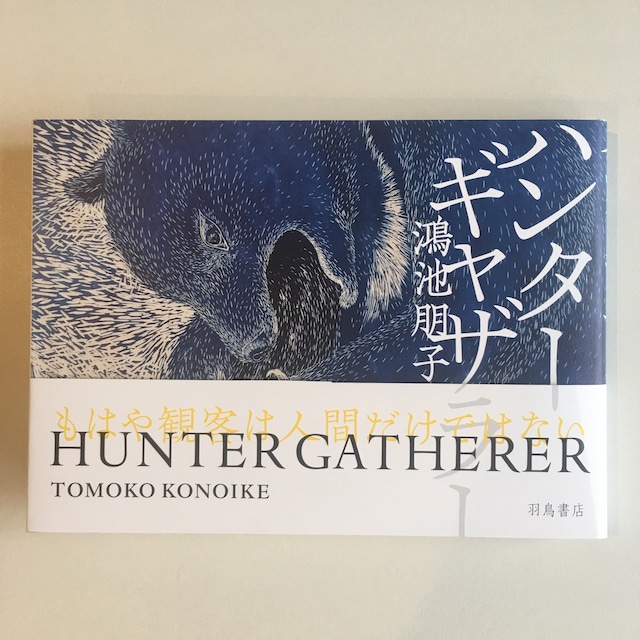
鴻池朋子『ハンターギャザラー』
¥3,080
▼体裁 A5判ヨコ 上製 128頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-73-4 C1071 2018年11月刊行 写真:永禮 賢 ブックデザイン:小川順子 秋田県立近代美術館「鴻池朋子 ハンターギャザラー」展 2018年9月15日〜11月25日 https://www.akita-abs.co.jp/konoike/ もはや観客は人間だけではない 奥羽山脈に響くうたに乗って 鴻池の侵犯はさらにつづく 自然との摩擦からおこす 確かなエネルギー変換へ ▼概要 現代アーティスト、鴻池朋子の最新作品集。 獲物を捕り料理する、木を伐採し石を積み家にする、モチーフを集め絵画にする。ハンターギャザラー(狩猟採集民)として人間は、自然を人間界へ引きずり込む方向のみへと文化を発展させてきた。この〈原型〉をいかに解体、転換できるか。 喰う動物たちの姿を描いた幅8m×高さ6mのカービング(板彫り絵画)、東北で害獣駆除された動物たちの毛皮と山脈の空間「ドリーム ハンティング グラウンド」などの新作を収録。 [目次] ロンドンのカレー屋で 村井まや子(対談) 木枠のなかで宗教を想う 江川純一 かたどる 三浦佑之(対談) かかとに棲む狼 鴻池朋子 呪文/山に食べられる/竜巻/毛皮/啼き声/トンビ/刺しては縫う物語/宝と棺/海にのまれ/見る人よ何を見ている/1といっぱい/大切なことは言葉にしない 地球にぶたれる 鴻池朋子 ハンターギャザラー 鴻池朋子 Hunter Gatherer Tomoko Konoike 展覧会記録 作品一覧 List of Works ▼プロフィール 鴻池朋子(こうのいけ・ともこ) 美術家。1960年秋田県生まれ。様々なメディアでトータルインスタレーションを行い、芸術の問い直しを試みている。近年では2016年「Temporal Turn」スペンサー美術館・自然史博物館(カンザス大学)、2017年「Japan-Spirits of Nature」アクバラル美術館(スウェーデン)、2018年「Kalevala」ケラバ美術館(フィンランド)など。個展は2009年「インタートラベラー 神話と遊ぶ人」東京オペラシティ、2015年「根源的暴力」神奈川県民ホール、2018年「Fur Story」 Leeds Arts University(イギリス)など。現在、秋田県立近代美術館にて「鴻池朋子 ハンターギャザラー」を開催中。 [著書]『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(2009年)、『焚書 World of Wonder』(2011年)、『根源的暴力』(2015年)、『どうぶつのことば 根源的暴力をこえて』(2016年)、いずれも羽鳥書店刊。
MORE -
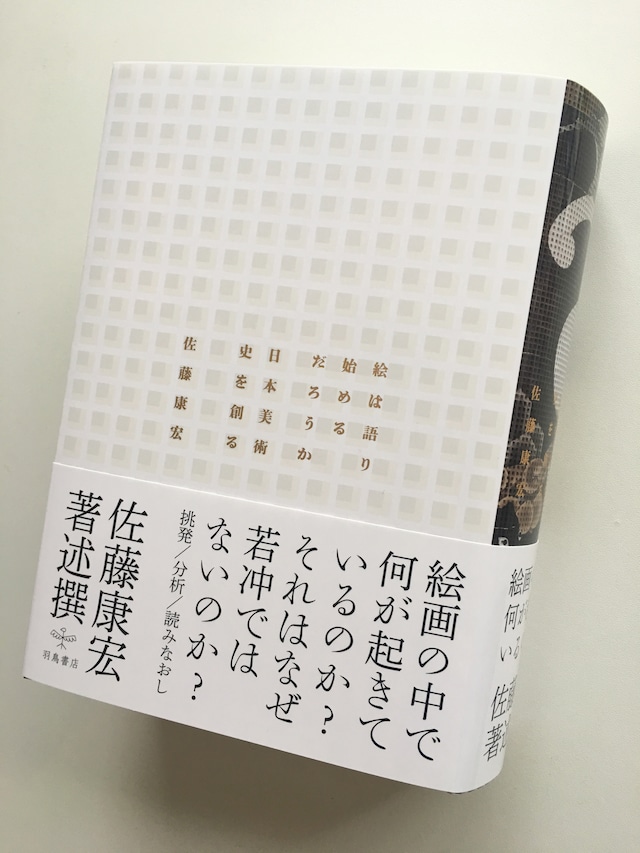
佐藤康宏『絵は語り始めるだろうか──日本美術史を創る』
¥13,200
▼体裁 A5判 上製 960頁 本体価格 12,000円+税 ISBN 978-4-904702-72-7 C0071 2018年12月刊行 ブックデザイン:白井敬尚形成事務所(白井敬尚・江川拓未) ▼概要 絵画の中で何が起きているのか? それはなぜ若冲ではないのか? 佐藤康宏著述撰 挑発/分析/読みなおし 「絵は語り始めるだろうか」(1993年)以降20余年の間に発表した論考のなかから31編を〈どういえばいいのだろう〉〈記述と鑑識〉〈語りなおす〉〈批評と翻訳〉の4部構成にまとめる。すべての論考の末尾には「後記」(短い解題、補註)を付す。図版402点掲載。 ▼目次 どういえばいいのだろう 1 絵は語り始めるだろうか 2 中国絵画と日本絵画の比較に関する二、三の問題──戸田禎佑『日本美術の見方』を受けて 3 日本絵画の中の文字 4 境界の不在、枠の存在──日本美術について私が知っている二、三の事柄 5 つなげて見る──「名作誕生」展案内 6 連想・日本美術史附 宣伝文二題 記述と鑑識 7 ディスクリプション講義 8 若冲という事件 9 真贋を見分ける──江戸時代絵画を例に 10 若冲・蕭白とそうでないもの 11 プライス本鳥獣花木図が若冲の作ではないこと──辻惟雄氏への反論 語りなおす(1) 12 室町の都市図 13 高雄観楓図論 14 南蛮屛風の意味構造 15 又兵衛風諸作品の再検討 16 物語絵の伝統を切断する──岩佐又兵衛「梓弓図」 17 見返り美人を振り返る 18 江戸の浮世絵認識 語りなおす(2) 19 中国の文人画と日本の南画 20 戦略としてのアナクロニズム──明末奇想派と曾我蕭白 21 蕭白のいる美術史 22 雨後の菡萏──渡邉崋山「芸妓図」を読む 23 雅の断末魔──菊池容齋「呂后斬戚夫人図」 24 近代の日本画──前近代の眼で 25 小林清親の東京名所図──「海運橋」を中心に 批評と翻訳 26 文化庁の仕事──見えない博物館 27 国立博物館・美術館等の独立行政法人化問題──美術史学会からのアピール 28 放送大学試験問題文削除事件 29 書評・選評 30 ノーマン・ブライソン著 佐藤康宏訳「言説、形象──『言葉とイメージ』第一章」 31 ノーマン・ブライソン著 佐藤康宏訳「身体を西洋化する──明治洋画における女性・美術・権力」 作品名索引 人名索引 図版一覧 あとがき──日付のある文章の後に ▼著者プロフィール 佐藤康宏(さとう やすひろ) 1955年、宮崎県生まれ。東京大学文学部美術史学専修課程卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了。東京国立博物館学芸部資料課文部技官、文化庁文化財保護部美術工芸課文化財調査官(絵画部門)、東京大学文学部助教授(美術史学専修課程)を経て、現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。 日本美術史、特に室町時代から江戸時代初期にかけての風俗画、若冲・蕭白と南画を中心とする江戸時代絵画を専門とする。絵画に隠された意味の構造を読み解き、美術作品と社会状況との関連を追う。 『講座 日本美術史』(全6巻、東京大学出版会、2005年)の編集・執筆を手がけたほか、著書に『若冲・蕭白』(小学館、1991年)、『歌麿と写楽』『祭礼図』(至文堂、1996年、2006年)、『浦上玉堂』(新潮社、1997年)、『もっと知りたい伊藤若冲』(東京美術、2006年、改訂版2011年)、『改訂版 日本美術史』(放送大学教育振興会、2014年)、『湯女図──視線のドラマ』(平凡社、1993年。ちくま学芸文庫、2017年)など。論文「蕭白新論」(『新編名宝日本の美術27 若冲・蕭白』、小学館、1991年)で第四回國華賞を受賞。著書『絵は語る11 湯女図──視線のドラマ』(平凡社、1993年)で第6回倫雅美術奨励賞を受賞。
MORE -
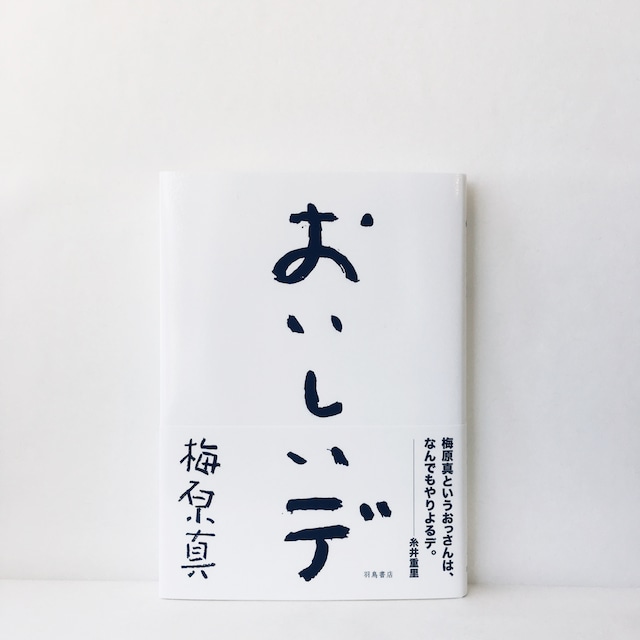
梅原真『おいしいデ』
¥3,080
A5判・並製・272頁・オールカラー 2018年6月末頃刊行 本体2,800円 ISBN 978-4-904702-71-0 C0070 基本デザイン:梅原真 デザイン協力:原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『LITTLE』第1号 2018年8月20日(イオグラフィック発行) 「‥‥梅原さんは(中略)、売りに困っている生産物をおいしく加工のアイディアも出し、おいしいパッケージとおいしいネーミングでたくさん送り出してこられました。このご本をめくりながら改めてまっすぐな好もしい人だと思います。」(大橋 歩) 『高知新聞』 2018年7月15日書評(評・竹内一/高知新聞社学芸部) 『ブレーン』2018年9月号 エディターズブックセレクト ・共同通信からインタビュー記事が配信され(8/6)、21紙に掲載。 ・ラジオJ-Wave「BOOK BAR」(8/25放送)で紹介(大倉眞一郎さん)。 https://www.j-wave.co.jp/blog/bookbar/book_info/ ・ブックサイト「好書好日」にインタビュー掲載(9/12)https://book.asahi.com/article/11809948 ▼概要 梅原真というおっさんは、なんでもやりよるデ ─── 糸井重里 梅原真が「おいしいデザイン」とその秘訣を絶妙な語り口で書き下ろし、カラー写真とともに一挙公開する破格のデザイン書。 ローカルの一次産業のデザインを長年てがけ、 “考え方”そのものを変えるところからデザインし、マイナスをプラスに転換して「あたらしい価値」を生み出してきた梅原真。デザインワークを初めて収めた前著『ニッポンの風景をつくりなおせ── 一次産業×デザイン=風景』が刊行された2010年以降、NHK「プロフェッショナル」などでも紹介されて注目を集め、高知だけでなく全国から依頼が舞い込む事態に。にわか依頼をどんどん断りながらも、しかし、心揺さぶるひたむきな生産者に出会えば、どうにかせないかんと発奮し、ときに叱りとばしつつ、ユーモアで包み込む「おいしいデザイン」で消費者との間を見事につないでいく。 「デザインは経営資源」と説き、「土地の力を引き出すデザイン」をテーマとする梅原のゆるぎない物差しからは、地域再生のためのヒントもたくさん。 「デザインは問題解決ソフト」、「デザイナーとは問題解決人」と言い切る梅原が、海から山へ、里から街へと奔走し、“絶体絶命”の淵にいる生産者の志に応えていく──瀬戸内の島で一家総出の手作業で加工されたいりこ、口蹄疫で打撃をうけた養豚場の手塩にかけた加工品、有機飼料と広い飼育環境にこだわった鶏の卵、老舗和菓子屋の新たな試みを後押しする最新の仕事も含め、本書では26の仕事を紹介。前著でも紹介された、一本釣りカツオ漁の風景を守った「漁師が釣って 漁師が焼いた」藁焼きたたきや、衰退していた四万十の栗をもりかえした「しまんと地栗」などのさらなる展開も収録。 [主要目次] まえがきがわりのインタビュー くり/いりこ/ぶた/きびなご/おちゃくり/かつお/マッシュルーム/煎り酒/たまご/アイス/なっとう/山田まん/紅茶/新聞/ひがしやま/なまこ/土左日記/岩がき/ひもの/ところてん/もも/ふるさとの台所/摘み草 ひのき/ロール/うどん/竜馬 梅原真とニッポン 原研哉 あとがき *詳細目次は以下を参照(見出しを総覧するのも面白いです) http://www.hatorishoten-articles.com/newbook/6367550 ▼刊行記念トークイベント 「“絶体絶命”のデザイン」 *終了しました 梅原真 × 畦地履正 トークイベント 2018年7月22日(日)14時〜 青山ブックセンター本店・大教室 参加費 1,350円(税込) http://www.aoyamabc.jp/event/desperate/ ▼プロフィール デザイナー。高知市生まれ。放送局の美術スタッフとして勤務後、1980年よりフリーランス。高知というローカルに拠点を置き「一次産業× デザイン=風景」という方程式で活動する。かつおを藁で焼く「一本釣り・藁焼きたたき」。柚子しかない村から「ポン酢醤油・ゆずの村」。荒れ果てた栗の山から「しまんと地栗」。世界中どこにでもある新聞から「しまんと新聞ばっぐ」。高知県の森林率84%をおもしろがる「84はちよんプロジェクト」。離島、海士町のアイデンティティ「ないものはない」。そして砂浜しかない町に「砂浜美術館」のプロデュース。「土地の力を引き出すデザイン」で2016毎日デザイン賞・特別賞受賞。武蔵野美術大学客員教授。 2018年6月27日 初版 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣
MORE -
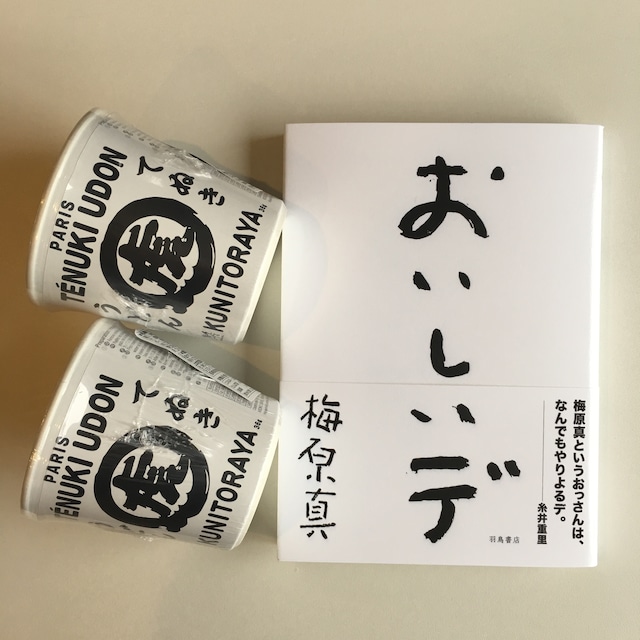
おいしいデ+てぬきうどん2個 限定セット
¥3,768
SOLD OUT
★ 高知とパリのうどん店 国虎屋と、最上級の鰹節をつくりつづける老舗 林久右衛門商店とのコラボ商品「てぬきうどん」が発売に ★ <送料無料|別々に買うよりもちょっとお得> 梅原真さんの『おいしいデ』では、パリに初めて店を出したうどん屋として、高知の国虎屋が紹介されています。 「2017年冬のある日、パリのうどん屋の主人、野本将文さんから携帯にボンジュールと電話がかかってきた。いつものゆっくりとした喋り方で「梅ちゃんの真似をして考えてみた。インスタントのてぬきうどんを作りたいがよ」という。」 本のなかでは、商品開発中で、デザインができあがったくらいのことまでが収録されています。 「パリの国虎屋うどんは、パリで毎日打っているが、フリーズドライの即席「てぬきうどん」はオールジャパン体制で、味はオリジナルで看板の「国虎うどん」の味付けだ。ベースとなる鰹節、いわし削り節、宗田鰹節、ゆず皮、酒粕、味噌など、ふるさと高知の素材が中心で、小麦も醤油もすべて日本国産。それをパリからヨーロッパに向かって発売する。」 この「てぬきうどん」がいよいよ発売となりました。製造は鰹節の老舗・林久右衛門商店。ただし、商品はフランス向けに製造されており、国内では、高知・国虎屋と林久右衛門商店の直営店等、限られたところでしか購入できません。 「てぬきうどん」の詳細はこちらから *林久右衛門商店オンランショップ https://kyuemonshop.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&dpcnt=60&cat=001014 そこで、この出来たての「てぬきうどん」を『おいしいデ』とセットにして限定販売いたします! 『おいしいデ』をまだ読んでいない方への贈り物としてもぜひ!!
MORE -
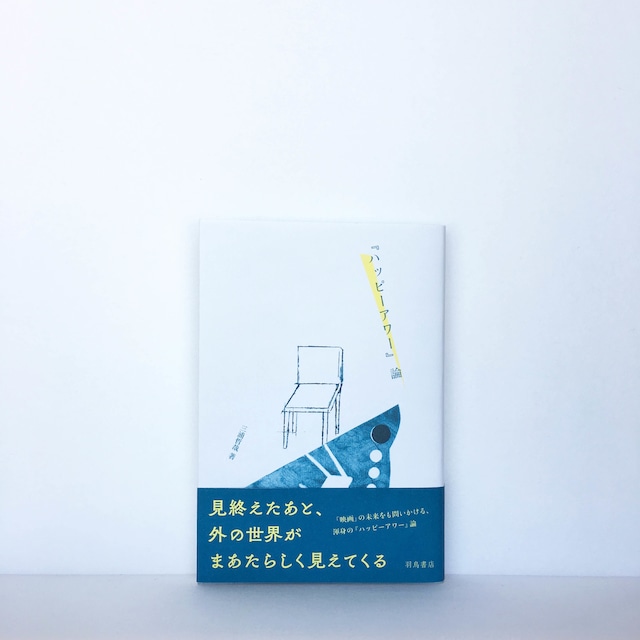
三浦哲哉『『ハッピーアワー』論』
¥2,420
SOLD OUT
四六判 並製 178頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-70-3 C0074 2018年5月刊行 装幀:小川順子 装画:山本由実 ひたすらな孤立をあえて選択することで、無限に開かれたコミュニケーションを奇跡のように押し拡げてみせた濱口竜介の『ハッピーアワー』の美しさ。その美しさをあえて言葉にしようとする三浦哲哉の『「ハッピーアワー」論』のひたすら無謀な情熱。そのありえない出会いのさきに、濱口の傑作『寝ても覚めても』による無謀さの擁護が、すでに終わりかけている平成日本の目には見えない焦点を、ひそかに、だが鋭く、視界に浮上させている。 ────蓮實重彦(映画評論家) ▼概要 見終えたあと、外の世界がまあたらしく見えてくる。 映画批評家・三浦哲哉による、渾身の『ハッピーアワー』論。 濱口竜介監督の5時間17分におよぶ話題作『ハッピーアワー』(2015年)。その異例ともいえる上映時間にこめられた密度の濃い映画的仕組みを、丁寧かつスリリングに解き明かし、映画史の中に位置づける。書下し。 [主要目次]*詳細目次はページ下を参照 序 第一章 重心 第二章 台詞 第三章 変化 結論 『ハッピーアワー』のあとに見たい映画リスト ▼映画『ハッピーアワー』公式サイト 最新情報はこちらよりご確認ください。上映会情報も。 *上映会 5月12日(土)15時30分〜、26日(土)11時30分〜 会場:ブックハウスカフェ http://hh.fictive.jp/ja/ ▼刊行記念トークイベント 三浦哲哉×濱口竜介「『ハッピーアワー』という幸福な時間」 5月24日(木)19時〜 エスパス・ビブリオ *満員御礼にて終了 http://espacebiblio.superstudio.co.jp/?p=6695 ▼プロフィール 青山学院大学文学部准教授。映画批評・研究、表象文化論。1976年郡山市生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了。著書に『サスペンス映画史』(みすず書房、2012年)、『映画とは何か──フランス映画思想史』(筑摩選書、2014年)。共著に『ひきずる映画──ポスト・カタストロフ時代の想像力』(フィルムアート社、2011年)、『オーバー・ザ・シネマ 映画「超」討議』(石岡良治との共編著、フィルムアート社、2018年)。訳書に『ジム・ジャームッシュ・インタビューズ──映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』(東邦出版、2006年)。 2018年5月17日 初版 印刷・製本 大日本法令印刷 [詳細目次] 序 第一章 重 心 物語の要約 「心理表象主義」を超えて 「重心」 鵜飼のワークショップ サスペンス なぜ倒れるのか テーブルを挟んだ対面状態 純の試練 有馬温泉の四人 芙美の孤立 桜子の揺らめき あかりの模索 第二章 台 詞 「台詞が演者をサポートする」──『東京物語』の原節子 純と「せやな」 桜子と「わからへん」 あかりと「なんやねん」 芙美と「これか」 拓也と「まじか」 良彦と「どうすんねん」 鵜飼と「聞いてもいいですか?」 柚月と「すいません」 『ハッピーアワー』の言語 第三章 変 化 「自己認識」の変化 セルフモニタリング 撮影現場におけるセルフモニタリング=「自己吟味」 朗読会とその打ち上げにおける変化の連鎖 朗読会のアドリブ フィクションの開口部 さまざまな「好き」 公平の変化 交わらなさ 「もう遅い」と「まだ途中」 芙美の変化 結論 『ハッピーアワー』のあとに見たい映画リスト』 註 あとがき
MORE -
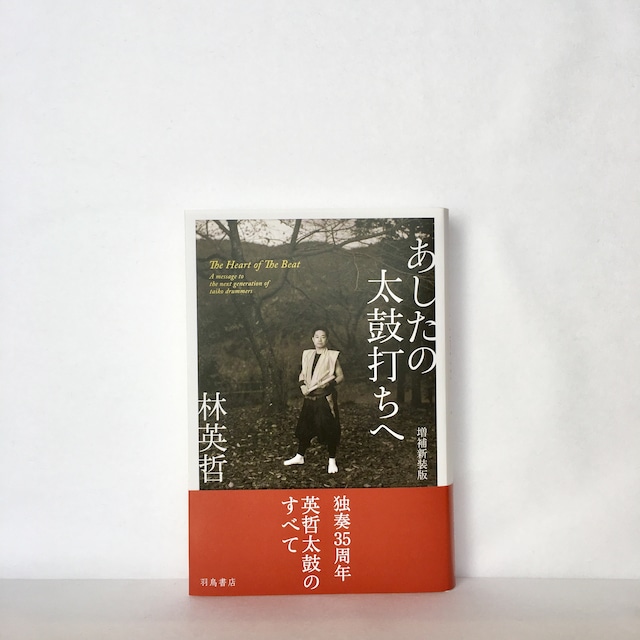
林英哲『あしたの太鼓打ちへ 増補新装版』
¥2,860
四六判 上製 306頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-68-0 C0073 2017年10月下旬刊行 ▼書評・記事 朝日新聞「仕事力 「どこにでも生きる道はある」林 英哲が語る仕事(全4回) http://www.asakyu.com/column/?id=1820 ▼概要 独奏35周年 英哲太鼓のすべて 書下ろし「太鼓打つ子ら」、ジャズピアニスト山下洋輔との対談「ぼくらがこうして出会うまで」、秘蔵写真を新たに収録。 新しい和太鼓史を創始した林英哲が、未来の太鼓打ちへ捧ぐ── 独自に開拓した奏法・打法をつまびらかにした唯一無二の「太鼓論」をはじめ、「太鼓談」「太鼓録」、自伝「太鼓記」を収めた決定版。 ▼目次 Ⅰ 太鼓論 その一 僕に流儀はない その二 記憶が肉体になる その三 太鼓を打つ意志 その四 無意識を獲得する その五 練習について その六 定型のない表現 その七 リズムと生理 その八 右手と左手 その九 大太鼓が打てるまで その十 屋台囃子の誕生 その十一 無法松と僕 その十二 命の本音 その十三 聞こえる音、聞こえない音 その十四 人が月になる時 その十五 単色の虹 その十六 非日常的肉体 その十七 女性と太鼓 その十八 バチについて その十九 人は服で決まる その二十 道具を工夫する その二十一 聴衆論 Ⅱ 太鼓談 ジャズピアニスト・山下洋輔さんと語る──ぼくらがこうして出会うまで 加賀浅野家・浅野昭利さんに聞く──太鼓作りの証言 Ⅲ 太鼓録 自分だけ大変なわけじゃない ボストン、そしてニューヨーク 父の場所 一九七五・四月 to 一九九五・九月 今世紀最後、大興奮ドイツ・ソロツアー 長い長い夏の旅 ハヤシ、ヤマシタ! さまざまな風を受けながら 還暦御礼 ナント、狂乱の日々 「風雲の会」誕生──風雲を巻き起こす英傑と弟子 Ⅳ 太鼓記 こうして僕は太鼓打ちになった 「太鼓打つ子ら」──立ち向かう、未来の太鼓打ちへ 独奏三十五周年のあとがき ▼著者プロフィール 林 英哲(はやし えいてつ) 太鼓奏者。11年のグループ活動を経て、1982年太鼓独奏者として活動を開始。84年初の和太鼓ソリストとしてカーネギーホールにデビュー、国際的に高い評価を得る。以後、太鼓独奏者としてロック、ジャズ、現代音楽、民族音楽などの演奏家と共演しながら、かつての日本の伝統にはなかったテクニックと体力を要する大太鼓のソロ奏法の創造、多種多様な太鼓群を用いた独自奏法の創作などジャンルを超越した、全くオリジナルな太鼓表現を築きあげる。2000年にはドイツ・ワルトビューネでベルリン・フィルと共演、2万人を超える聴衆を圧倒させるなど、日本から世界に向けて発信する新しい「太鼓音楽」の創造に取り組み続け、国内外でますます活躍のフィールドを広げている。1997年芸術選奨文部大臣賞、2001年日本伝統文化振興賞、2017年松尾芸能賞大賞を受賞。 公式HP http://eitetsu.net
MORE -

鴻池朋子『Tornado Hunting』(委託販売品)
¥1,650
SOLD OUT
★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNがついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 A4判 並製 22頁 オールカラー 本体価格1500円+税 発行:ミミオスタジオ 2017年10月 鴻池朋子の米国カンザスでの、旅と展覧会の様子が、写真とテキストの冊子となりました。 「Temporal Turn 現代アジアにおける芸術と思索」展 カンザス大学スペンサー美術館(アメリカ) 2016年11月10日〜2017年3月12日 (下記本文より抜粋) ...眺めていると、あるはずのない人の形がジオラマ中央に見えた。動物剥製しかいないのに、どういうわけか私はその構図の中心に人影を幻視してしまうのだ。だから展示は、試しにリアルな子どもの脚の形を鎮座させてみようと。そうしたら多分、この博物館は「完成」する。 ウインドウの中は古い合成樹脂のような化学物質の匂いがピリピリと鼻についた。そして子どもの下半身を泉の縁に腰掛けさせる。腰の断面には材質が剥製とグラデーションするように狼の毛皮を巻きつけた。すると、その場所はまるで100年もの長い間、ずっと剥製たちがこの作品のために空けておいてくれた「王座」のように見えた。うっとりする光景だろう。 ところが私は、設置後いやーな気分に取り憑かれた。博物館というものが隠喩していたことを露見させてしまったような、批判めいた哲学的な匂いが立ち込め、カラッとしないのだ。カラッとしないから、知的なセンチメンタルに引き寄せられてしまい、面白い展示なのにバカっぽい強度がでない。しかもそれを修正できない。その後も嫌な気持ちは尾を引いた。もうこういう誰かがやったような手口はやめよう。... ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/ ▼関連書 鴻池朋子 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4868936 『焚書 World of Wonder』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873345 『根源的暴力』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874177 『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4835702
MORE -

工藤庸子×蓮實重彦『〈淫靡さ〉について』はとり文庫005
¥1,430
A6判並製(文庫判) 240頁 本体価格 1,300円+税 ISBN 978-4-904702-67-3 C0095 2017年7月刊行 デザイン 原研哉+中村晋平+大橋香菜子 ▼概要 三島由紀夫賞受賞『伯爵夫人』の衝撃から1年──"作者"と、『論集 蓮實重彥』の編者が織りなす対談集。2016年7月と12月に、工藤庸子編『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)と工藤庸子『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ』(東京大学出版会)の刊行記念として行われた二つの対談。ともにフランス文学研究の第一線にあり元同僚でもある二人が、女性・フィクション・大学を軸に、近代から現代を縦横に語る。工藤庸子渾身の書下ろし『伯爵夫人』論も収録。 ▼著者 工藤庸子(くどう ようこ) フランス文学者。東京大学名誉教授。『論集 蓮實重彥』(27人の「非嫡出子」による蓮實重彥論)の編者。三部作『ヨーロッパ文明批判序説』『近代ヨーロッパ宗教文化論』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ』(2003, 2013, 2016、いずれも東京大学出版会) 蓮實 重彥(はすみ しげひこ) フランス文学者、文芸批評家、映画批評家、小説家。第26代東京大学総長、同大学名誉教授。 ▼目次 Introduction にかえて──功成り名を遂げた元総長がなぜ? というごく自然な疑問をめぐるKYの独り言 工藤庸子 【対談】『論集 蓮實重彥』についてお話させていただきます 【対談】女性・フィクション・大学──スタール夫人×伯爵夫人 伯爵夫人のために──フィクション・映画・幽霊 工藤庸子 Conclusion にかえて──ちょうどそのときたまたまそこにいてくれたことの淫靡さを言祝ぐ 蓮實重彥
MORE -
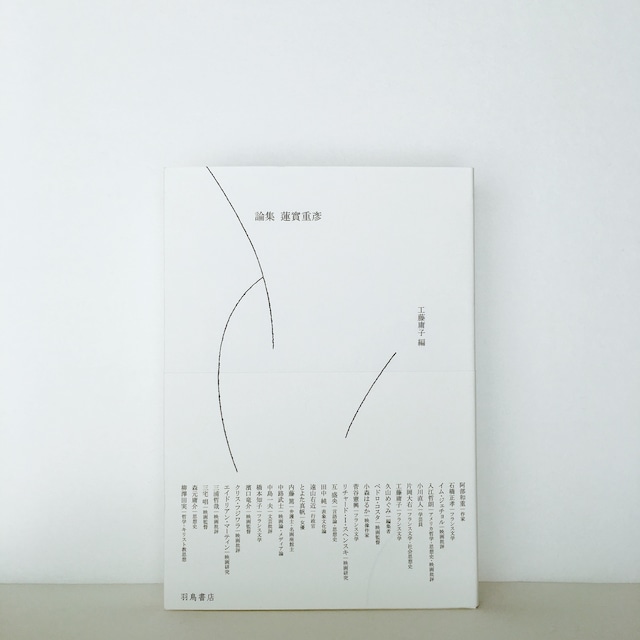
工藤庸子[編]『論集 蓮實重彦』
¥5,940
A5判 上製 640頁 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-61-1 C0095 2016年7月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『TARZAN』2016年8月11日号 「グレイストーク書店のレコメン棚トーク」今号の4冊 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-08-08 ▼概要 束になってかかってみました。 『監督 小津安二郎』、『「ボヴァリー夫人」論』、『伯爵夫人』の著者は何者なのか? 27名の「非嫡出子」による蓮實重彦論。 *特別収録 蓮實重彦「姦婦と佩剣──十九世紀フランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき」(『新潮』2014年8月号) [目次] 姦婦と佩剣──十九世紀のフランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき 蓮實重彦 ボヴァリー夫人のことなどお話させていただきます──蓮實重彦先生へ 工藤庸子 『「ボヴァリー夫人」論』では思い切り贅沢をさせていただきました──工藤庸子さんへの返信 蓮實重彦 I 義兄弟の肖像──『帝国の陰謀』とその周辺をめぐって 田中 純(表象文化論) Sign‘O’the Times――『伯爵夫人』を読む 阿部和重(作家) 批評と贅沢──『「ボヴァリー夫人」論』をめぐって 菅谷憲興(フランス文学) 「二次創作」に抗する「二次創作」──蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』の「序章 読むことのはじまりに向けて」と「I 散文と歴史」を読む 石橋正孝(フランス文学) A comme art, et ...──Aはart(芸術)のA、そして…… 橋本知子(フランス文学) 塵の教え──フィクションに関するとりとめない註記 森元庸介(思想史) さらなる「運動の擁護」へ 柳澤田実(哲学・キリスト教思想) 批評家とは誰か──蓮實重彦と中村光夫 中島一夫(文芸批評) 蓮實重彦のイマージュ、反イマージュの蓮實重彦──「魂の唯物論的擁護」とは何か 互 盛央(言語論・思想史) 「昨日」の翌朝に、「アカルイミライ」の約束もなく──蓮實重彦による「文学史」と「映画史」 片岡大右(フランス文学・社会思想史) II 蓮實教授との三時間、日本の列車の車中にて ペドロ・コスタ(映画監督) 映画からこぼれ落ちそうになる男 三浦哲哉(映画批評) 『監督 小津安二郎』の批評的事件 クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) 犯し犯される関係の破棄──曽根中生・蓮實重彦・日活ロマンポルノ 久山めぐみ(編集者) 見ることを与えられて──蓮實重彦への讃辞 エイドリアン・マーティン(映画研究) メディア化する映画──一九二〇/一九三〇年代から二〇〇〇/二〇一〇年代へ 中路武士(映画論・メディア論) 蓮實について リチャード・I・スヘンスキ(映画研究) 抽象化に対抗して──蓮實重彦の映画批評 イム・ジェチョル(映画批評) シネマとアメリカ──蓮實重彦のふたつの顔 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評) III 遭遇と動揺 濱口竜介(映画監督) 胸の高鳴りをおさえながら 三宅 唱(映画監督) 眼差しに導かれて 小森はるか(映像作家) 私は如何にして心配するのをやめて「ハスミ・シゲヒコ」の影響を脱したか 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 恩師 蓮實先生 遠山右近(行政官) 不実なる誘いにのって 小川直人(学芸員) 蓮實のおじちゃま とよた真帆(女優) 『伯爵夫人』とその著者を論じるための権力論素描──編者あとがき 工藤庸子 蓮實重彦 著書目録 *執筆者(50音順) 阿部和重(作家) 石橋正孝(フランス文学/立教大学) イム・ジェチョル(映画批評) 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評/東京大学大学院) 小川直人(学芸員/せんだいメディアテーク) 片岡大右(フランス文学・社会思想史/東京大学) 工藤庸子(フランス文学) 久山めぐみ(編集者/文遊社) ペドロ・コスタ(映画監督) 小森はるか(映像作家) 菅谷憲興(フランス文学/立教大学) リチャード・I・スヘンスキ(映画研究/バード大学) 互 盛央(言語論・思想史/講談社) 田中 純(表象文化論/東京大学) 遠山右近(行政官) とよた真帆(女優) 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 中路武士(映画論・メディア論/鹿児島大学) 中島一夫(文芸批評/近畿大学) 橋本知子(フランス文学/京都女子大学) 濱口竜介(映画監督) クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) エイドリアン・マーティン(映画研究) 三浦哲哉(映画批評/青山学院大学) 三宅 唱(映画監督) 森元庸介(思想史/東京大学) 柳澤田実(哲学・キリスト教思想/関西学院大学) ▼関連書 蓮實重彦 『「ボヴァリー夫人」拾遺』 工藤庸子 訳・解説 『いま読むペロー「昔話」』 田中純 『過去に触れる』 内藤篤『円山町瀬戸際日誌』
MORE -
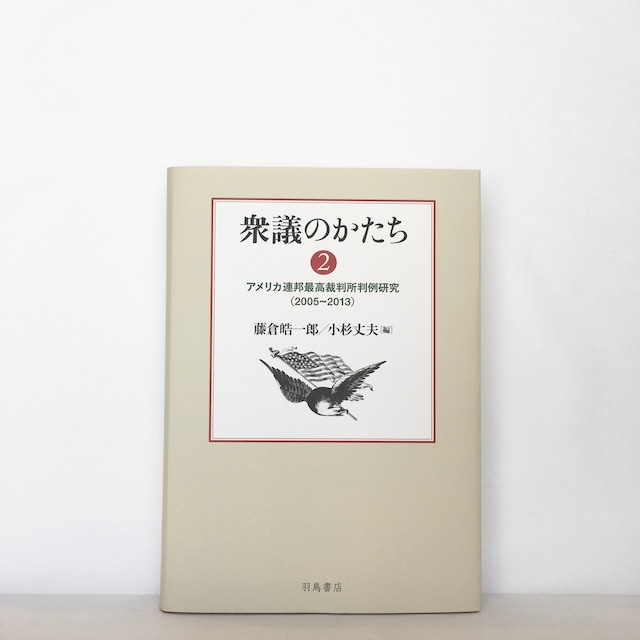
藤倉皓一郎・小杉丈夫[編] 『衆議のかたち2──アメリカ連邦最高裁判所判例研究(2005〜2013)』
¥6,820
A5判・上製・376頁 本体価格 6,200円+税 ISBN 978-4-904702-66-6 C3032 2017年7月刊行 日本の法律家が新しい判例の意義を問う、アメリカ法研究の最前線。 英米法研究者・法曹からなる岡原記念英米法研究会によるアメリカ連邦最高裁判所の判例評釈集。第1巻(東京大学出版会刊)はレーンクイスト・コートの後半約10年間の最高裁判例を扱ったが、第2巻はロバーツ・コートの8年間が対象。アメリカ社会の激しい動きに対応した、医療保険改革法についての「オバマケア事件判決」、同性婚の合憲性に関する「DOMA事件判決」など32件収録。
MORE -
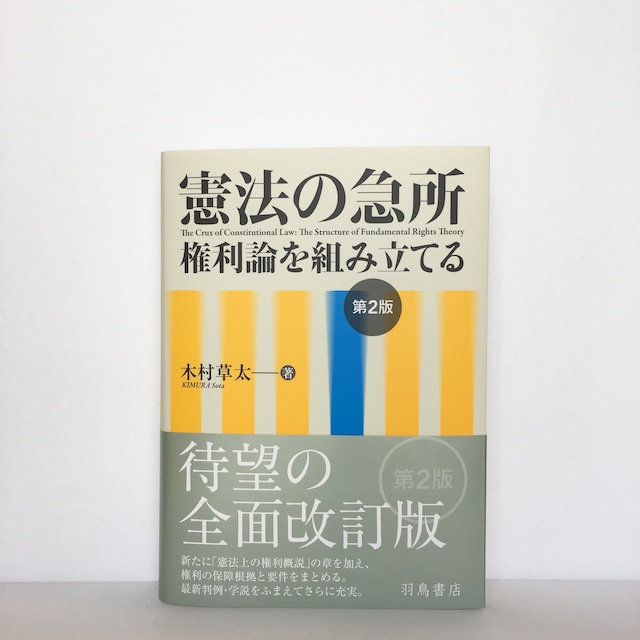
木村草太『憲法の急所──権利論を組み立てる 第2版』
¥3,520
A5判 並製 440頁 本体価格 3,200円+税 ISBN 978-4-904702-65-9 C3032 2017年3月刊行 装幀 馬面俊之 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 待望の全面改訂版。新たに「憲法上の権利概説」の章を加え、権利の保障根拠と要件をまとめる。最新判例・学説をふまえてさらに充実。 判例ベースの主要論点を網羅した演習問題を素材に、具体的な議論の組み立て方を説明し、著者による論証例を付す。法科大学院生・学部上級生に必携の演習書。 [主要目次] I 講義編 憲法上の権利の知識と手順 第1章 憲法上の権利の基礎知識 第1節 憲法上の権利の概念と分類 第2節 自由権の基礎知識 第一款 防御権 第二款 特定行為排除権 第3節 請求権の基礎知識 第4節 平等権の基礎知識 第2章 憲法上の権利の基本手順 第1節 自由権の基本手順 第一款 防御権の基本手順 第二款 特定行為排除権の基本手順 第三款 自由権の競合 第2節 請求権の基本手順 第3節 平等権の基本手順 第4節 まとめ 第3章 憲法上の権利概説 第4章 私人間効力論 II 演習編 権利論を組み立てる 第5章 精神的自由権 第1問 国歌起立斉唱拒否事件 第2問 水泳受講拒否事件 第3問 月島宿舎ビラ配り事件 第4問 妄想族追放条例事件 第6章 経済的自由権 第5問 ペットボトル輸出規制事件 第6問 学習塾距離規制事件 第7章 平等権・請求権 第7問 Y市育児手当事件 第8問 生活保護申請却下・基準減額事件 第9問 住基ネット起因損害の賠償制限 ▼プロフィール 木村草太(きむら そうた) 1980年 横浜に生まれる 2003年 東京大学法学部卒業 2003年 東京大学大学院法学政治学研究科助手・憲法専攻 (2006年まで) 現 在 首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部法学系教授 [著書] 『平等なき平等条項論──equal protection条項と憲法14条1項』(東京大学出版会、2008)、『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書、2012)、『憲法の創造力』(NHK出版、2013)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP新書、2014)、『憲法という希望』 (国谷裕子との対談収録、講談社現代新書、2016)など。 公式ブログ「木村草太の力戦憲法」 http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr
MORE -

長谷部恭男『憲法入門』
¥2,420
******************* 2017年5月 電子版発行 以下のサイトで購入できます(順次取り扱い開始)。 GALAPAGOS STORE / BOOKSMART / VarsityWave eBooks / やまだ書店 / Bookbeyond / iBookstore / Kindle / dマーケット BOOKストア / koboイーブックスストア 〈スマートフォン向け〉boocross / どこでも読書 / TBSブックス / TSUTAYAミュージコ / コダワリ編集部イチオシ / よもっと!! ******************* 四六判 上製 188頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-05-5 C3032 2010年1月刊行 ブックデザイン 原 研哉+松野 薫 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 日経ビジネスオンライン ビジネスマンだって、東大で勉強してみたい!「学問の入口フェア2010 LIVE東大人気講義」応援企画(前編) 『法学セミナー』2010年6月号 ブック・レビュー「通念の盲点をつく 憲法の新たな読み解き」評者・赤坂正浩(神戸大学教授) 『ハイローヤー』2010年8月号 ブックレビュー(評者・ハイローヤー編集部) ▼概要 憲法がわかる 第一線研究者による日本国憲法の入門書決定版 読んだだけではよく意味が分からない条文、普通のことばの意味とは違った意味で受け取るべき条文を大胆かつ軽やかに分かりやすく解説する。ですます体。文献解題付き、日本国憲法全文収録。 [目次] はしがき 第一章 憲法学への招待 一 国家のあるところ、憲法あり 二 社会契約論 三 契約か慣行か 四 憲法の制定? 五 現に受け入れられている憲法 六 立憲主義 [文献解題] 第二章 表現の自由 一 違憲審査と民主政 二 「二重の基準」の理論 三 表現の自由を制約する法令 四 政府が設定・提供する場 五 放送の自由と規律 [文献解題] 第三章 学問の自由 一 学問の自由の特殊性 二 なぜ学問の自由を保障するか 第四章 信教の自由と政教分離 一 信教の自由と立憲主義 二 政教分離原則の背景 三 目的効果基準 第五章 財産権 一 財産権の保障とその内容 二 ジョン・ロックの考え方 三 デイヴィッド・ヒュームの考え方 四 公共の福祉に適合する定め 五 収用と正当な補償 [文献解題] 第六章 職業選択の自由 一 職業選択の自由 二 違憲審査基準 三 なぜなのか──民主的政治過程が生み出す「公益」 第七章 人身の自由 一 人身の自由 二 適正手続の保障 三 なぜ手続の適正さが要求されるのか 四 死刑は残虐か [文献解題] 第八章 社会権 一 生存権 二 教育を受ける権利 三 労働基本権 第九章 参政権 一 参政権の性格 二 選挙権の保障の意味 三 投票価値の平等 四 なぜ多数決なのか [文献解題] 第一〇章 平等 一 法適用の平等と法内容の平等 二 目的と手段の合理的関連性 三 個人を平等な存在として扱っているか 四 その他の判例 五 ベースラインはあるか [文献解題] 第一一章 包括的基本権 一 一三条と「新しい権利」 二 プライヴァシーの権利──なぜ保障されるのか 三 索引情報 四 個人として尊重される 第一二章 誰の権利を保障するのか 一 外国人の権利 二 説明できるか──国ごとの責任分担 三 未成年者の権利 四 「法人の人権」 五 天皇および皇族の権利 六 誰から保障するのか [文献解題] 第一三章 代表民主政の原理 一 代表民主政 二 ルソーの『社会契約論』 三 直接民主政は善い政体か 四 競合し協奏する民主政 [文献解題] 第一四章 代表民主政の機構 一 憲法の尊厳的部分と機能的部分 二 議院内閣制 三 衆議院の解散 四 内閣の構成 五 両院のねじれ 六 裁判員制度 第一五章 平和主義 一 マッカーサー・ノート 二 戦力不保持原則 三 戦争と憲法原理 [文献解題] 第一六章 憲法の改正 一 憲法改正の手続 二 改正の限界 [文献解題] 日本国憲法 判例索引/事項索引 ▼プロフィール 長谷部恭男(はせべ やすお) 1956年 広島に生まれる 1979年 東京大学法学部卒業 東京大学教授をへて 現 在 早稲田大学法学学術院教授 [主要著書] 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991) 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』(弘文堂、1992) 『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999) 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』(東京大学出版会、2000) 『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004) 『憲法とは何か』(岩波新書、2006) 『Interactive 憲法』(有斐閣、2006) 『憲法の理性』(東京大学出版会、2006) 『憲法 第4版』(新世社、2008) ▼関連書籍 長谷部恭男『憲法の境界』(羽鳥書店、2009) 長谷部恭男『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)
MORE -
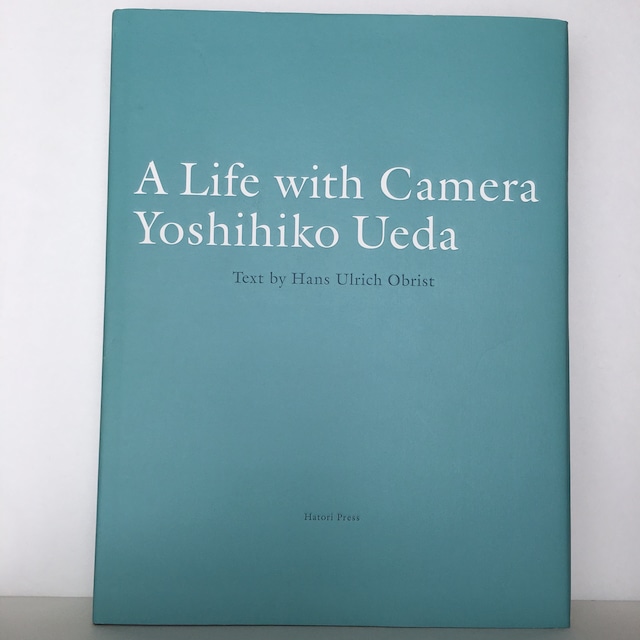
上田義彦『A Life with Camera』
¥19,800
SOLD OUT
A4判変型 上製クロス装 586頁 本体価格 18,000円+税 ISBN 978-4-904702-53-6 C0072 2015年4月刊行 テキスト ハンス・ウルリッヒ・オブリスト 編集 上田義彦、菅付雅信、中島英樹 ブックデザイン 中島英樹 印刷・製本所 サンエムカラー *展覧会情報 『A Life with Camera』刊行記念展覧会 Gallery 916 2015 年 4 月 10 日~2015 年 12月 27 日 http://gallery916.com/exhibition/alifewithcamera/ ▼書評・記事 ▼概要 眼差しの快楽 写真家上田義彦の集大成 1982年にデビューして以来、写真の第一線で活躍し、数多くのポートレイトや自然、スナップ、広告などを撮りつづけてきた 上田義彦の30有余年の活動を集大成した写真集。厖大なプリントの中から選び配列・構成した本写真集は、上田義彦の世界の魅力を余すところなく伝える。 ▼プロフィール 上田義彦 (うえだ よしひこ) 1957 年 兵庫県生まれ、写真家、多摩美術大学教授。東京 ADC 賞最高賞、ニューヨークADC賞、カンヌ国際広告祭グラフィック部門銀賞、朝日広告賞、日本写真協会 作家賞など国内外の様々な賞を受賞。 代表作として、ネイティブアメリカンの神聖な森を撮影した『QUINAULT』(京都書院、1993)、「山海塾」を主宰する前衛舞踏家・天児牛大のポートレイト集『AMAGATSU』(光琳社、1995)、自身の家族に寄り添うようにカメラを向けた『at Home』(リトルモア、2006)、屋久島で撮り下ろした森の写真『Materia』(求龍堂、2012)、ガンジス川の人々を撮った『M.Ganges』(赤々舎、916Press、2014)。また作品は、Kemper Museum of Contemporary Art(Kansas City)、New Mexico Arts(Santa Fe)、Hermès International(Paris)、Stichting Art & Theatre(Amsterdam)、Bibliothèque nationale de France(Paris)などにそれぞれ収蔵されている。 上田義彦 公式HP http://www.yoshihikoueda.com/#/p
MORE -
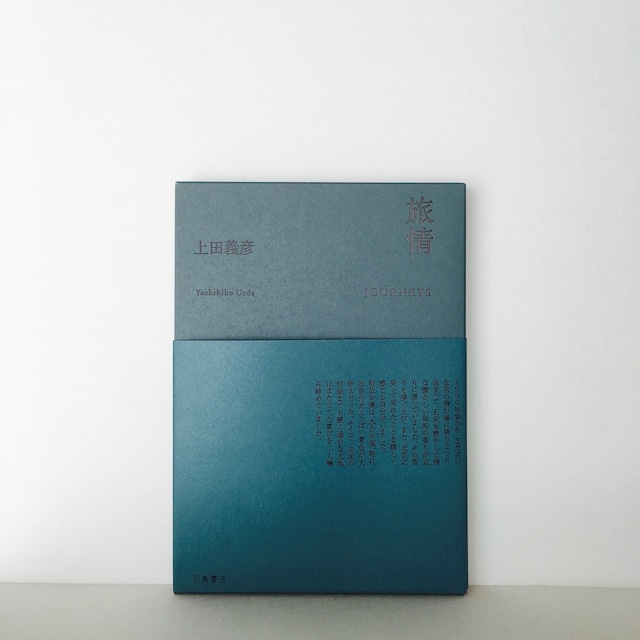
上田義彦『旅情』
¥3,960
SOLD OUT
*上田義彦写真展「森の記憶」開催中 竹芝・Gallery 916 4.14〜7.2 http://gallery916.com/exhibition/ A5判 並製・函入 200頁 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-54-3 C0072 2015年10月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷・製本所 サンエムカラー ▼書評・記事 『ブレーン』2015年12月号 WEB 朝日新聞デジタル(2015.12.4)http://www.asahi.com/and_w/gallery/1204_ryojo/ 『日本カメラ』 2016年2月号 中国の故事『胡蝶の夢』のような世界の大小の尺度があいまいになっていく(評:冨山由紀子) 『popeye』 2016年2月号 松浦弥太郎 料理と本の話。vol.3~焼きそばと旅情。 ▼概要 どこか深いなつかしさを覚える上田義彦の旅のまなざし。 1980年代後半から2011年まで、撮影旅行でめぐった中国各地のスナップ160点を収録。 ▼プロフィール 上田義彦 (うえだ よしひこ) 1957 年 兵庫県生まれ、写真家、多摩美術大学教授。東京 ADC 賞最高賞、ニューヨークADC賞、カンヌ国際広告祭グラフィック部門銀賞、朝日広告賞、日本写真協会 作家賞など国内外の様々な賞を受賞。 代表作として、ネイティブアメリカンの神聖な森を撮影した『QUINAULT』(京都書院、1993)、「山海塾」を主宰する前衛舞踏家・天児牛大のポートレイト集『AMAGATSU』(光琳社、1995)、自身の家族に寄り添うようにカメラを向けた『at Home』(リトルモア、2006)、屋久島で撮り下ろした森の写真『Materia』(求龍堂、2012)、ガンジス川の人々を撮った『M.Ganges』(赤々舎、916Press、2014)。また作品は、Kemper Museum of Contemporary Art(Kansas City)、New Mexico Arts(Santa Fe)、Hermès International(Paris)、Stichting Art & Theatre(Amsterdam)、Bibliothèque nationale de France(Paris)などにそれぞれ収蔵されている。なお、最新刊は、30年以上の濃密な写真生活が結実したレトロスぺクティヴ『A Life with Camera』(羽鳥書店、2015)。 上田義彦 公式HP http://www.yoshihikoueda.com/#/p
MORE -
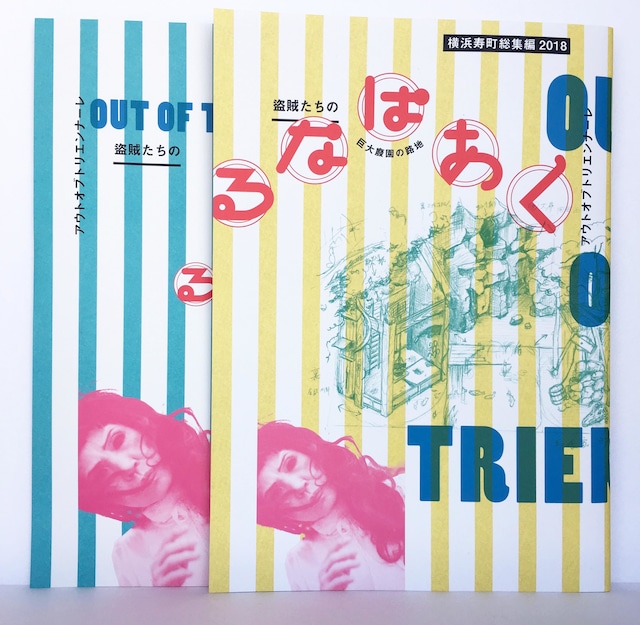
水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』2017&2018セット(委託販売品)
¥2,200
*セット販売 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく特集号。 会期途中に製作された2017年9月の特別編集号と、2018年4月の新宿花園神社公演にあわせて製作された「総集編」の特別編集号との2冊セットでお届けします。 ▼各号の詳細は、以下をご覧ください。 水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』(2017) http://www.hatorishoten.co.jp/items/8470262 水族館劇場『横浜寿町公演 【総集編 2018】FishBone 特別編集号』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150519
MORE -
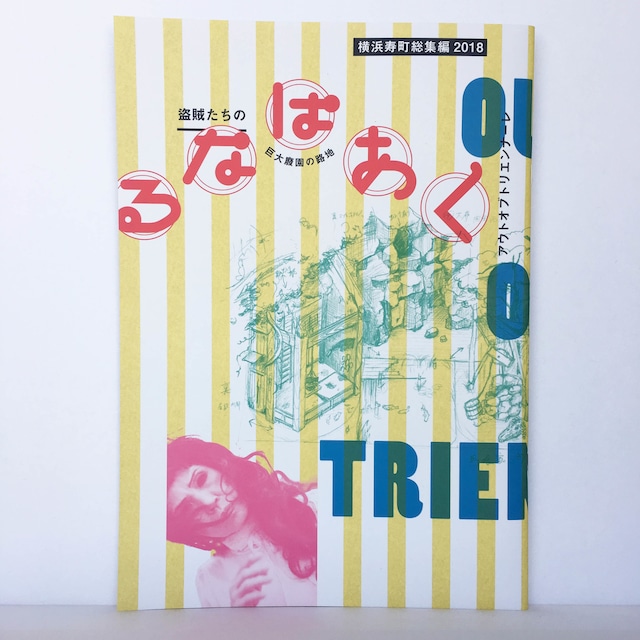
水族館劇場『横浜寿町公演 【総集編 2018】FishBone 特別編集号』(委託販売品)
¥1,430
★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNはついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 *会場等では税込1300円で販売しておりましたが、消費税をつけた価格に変更いたしました。ご了承ください。 A4判 並製(中綴じ製本) 44頁 オールカラー デザイン:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2018年4月15日 ▼概要 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく【総集編】! アウトオブトリエンナーレ 2017.8.3─9.17 「盜賊たちのるなぱあく」 芝居公演 2017.9.1─5 / 9.13─17 「もうひとつの この丗のような夢 寿町最終未完成版」 特設サイト:http://www.suizokukangekijou-yokohama2017.com/ 水族館劇場公式HP:http://suizokukangekijou.com/ 今号(2018)は、2017年横浜寿町の夏を、町の関係者の声、るなぱあく参画者やヨコトリ関係者、一線の研究者のエッセイなど、るなぱあく全体の総集編として、新たに27名の書下し原稿を収録。前号(2017)で掲載できなかった、芝居を中心としたるなぱあく会期後半のグラビアを一挙公開。 ▼前号(2017)および、セット販売(2017&2018) 2017年版 FishBone特別編集号(1,404円) http://www.hatorishoten.co.jp/items/8470262 2017&2018 FishBone特別編集号セット(税込2,160円) http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150539 ▼目次 みえない境界からあふれでるように叫びとささやきが呼んでいる 桃山 邑 世の終わり 近づきくればいつの日か おれたちの出番くると知りそめ 野本三吉 とある実録・寿町 千代次 水族館劇場の寿町公演を観て 村田由夫 寄せ場寿町の夏 小林直樹 水族館劇場の芝居 佐藤眞理子 二〇一七年夏、横浜寿町に異変がおきた! 長澤浩一 「寿には娯楽がない」という 近藤 昇 今年の寿町夏祭り、何故いつもの場所でやらないんだろう? 石井淳一 盜賊たちの思い出のるなぱあく 癸生川 栄 月明かりに立って 相澤虎之助 るなぱあく古書街 宮地美華子 ゴドー達の街へ 津田三朗 あてにしないで待て もうひとつふたつの夢 この丗のような白昼夢(るなぱあく) 椹木野衣 「この丗のような夢」@寿町 逢坂恵理子 島と星座とガラパゴスと水族館劇場──「この丗のような夢 寿最終未完成版」公演顛末記 庄司尚子 台風への備え 野口敦子 水族館劇場の美学――「関係性の美学」でも「敵対性の美学」でもなく 藤田直哉 「水」の奇跡 毛利嘉孝 新生果実 村井良子 水族館劇場へようこそ 桑田光平 ジャズと演歌と桃山邑 佐藤良明 黒い翁 安藤礼二 孤独な熾火たちのために──「盜賊たちのるなぱあく」の名残 田中 純 鈴木清『天幕の街』より ▼「盜賊たちのるなぱあく」参画者 会田誠・毛利嘉孝・藤田直哉・野本三吉(加藤彰彦)・鬼海弘雄・岡本光博・葵生川栄・大島幹雄・ボッチン・大坂秩加・尾形一郎/尾形優・津田三朗・渡辺友一郎・映像制作集団 空族・安田登・玉川奈々福・本橋信宏・東良美季・鈴木義昭・伊藤裕作・田中優子・翠羅臼・高沢幸男・荒木剛・田中純 ▼関連書 ▽ 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 ▽ 田中純 『過去に触れる───歴史経験・写真・サスペンス』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874205 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873243 ▽ 尾形一郎 尾形優 『私たちの「東京の家」』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873707 『沖縄彫刻都市』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873995 ▽ 高山宏 『夢十夜を十夜で』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873501
MORE -
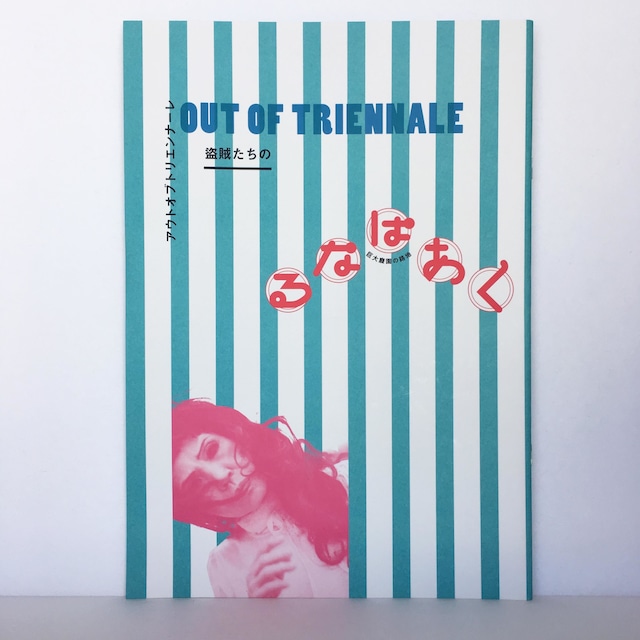
水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』(2017)(委託販売品)
¥1,430
★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNはついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 *会場等では税込1300円で販売しておりましたが、消費税をつけた価格に変更いたしました。ご了承ください。 A4判 並製(中綴じ製本) 44頁 オールカラー デザイン:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2017年9月1日 ▼概要 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく総力特集! アウトオブトリエンナーレ 2017.8.3─9.17 「盜賊たちのるなぱあく」 芝居公演 2017.9.1─5 / 9.13─17 「もうひとつの この丗のような夢 寿町最終未完成版」 特設サイト:http://www.suizokukangekijou-yokohama2017.com/ 水族館劇場公式HP:http://suizokukangekijou.com/ グラビアページでは、るなぱあくの全景・全容を紹介。「この丗のような夢」三部作を構成する、三重県芸濃町公演、新宿花園神社公演、それぞれの特集ページも。 21名にのぼる寄稿者による充実のテキストを収め、るなぱあく参画者・役者・スタッフの詳細な紹介文も必見。 ▼目次 道窮まり命乖くも 桃山 邑 どっこい人間節の街 ── 老いていくことの意味 野本三吉 寿町でブルースを 二見 彰 黒い翁(サトゥルヌス)の子供たち ──トリエンナーレを地底から撃つために 田中 純 序破急ならぬ、破序急、そして転々々……旅は続く 淺野幸彦 藝能の根源から 安田 登 地霊と共に生まれ変わる「この丗の夢」 大島幹雄 江戸文化のからくり 田中優子 天幕芝居の原像 翠 羅臼 桃山讃江 内堀 弘 観劇記 ── 水族館劇場「この丗のような夢・全」への返歌 三枝明夫 雑感 水族館劇場と写真家・鈴木 清 ── 夢と現のマージナル 鈴木 光 一九八七年、その頃ぼくは何をしていただろう 那須太一 寿の空をヒラヒラと 秋浜 立 誰のための芸術? 毛利嘉孝 水族館劇場が、地域アートに齎すかもしれないもの 藤田直哉 水族館劇場さんとの関わり 岡本光博 一夏の「幻」を捉えるために。 居原田 遥 楽日、寿町に行ってみよう(かな) 高山 宏 思ふ行くへの …… 。 中原蒼二 編集後記にかえて 矢吹有鼓 執筆者・参画者・役者・スタッフ紹介 ▼「盜賊たちのるなぱあく」参画者 会田誠・毛利嘉孝・藤田直哉・野本三吉(加藤彰彦)・鬼海弘雄・岡本光博・葵生川栄・大島幹雄・ボッチン・大坂秩加・尾形一郎/尾形優・津田三朗・渡辺友一郎・映像制作集団 空族・安田登・玉川奈々福・本橋信宏・東良美季・鈴木義昭・伊藤裕作・田中優子・翠羅臼・高沢幸男・荒木剛・田中純 ▼関連書 ▽ 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 ▽ 田中純 『過去に触れる───歴史経験・写真・サスペンス』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874205 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873243 ▽ 尾形一郎 尾形優 『私たちの「東京の家」』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873707 『沖縄彫刻都市』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873995 ▽ 高山宏 『夢十夜を十夜で』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873501
MORE -
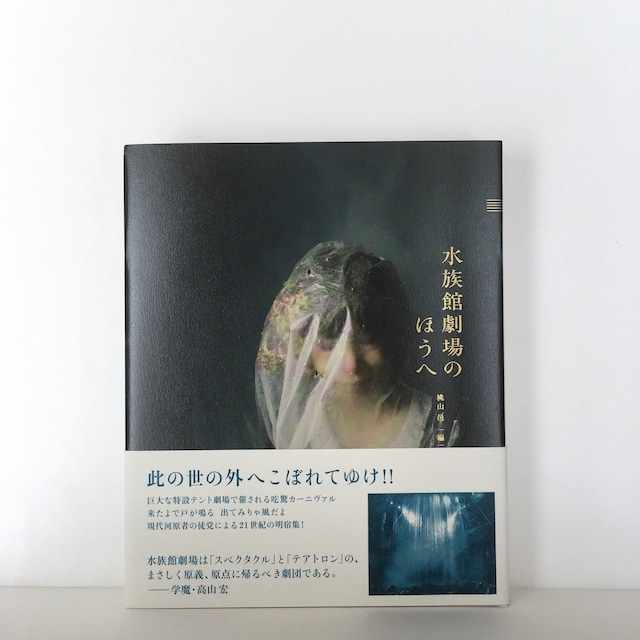
桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』
¥6,380
B5判変型(H224×W182) 上製 452頁(カラー32頁) 本体価格 5,800円+税 ISBN 978-4-904702-41-3 C0074 2013年6月刊行 ブックデザイン 近藤ちはる(UltRA Graphics) 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 *公演情報 *トークイベント (終了しました) 大島幹雄×桃山邑「サーカスと藝能」 古書ほうろう 2015年9月18日 http://horo.bz/event/oshimamikio-momoyamayu20150918/ ▼書評・記事 『文学』 2013年7・8月号〈特集:浅草と文学〉(岩波書店) 冒頭に「水族館劇場座主桃山邑に」と掲げた、高山宏先生の寄稿 「「尖端的だわね。」──『浅草紅団』の〈目〉」 が掲載されています 『西日本新聞』2013年8月11日書評 「本を閉じても心はまだ水族館劇場の世界を漂って、まるで、昼と夜が交差する一瞬の逢魔が刻の人さらいにあったよう。切ない懐かしい危うい心模様なのだ。」(評者 姜信子) 『東京新聞』2013年12月29日「2013 私の3冊」 姜信子「今年一番の不穏の書。この世のはずれの河原から逢魔が刻(とき)の幻のようにやってくる野外劇集団「水族館劇場」。その二十五年の道のりはまるで一瞬の夢みたいで、せつなくて、禍々しくて、人をかどわかしたり、ひそかに世界を揺さぶったり」 『本の雑誌』2014年1月特大号「2013年度 私のベスト3」 「この人たちのテント芝居を昔から見ていた。大仕掛けも、いかがわしさも、まるで祭りの見世物小屋のようで、終われば蜃気楼のように消えていく。でも、その人たちと挨拶一つしたことがない。テントはこの世の外のことなのだ。それがまるごと本になった。なんと無粋と思ったが、それでも読めばやはり面白い。一夜、途方もない物語を聞くようであった」(内堀弘) ▼概要 此の世の外へこぼれてゆけ ! ! 巨大な特設テント劇場で催される吃驚カーニヴァル 来たよで戸が鳴る 出てみりゃ風だよ 現代河原者の徒党による21世紀の明宿集! 水族館劇場は「スペクタクル」と「テアトロン」の、まさしく原義、原点に帰るべき劇団である。 ──学魔・高山宏 1987年の旗揚げ以来、野外劇・テント芝居をつづけてきた「水族館劇場」という名の芝居集団。みずから建てる巨大なテント劇場で繰りひろげる独自の世界は、年を追うごとに新たな観客をよびよせ、注目度を増している。水族館劇場の何が人を魅了するのか。一般の演劇とは一線を画した集団の、全貌と思想を明らかにする。 [主要内容] 水族館劇場旗揚げ25年、“いま”そして“これから” ・座長・桃山邑による書き下し、水族館劇場精神史「野戦攻城の旗」 ・表も裏も全公開、ブックパノラマ台本『NADJA 夜と骰子とドグラマグラ』 ・女優・千代次が語り下す、野外劇・テント芝居40年、寄せ場興行17年の軌跡 ・冬の寄せ場へ、路上芝居ユニット〈さすらい姉妹〉の『谷間の百合』台本 ・“水の劇場”をいろどりささえる、棟梁・舞台監督・美術の裏方座談会 ・早稲田演劇博物館、九州大学総合研究博物館での舞台・宣伝美術展を紙上再現 ・終わりなき旅へ誘う、高山宏・毛利嘉孝・津田三朗・梅山いつき特別寄稿 ・400点以上の写真で解き明かす、大仕掛けを自在にあやつる芝居集団の全貌 ▼劇団プロフィール 水族館劇場 1987年に桃山邑らによって結成された野外劇集団。中世河原者の系譜にみずからを位置づけて全国に神出鬼没。役者や裏方も鳶、踊り子、放浪芸人など、あらゆる階層から集結する。自分たちで 高さ13メートルにおよぶ巨大な仮設劇場(ごや)を建設。劇団の代名詞とも言える25トンにも及ぶ本水を使った演出、大掛かりな舞台装置、馬や白梟など動物も使って、既存の劇場では見ることのできない祝祭パノラマを現出。天幕は張るが、一度として同じ形の劇場をつくらない。いっぽうで寄せ場といわれる、現代社会の最下層労働者が蝟集する街にも進駐。〈さすらい姉妹〉として冬の路上で投げ銭芝居を上演。現代演劇の本流から大きく逸脱した傾奇者(かぶきもの)の精神が、四半世紀を経て注目をあつめている。2009年、企画展示「やぶれ船で流浪する水夫たち──水族館劇場20年の航跡」が早稲田大学坪内博士記念演劇博物館で、2012年には「場をつくる──大水族館劇場展」が九州大学総合研究博物館で開催された。 水族館劇場 公式HP http://www.suizokukangekijou.com/ ●編者プロフィール 桃山 邑(ももやま ゆう) 1958年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。驪團(りだん)を経て1987年に水族館劇場として、あたらしく一座創設。へっぽこ役者三人で大八車を引いて筑豊炭鉱街へむかう。東京に戻って劇場機構を拡大しながら、寺社境内を漂流してゆく。水族館劇場をいちど限りのメラヴィリアとして見物衆に堪能してもらうために危険な仕掛けをつぎつぎに考案、役者の反発を買いながら現在にいたる。不思議な縁でむすばれた、さまざまな世直しの一味とも連携をつづける。その試行がどこにたどりつくのか誰も知らない。
MORE -
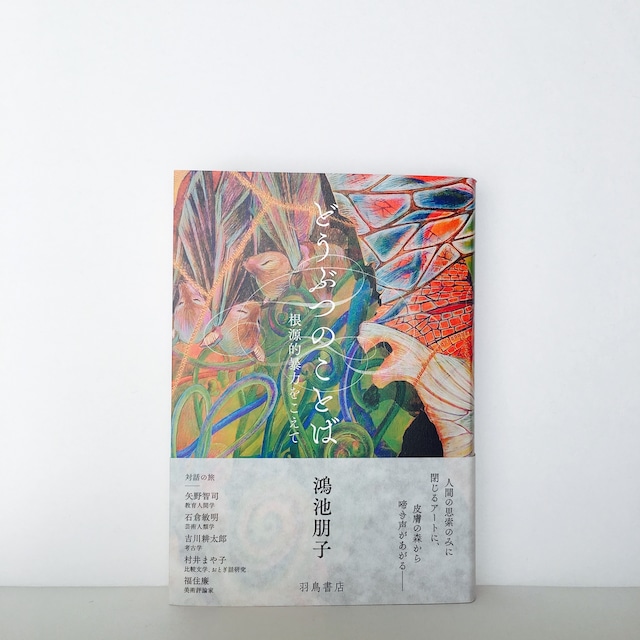
鴻池朋子『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』
¥3,740
A5判 上製 384頁 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-63-5 C0070 2016年9月刊行 ブックデザイン 小川順子 *展覧会情報 神奈川県民ホールギャラリー 鴻池朋子展「根源的暴力」 2015年10月24日~11月28日 http://www.kanakengallery.com/detail?id=33712 群馬県立近代美術館 鴻池朋子展「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」 2016年7月9日〜8月28日 http://mmag.pref.gunma.jp/kakoten/h28/h28exh02.htm 新潟県立万代島美術館 鴻池朋子展「皮と針と糸と」 2016年12月17日~ 2017年2月12日 http://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E6%9C%8B%E5%AD%90%E5%B1%95/ ▼書評・記事 共同通信/各紙 2016年10月16日 美術家が記す回復の記録(評者:椹木野衣) 「本書は、東日本大震災を経て、それまでの型にはまった自分の表現にまったくリアリティーを持てなくなった著者が、次第に作ることを回復していく現在進行形の記録である。その際、重要な導きの糸となったのが、動物という存在だった。‥‥」 『朝日新聞』 2016年10月30日 現代社会揺さぶるアートの力(評者:大竹昭子) http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2016103000003.html 『朝日新聞』 2017年3月9日 折々のことば 689(鷲田清一) 本書からの一節が引かれています。 http://www.asahi.com/articles/ASK383VWFK38UCVL004.html ▼概要 人間の思索のみに閉じるアートに、皮膚の森から啼き声があがる── アーティスト・鴻池朋子が、東日本大震災をきっかけに芸術の始まりに立ち戻り、人間がものをつくることを問い直す。さまざまな専門家との対話と、書き下ろしを収録。 対話の旅 矢野智司(教育人間学)、石倉敏明(芸術人類学)、吉川耕太郎(考古学)、村井まや子(比較文学、おとぎ話研究)、福住廉(美術評論家) [目次] 風が語った昔話 描くことも食べることも I あたらしい声 人間と動物の境界に出現するアート 矢野智司 動物絵本という謎──いつも動物がでてくる不思議 生命を開く動物絵本──子どもが動物になる アートが開く生命のへの途──洞窟から都市空間へ 世界を区切る境界線の生まれるところ──始原へ 「人間の向こう側」へ 石倉敏明 「新しい地図」を描く試み ひっくり返された世界像 つくれないアーティスト 鴻池朋子 トークセッション 矢野智司×石倉敏明×鴻池朋子 交換の原理を突破する 食べる食べられる関係 地球の穴とパブリックアートの役割 土の下の大きなウサギ 都市の起源にある暴力 II ダイアログの旅 「贈与」と「交換」 矢野智司×鴻池朋子 複数のドア 私とは何者か?と、問わない私とは何か 私の言葉は私のつくった言葉ではない 書き残さない人 物が異質な何かに変わる瞬間 生々しすぎるもの 賢治と似たような人々 「最初の先生」は何度も生まれてくる 森のなかの一軒家 既存を揺さぶるもの 世界の掴み方 贈与によって開かれる異類婚 初めてつくるもの 吉川耕太郎×鴻池朋子 始めてつくるもの──石器の出現 組み合わせる魔法 考古学が不得意である「心」 分類しないことで見えてくるもの 生きものが見渡せる町 狩猟──動物の擬人化 針と皮鞣し 切り離す男性、つなぐ女性 目に見えない文化 同じものではいられない 村井まや子×鴻池朋子 歴史的分類以外の分類──ポテトスープのつくり方 異類婚の花嫁衣装を縫う 使えるものは何でも使う 出現してきた父性 本当に恐ろしいものに出会うために 同じものではいられない──変身 見てはいけないものを見る おとぎ話の一読者であること wonder を引き出す wonder を共有する 夜の山を歩く子 福住廉×鴻池朋子 誰にでもできるもの そこに私はいませんよ そこにこそ何かがある 夜の山を歩く子 美術と無関係であるとは言わせない 起こっている途中 III どうぶつのことば 想像力 動物、猟 動物の言葉を借りにいく 旅にでる 「東北を開く神話」の声 地球の穴とパブリックアート 「美術館ロッジ」 飛ぶ小屋 氷結する絵 物語るテーブルランナー 自分の体験をオーブンで焼く 人間以外の声 地球の断面図 狼の下半身 地球はふたたび凍りはじめる 狼頭巾をかぶる少女 ある三匹の語り 東北の博物館職員の語り ある人類学者の語り ある女性の語り 皮緞帳をくぐり ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 *著作 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(羽鳥書店、2009年) 『焚書 World of Wonder 』(羽鳥書店、2011年) 『根源的暴力』 (羽鳥書店、2015年) 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/
MORE -

鴻池朋子『根源的暴力』
¥3,080
A5判変型(130×210mm) 並製 152頁 付録|「皮緞帳」作品 八つ折り 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-58-1 C1071 2015年12月刊行 ブックデザイン 小川順子 【日英併記】 ★第50回造本装幀コンクール 審査員奨励賞 受賞 *展覧会情報 神奈川県民ホールギャラリー 鴻池朋子展「根源的暴力」 2015年10月24日~11月28日 http://www.kanakengallery.com/detail?id=33712 群馬県立近代美術館 鴻池朋子展「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」 2016年7月9日〜8月28日 http://mmag.pref.gunma.jp/kakoten/h28/h28exh02.htm 新潟県立万代島美術館 鴻池朋子展「皮と針と糸と」 2016年12月17日~ 2017年2月12日 http://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E6%9C%8B%E5%AD%90%E5%B1%95/ ▼書評・記事 『月刊アートコレクターズ』 2016年2月号 震災を経て、「なぜつくるのか」という根源的な問いに再び挑んだ作家の成果をみることができる。 ▼概要 もはや 同じものでは いられない── 地球の振動を敏感に感じとった鴻池朋子は それまでの皮膚を脱ぎ捨て、 新たな動物の着物を縫いはじめた。 [収録テキスト] 裂け目にて 奥脇嵩大(青森県立美術館学芸員) 迎え入れる手 坂本里英子(セゾン現代美術館学芸員/VOLCANOISE代表) ゆっくりと停止 鴻池朋子 ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 *著作 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(羽鳥書店、2009年) 『焚書 World of Wonder 』(羽鳥書店、2011年) 『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』 (羽鳥書店、2016年) 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/
MORE -
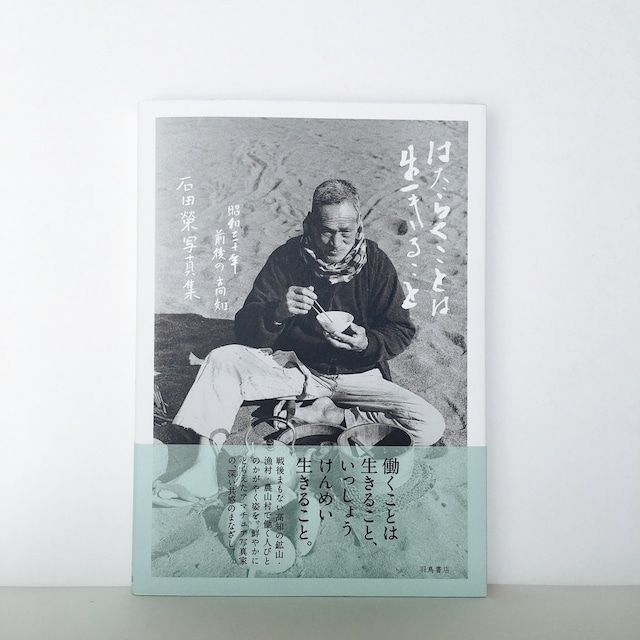
石田榮『はたらくことは、生きること──昭和30年前後の高知』
¥3,960
B5判 並製 200頁 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-62-8 C0072 2016年7月刊行 監修 堀瑞穂 題字 華雪 アートディレクション・デザイン 長尾敦子 *展覧会 Gallery 176 2016年11月6日〜11月23日 「はたらくことは 生きること—昭和30年前後の高知」写真集出版記念写真展 http://176.photos/exhibitions/161106/ ふげん社 2017年4月11日〜29日(予定) *応援サイト https://ikirukoto.tumblr.com/ 推薦コメント掲載者一覧(2016年9月22日現在) 菊田樹子(インディペンデント・キュレーター)/吉岡さとる(写真家 高知在住)/紅露 拓(湘南写真倶楽部)/岡本明才(沢田マンションギャラリー room38)/フランク・リチャード・チェイス/大日方公男(東京新聞・文化部)/辻山良雄(Title)/五坪侑恵(ジュンク堂書店)/田川怜奈(恵文社一乗寺店)/Nahoko Yamaguchi/横山起也(NPO法人LIFE KNIT)/若井浩子(Books and Modern)/尼崎 マツタケ食堂 松井/橋本佳子(映画プロデューサー )/松谷友美(写真家)/山下 豊(写真家)/木村 準(gallery 176)/平林達也(フォトグラファーズ・ラボラトリー)/平間至(写真家)/松田拓巳(North Lake Cafe & Books)/酒居郁二(bistro192)/ヨシダキミコ(ギャラリー 棚元)/中藤毅彦(写真家)/島田潤一郎(夏葉社代表)/小林紀晴(写真家)/タカザワケンジ(写真評論家、ライター)/華雪(書家)/師岡清高(大阪芸術大学 写真学科 教授)/綾 智佳(The Third Gallery Aya)/名久井伴久(日本写真協会会員)/奥野政司(京都写真クラブ)/佐野誠司(株式会社 on and on)/大澤友貴(写真研究)/堀 瑞穂(フォトエディター) *写真集専門サイト「shashasha」での紹介ページ https://www.shashasha.co/jp/book/hataraku-koto-wa-ikiru-koto-work-is-life ▼書評・記事 『東京新聞』 2016年9月4日「アートな本」 「(前略)大人たちは日がな汗まみれで働き、子守や手伝いをする子どもの姿も。そんな暮らしや労働が当たり前だった時代の記録だ。働くことは喜びでも苦役でもあるが、いきることにつながるその姿がまぶしい。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-09-06 『朝日新聞』 2016年9月18日書評 「日曜カメラマンが撮るものといえば、美しい風景や日常のスナップが思い浮かぶ。引き揚げ者からもらったカメラで撮り始めたという90歳の石田榮はしかしし、昭和30年ごろには高知で働く人々を追っている。」 http://www.asahi.com/articles/DA3S12565101.html 高知で暮らす女性たちの応援紙『k+』vol.117 2016年9月22日号 夏葉社 島田 潤一郎|第6回|読む時間、向き合う時間 http://www.kochinews.co.jp/image/media/k_puls_vol117.pdf 『北海道新聞』 2016年9月25日書評 「ごろんとした石灰岩を荷車に積んで坂道を運ぶ男女や浜で地引き網漁に汗を流す漁師など、いずれも厳しい労働現場にあって笑顔が光る。(中略)作品からは被写体との距離の近さが感じられる。戦時中、特攻隊の整備兵だった撮影者の経験が人へのまなざしに表れているように思う。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-09-28 『しんぶん赤旗』 2016年10月2日書評 「(前略)かつて高知の鉱山や漁村、農村などで撮ったネガから約60年ぶりによみがえった写真です。多くが貧しかった時代、それでも生きる喜びにあふれた笑顔がまぶしい。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-10-05 『朝日新聞』2017年4月25日 91歳、60年前に捉えた働く笑顔 アマ写真家、東京で出版記念展 「高知の地で働く人々を温かくとらえた作品郡は、確かな撮影思想と表現に支えられている。同時に、戦後のアマチュア写真の歩みも物語る。」http://www.asahi.com/articles/DA3S12909725.html 『日本カメラ』2017年6月号[今月のPhoto & People] 「長く写真を続けていると、眠ったままのネガが膨大に残るはずだ。ある時、そこに光が当てられ、貴重な時代の記録であることに気づく。(中略)「引越しの度に家人から(60年前に撮った写真のネガの)処分を迫られたが、本能的に引っ越し荷物に入れてきました」と石田榮さんは言う。‥‥」 『高知新聞』2018年1月7日 著者インタビュー掲載 ▼概要 働くことは生きること、 いっしょうけんめい生きること。 戦後まもない高知の鉱山・漁村・農山村で働く人びとのかがやく姿を、鮮やかにとらえたアマチュア写真家の、深い共感のまなざし。 石田榮は、特攻隊を送り出す整備兵をへて、敗戦後、海外引揚者から譲り受けたカメラで写真と出会った。 働いて日々を生き抜くなかで、休みの日、カメラ片手に日曜日でも体を張って働く一次産業の人びとへ会いに通った。 昭和30年前後の5年ほどの間に撮られた写真は、ネガのまま半世紀を超え、人々の笑顔を甦らせる。 [収録テキスト] 私の写真人生 石田榮 切り取られた「昭和」のひとコマ 堀瑞穂(フォトエディター) 白菊──高知海軍航空隊の航空機整備兵として 石田榮 ▼プロフィール 石田 榮(いしだ さかえ) 1926(大正15)香川県綾歌郡に生まれる 1940(昭和15)14歳 株式会社東洋工作所(大阪)において機械見習工 1943(昭和18)17歳 香川県綾歌郡岡田村立青年学校本科繰上卒業 佐世保海兵団に入団、海軍航空整備兵 1944(昭和19)18歳 海軍普通科飛行機整備術練習生終了(102期) 高知海軍航空隊に所属 以降、出水海軍航空隊、河和海軍航空隊、高知海軍航空隊 1945(昭和20)19歳 鹿屋海軍航空隊で特攻機を整備し、特攻隊を送り出す 8月15日 終戦 1947(昭和22)21歳 協和農機株式会社(高知)勤務 1950(昭和25)24歳 旧満州の引揚者から「徳国製」の蛇腹式セミイコンタを入手 1951(昭和26)25歳 結婚 1954(昭和29)28歳 高知の「ソニアフォト」入会 1963(昭和38)37歳 慶應義塾大学経済学部通信制課程入学 1974(昭和49)48歳 大阪商工会議所経営指導員 1986(昭和61)60歳 石田実践経営事務所開設、経営コンサルタント 2012(平成24)86歳 7月 ニコンサロンbis大阪で個展 2014(平成26)88歳 4・7月 ニコンサロンbis大阪と新宿で第2・3回目の個展
MORE -

尾形一郎・尾形 優『沖縄彫刻都市』
¥3,740
A5判 並製 160頁(カラー72頁) 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-48-2 C0052 2015年2月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『北海道新聞』2015年3月8日、『西日本新聞』2015年3月22日書評 「沖縄はコンクリートブロックの建築物であふれている。加えて彫刻も。本土には見られない独自の建築潮流を、共に建築家、写真家、現代美術家である夫婦が読み解いた。210点の写真と5つの解説文とにより沖縄戦後史の一面を知ることができる。・・・」 『沖縄タイムス』2015年3月21日書評 「本書を手にして、パラパラッとページをめくると、今も現存する懐かしい建物の風景が現れてくる。沖縄の戦後の風景を彩った花ブロックを多用した建物の数々。団塊の世代に属するボクらの風景と言っても過言ではない。 (中略)読者は、自らの復興の空間を重ねながら、今も現存する懐かしい空間と出会うはずである。」(評・ローゼル川田・水彩画家) ▼概要 沖縄はなぜコンクリートブロックで溢れているのか? 写真210点とエッセイでつづる、建築から見たもうひとつの沖縄戦後史。 アメリカ軍統治下の時代に建てられたコンクリートブロックの建物は、沖縄の風土と軍事的な環境が反映された、彫刻的な民家の建ち並ぶ景観をうみだした。 [目次] 沖縄文化地図 序文 1. アメリカ軍が持ち込んだ軍用物資 スパムとコンクリートブロック コンクリートの島 花ブロック 2. 街のあちこちに出現する抽象彫刻 コンクリートブロックの彫刻 亀甲墓とランドスケープ 3. 憧れのコンクリート住宅 モダニズム建築 外人住宅 4. ハイアートが民家になった 木造建築と沖縄の伝統 木造からスラブヤへ 沖縄モダニズムの誕生 離島への伝播 5. 戦争とアニミズムの記憶、革命とプリミティヴィズムの記憶 沖縄構成主義とロシア構成主義 あとがき 英文要約 街で見られる能勢孝二郎の彫刻 参考文献/奥付 ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 『私たちの「東京の家」』(羽鳥書店、2014年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw
MORE -
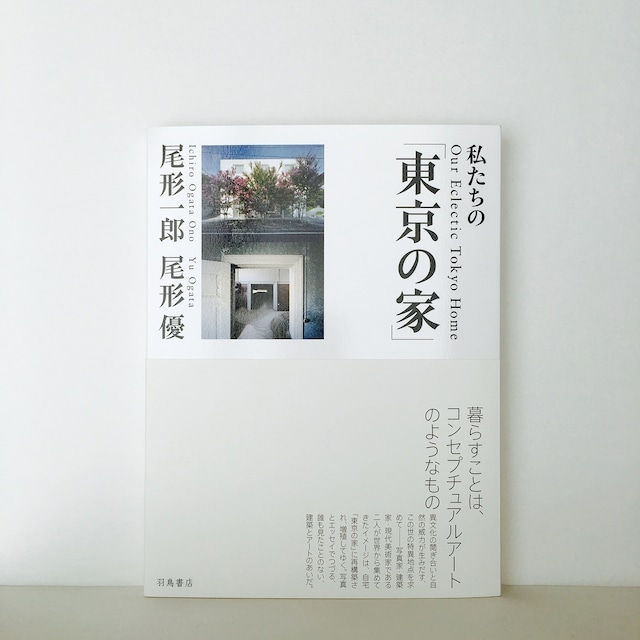
尾形一郎・尾形 優『私たちの「東京の家」』
¥5,940
B5判変型 上製 160頁(カラー80頁) 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-47-6 C1070 2014年9月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 【日英併記】 ▼概要 暮らすことは、コンセプチュアルアートのようなもの 異文化の鬩ぎ合いと自然の威力が生みだす、この世の特異地点を求めて── 写真家・建築家・現代美術家である二人が世界から集めてきたイメージは、自宅「東京の家」に再構築され、増殖してゆく。 写真とエッセイでつづる、誰も見たことのない、建築とアートのあいだ。 生きて変容するアートの記録。 ●「東京の家」に集まる世界のイメージ ・ 噴火に消えた中米グァテマラの首都アンティグア ・ 原始宗教が匂い立つメキシコ教会堂のウルトラバロック ・ 欲望うごめく日本のサムライバロックが織りなす迷宮 ・ ナミビアの砂漠に埋もれた鉱山廃墟のドイツ住宅 ・ 要塞のごとき中国の農家と折衷建築の商店街 ・ ギリシャで見つけた「東京の家」は白い鳩小屋 [目次] 序文 撮影することから私たちの家づくりは始まった グァテマラ──巨大地震の記憶を建築現場に重ねる メキシコ──写真が内包する宇宙を建築に変換する 日本──迷宮を大型プリントで再構築する ナミビア──二人の原風景を一つにする 中国──ディスレクシアの世界を鉄道模型で再現する ギリシャ──「東京の家」を再発見する ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw
MORE -
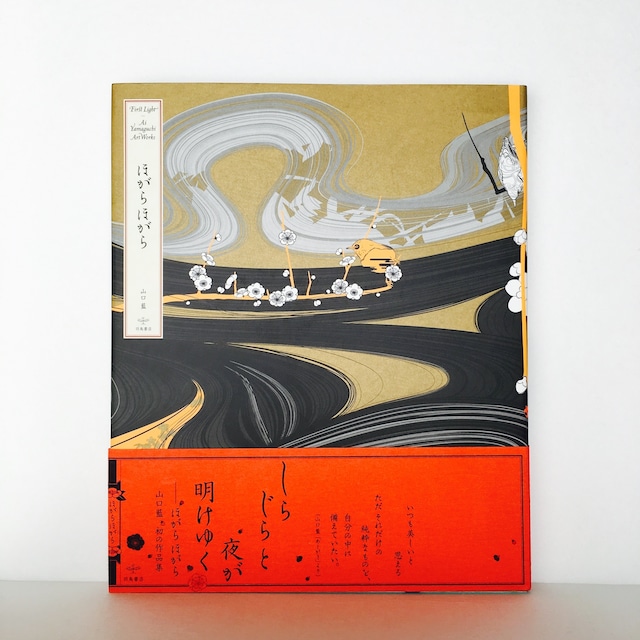
山口藍『ほがらほがら』
¥4,620
A4判変型 上製 136頁 カラー 本体価格 4,200円+税 ISBN 978-4-904702-13-0 C1070 2010年7月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 寄稿:斎藤環 英語・中国語対訳付き 印刷 サンエムカラー 製本 牧製本印刷 【日英中併記】 *特装版 ニニュワークスの取り扱いになります http://www.ninyu.com/ ▼書評・記事 『idea』no.342, 2010年9月号「新刊紹介」 『美術手帖』2010年10月号「新着のアート&カルチャー本から」 *ブログでの紹介 弐代目・青い日記帳 ほがらほがら http://bluediary2.jugem.jp/?eid=2207 *山口藍作品の掲載雑誌 『VOGUE NIPPON』2010年8月号 「アーティスト山口藍が描く、ファッション空想絵図」 ▼概要 しらじらと夜が明けゆく──ほがらほがら 山口藍・初の作品集 1998年のデビューから2010年2月の個展「きゆ」までに発表された作品を多数収録し、これまでの集大成ともいえる作品集。山口藍の中核的な作品である“ふとんキャンバス”に始まり、近年の大型作品である“組立式壁画”など、さまざまな作品形態とその足跡を一覧できる。作家活動のひとつの区切りとして刊行される本書は、山口の魅力を存分に語る、充実の一冊となる。 [目次] “あいだ”へと向かう“まなざし” 斎藤環 山口藍作品(Exhibitions : 1998-2010) 初期展覧会出品作品 かむろ 春に知られる花 笑門来福 Ai Yamaguchi, NEW PAINTINGS ai yamaguchi 後朝 すくうとこ はるのゆくへ OFFICINA ASIA おやすみ Aランチ take art collection 2005 shu uemura boutique, San Francisco, California 2004,2005 SHU UEMURA SKIN PURIFIER art work by ai yamaguchi Fiction@love 山、はるる 花は野にあるように きゆ ほがらほがら 山口藍 作品一覧 山口藍プロフィール ▼プロフィール 山口 藍(やまぐち あい) 1977年東京生まれ。女子美術大学芸術学部工芸科織専攻にて学ぶ。1999年ninyu works結成。江戸の風俗を下敷きに創作した「とうげのお茶や」で遊女として暮らす女の子たちの姿を、独特の支持体を用い、繊細で明解な描線と色面で表現する。 公式HP ニニュワークス http://www.ninyu.com/
MORE -
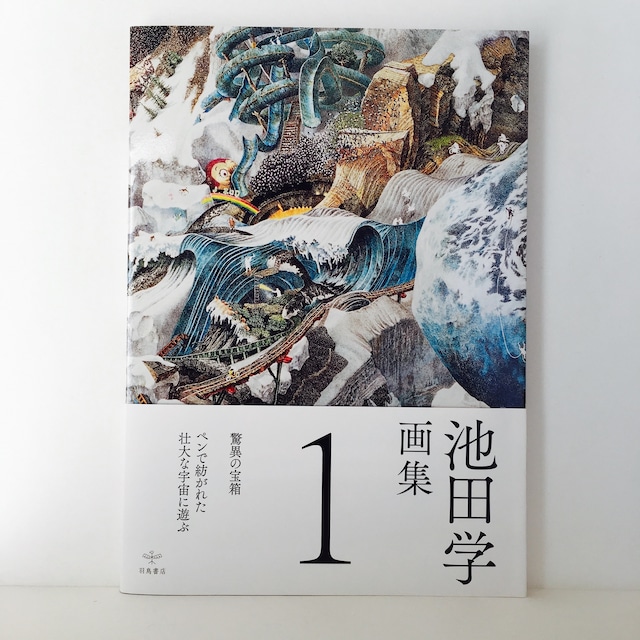
池田学『池田学画集1』
¥4,180
◇ ◇ サイン本をお送りします ◇ ◇ A4判 並製 112頁 カラー 本体価格3,800円+税 ISBN 978-4-904702-18-5 C1071 2011年12月刊行 ブックデザイン 有山達也+池田千草(アリヤマデザインストア) 寄稿:片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター) 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 【英語・中国語対訳付き】 *個展情報 「池田学展 The Pen ―凝縮の宇宙―」 佐賀県立美術館 2017年1月20日(金)〜3月20日(月祝) (会場では、『池田学画集1』の販売はありません) http://tokushu.saga-s.co.jp/ikedamanabu/ *Web連載「池田学のバンクーバー日記」(2013年8月終了) http://www.hatorishoten-articles.com/ikedamanabu ▼概要 驚異の宝箱──ペンで紡がれた壮大な宇宙に遊ぶ 超細密なペン画で観る者を圧倒する池田学の初画集。《再生》(2001)、《存在》(2004)、《興亡史》(2006)、《予兆》(2008)など、1年以上かけて制作した作品を核に、最新作を含め45点を収録。 収録作品(ページ/作品タイトル/制作年) 003 巌ノ王/King of Rocks (1998) 008 森/Forest (1998) 012 けもの隠れ/Refuge of the Wild (1999) 016 かぶとむし /Rhinoceros Beetle (1999) 017 ぶなしめじ/Bunashimeji Mushrooms (1999) --- ブロッコリーの木/Broccoli Tree (1998) 018 ブッダ/Buddha (2000) 024 再生/Regeneration (2001) 032 記憶/Memories (2002) 034 銀河鉄道/Galactic Train (2004) 036 古民居/Old Folkhouse (2004) 037 美しい土地/Beautiful Land (2004) 038 存在/Existence (2004) 046 領域/Territory (2004) 048 くさかまきり/Grass Mantis (2004) 049 はなかまきり/Flower Mantis (2004) 050 方舟/Ark (2005) 056 蛸/Tentacles (2004) 057 罠/Trap (2004) 058 興亡史/History`s Rise and Fall (2006) 066 バイク武者(興亡史より)/Bike Warrior (episode from History`s Rise nad Fall) (2006) --- 紙武者(興亡史より) /Paper Warrior (episode from History`s Rise nad Fall) (2006) 067 二の丸御殿(興亡史より)/Ninomaru Palace (episode from History`s Rise nad Fall) (2007) 068 予兆/Foretoken (2008) 076 航路/Waterway (2008) 077 竜/Dragon (2008) 078 氷流(予兆より)Ice Stream (episode from Foreoken) (2009) 079 灯台/Light House (2009) 080 Mother Tree/Mother Tree (2009) 081 終着/Terminal (2009) 082 Victim (2009) 087 波/Wave (2010) 088 氷窟/Ice Cavern (2010) 089 とぐろ/ Swallowing (2010) 090 命の飛沫/ Lifeblood Spanish (2010) 092 Bait /Bait (2010) 093 梅雨虫/Tsuyumushi (2010) 094 Gate (2010) 096 香葬/Conffin Incense (2010) 098 眠るツチブタ/Aardvark Asleep (2005) 100 カバ/Hippopotamus (2009) 101 ウマヅラコウモリ/Hammer-headed Bat (2010) --- トラ/Tiger (2007) 102 グレビーシマウマ/Grevy`s zebra (2008) --- マレーグマ/ Sun bear (2010) 宇宙の空/Voids in the Universe 片岡真実/KATAOKA Mami(森美術館チーフ・キュレーター) あとがき/ Afterword ▼プロフィール 池田 学(いけだ まなぶ) 1973年佐賀県多久市生まれ。98年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。卒業制作にて紙に丸ペンを使用した独自の細密技法を確立。2000年同大学院修士課程を修了。2011年から1年間、文化庁の芸術家海外研修制度でカナダ・バンクーバーに滞在。2013年よりアメリカ・ウィスコンシン州マディソンにて滞在制作を行っている。 ▼関連書籍 池田学+三瀬夏之介『現代アートの行方』
MORE -
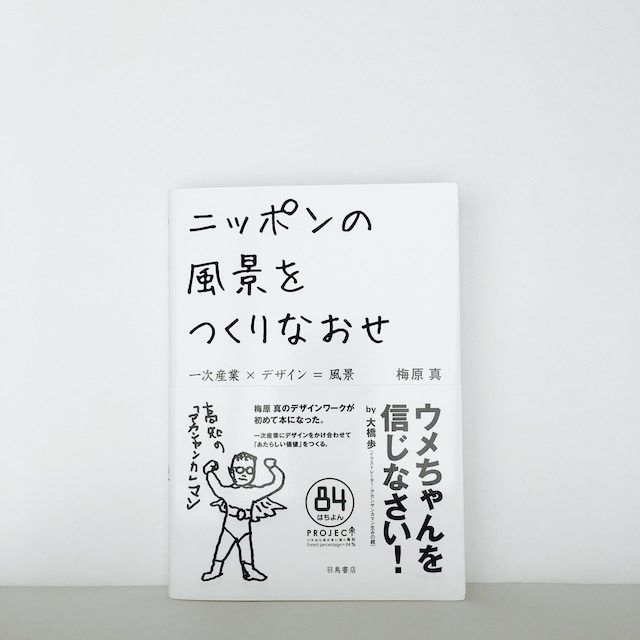
梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ── 一次産業×デザイン=風景
¥2,860
A5判 並製 240頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-12-3 C0070 2010年7月刊行 ブックデザイン 基本デザイン: 梅原 真 デザイン協力: 原 研哉+中村晋平 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 ▼書評・記事 『ダヴィンチ』 2013年7月号 「この本にひとめ惚れ」コーナーで、糸井重里さんが梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ』を選んでくださいました。「彼の取り組みには注目している。来る仕事を全力でやる人なのだ。その仕事ぶりはすごいの一言」。 『日経ビジネスオンライン』2013年10月23日 「古新聞をバッグに変えて世界に売り込め! 新聞バッグの生みの親、梅原サンに発想のヒントを聞いてみた」で梅原真さんがとりあげられました。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20131017/254713/?rt=nocnt NHK Eテレ『東北発★未来塾』(毎週木曜日23:00~23:20) 2013年11月の講師に梅原真さんが登場しました。テーマは「デザインのチカラ」 ▼概要 一次産業にデザインをかけ合わせて「あたらしい価値」をつくりだす、 デザイナー梅原真の仕事が初めて本になった。 「ウメちゃんを信じなさい!」 by 大橋歩(イラストレーター・アカンヤンカマン生みの親) ここにあるのはすべて「アカンヤンカ」から始まった仕事です―― 土佐の一本釣り鰹漁船の風景を守った「漁師が釣って、漁師が焼いた」藁焼きたたき、地域の個性を逆手にとった「島じゃ常識・さざえカレー」、箱モノ行政まっ盛りのバブル時代にTシャツを砂浜にひらひらさせた「砂浜美術館」、森林率84%の高知から発信する「84(はちよん)プロジェクト」……梅原真のデザインワーク&コンセプトワーク47点。デザインはどのようにして生まれるのか。著者による依頼人紹介付き。 「本書がいい意味で、日本の尻を叩いてくれることを期待したい。」 (原研哉「しらうおや尾頭付きが二万匹」より) [主要目次] 一次産業×デザイン=風景MAP なんで全部静岡に出すんじゃ[100%静岡茶?] ひらひらします[ボクは町長室の中でアブラアセを掻いていた] ラッキョウの花見[7時のニュース] 漂流物展[ゴミでポスター] 漁師が釣って漁師が焼いた[8年で20億、20年で50億] 四万十川を新聞紙で包む[地球を新聞紙で包む] タノシキ農村[フランス語ではありません] 川のりを干す風景[よごれた川] 島じゃ常識[離島のカレー] むら[村か町か] スタジオジブリではなくシマントジグリ[農村再生] 天空のおやじ[コムデギャルソン──子供のように] 鶴の湯のフランス[これでエエダス] 秘湯は津波[HITOH] ヤンキーのあさり[ぷりぷり] シブガキ隊[加齢臭] 邪を払うじゃばら[とおい村] ラフスケッチ[原発の町] てらこやのようなかみこや[畑から和紙をつくるガイジン] オーガニック[江戸製法] シロ・ド・イナカ[純国産・砂丘のぶどう] カツオとアイス[塩アイス] ラストリバー[答えは水の中] 「ユニットバス」が「ひのき風呂」[銀行がお買い上げ] 山崎一郎さんはどこ?[K] okeok. com[金髪娘のおやじギャグ] ニューヨークの桶[桶コラム] obusession[これもまたオヤジギャグ] 修景[だんな] ピナさようなら[くじら] INFORMATIONのある風景 ふんばりきれるか?[やんばらー] 近藤けいこのナチュラルベジ[野菜の時代] 恐ろしい──美しい──かわいい[真っ暗闇] EARTHDAY[イラストレーターなワタシ] 間城正博作[紀ノ国屋行き] シャモで農村の風景を作り直す[龍馬が食べ損ねたシャモ] ルーブルにいこう!![世界で一番薄い紙] ジブンモノサシ[村長] 経済47番目の国のしあわせ[とさのかぜ] 去りゆく技 季節からの電話 勝手に重要文化財[太鼓判] 84(はちよん)[サプライズ] CO2のカンヅメ[2020年|-25] 84木づかいサイン[間伐で日本の風景をつくる] 84やさいカフェ[No SKIP! 地産池消のやさいカフェ] アカンヤンカマン/師匠 大橋歩(イオグラフィック) しらうおや尾頭付きが二万匹 原 研哉 プロフィール 梅原真デザインワーク ▼プロフィール 梅原 真(うめばら まこと) グラフィックデザイナー、武蔵野美術大学客員教授。1950年高知市生まれ。1972年、大阪経済大学経済学部を卒業後、高知に戻りRKCプロダクション美術部に入社。日本テレビで研修の後、スタジオの大道具担当に。25歳の時、スペインへ渡り休職。1979年、退職後アメリカ大陸を横断。サンフランシスコ滞在を経て帰国。1980年梅原デザイン事務所設立。土佐を拠点に、一次産業再生をテーマとして全国で活動中。 公式HP http://umegumi.jp/ NPO 84はちよんプロジェクト 代表。 2011年より、秋田県イメージアップ戦略アドバイザーをつとめる。 ◎梅原さんデザインの商品特集ページ 道の駅「四万十とおわ」(四万十ドラマ)|しまんとニュース ▼関連書籍 梅原真×原研哉『梅原デザインはまっすぐだ!』 原研哉[編]『みつばち鈴木先生──ローカルデザインと人のつながり』 迫田司『四万十日用百貨店』
MORE -
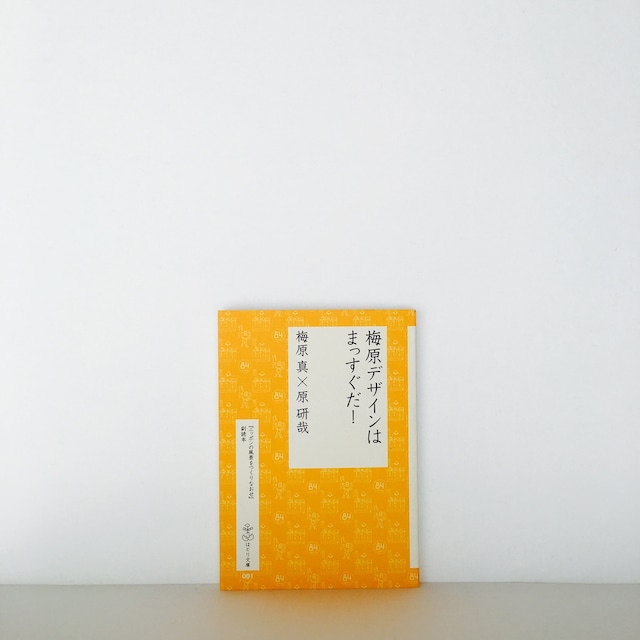
梅原真・原研哉『梅原デザインはまっすぐだ!』(はとり文庫001)
¥770
A6判 並製 136頁 本体価格 700円+税 ISBN 978-4-904702-23-9 C0070 2011年6月刊行 ブックデザイン 原 研哉+中村晋平 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 グラフィック・デザイナーの梅原真、原研哉による対談。 土佐を拠点に活躍する梅原真の仕事をまとめた『ニッポンの風景をつくりなおせ』刊行記念として2010年7月に行われた公開対談では、10年来の友人でもある “芸風”のちがうデザイナー同士の息のあった掛け合いが会場を魅了。 収録:2010年7月20日(青山ブックセンター本店) [目次] ミツバチにつなげてもらった縁 ひらひらします──砂浜美術館 漂流物展 島じゃ常識・さざえカレー さざえカレー後日談 なぜ、さざえ? 漁師が釣って、漁師が焼いた “確信”以前と以後? 高校・大学時代 テレビの仕事 デザイナーへの道のり アメリカ遊学からデザイナー初仕事へ アカンヤンカ 84はちよんプロジェクト ローカルとデザイナー 日本というローカル 日本の「本当」を探す 抽選会 質疑応答 嘆いていてもアカンヤンカ 本質だと思えば、それはやがてやってくる 梅原真を飛ばす風 人生相談? 東京のデザイン・デザイン。 梅原 真 ▼プロフィール 梅原 真(うめばら まこと) グラフィックデザイナー、武蔵野美術大学客員教授。1950年高知市生まれ。1972年、大阪経済大学経済学部を卒業後、高知に戻りRKCプロダクション美術部に入社。日本テレビで研修の後、スタジオの大道具担当に。25歳の時、スペインへ渡り休職。1979年、退職後アメリカ大陸を横断。サンフランシスコ滞在を経て帰国。1980年梅原デザイン事務所設立。土佐を拠点に、一次産業再生をテーマとして全国で活動中。 NPO 84はちよんプロジェクト 代表。http://www.kochi-84project.jp/ 2011年より、秋田県イメージアップ戦略アドバイザーをつとめる。 [著書]『ニッポンの風景をつくりなおせ── 一次産業×デザイン=風景』 公式HP http://umegumi.jp/
MORE -

澤田教一『澤田教一 故郷と戦場』
¥4,950
SOLD OUT
A4判変型 並製 296頁(カラー240頁) 本体価格 4,500円+税 ISBN 978-4-904702-64-2 C0072 2016年10月刊行 ブックデザイン 小川順子 *展覧会情報 青森県立美術館開館10周年記念 「生誕80周年 澤田教一:故郷と戦場」 2016年10月8日〜12月11日 http://www.aomori-museum.jp/ja/exhibition/89/ 2017年 IZU PHOTO MUSEUMへ巡回 ▼書評・記事 共同通信/各紙 『東奥日報』2016年12月6日 「澤田教一展」全国最高賞/カタログ展で青森県立美術館写真集 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20161206020396.asp 『産経新聞』2016年12月31日 ベトナム戦争最前線…34歳で銃弾に倒れたカメラマンの326点 『故郷と戦場』澤田教一 http://www.sankei.com/life/news/161231/lif1612310016-n1.html ▼概要 青森市に生まれ育ち、カメラ店に勤めた米軍三沢基地時代を経て、東京、ベトナム、カンボジアへ 澤田教一が伝える「アメリカの戦争」 青森県立美術館に寄託された約23,000カットにおよぶフィルムや膨大な資料を調査。半世紀近い時をこえて遺されたネガを、高精細デジタルカメラで撮影して甦らせる。カラー、モノクロをまじえて時代を追い、発表カット前後のシークエンスも多数掲載。 青森・三沢に撮られた写真、世界中に配信された電送写真、前線からフィルムを送った封筒、従軍時に持ち歩いた手帖、原稿が掲載された新聞・雑誌、夫人への手紙、「ピュリツァー賞ポートフォリオ」全28点(初公開)など、貴重な資料とともに、澤田の34年の生涯をたどる。 図版327点 寄稿:生井英考、石川文洋 青森県立美術館「澤田教一:故郷と戦場展」公式写真集 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。 ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 『澤田教一 故郷と戦場』正誤表 (2016年10月31日) http://www.hatorishoten.co.jp/sawada_seigo-hyo_201610.pdf ▼プロフィール 澤田教一(さわだ きょういち) 1936年 青森県青森市に生まれる。 1954年 三沢米軍基地内の写真機店で働きながら、本格的に写真を撮り始める。 1961年 米軍将校から譲り受けたライカを携え、プロの写真家として活躍するために上京。同年12月UPI東京支局に入社。 1965年 UPIサイゴン支局写真部に特派員として赴任。9月、代表作となる《安全への逃避》を撮影。この写真で12月、第9回ハーグ世界報道写真展のグランプリを受賞。また同作は、第23回USカメラ賞も受賞。 1966年 《安全への逃避》でピュリツァー賞を受賞。《泥まみれの死》、《敵をつれて》が第10回ハーグ世界報道写真展で第一位、二を受賞。 1968年 UPI香港支局写真部長として転勤。第26回USカメラ賞。 1970年 サイゴン特派員として再びベトナムに赴任。同年10月、カンボジア取材中、プノンペン近郊で銃撃され34歳で死亡。カンボジアを取材した一連の写真で、死後、70年度のロバート・キャパ賞を受賞している。
MORE -
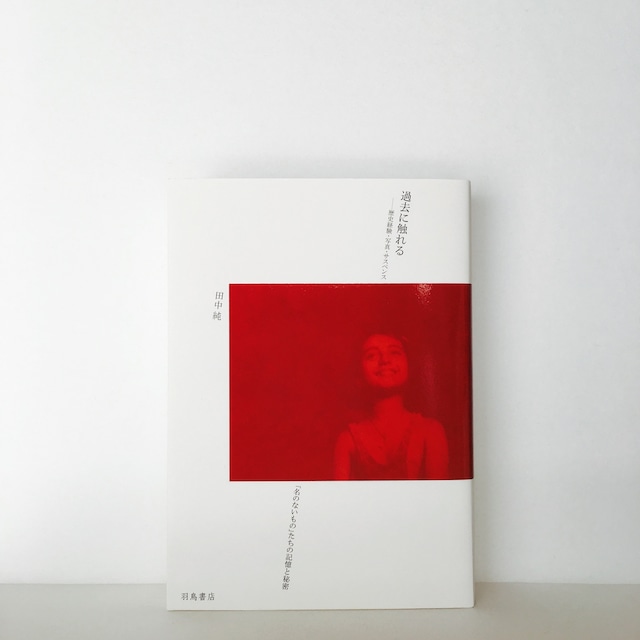
田中純『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』
¥5,500
SOLD OUT
A5判 並製 620頁 本体価格 5,000円+税 ISBN 978-4-904702-60-4 C3010 2016年4月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『美術手帖』2016年7月号 『図書新聞』2016年7月23日号 上半期読書アンケート http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-07-22 『ハヤカワ ミステリ マガジン』2016年9月号「ミステリ サイド ウエイ」 『Book Club Kai News Letter』2016 summer (VOl. 102) ▼概要 「名のないもの」たちの記憶と秘密。 歴史的想像力が極度の緊張を持って過去に向かうとき、いまだ決定されていない未来がたちあがる。 歴史経験の現場で、思考の襞をたどる── 堀田善衞、宮沢賢治、橋川文三、松重美人、畠山直哉、牛腸茂雄、多木浩二、ヨーハン・ホイジンガ、アビ・ヴァールブルク、ジルベール・クラヴェル、ダニエル・リベスキンド、W・G・ゼーバルト、ヴァルター・ベンヤミン、ロラン・バルト、ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 「過去に触れる」という「歴史経験」を探究するエッセイ集成。とりわけ写真を通した過去との接触という出来事に着目して、小説家、詩人、思想家、建築家、美術史家、文学者、写真家たちの具体的な歴史経験から「過去に触れる」瞬間を描きだす。また、その経験を伝達する歴史叙述のあり方を「サスペンス」の原理のうちに見出し、本書の探究もまた、サスペンスの様相を呈したスリリングな展開をみせる。「過去に触れる」旅の果てに見えてくる、歴史および写真における「希望」とは何か。書下しを含めた19本のエッセイでつむぐ。図版127点収録。 [主要目次] はじめに 序 危機の時間、二〇一一年三月 第1章 歴史の無気味さ──堀田善衞『方丈記私記』 第2章 鳥のさえずり──震災と宮沢賢治ボット 第3章 渚にて──「トポフィリ──夢想の空間」展に寄せて 第4章 希望の寓意──「パンドラの匣」と「歴史の天使」 I 歴史の経験 第1章 過去に触れる──歴史経験の諸相 第2章 アーシアを探して──アーカイヴの旅 第3章 半存在という種族──橋川文三と「歴史」 第4章 いまだ生まれざるものの痕跡──ダニエル・リベスキンドとユダヤ的伝統の経験 II 極限状況下の写真 第1章 剥ぎ取られたイメージ──アウシュヴィッツ=ビルケナウ訪問記 第2章 歴史の症候──ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『イメージ、それでもなお』 第3章 イメージのパラタクシス──一九四五年八月六日広島、松重美人の写真 III 歴史叙述のサスペンス 第1章 迷い蛾の光跡──W・G・ゼーバルトの散文作品における博物誌・写真・復元 第2章 歴史素としての写真──ロラン・バルトにおける写真と歴史 第3章 歴史小説の抗争──『HHhH』対『慈しみの女神たち』 第4章 サスペンスの構造と歴史叙述──『チェンジリング』『僕だけがいない街』『ドラ・ブリュデール』 第5章 歴史という盲目の旅──畠山直哉『気仙川』を読む IV 歴史叙述者たちの身振り 第1章 歴史の現像──ヴァルター・ベンヤミンにおける写真のメタモルフォーゼ 第2章 記憶の色──ヴァルター・ベンヤミンと牛腸茂雄の身振りを通して 第3章 「歴史の場(ヒストリカル・フィールド)」の航海者──「写真家」多木浩二 結論 歴史における希望のための十のテーゼ 註/跋/書誌・フィルモグラフィ/図版一覧/人名索引/事項索引 ▼プロフィール 田中 純 (たなか じゅん) 1960年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授・表象文化論(思想史・イメージ分析)。 [主要著書] 『都市表象分析I』(INAX出版、2000) 『ミース・ファン・デル・ローエの戦場』(彰国社、2000) 『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』『死者たちの都市へ』(青土社、2001、2004、サントリー学芸賞受賞) 『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞) 『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008、毎日出版文化賞受賞) 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010) 『建築のエロティシズム 世紀転換期ウィーンにおける装飾の運命』(平凡社新書、2011) 『冥府の建築家 ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房、2012) 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010) 公式ブログ Blog (Before- & Afterimages) http://news.before-and-afterimages.jp/index.html *『過去に触れる』関連書籍リスト 選書・田中純 http://before-and-afterimages.jp/news2009/2016/04/post-227.html
MORE -
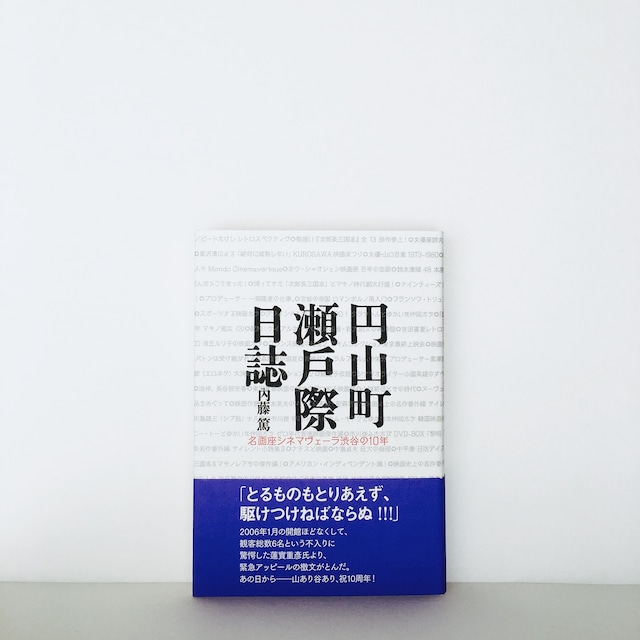
内藤篤『円山町瀬戸際日誌──名画座シネマヴェーラ渋谷の10年』
¥2,640
四六判 並製 346頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-59-8 C0074 2015年12月刊行 ブックデザイン 大森裕二 ▼書評・記事 『Real Sound 映画部』内藤篤氏インタビュー 「映画には過去も現在もない」シネマヴェーラ渋谷館主が明かす、名画座経営10年の信念 http://realsound.jp/movie/2015/12/post-676.html 『Cut 』2016年2月号 「著者の映画愛溢れるエッセイ」「映画ファン必読の一冊」http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-01-25 『BOOKSTAND映画部! 』【映画を待つ間に読んだ、映画の本】 第26回 『円山町瀬戸際日誌/名画座シネマヴェーラ渋谷の10年』~名画座の経営は、「解せぬ!!」ことの連続なのだ。 (文/斉藤守彦)http://bookstand.webdoku.jp/cinema/saitou/201601/23120000.html 『新潮45』2016年2月号 「弁護士兼名画座館主の映画愛」(評/文芸ジャーナリスト・佐久間文子)http://www.bookbang.jp/review/article/507487 『読売新聞』2016年1月31日 本よみうり堂「著者来店」 弁護士の傍ら名画座開館「弁護士として映画や音楽の法実務に関わる一方で、2006年に名画座「シネマヴェーラ渋谷」を東京渋谷区円山町に開館、「映画狂い」の性分を生かし二足のわらじを履く。(中略)「期待しないで見た映画が面白いと感動も大きい。ネットで評判を調べて見るのはもったいない」。上映プランの一つ一つに未来の映画ファンへの思いを込めている。」(記事・多可政史) http://www.yomiuri.co.jp/life/book/raiten/20160201-OYT8T50065.html?from=tw 『考える人』(新潮社)メールマガジン 「弁護士はいかにして名画座館主となりしか」(「考える人」編集長 河野通和) 『産経新聞』2016年3月6日「聞きたい。」 一本一本に愛情を込めて「シネコン全盛の昨今、個人経営の映画館を、それも世の趨勢から取り残されたような名画座を、東京・渋谷の円山町に開設して10年がたつ。いまだに客の好みがわからないとぼやくが、それでも何だか楽しそうな様子が行間から漂ってくるのは気のせいか。(後略)」(記事・藤井克郎) http://www.sankei.com/life/news/160306/lif1603060021-n1.html ジュンク堂書店PR誌『書標』(ほんのしるべ)2016年3月号 著書を語る 「『円山町瀬戸際日誌』を上梓して」(内藤篤)https://honto.jp/store/news/detail.html?nwid=1000018276&shgcd=HB300&extSiteId=junkudo&cid=eu_hb_jtoh_0411 『キネマ旬報』5月上旬号 「ゆるやかな空気の変化を記したメモワール」(評/佐野亨) 『映画芸術』455号 「二十一世紀的名画座の成り立ちと日常」(評/千浦僚) ▼概要 弁護士業と二足のわらじを履く、館主の一喜一憂と、「名画座」の行く末を描く、名画座館主のエッセイ 。10年間の「番組一覧」付。 シネマヴェーラ渋谷 開館10周年記念刊行 http://www.cinemavera.com/index.html 「とるものもとりあえず、駆けつけねばならぬ ! ! !」 2006年1月の開館ほどなくして、観客総数6名という不入りに驚愕した蓮實重彦氏より、緊急アッピールの檄文がとんだ。あの日から──山あり谷あり、祝10周年! [目次] 円山町三国志 または、余は如何にして名画座親父となりし乎 円山町瀬戸際日誌 山口百恵編 鈴木清順編 「廃墟としての90年代」仕込み編 最終兵器・鈴木則文降臨! 清水宏あるいは「素材論的憂鬱」 グラインドハウス A GO GO!! 生誕100年マキノ雅弘 宴の準備 生誕100年マキノ雅弘 宴の始末 混迷と繁忙の7月 年末年始への慌ただしさ サヨナラだけが人生だ 新・円山町瀬戸際日誌 岸田森は「持ってる男」なのか? 喜劇監督としての野村芳太郎 千葉チャンはお祭りである 11度目の「映画史上の名作」の夏 あるいは興行事情激変の巻 台北番外編 ナゾの監督・中村登 洋画でカラブリ? 佐分利信でリベンジ? 韓国映画の怪物たち 曾根中生追悼! 映画史上の名作で一息 ワイズマン! 岡本喜八讃歌 神代辰巳没後20周年 安藤昇 祝芸能生活50周年 ルビッチ・タッチ! あとがき 番組一覧 ▼プロフィール 内藤 篤 (ないとう あつし) 1958年東京生まれ。弁護士(1985年登録)・ニューヨーク州弁護士(1990年登録)。2006年より名画座「シネマヴェーラ渋谷」館主。 東京大学教養学部の蓮實重彦映画ゼミに1年半モグリで参加。東京大学法学部卒業後、大手渉外法律事務所に勤務ののち、1994年に内藤・清水法律事務所(青山綜合法律事務所と改称)を開設。主たる仕事領域は、エンタテインメント(映画、音楽、演劇、音楽出版、マーチャンダイジング、アート取引、玩具、広告等)およびメディア/コミュニケーション関係(放送、出版、インターネット等)の法実務。慶應義塾大学法科大学院講師および一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師(ともにエンタテインメント法担当)。 *主要著書 『ハリウッド・パワーゲーム──アメリカ映画産業の「法と経済」』(TBSブリタニカ、1991年、平成3年度芸術選奨文部大臣新人賞受賞) 『エンタテインメント・ロイヤーの時代──弁護士が語る映像・音楽ビジネス』(日経BP出版センター、1994年)、『走れ、エロス!』(筑摩書房、1994年) 『エンタテインメント契約法[第3版]』(商事法務、2012年) [共著] 『パブリシティ権概説[第3版]』(木鐸社、2014年) 『映画・ゲームビジネスの著作権 [第2版]』(CRIC、2015年) [翻訳書] 『エンターテインメント・ビジネス──その構造と経済』(ハロルド・L・ヴォーゲル著、リットーミュージック、1993年)
MORE -
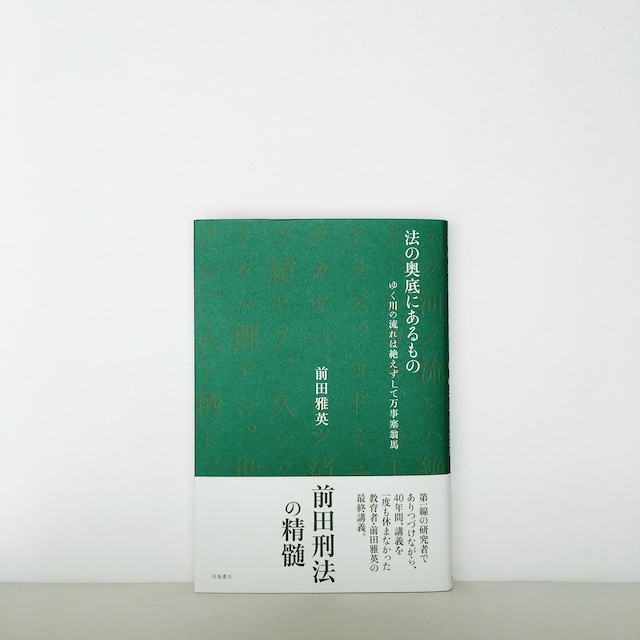
前田雅英『法の奥底にあるもの──ゆく川の流れは絶えずして万事塞翁馬』
¥2,200
四六判 並製 152頁 本体価格 2,000円+税 ISBN 978-4-904702-57-4 C3032 2015年11月刊行 ブックデザイン 大森裕二 ▼書評・記事 『読売新聞』2015年12月6日 本よみうり堂「著者来店」 講義に情熱 休まず40年「(前略)時代の流れで変わる判断を、法理論にくみ上げて説明することが法律家の仕事と考える。「○か×かどちらかと言われても、答えは見つからない。足して2で割るのも間違っている」。調和点を求める過程こそが重要だという。(後略)」(記事・原田和幸) http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2015-12-16 『都市問題』2016年6月号 評者:小石川裕介(後藤・安田記念東京都市研究所研究員) ▼概要 前田刑法の精髄。 刑事法学の第一線研究者でありつづけながら、40年間、講義を一度も休まなかった教育者・前田雅英の最終講義。 [目次] Ⅰ 四〇年間の講義 大陸移動説と「アメリカ大陸の発見」 万事塞翁馬 「銀行員半沢直樹」の世界 犯罪の増減は振り子のように 一九七五年という転換点 戦後社会の「波」と法理論の変化 最高裁の大きなうねり 財産犯の本質論の揺れ動き 未遂と共犯と大陸移動説 学問と縁──目黒区八雲(一九四九年) 刑法研究会と東京大学出版会 『刑法講義』と『刑事訴訟法講義』 判例研究の意味 「真理」は動くものである──儚いもの? 行為無価値論を採用しなければ社会は静止する? 行為無価値論と結果無価値論の対立の意味 新過失論と戦後の高度経済成長 公害現象と価値観の反転 Ⅱ 法理論から結論は導けない──法解釈とは価値判断である 死刑廃止論と表現の自由 法解釈は価値判断を隠す手品である 「どちらが正しいのか」と言ったとき、「問」まで雲散する 「場」が変われば答えも変わる──刑罰論の変化 解釈は考量である 異次元のものの比較 疑わしきは被告人の利益に──刑事法の衡量の特殊性? 「立場」が変われば結論も変わる? 「法」は相対的である 西欧近代からの「守・破・離」 リスト=シュミット二五版 国民の規範意識とポピュリズム 「価値」は不条理なもの 日本は「判例法国」である 実質的犯罪論 団藤刑法学と三島由紀夫の自殺 形式的犯罪論の極──中山刑法 実質的犯罪論と『可罰的違法性論の研究』 実質的構成要件論──構成要件該当性判断は、価値評価を伴う 実質的違法論 実質的責任論 日本的共犯論 量刑と理論──理論と結論の関係の典型 判例への信頼と実質的犯罪論 あとがき ▼プロフィール 前田雅英(まえだ まさひで) 1949年 東京に生まれる 1972年 東京大学法学部卒業 1975年 東京都立大学法学部助教授 1988年 東京都立大学法学部教授 2005年 首都大学東京法科大学院教授 現 在 日本大学大学院法務研究科教授 [主要著書] 『可罰的違法性論の研究』(東京大学出版会、1982年) 『刑法演習講座』(日本評論社、1991年) 『現代社会と実質的犯罪論』(東京大学出版会、1992年) 『刑法の基礎 総論』(有斐閣、1993年) 『刑法から日本をみる』共著(東京大学出版会、1997年) 『少年犯罪──統計からみたその実像』(東京大学出版会、2000年) 『裁判員のための刑事法入門』(東京大学出版会、2009年) 『ハンドブック刑事法──罪と罰の現在』(東京法令出版、2014年) 『刑事訴訟法講義[第5版]』共著(東京大学出版会、2014年)(初版2004年) 『刑法総論講義[第6版]』(東京大学出版会、2015年)(初版1988年) 『刑法各論講義[第6版]』(東京大学出版会、2015年)(初版1989年)
MORE -

山本浩二『もうひとつの自然×生きている老松』
¥5,500
B5判 並製 透明ケース入り 120頁 本体価格 5,000円+税 ISBN 978-4-904702-56-7 C1071 2015年11月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 印刷所 株式会社 山田写真製版所 製本所 株式会社 渋谷文泉閣 ▼書評・記事 『日刊ゲンダイ』2015年11月25日「路地裏の読書術」 創造と批評を一身に具える稀有の画家「(前略)この画家にとっては、ひとつの作品が生まれてくることは奇跡であり、かれは自らの身体を、この創造に貸し与える。同時に、かれにとっては、ひとつの作品は、それまで存在してきたすべての作品に対する批評でもある。(後略」)」(評・平川克美) http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2015-12-04 ▼概要 山本浩二画集 もうひとつの自然×生きている老松 「生きているもの」の生命過程そのものを描く ──内田 樹 画家・山本浩二が近年挑みつづける「もうひとつの自然」と「老松」の作品群。現代抽象画の可能性を拓き、芸術の極北へ。 光を放つ豊かな色彩と、何層にも重ねられた筆致の深みを、高輝度インキ印刷で再現する。 [収録エッセイ] 内田樹(思想家/武道家) 山内麻衣子(金沢能楽美術館) 山本浩二 抽象的な図形だけを描き続けてきたその山本が、あるときから自然界に実在するものの「かたち」のうちに彼の創作意欲をはげしく刺激するものを見出した。とりあえずは一枚の葉のかたちだった。それは生命だけが創り出すことのできるかたちである。生まれ、育ち、衰え、枯れる、一瞬の休止もなく流れるようなプロセスだけが創り出すことのできるかたちである。 ──内田樹「山本浩二の老松」より ▼プロフィール 山本浩二(やまもと こうじ) 画家。1951年生まれ。日本における抽象画の代表的作家の一人で、イタリア・ミラノを拠点に国際的に活躍する。2011年、内田樹氏の合気道場「凱風館」の能舞台に、抽象画による「老松」を制作し話題となる。2013年、ミラノ・ガレリアの老舗ボッカ書店に天井壁画を常設。2015年1月の芦屋シューレを皮切りに、5月大阪・中之島de sign de >、10月の銀座・永井画廊を経て、2016年秋にはミラノ・ロレンツェッリ・アルテで個展を開催。 大阪・中之島de sign de > http://designde.jp/2015/05/another-nature-x-a-living-old-pine/
MORE -
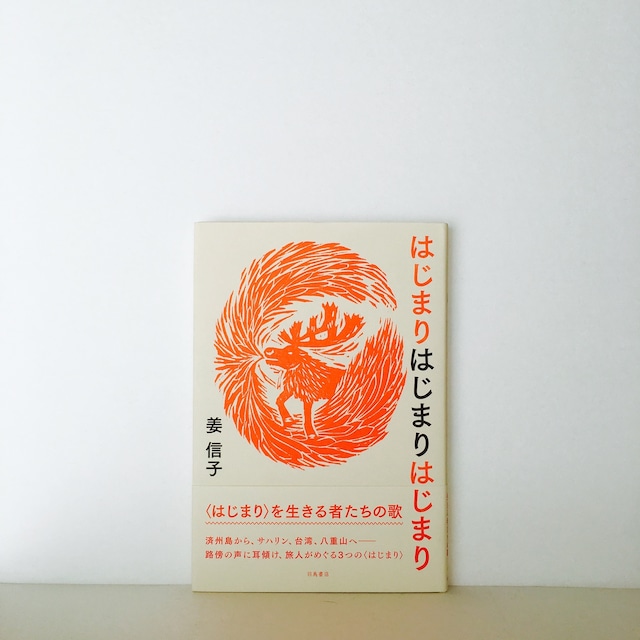
姜信子『はじまりはじまりはじまり』
¥2,640
四六判 上製 80頁(オールカラー) 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-55-0 C0095 2015年9月刊行 ブックデザイン 大西隆介(direction Q) *刊行記念 原画展示&トークイベント 2015年9月1日(火)~9月10日(木) トークイベント 9/9(水) 19:00~ 出演:姜信子 司会:跡上史郎 ゲスト:渡部八太夫 熊本 橙書店 http://www.zakkacafe-orange.com/top/ 2015年9月22日(火・祝)~10/3(土) オープニングパーティー 9/22(火・祝) 18:00~ トークイベント 10/2(金) 19:00~ 出演: 姜信子 ゲスト: 山福朱実、屋敷妙子、早川純子、塩川いづみ 東京築地 ふげん社 http://fugensha.jp/ ▼書評・記事 『東京新聞』夕刊 2015年10月24日 「神話を思わせる三つの物語が、美しい挿絵とともに収録されている。中の一作「うたのはじまり」には、ある詩と、その制作にまつわるエピソードが盛り込まれた。詩は3・11後に開かれた「足りない活字のためのことば展」に著者が寄せたもの。被災した印刷工場の床に散らばり廃棄されそうになっていた「文字の足りない活字」を使って作った。詩の成り立ちが、物語の中の神話と結び付く。」 ▼概要 〈はじまり〉を生きる者たちの歌 済州島から、サハリン、台湾、八重山へ── 路傍の声に耳傾け、旅人がめぐる3つの〈はじまり〉 姜信子が書下し、4人の画家が描く〈はじまり〉の物語 [画]山福朱実、屋敷妙子、早川純子、塩川いづみ 「あいのはじまり」 石が語る神話ソルムンデハルマン 「うたのはじまり」 文字をなくしたウイルタとブヌンの民 「たびのはじまり」 永遠の旅人まゆんがなし ▼プロフィール 姜信子(きょう のぶこ) 1961年横浜市生まれ。詩人・作家。86年、「ごく普通の在日韓国人」でノンフィクション朝日ジャーナル賞受賞。主著に『かたつむりの歩き方』『私の越境レッスン』『うたのおくりもの』(以上、朝日新聞社)、『日韓音楽ノート』『ノレ・ノスタルギーヤ』『ナミイ! 八重山のおばあの歌物語』『イリオモテ』(以上、岩波書店)、『棄郷ノート』(作品社)、『安住しない私たちの文化』(晶文社)、『今日、私は出発する ハンセン病と結び合う旅・異郷の生』(解放出版社)、『はじまれ 犀の角問わず語り』(サウダージ・ブックス+港の人)ほか。翻訳に李清俊『あなたたちの天国』(みすず書房)、共著に『追放の高麗人』(アン・ビクトルと、石風社)、『旅する対話』(ザーラ・イマーエウと、春風社)、編集に『死ぬふりだけでやめとけや 谺雄二詩文集』(みすず書房)等。近著に『生きとし生ける空白の物語』(港の人)、『声 千年先に届くほどに』(ぷねうま舎)。路傍の声に耳傾けて読む書く歌う旅をする日々。
MORE -
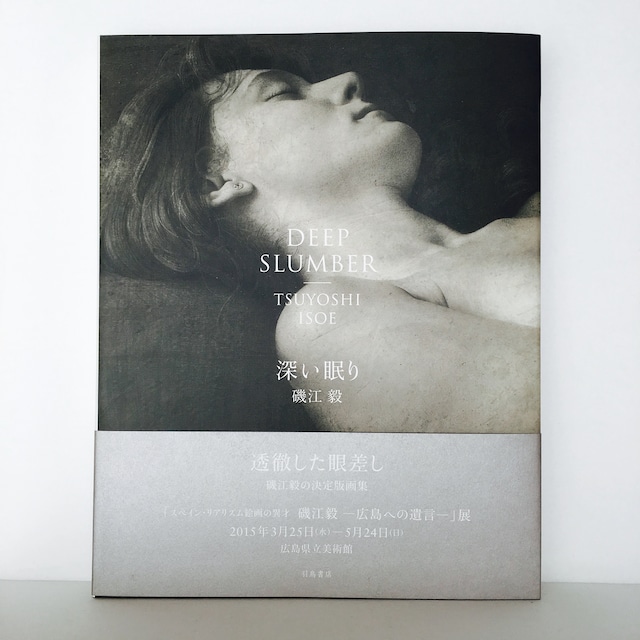
磯江毅『深い眠り』
¥4,950
A4判変型 上製 280頁(カラー176頁) 本体価格 4,500円+税 ISBN 978-4-904702-52-9 C1071 2015年4月刊行 ブックデザイン 一瀬貴之 印刷・製本所 サンエムカラー *展覧会情報 広島県立美術館 2015年3月25日~5月24日 スペイン・ リアリズム絵画の異才 磯江毅 ―広島への遺言―展 http://www.hpam.jp/special/index.php?mode=detail&id=126 ▼書評・記事 『読売新聞』2015年6月7日 「(前略)若くしてスペインで画法を学んだ磯江毅の決定版画集である。フランコ独裁政権が長く続いたスペインでは、現代絵画の潮流とは一線を画して、写実主義が確固と根を下ろしていた。(中略)スペインと日本、静物から人物へと頁をめくる時間が、たまらなくいとおしい。」(評・牧原出) ▼概要 透徹した眼差し 写実を超えて存在の本質を描く、 磯江毅の決定版画集 西洋絵画の伝統とスペイン・リアリズムの土壌から生まれ、写実を超えて存在の本質を描く画家、磯江毅(1954-2007)の決定版画集。初期作品から絶作、デッサンまで、初公開多数を含む197点収録。 [目次] 作品図版I 1977-2007 作品図版II 習作デッサンを中心に 磯江 毅「真の写実を求めて」「写実考」 [寄稿] 今福龍太「写実という自由」 諏訪 敦「言葉たちをあつめて」 石黒賢一郎「スペインでの濃密な時間」 水野 暁「現実へのこだわり──肉眼が捉えた絵画の記憶」 山本浩二「深い眠り──磯江毅の光跡」 作品コメント/略年譜/作品一覧/参考文献 [主な収録作品] 彩鳳堂画廊 作家紹介 http://saihodo.com/artists/detail/isoe.html
MORE -
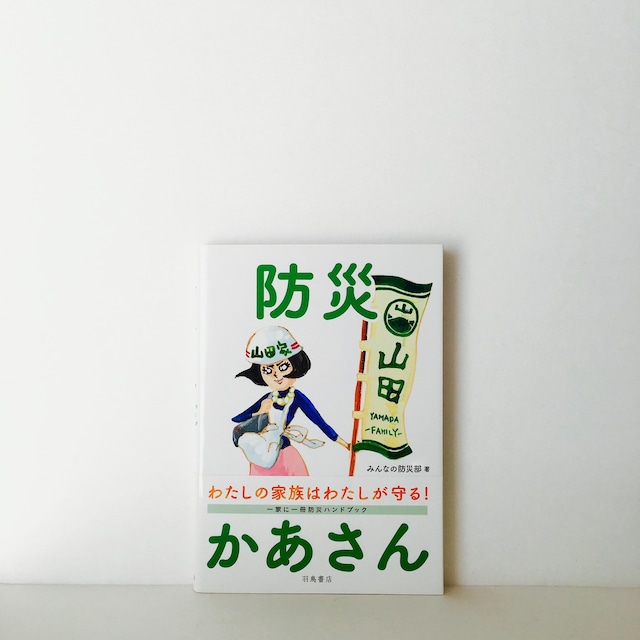
みんなの防災部『防災かあさん』
¥990
B6判 並製 216頁(オールカラー) 「家族防災宣言」とじ込み付 本体価格 900円+税 ISBN 978-4-904702-51-2 C0036 2015年3月刊行 ブックデザイン 小川順子 印刷所 山田写真製版所 製本所 渋谷文泉閣 *企業や自治体・団体様へ 『防災かあさん』をまとめて導入される場合は、CONTACTページよりお問い合わせください。 ▼書評・関連ニュース 内閣府『平成27年度 広報ぼうさい夏号』(第79号) 国連防災世界会議の関連事業「防災産業展」(2015年3月15-17日)に出展 『河北新報』2015年4月7日書評 2015年4月7日4月14日 HNK仙台「てれまさむね」で紹介 特集(くらし 安心・安全「母親の視点 防災バッグ新たな形」) TBSラジオ「防災居酒屋」(2015年2月15日)に『防災かあさん』編集長の石川淳哉さんが出演 http://www.tbsradio.jp/category/page/bousai.html TBSラジオ「明日へのエール」(2015年3月28日)に『防災かあさん』編集長の石川淳哉さんが出演 http://www.tbsradio.jp/yell/2015/03/post-133.html 新刊.jpニュース(2015年3月30日)で紹介。各ポータルサイトにも配信。http://www.sinkan.jp/news/5594 ▼概要 日本は災害大国。防災を「わがコト」に。 日頃の備え、災害時の行動から避難所生活まで 90問の多様なQ&Aで身につける防災知識。 [目次] はじめに 第1章 防災かあさん度セルフチェック 第2章 暮らしのシチュエーション 第3章 知っておこう日本の災害「地震&津波」 第4章 いざというとき役立つ知識と技術「行動開始」 第5章 いざというとき役立つ知識と技術「いざ避難所へ」 第6章 知っておこう日本の災害「いろいろな災害」 第7章 知っておきたい「避難所生活」 第8章 知っておきたい「避難所生活」──長期化&解散まで 第9章 今日から始める防災力アップ 最終章 家族防災宣言をつくろう あとがき 三陸の母たちが語る「あの日」と「教訓」1~9 ▼プロフィール みんなの防災部(ミンナノボウサイブ) https://bosai.tasukeaijapan.jp/ 「自然災害から1人でも多くの人の命を救うこと」を使命として、「日本にいまこそ必要な新しい防災のかたちを、みんなで一緒に作ること」を活動目的に「みんなの防災部」は生れました。2011年に起きた東日本大震災からしばらくの時をへて、人々が未来に向けてようやく歩み出した頃のことです。 そもそもの始まりは、発災10日後に、クラウド上に集まった世界中の人々で創り上げた復興支援情報ポータルサイト「助けあいジャパン」です。佐藤尚之(クリエイティブ・ディレクター、ツナグ代表取締役)、石川淳哉(ソーシャル・バリュー・プロデューサー、ドリームデザイン代表取締役)のふたりの創始者によって政府に働きかけて開設されたサイトは、被災地の人々と支援したい世界中の人々とをつなぐ前線基地となり、あらゆる知恵と技術とマンパワーが集結しました。民間と政府が垣根を超えて初めて連携して情報発信に取り組み、内閣府より公益社団法人として認可を受けた「助けあいジャパン」は、寄附集めや事業支援、ボランティアの送り込み、地元情報発信などの活動を続けてきました。その運営には、業界や所属や国境を超えた何百という民間の人が、自分の「できること」を持ち寄って参加しています。 その活動の中から、防災事業の担い手として誕生したのが「みんなの防災部」、クラウド上の協議体です。日本に津々浦々に共通する防災というテーマに取り組むため、全国の有識者、災害ボランティアのみなさん、防災を推進する一般のみなさんへ参加を呼びかけ、協力を仰いでいます。 そして何よりも、災害大国日本に暮らすみなさんに、ぜひ入部してほしい。「みんなの防災部」は子どもから大人まで誰もが部員になれる、防災を楽しく学び、身につける部活です。 Facebookグループ「防災かあさんの会」にご参加下さい! 防災かあさんの会は、「防災かあさん」を育てるためにつくられたグループです。必ず来るであろう災害から一人でも多くの命を救うため、情報交換をしたり日頃疑問に思っていることを相談して、もっとパワフルな家族の頼れる「防災かあさん」になるための交流の場所です。本書に収められた問題や解説についてのご意見・ご質問や、防災をめぐる話なら自由なトークも大歓迎です。みなさんの参加をお待ちしております。 ★Facebookで「防災かあさんの会」を検索 『防災かあさん』編集長 石川淳哉 http://dream-d.net/ishijun/profile/
MORE -

成田亨『成田亨の特撮美術』
¥4,180
菊判 並製 282頁 本体価格 3,800円+税 ISBN 978-4-904702-50-5 C1071 2015年1月刊行 ブックデザイン 大西隆介(direction Q) レイアウト 山口潤(direction Q) 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣 ▼書評・記事 『毎日新聞』2015年2月8日書評 「独自の技術を編み出しながら実写のようなリアルな場面を作り上げ、特撮が嫌いだった名匠・今井正監督に、試写で「やっぱり実写はいいね」と言わしめた。」 ▼概要 特撮美術のバイブル 「ウルトラ」の怪獣や宇宙人のデザインをてがけた成田亨は、独自に編み出した技術を駆使して“特撮に見えない特撮”を追求した。 54作品(映画・テレビ・舞台・ディスプレイ)と貴重写真235点を通して伝える、成田亨の特撮美術の神髄! [目次] S・F・X(特殊撮影)の可能性 第1章 映画とは何か 1 文化の中の映画の位置 2 映画の位置 3 芸術の分類 4 特殊撮影とは何か 5 映画のための特殊撮影 6 特撮映画 7 特撮映画の美術 8 特撮映画の企画デザイン 第2章 特撮デザイナーの準備 1 脚本を読む 2 打ち合わせをする 3 資料を集める 4 コンテを描く[絵コンテシステム] 5 見積もり予算を組む 6 再び打ち合わせをする 7 セットデザインをする 8 特撮スタッフの打ち合わせ 9 特撮美術スタッフの打ち合わせ 第3章 特撮美術の作業1[セット] 1 平台を敷く 2 ホリゾントを塗る 3 雲を描く 4 山を作る 5 川を作る 6 樹木を作る 7 民家を作る 8 瓦を作る 9 ビルを作る 10 橋を作る 11 海を作る 12 風洞による特撮 13 回転バック 14 汚し 15 星空 16 夜景 第4章 特撮美術の作業2[外注] 1 飛行機のミニチュア 2 船、艦のミニチュア 3 車のミニチュア 4 汽車のミニチュア 5 戦車のミニチュア 6 金属製のミニチュア 7 ビルのミニチュア 8 アイドル・キャラクターの製作 9 怪獣の製作 10 宇宙人の製作 11 新兵器のミニチュア 第5章 特撮の効果 1 飛行機を飛ばす 2 船の航行 3 車を走らせる 4 汽車を走らせる 5 ロケット発射 6 波を立てる 7 燃える町 8 爆破 9 切り出しによるミニチュア・セット 10 原爆を撮る 11 強遠近法模型 12 強遠近法ミニチュア・セット 13 逆遠近法ミニチュア・セット 14 錯視遠近法 15 合成 16 カメラの効果 17 水中撮影の特撮 18 ロケーションによる特撮 19 水中撮影 20 水槽の特撮 第6章 特撮美術の応用 1 特撮の応用1[舞台の特撮] 2 特撮の応用2[新映像の特撮] 3 特撮美術の応用1[舞台の特撮美術] 4 特撮美術の応用2[博覧会・展覧会の特撮美術] 旧版あとがき 写実的ミニチュアワークの集大成 樋口真嗣 成田亨の相棒として 成田流里 復刊にあたって 成田カイリ 作品一覧 ▼プロフィール 成田 亨(なりた とおる) 1929(昭和4) 9月3日神戸市に生まれる。1930年4月青森県に転居後、囲炉裏の炭をつかんで左手火傷。小中学校時代を再び兵庫県で過ごし、空襲に遭遇。青森県で終戦を迎える。県立青森高等学校卒業後、画家・阿部合成、彫刻家・小坂圭二の指導を受ける。 1950(昭和25) 武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。3年次に彫刻科に転科し清水多嘉示に師事。 1954(昭和29) アルバイトで東宝映画「ゴジラ」の撮影現場の手伝いをしたことをきっかけに、映画美術の世界に入り、彫刻家として新制作展(1955[昭和30]年の第19回展から1971[昭和46]年の第35回展まで)に出品を続けながら、映画の特撮シーンを数多く手がける。 1960(昭和35) 東映で特撮美術監督。1962(昭和37)年第26回新制作展で《八咫》が新作家賞受賞、協友となる。 1965(昭和40) 円谷特技プロダクションと契約、「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「マイティジャック」の怪獣、宇宙人、メカニックのデザインのほか、特技全般を手がける。 1968(昭和43) 円谷プロを離れる。以後、ディスプレイデザイン、舞台、テレビ、映画の特撮を数多く担当。 1969(昭和44) (株)モ・ブルを設立。 1970(昭和45) 日本万国博覧会の岡本太郎作《太陽の塔》の内部に《生命の樹》をデザイン。 1972(昭和47) 「突撃 ! ヒューマン !!」のキャラクターデザイン他特技全般を担当。 1983(昭和58) 六本木アネックスで個展。朝日ソノラマより画集出版。 1990(平成2) 京都府大江町(現・福知山市)に《鬼モニュメント》を制作。 1991(平成3) 東京・銀座に「ギャラリー宇輪」開設(1992年まで)。 1994(平成6) 北上市立鬼の館のためにレリーフ《鬼幻影》を制作。 1996(平成8) フィルムアート社より『特撮と怪獣 わが造形美術』、『特撮美術』刊行。 1999(平成11) 水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された椹木野衣企画の「日本ゼロ年」に出品。同年青森県が、ウルトラ関係のデザイン原画189点を購入。2006(平成18)年開館の青森県立美術館の所蔵品となった。 2002(平成14) 2月26日、多発性脳梗塞のため永眠。享年72歳。
MORE -
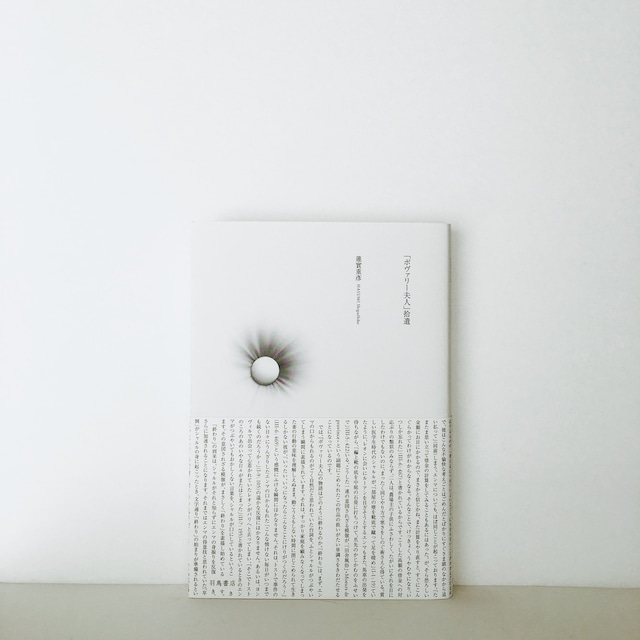
蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」拾遺』
¥2,860
四六判 上製 312頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-49-9 C0095 2014年12月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼概要 文学批評の金字塔『「ボヴァリー夫人」論』の刊行前後の講演および著者による『ボヴァリー夫人』の要約を収める。 [目次] フローベールの『ボヴァリー夫人』──フィクションのテクスト的現実について 「かのように」のフィクション概念に関する批判的な考察──『ボヴァリー夫人』を例として フローベールの『ボヴァリー夫人』をめぐって──珊瑚樹と晴雨計の置かれた天井の低い部屋について とことん『「ボヴァリー夫人」論』を語る──リゾンからヨンヴィルまで 【鼎談】“生まれたばかりの散文”と向き合う 蓮實重彦×工藤庸子×菅谷憲興 【鼎談】「シャルル・ボヴァリーは私だ」 蓮實重彦×渡部直己×菅谷憲興 『ボヴァリー夫人』には、いかなる事態がどのように推移しているか──要約というには長すぎるテクスト要約の試み 初出一覧/あとがき/書誌 ▼プロフィール 蓮實 重彦(はすみ しげひこ) 1936年東京生まれ。 60年東京大学文学部仏文科卒。 大学院進学後、フランス政府給費生としてパリ大学に留学。 フローベール『ボヴァリー夫人』に関する論文で 65年に同大学文学人文科学部から博士号取得。 東京大学教養学部講師、助教授を経て、88年に教授。 93年から95年まで教養学部長、95年から97年まで副学長を歴任。 97年4月から2001年3月まで東京大学26代総長。現在は名誉教授。 『凡庸な芸術家の肖像──マクシム・デュ・カン論』(88年、青土社、近く講談社文芸文庫より再刊予定)で88年度芸術選奨文部大臣賞受賞、『監督 小津安二郎』(83年、筑摩書房)の仏訳Yasujiro Ozuはフランス映画批評家連盟文芸賞受賞。2014年6月に、原稿用紙2000枚の書下ろし『『ボヴァリー夫人』論』を刊行(筑摩書房)。その他著作多数。 文芸批評家・映画評論家としての貢献は海外でも高く評価され、97年にパリ第8大学から名誉博士号取得、99年フランス政府の「芸術文化勲章」受賞。
MORE -

成田亨『成田亨作品集』
¥5,500
SOLD OUT
★長らく品切れとなっておりましたが、2021年8月に重版(第3刷)します。それにともない、本体価格を5000円から8000円に改訂、カバー帯を新装しました。ご購入の際は、新サイトからご注文ください。 https://www.hatorishoten.co.jp/items/48111660 B5判変型 並製 400頁(カラー312頁) 本体価格 5,000円+税 ISBN 978-4-904702-46-8 C1071 2014年7月刊行 装丁・デザイン 大西隆介(direction Q) レイアウト 山口潤(direction Q) 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣 *当サイトでご購入の方には、特典「ヒューマンサイン[復刻版]」(展覧会時の特典)をお付けします。 ▼書評・記事 『毎日新聞』2014年9月21日 「「ウルトラマン」など特撮作品のデザインや美術を手がけた著者の集大成」 『読売新聞』2014年9月28日書評 「ウルトラマンやその怪獣をデザインしたことで知られる成田亨。本書は、そのデザイン原画だけでなく、特撮美術、彫刻、絵画まで、氏の全活動にわたる全515点を収録した決定版作品集だ(後略)」(評・青木淳) 『朝日新聞』2015年2月15日書評 「成田亨──という名前になじみがなくても、〈ウルトラマン〉〈カネゴン〉〈バルタン星人〉と聞けば、「ああウルトラ怪獣!」とすぐに思い出せるだろう。(そう、彼こそは、ウルトラマンやウルトラセブン、そしてウルトラ怪獣たちの生みの親。伝説の怪獣デザイナー、いや、「アーティスト」である。(後略)」(評・原田マハ) ▼概要 決定版作品集! ウルトラ、マイティジャック、ヒューマン、バンキッドから、モンスター大図鑑、特撮美術、後年の絵画・彫刻まで。未発表作品、実現しなかった幻の企画案も含む、全515点一挙収録。 成田亨の仕事は、「芸術って何だ」という根源的な問いに肉薄する! ── 村上隆(アーティスト) 「成田亨 美術/特撮/怪獣」展 オフィシャル・カタログ (展示700点のうち、515点を収録) 富山県立近代美術館 2014年7月19日~8月31日 福岡市美術館 2015年1月6日~2月11日 青森県立美術館 2015年4月11日~5月31日 [寄稿] 椹木野衣(美術批評家) 「成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで」 三木敬介(富山県立近代美術館学芸員) 「〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨」 山口洋三(福岡市美術館学芸員) 「四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?)」 工藤健志(青森県立美術館学芸員) 「成田亨が残したもの」「試論 成田亨と鬼、あるいは〈芸能〉を継ぐ者」 田中聡(映像作家) 「他界の扉」 [目次] 成田亨プロフィール 成田亨のこと 成田流里 感謝の言葉 成田カイリ 序にかえて──「成田亨 美術/特撮/怪獣」展の開催に至る、およそ15年の経緯 工藤健志 成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで 椹木野衣 成田亨が残したもの 工藤健志 1 |初期作品 1950-60年代 2 |ウルトラ 1965-67年 2-1|ウルトラQ 特撮美術の作業 成田 亨 2-2|ウルトラマン ウルトラマンの頃 成田 亨 メカニズム・デザインについて 成田 亨 2-3|ウルトラセブン 3 |マイティジャック 1968年 4 |ヒューマン 1972年 ヒューマン怪獣──風船獣の闘い 成田 亨 5 |バンキッド 1976年 6 |マヤラー/ Uジン 実現しなかった企画案1 1970-80年代 7 |未発表怪獣 1984-87年頃 天空獣のデザインの発想 成田 亨 8 |モンスター大図鑑 1985-86年 9 |日本・東洋のモンスター 1980-90年代 10| MU /ネクスト 実現しなかった企画案2 1989年+1990年代 11|1970-90年代の絵画・彫刻 阿部合成先生の思い出 成田 亨 12|特撮美術 原爆を撮る 成田 亨 〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨 三木敬介 四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?) 山口洋三 試論 成田亨と鬼、あるいは「芸能」を継ぐ者 工藤健志 他界の扉 田中 聡 成田亨 略年譜 成田亨 著作物および関連文献目録 作品一覧 ▼プロフィール 成田 亨(なりた とおる) 1929(昭和4) 9月3日神戸市に生まれる。1930年4月青森県に転居後、囲炉裏の炭をつかんで左手火傷。小中学校時代を再び兵庫県で過ごし、空襲に遭遇。青森県で終戦を迎える。県立青森高等学校卒業後、画家・阿部合成、彫刻家・小坂圭二の指導を受ける。 1950(昭和25) 武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。3年次に彫刻科に転科し清水多嘉示に師事。 1954(昭和29) アルバイトで東宝映画「ゴジラ」の撮影現場の手伝いをしたことをきっかけに、映画美術の世界に入り、彫刻家として新制作展(1955[昭和30]年の第19回展から1971[昭和46]年の第35回展まで)に出品を続けながら、映画の特撮シーンを数多く手がける。 1960(昭和35) 東映で特撮美術監督。1962(昭和37)年第26回新制作展で《八咫》が新作家賞受賞、協友となる。 1965(昭和40) 円谷特技プロダクションと契約、「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「マイティジャック」の怪獣、宇宙人、メカニックのデザインのほか、特技全般を手がける。 1968(昭和43) 円谷プロを離れる。以後、ディスプレイデザイン、舞台、テレビ、映画の特撮を数多く担当。 1969(昭和44) (株)モ・ブルを設立。 1970(昭和45) 日本万国博覧会の岡本太郎作《太陽の塔》の内部に《生命の樹》をデザイン。 1972(昭和47) 「突撃 ! ヒューマン !!」のキャラクターデザイン他特技全般を担当。 1983(昭和58) 六本木アネックスで個展。朝日ソノラマより画集出版。 1990(平成2) 京都府大江町(現・福知山市)に《鬼モニュメント》を制作。 1991(平成3) 東京・銀座に「ギャラリー宇輪」開設(1992年まで)。 1994(平成6) 北上市立鬼の館のためにレリーフ《鬼幻影》を制作。 1996(平成8) フィルムアート社より『特撮と怪獣 わが造形美術』、『特撮美術』刊行。 1999(平成11) 水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された椹木野衣企画の「日本ゼロ年」に出品。同年青森県が、ウルトラ関係のデザイン原画189点を購入。2006(平成18)年開館の青森県立美術館の所蔵品となった。 2002(平成14) 2月26日、多発性脳梗塞のため永眠。享年72歳。 2014年7月19日 初版 2014年9月10日 第2刷
MORE -
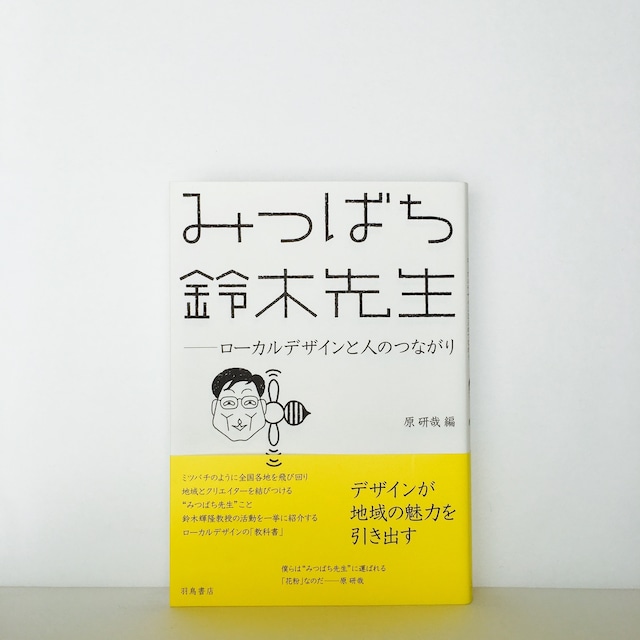
原研哉[編]『みつばち鈴木先生──ローカルデザインと人のつながり』
¥3,520
◇ ◇ サイン本をお送りします ◇ ◇ A5判 並製 304頁(カラー32頁) 本体価格 3,200円+税 ISBN 978-4-904702-45-1 C0070 2014年5月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 ▼概要 デザインが地域の魅力を引き出す ミツバチのように全国各地を飛び回り地域とクリエイターを結びつける“みつばち先生”こと鈴木輝隆教授の活動を一挙に紹介する、ローカルデザインの「教科書」 僕らは“みつばち先生”に運ばれる「花粉」なのだ ──原研哉 「みつばち先生 鈴木輝隆展」(松屋銀座/アートディレクション:原研哉)で紹介された10の事例とともに、地域づくりの牽引者たちと、関わったクリエイターたち(梅原真、隈研吾、大黒大悟、原研哉ほか)とのトークを収録。みつばち鈴木先生が「ローカルデザインの師」と仰ぐ、富山市八尾町の和紙工芸家・吉田桂介氏の仕事も紹介し、主宰する「ローカルデザイン研究会」全101回を記録し収める。 [登場する地域]北海道勇払郡むかわ町/北海道斜里郡清里町/秋田県仙北市田沢湖乳頭温泉郷/東京都八王子市高尾町/新潟県柏崎市高柳町/富山県富山市八尾町/長野県上高井郡小布施町/山梨県韮崎市穂坂町/山梨県甲州市勝沼町+北杜市/鹿児島県霧島市枚園町/鹿児島県西之表市種子島/半島(下北半島+幡多半島 他21半島) [目次] 先生は熱く人を結んでいく 原研哉 1 みつばち鈴木先生 みつばち先生 鈴木輝隆展 鈴木輝隆 デザインミツバチというこれからの仕事 ナガオカケンメイ むかわ町──北海道 土井博子+原 研哉 鶴の湯──秋田県仙北市田沢湖乳頭温泉 佐藤和志+梅原 真 高柳町──新潟県柏崎市 春日俊雄+小林康生+隈研吾+梅原 真 ハウジングアンドコミュニティ財団──東京都+全国 大内朗子+梅原 真 国土交通省半島振興室──東京都+下北半島+幡多半島 他21半島 大石麻子+大黒大悟+白井 亮 小布施堂──長野県小布施町 市村次夫+原 研哉+梅原 真 穂坂町──山梨県韮崎市 福田敏明+奥村文絵+三木俊一 中央葡萄酒──山梨県甲州市勝沼町+北杜市 三澤茂計+原 研哉 天空の森──鹿児島県霧島市枚園町 田島健夫+梅原 真 種子島──鹿児島県西之表市 河口 修+梅原 真 咲いている花を見逃さない──ローカルデザインのはじまり 原 研哉 2 ローカルデザインと人 これぞ秘湯・鶴の湯──乳頭温泉郷 梅原 真×佐藤和志×鈴木輝隆 じょんのび高柳──陽の楽家 隈研吾×小林康生×春日俊雄×鈴木輝隆 小布施の旦那衆──桝一市村酒造場と小布施堂 ナガオカケンメイ×市村次夫×鈴木輝隆 甲州ワインの誇り──中央葡萄酒 原 研哉×三澤茂計×鈴木輝隆 半島のじかん──23の半島の「風景・人・産物」 大黒大悟×原 研哉×鈴木輝隆 3 ローカルから世界を見る 吉田桂介さんとの出会い 鈴木輝隆 八尾の和紙づくり 吉田桂介×市村次夫 白秋先生のノートの束 吉田桂介 杖andステッキ 吉田桂介 八尾をたずねて 吉田桂介×原研哉×鈴木輝隆 土地に根を下ろす力 原研哉 4 ローカルデザイン研究会 ローカルデザインの可能性 鈴木輝隆 全101回の軌跡 執筆者一覧 初出一覧 ▼プロフィール 編者 原 研哉(はら けんや) グラフィックデザイナー。日本デザインセンター代表。1958年岡山市生まれ。産業文化の可能性を可視化し、新しい覚醒を生み出すことを重視して活動。2002年より無印良品のアートディレクター、 2012年には代官山蔦屋書店のアートディレクションを担当。「RE DESIGN」「HAPTIC」「SENSEWARE」「HOUSE VISION」など時代の価値観を更新していくキーワードを擁する展覧会を数多く手がける。2009-11年に北京・上海で大規模な個展を巡回、2013年に「世界で一番美しい本」賞、2014年に「ピエール・エルメ」のパッケージが話題になるなど活動領域は多岐にわたる。近著 『Designing Design』、『白』は各国語に翻訳され多くの読者を持つ。 “みつばち先生”こと鈴木輝隆(すずき てるたか) 江戸川大学教授。1949年名古屋市生まれ。1973年北海道大学農学部農学科卒業。神戸市役所、山梨県庁、総合研究開発機構を経て、現在、江戸川大学社会学部現代社会学科教授。「住民自治とローカルデザイン力から地域経営」が研究テーマ。各地の地域づくりに関わり、北海道清里町、ニセコ町、秋田県乳頭温泉「鶴の湯」、岩手県八幡平市、長野県小布施町、山梨県甲州市、東京都八王子市、高知県四万十ドラマ、鹿児島県西之表市(種子島)など、全国に地域づくりのネットワークを構築している。 主な著書に、『森林インストラクター入門』(共著、全国林業改良普及協会、1992年)、『観光振興実務講座 地域を活かすソフト戦略』(共著、日本観光協会、1997年)、『中山間地域のあり方に関する研究II』(共著、総合研究開発機構、1998年)、『環境市民とまちづくり・地域共生編』(共著、ぎょうせい、2003年)、『ろーかるでざいんのおと 田舎意匠帳 あのひとが面白い、あのまちが面白い』(全国林業改良普及協会、2005年)。
MORE -

並河進『Communication Shift──「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ』
¥1,760
SOLD OUT
* ただいま在庫切れです。 * 四六判 並製 162頁 本体価格 1,600円+税 ISBN 978-4-904702-44-4 C0034 2014年3月刊行 ブックデザイン 大西隆介(direction Q) ▼書評・記事 ▼概要 広告は社会のために何ができるか ソーシャルプロジェクトの経験と、広告の最前線で活躍する12名のクリエイターとの対話から、ヒト・モノ・コトをつなげる仕組みをうみだす「広告とコミュニケーションの未来」を切り拓く。 澤本嘉光・永井一史・箭内道彦・佐藤尚之・今村直樹・丸原孝紀 松倉早星・鈴木菜央・石川淳哉・東畑幸多・嶋浩一郎・中村洋基 (登場順) [目次] はじめに 第1章 原点──現状の広告に対するいくつかの疑問 広告づくりは、いったい誰のものか なぜ広告賞という単一の価値観しかないのか 広告の世界には、なぜ自己批判がないのか 広告は、大量消費をうながすことしかできないのか 広告は、そもそも社会をよくするためのものではないのか 第2章 模索する日々──広告は社会のために何ができるか これからの広告のありかた 1 企業を出発点に 「ほんとうにいいことをする」 「ともに行動する」マーケティングへ 効率の悪いコミュニケーションへ 広告づくりを「みんなのもの」に 企業のありかたのデザインへ 「一個人として」発想する 広告が信じてもらえるためには 2 NPO・個人・コミュニティを出発点に 「伝える」という技術 大量生産、大量消費のひずみ 広告のスキルで「通訳」する 個人の想いを伝えていく「仕組み」 3 社会課題を出発点に 広告が主体となる 「人の命を救う」マーケティングへ 未来の広告会社 未来の広告のありかた これからの広告は何をすべきか? 第3章 広告のポテンシャル──広告づくりの発想や技術 「無自覚」から「自覚」へ 「いや、こういう別の見方をすれば」 異なる意見の橋渡しをする 広告人の強み 閉塞し停滞したものを活性化させる 「ポテンシャルバリュー」を見通す 個人の心の中に「潜在的にあるもの」 広告的思想の可能性 広告の未来への提言 第4章 ヒト・モノ・コトはこれから“どう”つながっていくのか 3.11を越えて もうひとつの「つながりのレイヤー」を持つ さまざまな価値と価値を交換する「クラウドトレード」 人は、壁を越えたい生き物だ。 おわりに ▼プロフィール 並河 進(なみかわ すすむ) 1973年生まれ。電通ソーシャル・デザイン・エンジン クリエーティブディレクター/コピーライター。ユニセフ「世界手洗いの日」プロジェクト、祈りのツリープロジェクトなど、ソーシャル・プロジェクトを数多く手掛ける。DENTSU GAL LABO代表。ワールドシフト・ネットワーク・ジャパン・クリエーティブディレクター。受賞歴に、ACCシルバー、TCC新人賞、読売広告大賞など。著書に『下駄箱のラブレター』(ポプラ社、2007)、『しろくまくんどうして?』(朝日新聞出版、2009)、『ハッピーバースデイ3.11――あの日、被災地で生まれた子どもたちと家族の物語』(飛鳥新社、2012)、『Social Design――社会をちょっとよくするプロジェクトのつくりかた』(木楽舎、2012)他。上智大学大学院非常勤講師。
MORE -
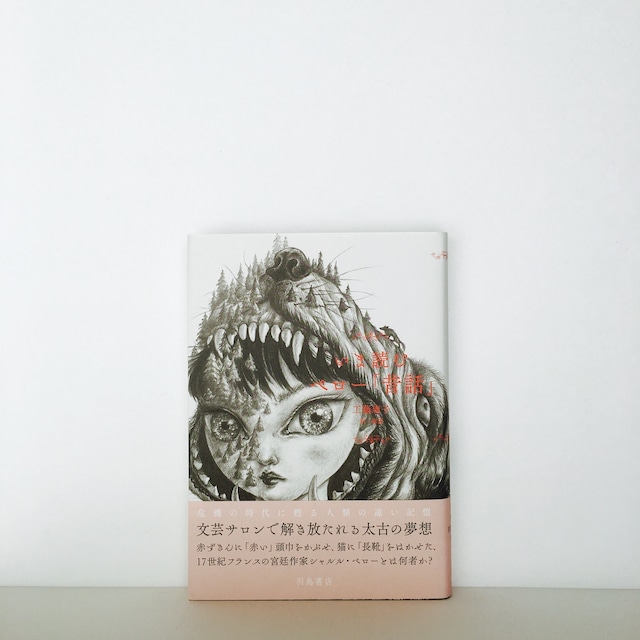
工藤庸子[訳・解説]『いま読むペロー「昔話」』
¥2,200
SOLD OUT
B6判 上製 218頁 本体価格 2,000円+税 ISBN 978-4-904702-42-0 C0097 2013年10月刊行 装画 鴻池朋子 ブックデザイン 小川順子 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 *刊行記念トークイベント (終了しました) 工藤庸子(仏文学者)×鴻池朋子(現代アーティスト)トークショー 「ペロー『昔話』:太古の夢想の森へ」 [日時]2013年11月22日(金) 19:00~21:00(18:30開場) [会場]エスパス・ビブリオ ▼書評・記事 『朝日新聞』2014年1月12日書評 「童話にあるようなモラルがここにはない。読む者は「突き放される」。しかし、このように突き放されるところに「文学のふるさと」があるのだ、という。/以来、私はペローの昔話が気になりいつか調べてみようと思っていたが、その機会がなかった。新訳と詳細な解説が付された本書は、そのような疑問に答えてくれるものであった」(評・柄谷行人) http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2014011400003.html ▼概要 文芸サロンで解き放たれる太古の夢想── 赤ずきんに「赤い」頭巾をかぶせ、猫に「長靴」をはかせた、17世紀フランスの宮廷作家シャルル・ペローとは何者か? 世界中で読み継がれてきたペローの『昔話』は、もともと大人向けの読み物として貴族の文芸サロンで誕生した。民間伝承と宮廷文化との出会いから生まれた物語の背景をふまえ仏文学者・工藤庸子が新たに訳す。充実の解説付。 [目次] マドモワゼルに捧ぐ 眠れる森の美女 赤頭巾 青ひげ 猫の大将 または長靴をはいた猫 仙女たち サンドリヨン または小さなガラスの靴 巻き毛のリケ 親指小僧 訳者解説 ペロー『昔話』と三つの謎 訳者あとがき ▼訳者プロフィール 工藤庸子(くどう ようこ) 1944年生まれ。東京大学名誉教授。専門はフランス文学、ヨーロッパ地域文化研究。 [主な著書] 『プルーストからコレットへ──いかにして風俗小説を読むか』(中公新書、1991年) 『小説というオブリガート──ミラン・クンデラを読む』(東京大学出版会、1996年) 『恋愛小説のレトリック──『ボヴァリー夫人』を読む』(東京大学出版会、1998年) 『フランス恋愛小説論』(岩波新書、1998年) 『ヨーロッパ文明批判序説──植民地・共和国・オリエンタリズム』(東京大学出版会、2003年) 『宗教vs.国家──フランス〈政教分離〉と市民の誕生』(講談社現代新書、2007年) 『近代ヨーロッパ宗教文化論──姦通小説・ナポレオン法典・政教分離』(東京大学出版会、2013年) 『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ──フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母』(東京大学出版会、2016年) 『論集 蓮實重彦』(編著、羽鳥書店、2016年) [主な訳書] アンリ・トロワイヤ『女帝エカテリーナ』(中央公論社、1980年) フロベール書簡選集『ボヴァリー夫人の手紙』(筑摩書房、1986年) バルガス・リョサ『果てしなき饗宴』(筑摩書房、1988年) コレット『牝猫』(岩波文庫、1988年) ミシェル・フーコー『幻想の図書館』(哲学書房、1991年) ミシェル・ビュトール『ディアベリ変奏曲との対話』(筑摩書房、1996年) プロスペール・メリメ『カルメン』(新書館、1997年) ピエール・ロティ『アジヤデ』(新書館、2000年) コレット『わたしの修業時代』(ちくま文庫、2006年) バルザック『ランジェ公爵夫人』(集英社、2008年) コレット『シェリ』(左右社、2010年) マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』(河出書房新社、2014年)
MORE -
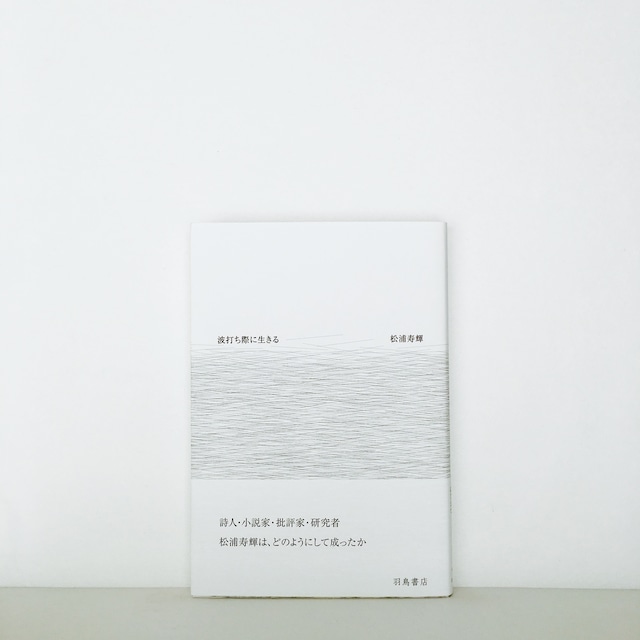
松浦寿輝『波打ち際に生きる』
¥2,420
四六判 上製 168頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-40-6 C1095 2013年5月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『読売新聞』 2013年6月2日書評 「「波打ち際に生きる──研究と創作のはざまで」と題する講演では、研究よ創作、教師と学生など様々な「波打ち際」のような場所で仕事をしてきた著者の東日本大震災後の思いもかたられている」。 『毎日新聞』 2013年6月30日書評 「詩人であり小説家であり批評家である著者は昨年3月、定年まで7年を残して東京大学の教壇を去った。その際におこなった「退官記念講演」と「最終講義」をまとめた本だが、柔軟かつ強靭な知的刺激に満ちている」。 ▼概要 詩人・小説家・批評家・研究者 松浦寿輝は、どのようにして成ったか 東京大学で教鞭をとりながら、詩人・小説家・批評家として活躍してきた著者の「東京大学退官記念講演」(2012年1月16日)と「東京大学最終講義」(2012年4月26日)を一冊にまとめる。巻末には、著者のコメント付き著作一覧を収録。 東京大学退官記念講演 「波打ち際に生きる──研究と創作のはざまで」 「波打ち際の心もとなさ」という感覚を手がかりに、これまでの仕事の流れを振り返り、貫いてきたものを考える。 最終講義 「Murdering the Time──時間と近代」 近代以降の重要なテクストに時間の主題がどのように現れているかを分析し、「時間システム」の拘束とそこからの解放の欲求という葛藤の構図を炙り出す。 松浦寿輝著作一覧──著者自身によるコメント ▼プロフィール 松浦寿輝(まつうら・ひさき) 1954年東京生まれ。作家、詩人。1988年に詩集『冬の本』で高見順賞、95年に評論『エッフェル塔試論』で吉田秀和賞、2000年に小説『花腐し』で芥川賞、05年に小説『半島』で読売文学賞を受賞するなど、縦横の活躍を続けている。東京大学名誉教授。
MORE -
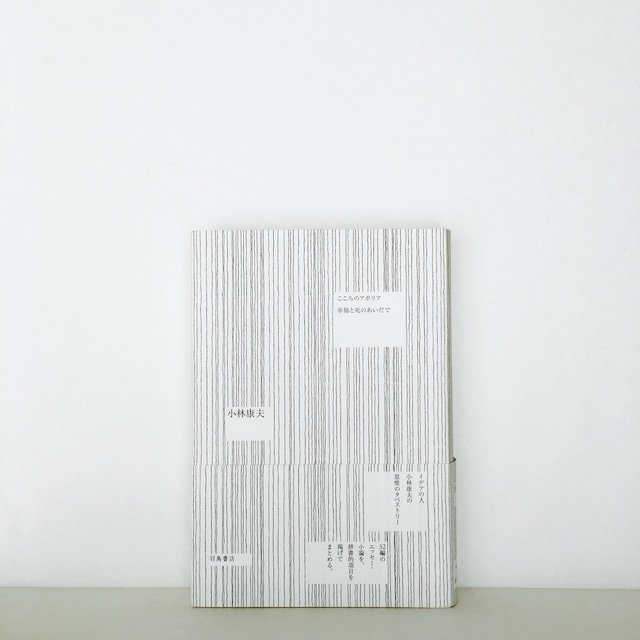
小林康夫『こころのアポリア──幸福と死のあいだで』
¥3,520
四六判 並製 432頁 本体価格 3,200円+税 ISBN 978-4-904702-39-0 C1010 2013年4月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『信濃毎日新聞』2013年6月23日、『南日本新聞』『大阪日日新聞』等 「「こころ」と題したテキストでは、世阿弥「檜垣」の老女が取り上げられる。白川の水をくみ続けながら、水の理に逆らって昔の火の理に帰ろうとする元・白拍子の両義的なこころの場を描く。(中略)32編の論考を収録」。 ▼概要 イデアの人 小林康夫の思惟のタペストリー 32のエッセー・小論を、辞書的項目を掲げてまとめる ここ十数年のあいだに、それぞれまったく異なる機会に書かれた32本。 「幸福」と「死」の両極のあいだで、そのときどきの生と思考の痕跡を記す。 「〈屑〉という本質的に断片である〈非-作品〉を取り集めることによって『無の光』が差し込むべき場をつくるという発想を惹起した。そうしたら、そのような非-統一性の場として、(もちろん矛盾の表現だが)不完全な「辞書」の空間のうちに自分が書き散らした〈生の破片〉、〈屑〉としてのテクストすべて投げ込もうか、という乱暴な計画が勃発した」(「あとがき」より) [目次] Ⅰ 幸福の器 1 幸福────モーツァルト『魔笛』 2 レペルトワール────存在を焼く火 Ⅱ こころのアポリア 3 こころ────世阿弥『檜垣』 4 スコレー/エネルゲイア────坂部恵の〈風〉 Ⅲ からだの真実 5 身体────われわれがそれであるもの 6 触覚なき接触────グレン・グールドと電気掃除器 7 手────ロラン・バルトの〈不器用さ〉 8 味気なさ────ロラン・バルト『中国旅行ノート』 9 a Cup of Humanity────岡倉天心『The Book of Tea』 10 秘密────「プライバシーの境界線」 11 逸脱────ヴァルター・ベンヤミンの「摂取同化」 Ⅳ 世界という庭で 12 物質的流動────モネの〈庭〉 13 アナーキズム────吉田喜重「美の美(モネ)」 14 空虚────ミシェル・フーコー『マネ論』 15 庭/織物────フランソワ・ルーアンのタブロー 16 青の神秘────Viktor & Rolf の「青」展 Ⅴ イマージュ/文字 17 イマージュ────宮川淳『鏡・空間・イマージュ』 18 顔────こんなにもあからさまで、こんなにも秘密の神秘 19 純粋な場所────佐伯祐三のパリの壁 20 見えるものと見えないもの────「白と黒」展 21 原-書────雪舟《破墨山水図》の方へ Ⅵ 声のダイモーン 22 遠隔作用────ニーチェ/ハイデガー/デリダの〈耳〉 23 ダイモーン────モデルニテにおける詩の根拠 24 呼びかけ────吉増剛造『オシリス、石の神』 25 名────吉増剛造『The Other Voice』 26 現-(da-)────吉増剛造『表紙』 27 エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ────大貫隆『イエスの経験』 28 religio────詩とreligio Ⅶ 終わりなき終わり 29 終わりなきもの────ショパン「ソナタ変ロ短調」 30 恐るべき否定性────「存在は苦である」 31 芸術の終わり────モロッコ海岸のレイヨウ(デュラス) 32 光────地中海の光を浴びて あとがき 人名索引 ▼プロフィール 小林康夫(こばやし やすお) 1950年東京都生まれ。東京大学名誉教授、青山学院大学大学院総合文化政策学研究科特任教授。表象文化論、現代哲学。 著書に、『起源と根源──カフカ・ベンヤミン・ハイデガー』(1991年)、『表象の光学』(2003年)、『歴史のディコンストラクション──共生の希望へ向かって』(2010年)、『存在のカタストロフィー──〈空虚を断じて譲らない〉ために』(2012年)(以上、未來社)、『光のオペラ』(筑摩書房、1994年)、『出来事としての文学──時間錯誤の構造』(講談社学術文庫、2000年)、『青の美術史』(平凡社ライブラリー、2003年)など多数。
MORE -

今村直樹『幸福な広告──CMディレクターから見た広告の未来』
¥2,860
四六判 上製 296頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-38-3 C0034 2012年11月刊行 ブックデザイン 副田高行+太田江理子(副田デザイン制作所) 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼概要 人と社会が幸福になる広告のありかた CMディレクターとして長く第一線で活躍してきた自身の経験をふまえ、広告そしてCMをとりまく現状とこれからを展望する。具体的な実例から見える広告の姿や、“地域”の広告がもつ可能性を追って、30数人にのぼる制作者や広告主へのインタビューを重ねた。広告クリエイターたちが3・11以降に示した活動や、制作者である著者が広告主に提案して実現させた独自の試み「オフ・コマーシャル」についても紹介。 広告業界にとどまらず、さまざまな企業の宣伝・広報を担う人たち、地域マネジメントにたずさわる人たち、企業や地域を牽引するリーダーたち、そのような現場の人たちへの重要なメッセージがつまった一冊。 [主要目次] はじめに 第1章 ところで、広告って何だろう? 1 ぼくは、クラフトマン 2 広告を定義してみる 第2章 信頼を生む広告、信頼で生む広告 1 たったひとつのこと 2 リーダーシップが効果的な広告を生む 3 個と個でつながる関係性 4 効果的な広告は信頼から生まれる 第3章 広告の制作現場から 1 サントリーウーロン茶 [サントリー×安藤隆・葛西薫] 2 キユーピーマヨネーズ [キユーピー×秋山晶] 3 いいちこ [三和酒類×河北秀也] 4 ソフトバンク [孫正義×佐々木宏] 5 ビッグアイデアの広告 6 「幸福な広告制作の現場」に共通すること 第4章 地域のデザインと広告の制作現場から 1 本質のデザイナー・梅原真 2 地デザイナー・迫田司 3 口蹄疫問題をめぐって [宮崎県×日高英輝] 4 一乗谷「町おこしプロジェクト」 [福井市×佐々木宏] 5 個と個のつながりと「参加性」 第5章 幸福な広告へ──CMディレクターから見た広告の現在と未来 1 広告は幸福な関係から生まれる 2 CMディレクターから見た広告制作のいま 3 “オフ・コマーシャル”という実験 4 三・一一と広告の現在 5 CMディレクターから見たCMの未来 参考文献 あとがき 今村直樹が会いに行った人々 ▼プロフィール 今村直樹(いまむら なおき) 1954年生まれ、岐阜県出身、CMディレクター。東北芸術工科大学映像学科教授。上智大学新聞学科卒業後、サン・アドなどの広告制作会社を経て、1988年に独立し、今村直樹事務所を設立。2002年よりCM制作者集団・ライブラリーを主宰している。サントリー、リクルート、資生堂、花王、ライオン、JR東海、JR東日本、トヨタ、日産、メルセデスベンツ、味の素、ソニー、パナソニックなど、数多くの企業のテレビコマーシャルを企画・演出してきた。ACC賞、ニューヨークADC 賞、消費者のためになった広告賞最優秀賞など受賞多数。最近の代表作に、第一生命・ダイワハウス・協和発酵キリン・ジャパネットたかたなどの企業広告、マスターカードPricelessシリーズ、シャープアクオス、住友生命などがある。2011年、早稲田大学大学院公共経営研究科を卒業し、地域活性化のための広告にも目を向けている。
MORE -

MIHO MUSEUM[編]『土偶・コスモス』
¥3,300
SOLD OUT
B5判変型 並製 344頁(カラー184頁) 本体価格 3,000円+税 ISBN 978-4-904702-37-6 C0070 2012年9月刊行 ブックデザイン 有山達也+中島美佳(アリヤマデザインストア) 【日英併記】 印刷・製本 サンエムカラー *展覧会情報 2012年秋季特別展「土偶・コスモス」 MIHO MUSEUM 2012年9月1日~12月9日 http://www.museum.or.jp/modules/im_event/?controller=event_dtl&input%5Bid%5D=78223 *フェア情報 「大縄文展」フェア@ジュンク堂書店池袋本店4F (2012年10月9日終了) ▼書評・記事 『日本経済新聞』2012年9月23日 『東京新聞』2012年9月23日 『読売新聞』2012年9月30日 NHK(Eテレ)日曜美術館「土偶~1万年前のアート誕生~」 2012年10月14日(日)朝9:00~10:00 再放送:10月21日(日)夜8:00~9:00 『芸術新潮』2012年11月号「大特集 縄文の歩き方」 ▼概要 土偶大集合 みみずく、遮光器、十字形、ハート形、河童形──縄文15000年の想像力 国宝3点・重要文化財21点を含む、土偶・土器、総数320点 現代人の魂を揺さぶる土偶のたくましい生命感に迫る MIHO MUSEUM 「土偶・コスモス展」公式カタログ 本書は、2012年9月1日より開催のMIHO MUSEUM(滋賀県甲賀市)秋季特別展「土偶・コスモス」の公式カタログを兼ねた書籍です。約150にのぼる所蔵者の協力によって実現した本展覧会は、縄文土偶の展示としてはかつてない規模を誇り、全国の土偶が一挙に大集結します。国宝3点・重要文化財21点を含む土偶約220点、縄文土器等もあわせ総数約320点にのぼる貴重な展示を1冊の本にしました。 2009年に大英博物館で開催された「The Power of Dogu」展、東京国立博物館で行われた帰国展には大勢の観客が訪れ話題になりましたが、今年に入って新たに、土偶としては4点目の国宝が指定されるなど、縄文土偶の注目度は非常に高まっています。その高まりに充分に応えるのが、本展覧会および本書です。 第1章のカラー図版ページでは、これまで資料的にしか見られることのなかった土偶の姿かたちを、写真家・藤森武氏による撮りおろし写真によって新たな角度から浮き彫りにします。また、実際の展示室をめぐるように図版が並び、個別作品の解説だけでなく、テーマをとらえながら変遷をたどり、時期によってまったく異なるこだわりや、地域を超えて共有される縄文人の感覚を追体験できる充実の構成となっています。 第2章では、国内各地の考古学専門家が集結し、あまり試みられたことのなかったアプローチで、最新の研究成果をとりこみながら、土偶の多彩な有り様を紹介します。 第3章では、縄文考古学の第一人者である小林達雄氏(國學院大學名誉教授)をはじめ、「土偶」展の発案者でもあるニコル・クーリッジ・ルーマニエール氏(大英博物館キュレーター)による論考など4本をそろえ、土偶の様々な拡がりを提示します。 [主要目次] 土偶・コスモス 辻 惟雄(MIHO MUSEUM館長) 遺跡地図/年表 第1章 土偶・コスモス 1 縄文土偶──物語性の造形 2 五体を揃え、女性らしくなる土偶 3 壊された土偶 4 さまざまなポーズ、異形のものたち 5 意味を持つ数 6 多様化する土偶と遮光器土偶の展開 7 西日本の土偶 8 縄文ランドスケープ “大湯環状列石” 9 ストーンサークルと「第二の道具」 10 縄文に魅せられた現代文化人 第2章 数字からみる土偶 1 土偶の種類/ 2 出土状況/ 3 出土点数/ 4 大きさ/ 5 壊れ方/ 6 色彩 第3章 土偶の世界 1 縄文土偶の誕生、そして大変身 小林達雄 2 縄文文化における数の観念 西田泰民 3 西アジアの土偶 泉 拓良 4 現代の土偶現象 ニコル・クーリッジ・ルーマニエール 遺跡一覧/出品目録
MORE -
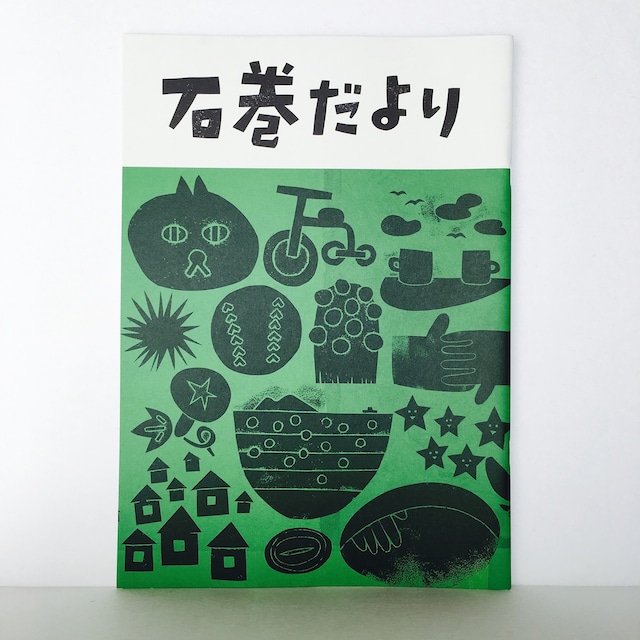
『石巻だより 通巻1-12号』(委託販売品)
¥1,018
★読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNはついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 「石巻だより」は2014年9月に創刊した折り込み新聞です。 発行人 小野智美:朝日新聞東京本社内部監査室員 川端俊一:朝日新聞東京社会部員 ASA石巻中央の協力により、宮城版『朝日新聞』に折り込んで届けられています。2015年5月までは月一度(なお、2015年1月号は休刊)、2015年5月以降は奇数月に発行。A3サイズの二つ折り、A4の4ページで構成しています。 羽鳥書店HPでは、この折り込み新聞のバックナンバーをPDFでご覧いただくことができます。 http://www.hatorishoten.co.jp/ishinomaki-dayori.html 『石巻だより 通巻1-12号』は、「石巻だより」1号~12号を合本にしたものです。 A4判 中綴じ 52頁 定価 1,000円 2016年3月刊行 当サイト以外での販売は ・往来堂書店 (東京都文京区千駄木2-47-11) ・古書ほうろう (東京都文京区千駄木3-25-5) ・古書信天翁 (東京都荒川区西日暮里3-14-13 コニシビル202) ・石巻まちの本棚 (宮城県石巻市中央2-3-16) のみとなっております。
MORE -
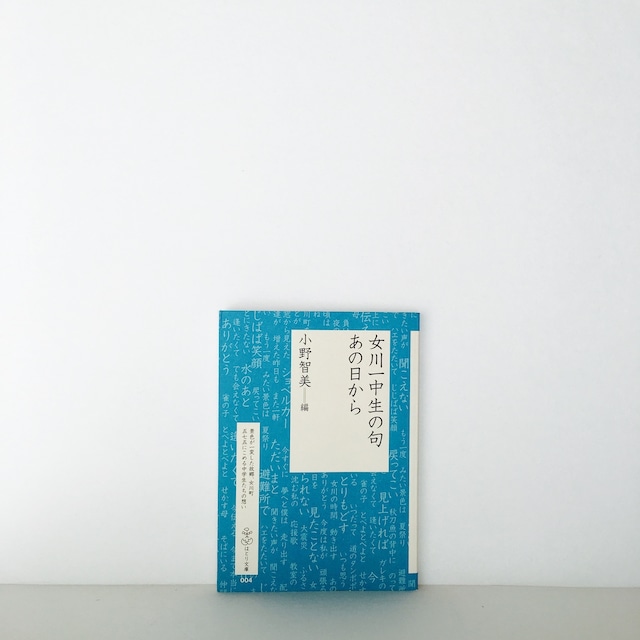
小野智美『女川一中生の句 あの日から』(はとり文庫004)
¥1,100
★現在、重版製作中です。 重版に伴い、3月中旬より本体価格を900円から1,000円に改定させていただきます。 A6判 並製 160頁 本体価格 1000円+税 ISBN 978-4-904702-36-9 C0030 2012年7月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平+大橋香菜子 印刷・製本 サンエムカラー ▼書評・記事 『本の雑誌』 2013年7月号 久田かおりさんが「会いたいけど会えない小説ガイド」で紹介してくださいました。「フタをして忘れようとしていた心の痛みを17文字に込めて吐き出した彼らの明日の幸せを祈らずにはいられない。(中略)ただ、ただ、一人でも多くの人に、この一冊を届けたい、そう思う」。 http://www.webdoku.jp/honshi/2013/7-130603174000.html ▼概要 景色が一変した故郷、女川町 五七五にこめる中学生たちの想い 津波が町を襲ったあの日から──2011年5月と11月に、宮城県女川第一中学校で俳句の授業が行われた。家族、自宅、地域の仲間、故郷の景色を失った生徒たちが、自分を見つめ、指折り詠んだ五七五。記者として編者は、友や教師や周囲を思いやり支えあう彼らの姿、心の軌跡を丹念にたどる。 記者である編者は、生徒たち一人ひとりと対話を重ね、彼らの俳句を紹介する記事を執筆した。2012 年1 月13 日~4 月13 日に朝日新聞宮城版に連載された記事の全文、および女川一中の担当教諭の寄稿、記事の後日談などの書き下ろし文章も収録。 [目次] はしがき (生徒たち22名の句の紹介)*当サイトではお名前をふせています 俳句で鍛え上げられた言葉 佐藤敏郎教諭「十五の心 国語科つぶやき通信」 大内俊吾校長の式辞 阿部航児さんの答辞 世界を駆けめぐった 最後の教材「レモン哀歌」 父と娘の15カ月 2度目の春 共振共鳴した日々を刻む すべては五七五の中に 佐藤敏郎 編者あとがき ▼編者プロフィール 小野智美(おの さとみ) 朝日新聞記者。1965年名古屋市生まれ。88年、早稲田大学第一文学部を卒業後、朝日新聞社に入社。静岡支局、長野支局、政治部、アエラ編集部などを経て、2005年に新潟総局、07年に佐渡支局。08年から東京本社。2011年9月から仙台総局。宮城県女川町などを担当。東松島市在住。著書に『50とよばれたトキ──飼育員たちとの日々』(羽鳥書店、2012年)。 *プロフィールは刊行当時(2020年現在、東京本社勤務)
MORE -
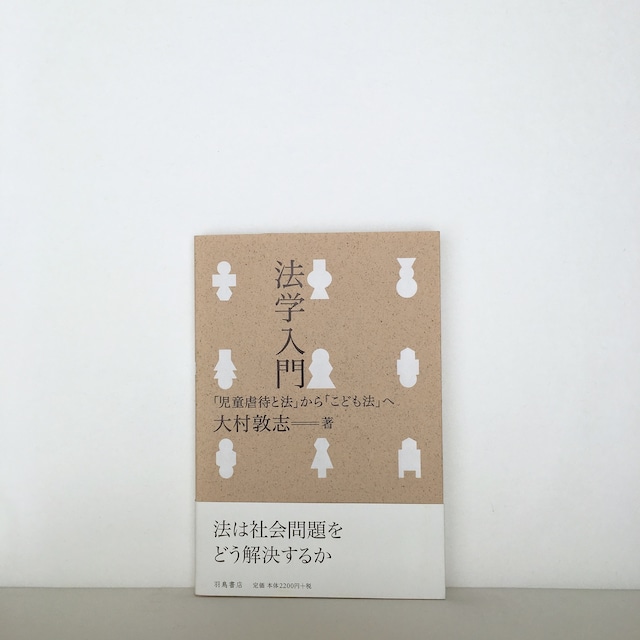
大村敦志『法学入門──「児童虐待と法」から「こども法」へ』
¥2,420
四六判 並製 136頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-35-2 C3032 2012年12月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷 研究社印刷 製本 矢嶋製本 ▼書評・記事 ▼概要 法は社会問題をどう解決するか 高校を卒業したばかりの人、あるいはこれから法を学ぼうという人に向けた、民法学の第一線研究者による「法と法学」の入門書。本文の解説とともにコメント形式で補足説明を加えながら、基礎的な理解をはじめ、全体を俯瞰する視点を養う。 法というものを通じて、私たちの生きる時代や社会を理解し、そのあり方について考えていく際のてがかりを提示する。 大きく2つのパートから構成され、Part 1「〈児童虐待と法〉から」では、「児童虐待」という一つの社会問題を切り口に、「法」と「社会」の両方の側から「法という現象」を解説・分析し、同時に、法学という学問について理解を深める。 Part 2「〈こども法〉へ」では、いま現在、私たちが生きるこの国で行われている立法について考え、児童虐待だけに限らず「こども」に関する法を全体としてとらえ、「法の歴史」の中で「現在」を、「法の体系」の中で「こども」を、それぞれにつかみだそうと試みる。 [主要目次] はじめに──法と法学への招待 Part 1 「児童虐待と法」から 第1章 児童虐待への法的対応 第2章 児童虐待防止法の社会的背景 Part 2 「こども法」へ 第3章 いま、法と法学は 第4章 こども法の構想 補 論 2011年の民法改正について 付録 児童虐待関連法令(抄) あとがき──この本の先へ ▼プロフィール 大村敦志(おおむら あつし) 1958年、千葉県生まれ。1982年、東京大学法学部卒業。現在、東京大学法学部教授。専門は民法。契約法、消費者法、家族法を中心に研究。主な著書に、『民法総論』(岩波書店、2001)、『生活民法入門──暮らしを支える法』(東京大学出版会、2003)、『基本民法1・2・3(第2版)』(有斐閣、2005)、『他者とともに生きる──民法から見た外国人法』(東京大学出版会、2008)、『18歳の自律』『22歳+への支援』(共著、いずれも羽鳥書店、2010、2011)『民法改正を考える』(岩波新書、2011)、ほか多数。
MORE -

光嶋裕介『幻想都市風景──建築家・光嶋裕介ドローイング集』
¥3,190
◇ ◇ サイン本をお送りします ◇ ◇ 四六判 並製 144頁 トリプルトーン印刷 袋とじ製本 本体価格 2,900円+税 ISBN 978-4-904702-34-5 C1071 2012年6月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷・製本 サンエムカラー 【日英併記】 *個展情報 森岡書店(ドローイング展) 2012年5月21日(月)~6月2日(土) ときの忘れもの(版画展) 2012年5月29日(火)~6月9日(土) ▼概要 「凱風館」への道 内田樹邸「凱風館」(道場兼住宅)を設計した建築家・光嶋裕介のドローイング集。旅のスケッチと地平線で続く記憶の風景はやがて処女作「凱風館」へと繋がる。 光嶋君の絵が粒子の集合だったので、僕はとっても嬉しくなりました。僕は世界は粒子の集合体だと考えています。粒子がないと生物は不安になります。粒子によって自分と世界の関係を確認できるからです。 ──隈 研吾 [収録テキスト] 光嶋裕介「“希望の建築”をめざして──建築家になるまでの地平線」 内田 樹「テクノロジカルな付喪神たち」 ▼プロフィール 光嶋裕介(こうしま ゆうすけ) 建築家、ドイツ建築家協会会員、一級建築士 1979年 米国ニュージャージー州生まれ。以降、奈良、カナダ、イギリス、東京で育ち、2004年早稲田大学大学院修士課程建築学専攻(石山修武研究室)卒業後、ザウアブルッフ・ハットン・アーキテクツ(ベルリン)に就職。2008年 ドイツより帰国し、光嶋裕介建築設計事務所を主宰。2011年 SDレビュー入選「凱風館」。現在、首都大学東京助教、桑沢デザイン研究所非常勤講師。ほぼ日刊イトイ新聞にて連載の「みんなの家。建築家一年生の初仕事」が、2012年7月に アルテスパブリッシングより単行本化。 光嶋裕介建築設計事務所 http://www.ykas.jp/ ほぼ日刊イトイ新聞 連載 「みんなの家。」http://www.1101.com/ourhome/index.html MATOGROSSO(マトグロッソ) 連載 「放課後のベルリン」http://matogrosso.jp/berlin/berlin-01.html
MORE -

小野智美『50とよばれたトキ──飼育員たちとの日々』
¥2,090
四六判 並製 208頁(カラー口絵8頁) 本体価格 1,900円+税 ISBN 978-4-904702-33-8 C0095 2012年5月刊行 ブックデザイン 有山達也+中島美佳(アリヤマデザインストア) 装画・挿画 がんも大二 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 佐渡のトキの話題や、トキに関わる取り組み、地域づくりなどを紹介するサイト「佐渡トキの話題」に『50とよばれたトキ』が紹介されました。 http://sado-toki-no-wadai.cocolog-nifty.com/sadozo/2012/07/post-ef40.html 『季刊ritokei(リトケイ)』2016年秋号(NO.18)「島Books & Cluture~Topics 島をより深く味わう1冊」 ▼概要 帽子に救われたトキ 真っ白なおしりから、光る卵がこぼれおちた。 帽子の中へすとん──「うわっ」 新米飼育員がとっさに受けとめた卵から生まれた50は、戦後の佐渡島で人の手によって育てられる五十番目のトキ。50とその家族、佐渡トキ保護センターの人々との、にぎやかでせつない毎日をつづる。 きれい好きで、おくびょうで、きちょうめんで、けなげなトキ。顔は真っ黒から灰色、レモン色、オレンジ色、そして赤色へ。羽は真っ白だったり、灰色に染まったり、朱鷺色に輝いたり。──知られてこなかったトキの多彩な姿を描く [目次] 50とその家族 佐渡トキ保護センターの案内図 佐渡トキ保護センターの紹介 はじめに──帽子で救われた卵 1章 初めての卵 飼育員になる/獣医師に会う/握手をかわす/弟子と師匠/キンに会う/卵を助ける 2章 名のない子 呼吸する卵/卵が動いた/さかごの卵/ヒナの誕生/えさを作る/失敗をこえて 3章 巣立ちの日 洗面器で日光浴/やさしいオス/ヒナたちの成長/ホオアカトキの子/八羽で引越し/わが家 4章 50の結婚 ドジョウだいすき/キンの小指/別れの朝/運命のリング/たたかう親/お見合いの日 5章 母になる日 こだわりの巣作り/初めての子育て/川の字/危機一髪/ストレス/ヒナの骨折 6章 共に歩んだ きずな/卵の法則/山の訓練所/冬の事故/大事な子/娘の旅立ち おわりに──飛ばせない飼育員 解説 保護の歴史/里のくらし/道拓いた人/導いたトキ/えさの開発 あとがき 登場人物の紹介 ▼プロフィール 小野 智美(おの さとみ) 朝日新聞記者。1965年名古屋市生まれ。88年、早稲田大学第一文学部を卒業後、朝日新聞社に入社。静岡支局、長野支局、政治部、アエラ編集部などを経て、2005年に新潟総局、07年に佐渡支局。08年から東京本社。09年9月に人事セクション採用担当課長。2011年9月から仙台総局。宮城県女川町などを担当。東松島市在住。 装画・挿画 がんも大二(がんも だいに) http://ganmodaini.com/website/ganmodaini.html 愛知県生まれ。絵本 『パトさん』(羽鳥書店、2011年)
MORE -
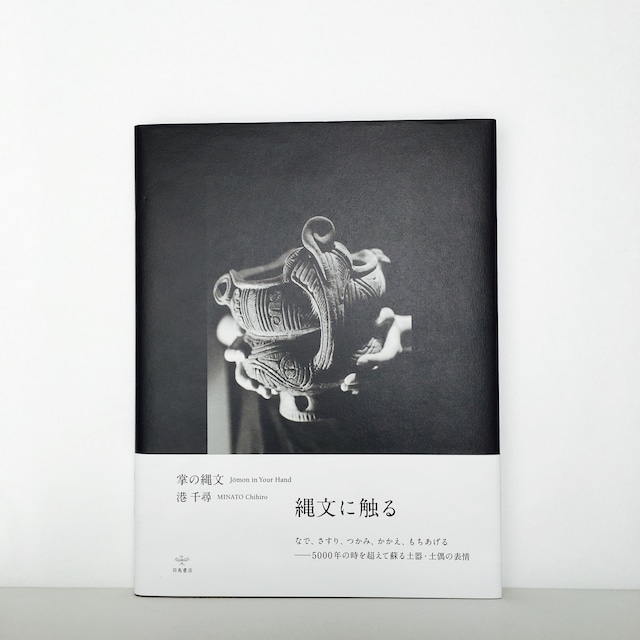
港千尋『掌の縄文』
¥4,400
B5判変型 上製 112頁 ダブルトーン印刷 本体価格 4,000円+税 ISBN 978-4-904702-32-1 C0072 2012年3月刊行 ブックデザイン 有山達也+中島美佳(アリヤマデザインストア) 印刷・製本 サンエムカラー 【日英併記】 ▼書評・記事 ▼概要 縄文に触る なで、さすり、つかみ、かかえ、もちあげる ── 5000 年の時を超えて蘇る土器・土偶の表情 人の手に抱かれた縄文土器・土偶の写真集。 写真家・港千尋が目を奪われた、土器を素手で持つ光景。見られるための展示品ではない、触られるために存在する土器や土偶の表情を、人の手とともに浮かびあがらせる。収録テキスト「抱かれた時間」では、岡本太郎が撮った、掌にのる縄文土器の写真を紹介。クロード・レヴィ=ストロースが縄文について語った唯一の文章「縄文展カタログ序文」(1998年、パリ日本文化会館にて開催)も再録する。 ▼プロフィール 港 千尋(みなと ちひろ) 1960年神奈川県生まれ。大学在学中に南米各地に滞在して以来、これまで赤道や大西洋など世界各地の自然と文化を対象に撮影してきた。主著『記憶──「創造」と「想起」の力』(講談社、1996)でサントリー学芸賞、展覧会「市民の色chromatic citizen」で第31回伊奈信男賞を受賞(2006)するなど、テキストとイメージの両面で創作を続けている。2007年には第52回ヴェネチア・ビエンナーレ美術展日本館コミッショナー、2008年には『HIROSHIMA 1958』(インスクリプト)の編集とキュレーションを務めるなど、幅広く活躍。主な写真集に『瞬間の山──形態創出と聖性』『文字の母たちLe Voyage Typographique』(以上インスクリプト、2001、2007)。近著に『レヴィ=ストロースの庭』(NTT出版、2008)、『書物の変──グーグルベルグの時代』(せりか書房、2010)、『パリを歩く』(NTT出版、2011)など。現在、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授、同芸術人類学研究所所員。
MORE -

ミヤケマイ『膜迷路 Down the Rabbit Hole』
¥5,280
◇ ◇ サイン本をお送りします ◇ ◇ A4判変型 並製 136頁 本体価格 4,800円+税 ISBN 978-4-904702-31-4 C1071 2012年1月刊行 ブックデザイン 有山達也+岩渕恵子(アリヤマデザインストア) 撮影 久家靖秀、繁田諭 他 印刷・製本 サンエムカラー 【日英併記】 *個展情報 「膜迷路 -Down the Rabbit Hole-」 Bunkamura Gallery(渋谷) 2011年12月23日~ 1月12日 http://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/111223miyake.html 個展タイトルを「膜迷路」と題し、3月兎(兎年の3月に起こった東日本大震災より着想を得ている)を追って穴に落ち、まるで不思議の国のアリスの世界に迷い込んでしまったかのごとく、平衡感覚や自分の常識に対して揺らぎを感じる日常の世界を、ミヤケマイならではのピュアでありながら毒のある独特な世界で展開する。 あるひとつの物事でも、見る視点によって、見えたり、歪んだり、見えなくなったりすることは誰にでもあること。世界には様々な解釈や理解の方法がある中で、人は自分の立ち位置によって、見える世界が違うのだというメッセージが込められたミヤケのハニカム構造体を用いた作品群など多数展示販売予定。 ベースにあるテーマは、「人の物差しを疑うより、自分の物差しを疑え」だと語るミヤケマイ。ミヤケは、これまでに数多くのギャラリーや美術館、アートフェアでの展示、さらには企業とのコラボレーションや本の装丁など、多岐に渡る活動を通じて進化を続けてきた。Bunkamura Galleryでは過去に2回の個展を開催。前回の個展の後、パリのエコール・デ・ボザールへの留学などを経験したミヤケマイが、5年の歳月を経てBunkamuraに帰ってくる。 個展の紹介記事「弐代目・青い日記帳」(2011/12/26) http://bluediary2.jugem.jp/?eid=2725 ▼概要 それでも世界はうつくしい ミヤケマイ最新作品集 2011年展覧会──壺中居「八百萬」(東京)、FINE ART ASIA 2011(香港)、横浜市民ギャラリー「ニューアート展 NEXT 2011 Sparkling Days」(横浜)、Bunkamura Gallery「膜迷路:Down the Rabbit Hole」(東京)──を中心に、最新作69点収録。ハニカム構造の作品群や日本美術のDNAをうけつぐ掛軸など、光と陰をたくみに用いながら天衣無縫に展開するミヤケマイの“2.5次元”世界を堪能する決定版作品集。 [寄稿] 浅井俊裕(水戸芸術館現代美術センター芸術監督) 内田真由美(アートコーディネーター) 中島利充(壺中居) 萩尾望都(漫画家) ▼プロフィール ミヤケマイ 横浜生まれ。独学。2001年より作家活動を開始。日本独自の感覚に立脚しながら、展示される空間を生かし、繊細かつ大胆にサイトスペシフィックな作品を展開する作家。画廊や美術館、アートフェアでの展示のみならず、企業とのコラボレーション(銀座メゾンエルメス、高島屋、森美術館ミュージアムショップなど)、本の装丁など、活動は多岐にわたる。2008-9年、奨学金を得て、Ecole Nationale superieur des Beaux-Arts(パリ国立美術大学大学院)に留学。2010年ドゥラメール・フィメール・アーティストアワードを受賞。作品集『おかえりなさい』(版画廊、2005年)、『ココでないドコか Forget me not』(芸術新聞社、2008年)。 公式HP http://www.maimiyake.com/
MORE -
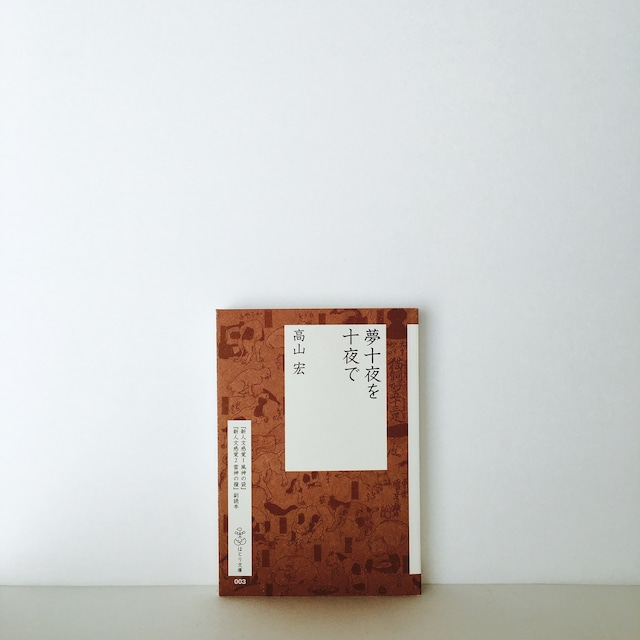
高山宏『夢十夜を十夜で』(はとり文庫003)
¥1,650
A6判 並製 312頁 本体価格 1,500円+税 ISBN 978-4-904702-30-7 C0070 2011年12月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平+大橋香菜子 印刷・製本 大日本法令印刷 *重版に際しまして、本体価格の変更をさせていただきました。1300円から1500円となります。ご了承ください。 (市場に流通している初版は1300円のままです。価格は、本体に記されているバーコードと本体価格表記に応じます) ▼書評・記事 ▼概要 大冊『新人文感覚』全2巻『風神の袋』『雷神の撥』に続く、高山宏の新境地。 学生たちと読み解く夏目漱石『夢十夜』の世界。書き下ろし300枚。驚きの想像力を発揮する学生たちと教師・高山宏との白熱コラボレーションが、 漱石研究へ新たな一石を投じる。 ▼プロフィール 高山 宏(たかやま ひろし) 1947年、岩手県久慈市生まれ。現在、大妻女子大学比較文化学部教授。 1968年刊行の『観念史事典』に魅了され、学の行き詰りがどういう感覚のどういう人々によって突破されるかの構造と歴史を追うのに夢中となり、結果的に領域横断的試みを続けるもの書きの一人となる。翻訳の質量は伝説的で、本人自身は翻訳家、最近はアート(Art/Ars)の人としての自覚が強い。別名学魔。 著訳書多数。代表作と本人信じるのは依然として「アリス狩り」4部作『アリス狩り』『目の中の劇場』『メデューサの知』『綺想の饗宴』(青土社)。翻訳ではロザリー・L・コリー『パラドクシア・エピデミカ』(白水社)。2011年に、合計2000頁近くにおよぶ大冊『新人文感覚』全2巻、『風神の袋』『雷神の撥』を刊行(羽鳥書店)。 高山 宏 『新人文感覚』全2巻 学魔・高山宏のここ15年間の集大成。全2巻、原稿枚数3500枚、図版840点。 数枚のエッセイから、60枚におよぶ論考まで、各87本収録。 『新人文感覚1 風神の袋』 『新人文感覚2 雷神の撥』
MORE -

高山宏『新人文感覚2 雷神の撥』
¥14,300
A5判 上製 1008頁 本体価格 13,000円+税 ISBN 978-4-904702-29-1 C0070 2011年11月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 *高山 宏 『新人文感覚』全2巻 学魔・高山宏のここ15年間の集大成。全2巻、原稿枚数3500枚、図版840点。 数枚のエッセイから、60枚におよぶ論考まで、各87本収録。 『新人文感覚1 風神の袋』 ▼書評・記事 ▼概要 各編タイトルの曲芸振りに始まり、 知の仏壇返す離れ業で本文を締める。 これじゃあ雷さまも撥鳴らして アンコール叫んじゃうタカヤマ文芸座! ──荒俣宏 (帯文より) フィギュラリズム、マンガ、笑い──マニエリスムの歴史と表象を闊歩する! [目次] 1 たかが英文学、されど英文学いのちがけ カタけりゃいいってもんじゃない──アルス・アマトリア論文術 桃山時代へスリップ・イン 図書館の五万数千冊のカード化に明け暮れた日々 マガジニズムという「小さな」マニエリスム 翻厄こんにゃく、或は命がけ 訳者の告白 この訳、機知甲斐ざたにつき──『フィネガンズ・ウェイク』解題 腐海の風景 キュアリアス・ビューティ──ウォルター・ペイター Born to be Wilde クリティックなんて「プー」!──A・A・ミルン文学の「プー」ラドックス プーはそこに降りて──子供部屋の中の森について 児童が問う百科、児童を問う百科 松岡正剛『遊学』 巽の方角に宝あり 椿説・由良君美の周辺 舞台吹き抜く松風のごとく 2 アリス・イン・ジ・アンダーグラウンド 1960s あまりにもボヘミアン──ルイス・キャロル新考 意味に風穴──六〇年代のキャロル・リヴァイヴァル 送──僕らは龍を殺せるか ラビリンスの時代 アリス・イン・フィギュアランド アリス・リミナル──ヤン・シュヴァンクマイエルとドロテア・タニング 「スラヴ」という世紀末的パラミーター 東欧が生んだ極上の不条理アート 「自然の歴史」のメタ映像化──ヤン・シュヴァンクマイエル作品集 アニメーティッド・ハウス──シュヴァンクマイエルとゴシック小説 69、何てエロチック──ヤン・コット追悼 ローマ発、異貌の英文学──マリオ・プラーツ マニエリスムのキケロー 新世紀シェイクスピア、いよいよ面白く──二〇〇〇年シェイクスピア祭記念講演 目を閉じて見る場所 パラドックスの毒 オンブロマニア──プロジェクションの近代史 四世紀たった今 近代的視覚空間の魅惑と閉塞を“視覚化”したやなぎみわの創意 夢の時間をありがとう 3 「マンガは萬画である」 こうしてくるんとひとまわり──絵本表象論・覚え メディア・コミックス──わずか四十年で四百年全表象史を駆け抜ける アニメーティングなもの──少しおおげさかも知れない 天真爛漫百貨店──『ラッキー嬢ちゃんのあたらしい仕事』 ぼくらを救った青春球場──『巨人の星』 ちば漫画の魅力──コマの中の空間の広がり 一九六九、青春東大望都暮し 4 見えるものはこんなにも楽しい(Ⅱ)──表象論応用篇 フィギュラティーフ──マサンのコレクションに寄せて メディア・ポエティックス──『オルペウスの声』と『メディアの法則』 「カトリック・パラノイア」の二十一世紀への遺言──マクルーハン『メディアの法則』 レター・コンシャス 遅さの豊かさ──エピストラリー・モード 電話が十七世紀からかかってくる──テレフォニックス論 球体ミレ二ア 近代が載る奔放なテーブル──OEDへの感謝 辞書放蕩 インテリア・バード──鳥、女、表象 遊弋する図像──クジラのイメージ瞥見 商標図像学入門 ヨハネ黙示録の終末界を行く フォーリング──多岐にして不可解なる世紀末に 「鳥の目」の文化史 鳥の目と虫の目──鳥瞰の近代史 月へトリップ──戸川純 讃 建築的創造力 5 ホモ・リーデンス(笑うヒト)になる──山口昌男 讃 夥しさの図像学 「笑い」が癒す遠近法の中の近代──一九六〇年代後半の「方法としての笑い」 逆説を弄す安吾 馬なき騎士が荒地を行く──『モンティ・パイソン』と『ホーリー・グレイル』 スラップスティック・シックスティーズ──トランスパーソナル心理学と 境界走殺──世紀末、「走り」の意味論 しまいにゃ笑うぞ──天才たけしの元気が出る世紀末 「ぼくんち」と呼ばれた笑い 郷愁映画のような昭和二十年代 ある夜のマレビト 6 マニエリスム、今日は──種村季弘 讃 終りのはじまり──種村季弘先生追悼 さよなら、カマラーデ──若桑みどり先生追悼 前衛と求道──多木浩二先生追悼 身内と胎内──『失われた庭』の僕 細部近代論覚え メディアの中の忍者学──六方手裏剣に仮託されたマニエリスム時代のトリックスター あらかじめ否定された「あとがき」──澁澤龍彦『サド復活』 「常数」としてのマニエリスム──ホッケ『迷宮としての世界』 イギリスからはじめて、話しはドイツ、フランス、イタリアなどユーロ圏に及ぶ──ネオ・バロック小説のこと 怪物の世界──「凶事」としてのロマン ほう、ホッケ教! マニエリスムの翻訳、翻訳のマニエリスム エンサークルメント──冲しきが若し 物語としてのキュレーション 7 さよならだけが人生だ 往生の物語──二〇〇二年七月 雷神口上 初出一覧/事項索引/書名索引/人名索引 ▼プロフィール 高山 宏(たかやま ひろし) 1947年 岩手県に生まれる 1974年 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了 現 在 大妻女子大学比較文化学部教授 [主要著書] 『アリス狩り』(青土社、1981、新版2008) 『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所、1992) 『ブック・カーニヴァル』(自由国民社、1995) 『カステロフィリア──記憶・建築・ピラネージ』(叢書メラヴィリア1、作品社、1996) 『エクスタシー──高山宏椀飯振舞I』(松柏社、2002) 『近代文化史入門──超英文学講義』(講談社学術文庫、2007)[『奇想天外・英文学講義』(講談社選書メチエ、2000)を改題] 『超人高山宏のつくりかた』(NTT出版、2007) 『かたち三昧』(羽鳥書店、2009) 『新人文感覚1 風神の袋』(羽鳥書店、2011) 『夢十夜を十夜で』(羽鳥書店、2011)
MORE -
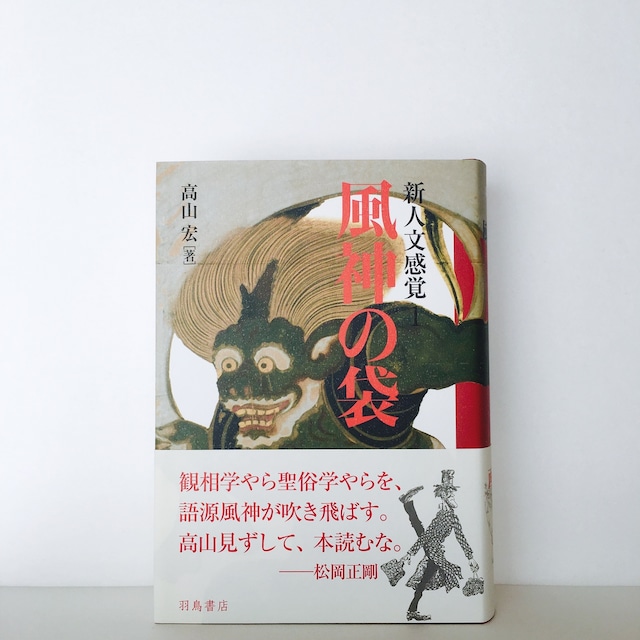
高山宏『新人文感覚1 風神の袋』
¥13,200
A5判 上製 904頁 本体価格 12,000円+税 ISBN 978-4-904702-27-7 C0070 2011年8月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 *高山 宏 『新人文感覚』全2巻 学魔・高山宏のここ15年間の集大成。全2巻、原稿枚数3500枚、図版840点。 数枚のエッセイから、60枚におよぶ論考まで、各87本収録。 『新人文感覚2 雷神の撥』 ▼書評・記事 ▼概要 観相学やら聖俗学やらを、 語源風神が吹き飛ばす。 高山見ずして、本読むな。 ──松岡正剛 (帯文より) 18世紀、「歩く」「見る」ことから一挙に花開いていった、観相学(フィジオノミー)の発達、推理小説の技術革新、ピクチャレスクの旺盛、百科総覧による視覚文化の横溢を、洋の東西を往還しながら、絢爛豪華に展開。 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 『新人文感覚1 風神の袋』 正誤表(2011年8月11日) http://www.hatorishoten.co.jp/teisei_fujin.pdf [目次] 1 ホモ・アンブランス(歩くヒト)になる──歴史を「歩き」直す方法 ゆっくり歩く 見えてくる 歩く、見る、書く──フィジオノミーというメソッドについて 物量と記号が氾濫する時代には、「小説」がふさわしい デフォー、あるいは〈敵〉? 近代の寓話──ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』 暗号で書かれた日記──サミュエル・ピープス『日記』 性懲りもなく証拠──ドキュメントの近代史 風刺の黄金時代を嗤う もう結構な話──ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』 ポンス熱死 運命ヴィジュアル 破顔一笑の本 フィジオノミー世紀末──顔で歴史を読む 禿頭王の恥じに始まる──かつらの近代史異説 「自由」をかぶった近代人──かつらの文化史、一番肝心なこと ザッツ・キャラクタリスティック──気質文学東西 逸れるたのしさ──「キャラクターをめぐって」 2 見ることに洋の東西はない──視覚文化論実践篇 既知のように語っていいのだろうか──モダニズム管見 ただ絵を論じても仕方がない──ポー文学のヴィジュアリティ 啓蒙イギリスの本屋さん もの知り近代の初め──エフライム・チェンバーズ アクチュアライズする目──身体また十八世紀に発す 十八世紀の身体を開く 十八世紀の一時間旅行 トゥーンベリ『江戸参府随行記』 エレキテルと探偵──平賀源内と夏目漱石が視た光と闇 アッカーとアーカート──源内は立派に世界文学 青い目のキョクテイ 大江戸マニエリスム事はじめ──高田衛『新編 江戸幻想文学誌』 マニエリストの才覚──『西鶴諸国ばなし』 表現者は身に繍るひと──松田修 「むしろ迂愚のごとく」のすさまじさ──その激語は一層のアウラを 歌麿のShell Shock──『潮干のつと』購入に感謝 大江戸新美術史──スクリーチ『大江戸視覚革命』 外連ピクチャレスク 視覚的快楽の閉回路へ のぞく近代──襞と襞の戯れ 聖と俗とをとりまぜながら、エロティックな文学は人と人との関係を反映する ポルノの黄金時代 マニエリスムの恋人たち、または口ほどにもあるメタ・ポルノ 『エロトス』の女芯に──荒木経惟の「猥褻」 もっとタフなフェミニズムのために パテリアリズム批判の切れ味 3 見えるものはこんなにも楽しい(Ⅰ)──表象論基礎篇 タブローのかたちをした空間──『言葉と物』と一九六〇年代 フーコー、跼蹐せず──『言葉と物』のアフターエフェクト 「物類」というタブローの宇宙──江戸本草学と花 二〇〇四年夏、オランダの光 珍しく花のある話──フローラル・ペインティング序説 プリズマティックス マニエリスムの王位継承者──ハムレットとドン・キホーテの図像学 自由放任の終わり──デフレと推理小説 『緋色の研究』を研究してわかること 百貨と胃袋──ゾラ・ヴィジュエル 「まったく新種の店」のパラダイム──ワナメイカーの世紀末 「世界は百貨店」とパリは言う 「パトロン」の系譜と機能──パトロネージからみたヨーロッパと日本の文化 美術館の収集品とは、略奪と権力の象徴 身体という「驚異の部屋」 メトニミックス──金子國義について インテリオフィリア──金子國義ふたたび 4 庭のように世界を旅する──ピクチャレスク遊学篇 「箱」ルネ=サンス──内藤ルネ讃 「風景画」の秘密──豪奢の夢① ラスキンとピクチャレスク 夢てふものは──『春昼』の風景 十九世紀美術史を映しだす鏡──ブロンテ姉妹と「絵」 廃墟としての世界 廃墟のパラドキシア ボマルツォの怪物庭園 フローラル小劇場──ガーデニングの世紀末 本当の「英国式」庭園について 動く密室──豪奢の夢②ツーリズムの近代(前) 乾いた日常を濡らす源「泉」 地図のポストモダン 軍隊のような旅──豪奢の夢③ツーリズムの近代(後) 世紀末、スポーツはたくらむ──自転車、オリンピック、闘牛 旅という想像力 5 家が「うち」と呼ばれるとき──幻想文学入門篇 辞書と偽書──「アンティレゴメナ」文学史覚え 植生の建築史──ヴィクトル・オルタの方へ マニエリスム──「あの人」としか言えないことの豊かさ ファウスト、ヴィクトリア朝に甦る それは繰り返す──『IT』を読む 家庭に潜む恐怖──スティーヴン・キング『IT』 本をデザインする家──『紙葉の家』に興奮した 「ホーンティッド・ハウス」論今般 いま読者に何が「ニードフル」か 「不気味なものが……」川端幻想文学の新しさ──「片腕」「眠れる美女」にふれて 6 私は人文がしめ殺されるのをこの目で見た 首都大学東京というグランド・ゼロに立つ 風神口上 初出一覧/事項索引/書名索引/人名索引 ▼プロフィール 高山 宏(たかやま ひろし) 1947年 岩手県に生まれる 1974年 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了 現 在 大妻女子大学比較文化学部教授 [主要著書] 『アリス狩り』(青土社、1981、新版2008) 『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所、1992) 『ブック・カーニヴァル』(自由国民社、1995) 『カステロフィリア──記憶・建築・ピラネージ』(叢書メラヴィリア1、作品社、1996) 『エクスタシー──高山宏椀飯振舞I』(松柏社、2002) 『近代文化史入門──超英文学講義』(講談社学術文庫、2007)[『奇想天外・英文学講義』(講談社選書メチエ、2000)を改題] 『超人高山宏のつくりかた』(NTT出版、2007) 『かたち三昧』(羽鳥書店、2009)
MORE -

木庭顕『現代日本法へのカタバシス』
¥8,580
SOLD OUT
*申し訳ありませんが、こちらの書籍は品切れです。 (重版予定はありません) A5判 上製 320頁 本体価格 7,800円+税 ISBN 978-4-904702-28-4 C3032 2011年10月刊行 装幀 原 研哉+大橋香菜子 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼概要 『ローマ法案内』の著者の初の論文集 現代日本の法、法学、実務、法学教育について論じた既発表8編と書下し2編(「『ローマ法案内』補遺」、「夏目漱石『それから』が投げかけ続ける問題」)を収録。ローマ法研究者ならではの根源的な批判と鋭い考察に満ちた待望の書。 *“カタバシス”とは――ギリシア語で冥府への下降を意味し、過去への通路を指示するが、ローマ法を専門とする著者にとって、むしろ現代の日本に「降りる」ことこそが冒険を意味するというアイロニー。 [目次] はしがき I 1 現代日本法へのカタバシス II 2 「客殺し」のインヴォルティーノ,ロマニスト風 3 占有概念の現代的意義 4 「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版 5 『ローマ法案内』補遺──主として日本の民事法との関連で 6 夏目漱石『それから』が投げかけ続ける問題 III 7 余白に 8 歴史学の認識手続と法学的思考 9 法学部──批判的紹介の試み 10 法科大学院と実定法学 ▼プロフィール 木庭 顕(こば あきら) 1951年生まれ。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。 『法存立の歴史的基盤』(東京大学出版会、2009年)で、日本学士院賞を受賞(2011年)。
MORE -

木村草太『憲法の急所──権利論を組み立てる』
¥3,080
SOLD OUT
*現在、改訂版(第二版)が刊行されています。 A5判 並製 360頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-26-0 C3032 2010年7月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 ウェブサイト「ジセダイ」|ザ・ジセダイ教官 「若き憲法学者・木村草太先生に、"法学のマインド"を学ぶ!」前後編 *後編では、『憲法の急所』が紹介されています。 http://ji-sedai.jp/special/kyokan/KimuraSouta.html 『法学セミナー』2011年12月号「ブック・レビュー」 「おそらく、本書が司法試験受験生から絶大な支持を受けた理由は、「論証例」であろうが、私の印象では、むしろ「検討編」に本書の特徴があるように思われる。……本書「検討編」には無駄がない。……知識の確認・補強に加え、憲法上の争点を抽出する直感力を磨く上で役立つであろう」(評者・小山剛先生/慶應義塾大学教授) 『週刊文春』2011年12月1日号「東大で一番売れている本は『憲法の急所』、ならば慶應は?」 『SPA!』2011年10月18・25日号「THE BESTSELLERS」東大生協書籍部(本郷)のベストセラー第1位として紹介。 ▼概要 攻防の争点=急所を掴む 急所をふまえ、権利論を組み立てるための 判例・学説に対する明晰な理解と論証技術を身に付ける 首都大学東京法科大学院で教鞭をとる著者が、上級憲法の講義をそのまままとめた演習書。憲法上の権利の基本的知識と権利論の考え方について解説した「講義編」と人権論を網羅した具体的事例を検証する「演習編」の二部構成。基本知識があれば理解できる丁寧な記述と新司法試験を想定した長文の問題を特長とする。演習編には最先端の学説を意識した解説に加え、著者による論証例を付す。独習者向けテキストとしても最適。 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。 ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 憲法の急所 正誤表 (2012年3月26日更新)★リンク準備中 [主要目次] Ⅰ 講義編 憲法上の権利の知識と手順 第1章 憲法上の権利の基礎知識 第1節 憲法上の権利の概念と分類 第2節 自由権の基礎知識 第3節 請求権の基礎知識 第2章 憲法上の権利の基本手順 第1節 自由権の基本手順 第2節 請求権の基本手順 第3章 私人間効力論 Ⅱ 演習編 権利論を組み立てる 第4章 精神的自由権 第1問 国歌伴奏拒否事件 第2問 水泳受講拒否事件 第3問 月島宿舎ビラ配り事件 第4問 妄想族追放条例事件 第5章 経済的自由権 第5問 ペットボトル輸出規制事件 第6問 学習塾距離規制事件 第6章 平等権・請求権 第7問 Y市育児手当事件 第8問 生活保護減額処分事件 第9問 住基ネット起因損害の賠償制限 ▼プロフィール 木村草太(きむら そうた) 1980年 横浜に生まれる 2003年 東京大学法学部卒業 2003年 東京大学大学院法学政治学研究科助手・憲法専攻 (2006年まで) 現 在 首都大学東京都市教養学部法学系・東京都立大学法学部准教授(兼任) (2016年4月、同大学教授) [著書] 『平等なき平等条項論──equal protection条項と憲法14条1項』(東京大学出版会、2008年) 公式ブログ「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr
MORE -
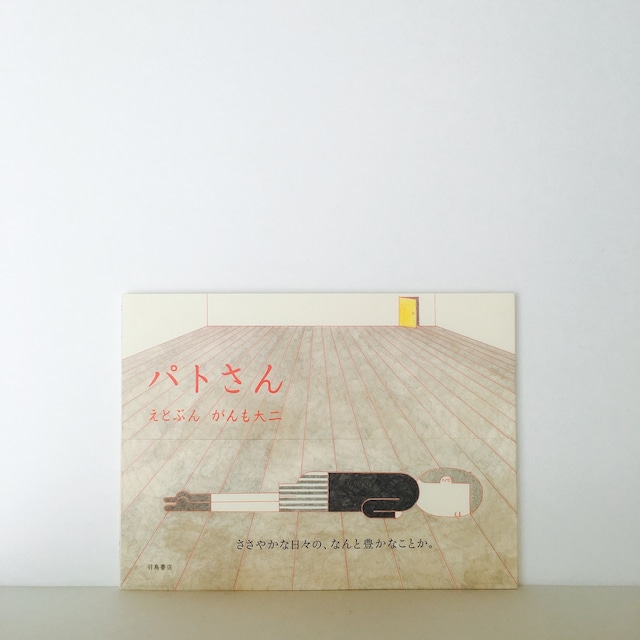
がんも大二『パトさん』
¥1,650
A5判変型 並製 34頁 本体価格 1,500円+税 ISBN 978-4-904702-25-3 C0071 2011年6月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 ▼ブログ等での紹介 心斎橋アセンス アセンス日記 「ツボにはまった!! 『パトさん』」http://boooook.exblog.jp/15626769/ What's up, Luke http://luke.jugem.jp/?day=20110713 ▼概要 ささやかな日々の、なんと豊かなことか。 29の絵と27の言葉でつなぐ、パトさんの人生。 ▼プロフィール がんも大二(がんも だいに) 愛知県生まれ。「パトさん」で第11回ピンポイント絵本コンペ優秀賞。 公式HP http://ganmodaini.com/website/ganmodaini.html ▼関連書籍 小野智美『50とよばれたトキ──飼育員たちとの日々』 装画・挿画 がんも大二 『石巻だより 通巻1-12号』 イラスト がんも大二
MORE -

三瀬夏之介・池田学『現代アートの行方』(はとり文庫002)
¥770
A6判 並製 128頁 本体価格 700円+税 ISBN 978-4-904702-24-6 C1071 2011年6月刊行 ブックデザイン 原 研哉+中村晋平 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 同じ1973年生まれの作家、三瀬夏之介と池田学による初顔合わせ対談。スケールの大きさで比較されることも多い二人が、初画集をほぼ同時に刊行。池田学が文化庁研修制度でカナダへ旅立つ直前に実現した公開対談では、二人の作風の違いや、意外な素顔がつぎつぎと明らかに。 収録:2011年1月14日(紀伊國屋サザンシアター) [目次] 1973年生まれの世代 高校教師時代 フィレンツェ研修の1年間、そして山形へ アウトドア派 絵の描き方 なぜ僕と話してみたいと?[学→夏] 肩書きは何?[夏→学] 「日本画」についてどう思う?[夏→学] 卒業後の生活のことは?[夏→学] 法廷画と自作との関係は?[夏→学] 画材は何を使っている?[学→夏] 絵に登場するモチーフの意味は?[学→夏] 白の部分はどうやって決めるの?[夏→学] どんなふうに制作しているの?[夏⇔学] 作品のサイズや絵肌については?[夏→学] 画集製作で大変だったことは?[学→夏] 2年かけて完成ってどんな感じ?[夏→学] 趣味は?[学→夏] ファミコンやった?[夏→学] なぜカナダ?[夏→学] 絵を描く理由は?[夏⇔学] あとがき 三瀬夏之介 あとがき 池田 学 ▼関連書籍 三瀬夏之介『冬の夏』 池田学『池田学画集1』
MORE -
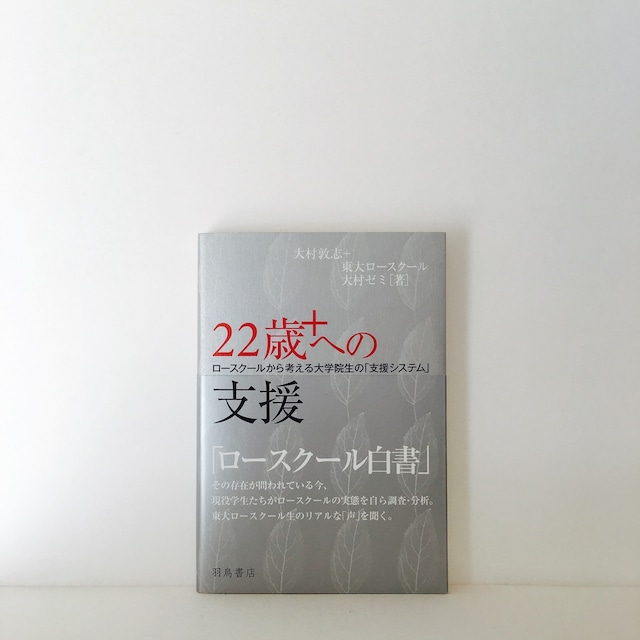
大村敦志+東大ロースクール大村ゼミ『22歳+への支援──ロースクールから考える大学院生の「支援システム」』
¥2,640
四六判 並製 176頁 本体価格 2,400円 ISBN 978-4-904702-22-2 C0032 2011年3月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼概要 「ロースクール白書」 その存在が問われている今、現役学生たちがロースクールの実態を自ら調査・分析。東大ロースクール生のリアルな「声」を聞く。大学院生全体を視野に入れながら、ロースクール生への支援のあり方、法曹養成制度のあり方を提言する。 [主要目次] はしがき 序 章 ロースクール生が直面している問題 第1章 ロースクール生の生活状況 1 修了生から見たロースクール 2 ロースクール生・法学部生へのアンケートから 第2章 支援制度の現状と課題 1 奨学金・授業料免除 2 寮 3 子育て支援 結 章 ロースクール生への支援とは 解説編 この本がめざすもの 大村敦志 メイキング編 この本ができるまで 竹内弘枝 あとがき ▼プロフィール 東大ロースクール大村ゼミ8名(2010年度) 竹内 弘枝 (たけうち ひろえ) 1982年 東京大学教育学部卒業 2006年 放送大学大学院修士課程卒業 現 在 (社)商事法務研究会研究員[法務教育担当] 大村 敦志 (おおむら あつし) 1958年 千葉県に生まれる 1982年 東京大学法学部卒業 現 在 東京大学法学部教授
MORE -
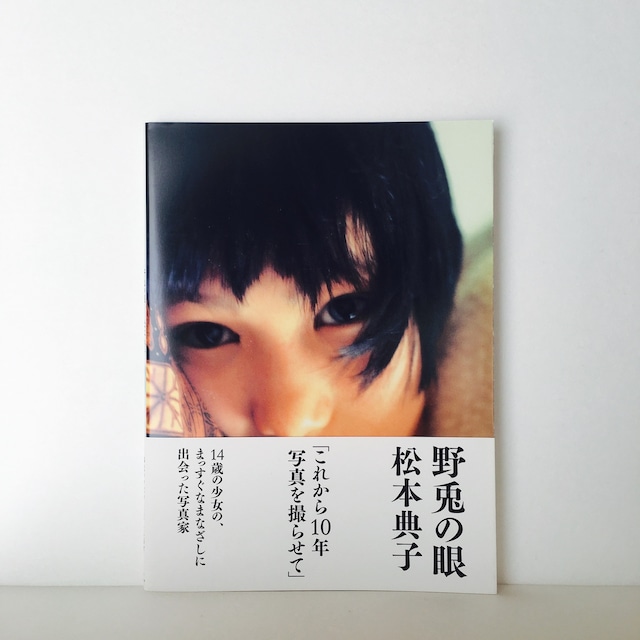
松本典子『野兎の眼』
¥3,740
◇ ◇ サイン本をお送りします ◇ ◇ B5判変型 並製 104頁 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-21-5 C0072 2011年4月刊行 ブックデザイン 有山達也+中島美佳(アリヤマデザインストア) 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 ▼書評・記事 『産経新聞』2011年4月23日 「意外なほど、肖像は少ない。半分以上は情景だ。メトロノーム、枯れた花、窓の外の雨…。時の流れを印象づけるモチーフが多い。写真集の終盤、幼い娘の写真にページを繰る手を止める。1歳半ぐらいだろうか。14歳だった少女と見比べて、つい笑みがもれる。みずみずしさにあふれた、労作にして秀作」。 『信濃毎日新聞』2011年5月1日 「彼女自身を捉えた写真は半分に満たない。色鮮やかな花や草木、緑豊かな山と海、空、飼い犬、友達、笑顔の家族、自宅の畳や壁時計…。彼女を包み込み、見守り、育んだ人と世界がそこにある。(…)100ページほどの写真集に、小さくて大きなドラマが収められている」。 『野兎の眼』 紹介ブログ 弐代目・青い日記帳 野兎の眼 http://bluediary2.jugem.jp/?eid=2481 ▼概要 「これから10年写真を撮らせて」 奥吉野の村の秋祭りで出会った14歳の少女を、10年かけて撮り続けた91枚の写真。まっすぐなまなざしを持った少女が、思春期をへてやがて大人になり母となる過程を、吉野の風景や日常の断片とともに鮮やかに映しとる。 寄稿:飯沢耕太郎 「共感覚の震え」 ▼プロフィール 松本典子(まつもと のりこ) 1970年、東京生まれ。自由の森学園高等学校、和光大学人文学部芸術学科卒業。インターメディウム研究所修了。第14回写真「ひとつぼ展」グランプリ受賞。写真集『うさぎじま』(早川書房、2007年)──広島県の大久野島、沖縄県のカヤマ島に棲む野生化したカイウサギたちの姿と植物、風景を撮った写真集。写真絵本『うさぎ うさぎ こんにちは』(『こどものとも 0.1.2』福音館書店、2011年)。 作家HP http://microcosmos.format.com/ *個展 「野兎の眼」東京展 2012年3月13日(火)~3月25日(日) 会場 CROSSROAD GALLERY (新宿区四谷) *パネル展示 吉祥寺ブックスルーエで『野兎の眼』のパネル展示を行いました。 期間 2011年4月1日~4月30日
MORE -

鴻池朋子『焚書 World of Wonder』
¥4,180
A4判変型 上製 48頁 本体価格 3,800円+税 ISBN 978-4-904702-20-8 C1071 2011年4月刊行 ブックデザイン 大西隆介(direction Q) 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 ▼概要 すばらしいせかい 「インタートラベラー」の壮大な世界観で話題を呼んだアーティスト鴻池朋子の絵本。何十億年の時を駆け、想像力をめぐる旅がはじまる──World of Wonder すばらしいせかい。鴻池朋子が本と遊びぬいた、本の絵本。生命のうねりを描くドローイングの鼓動を伝える。 ▼関連書籍 鴻池朋子『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』 鴻池朋子『根源的暴力』 鴻池朋子『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』 工藤庸子[訳・解説]『いま読むペロー「昔話」』 ▼プロフィール 鴻池朋子(こうのいけ ともこ) 秋田県生まれ、東京在住。1985年東京藝術大学日本画専攻卒業。絵画、彫刻、アニメーション、絵本、ゲームなどの手法を駆使して、現代の神話を壮大なインスタレーションで表現する美術家。森や街といった人間を取り巻くあらゆる環境のなかで作品を生みだし、独自の地図をつかって作品の中枢にある「遊び」へと観客を巻き込むなど、他に類を見ない創作活動は国内外で高い評価を得ている。主な個展に2006年「第0章」大原美術館、2009年「インタートラベラー 神話と遊ぶ人」東京オペラシティアートギャラリー(霧島アートの森巡回)他多数。書籍は絵本『みみお』(青幻舎)、『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(羽鳥書店)他。
MORE -
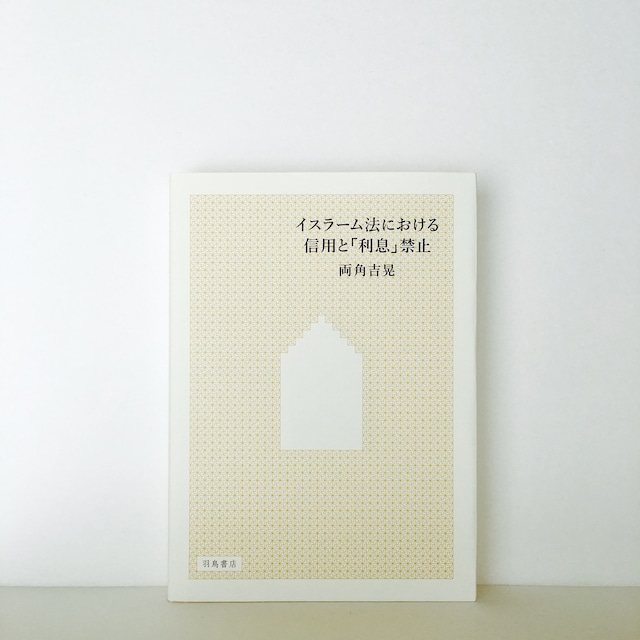
両角吉晃『イスラーム法における信用と「利息」禁止』
¥10,450
A5判 上製 336頁 定価: 9,500円+税 ISBN 978-4-904702-19-2 C3032 2011年1月刊行 装幀 中津創一郎 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼概要 「イスラーム金融」の本質を法律学から追求する本格的研究書 『法学協会雑誌』(1997-98)に発表した論考をベースにその後の研究成果を踏まえてまとめたもの。東京大学法学部とロースクールでイスラーム法を担当する著者初の学術書。イスラーム世界との交流には必須の書。 [主要目次] 凡例 アラビア語転写文字の読み方 序章 イスラーム法とは 第1節 「法」を指し示す2系統の用語 第2節 イスラーム法 第3節 イスラーム法の特徴 第4節 法解釈方法論 第5節 法学派 第6節 イスラーム法史概説 第1章 リバーを取り巻く問題状況 第1節 ムラーバハ契約を巡るイギリス裁判所の判決 第2節 従来のリバー理解 第3節 利息概念の検討 第2章 リバーおよび関連諸概念の分析 第1節 「売買」の基本的ルール 第2節 法学書に現れたリバーの定義 第3章 サルフ 第1節 サルフの定義 第2節 サルフの諸要件 第3節 サルフの諸要件とリバー禁止準則の関係 第4節 サルフにおける「増加」と「減少」 第5節 サルフのイカーラとイスティブダール 第6節 サルフにおける「相殺」 第7節 総括:サルフに固有の準則とリバー禁止準則との関係 第4章 サラム 第1節 サラムの定義とその特徴の概略 第2節 売主の手元にない物の「売買」の禁止 第3節 サラムの諸要件 第4節 サラムとリバー禁止準則の関係 第5節 サラムの代金および被売買物の受取前の「売買」 第6節 サラムの諸要件の中に現れた「ムフリス」および「イフラース」の概念 第7節 サラムの「売買」の意味 第5章 ムラーバハ 第1節 ムラーバハの定義 第2節 ムラーバハの諸要件 第3節 代金(原価額)について 第4節 代金に付加される費用 第5節 背信行為成立の諸要件 第6節 背信行為が明らかになった場合の効果 第7節 ムラーバハと信用供与 第6章 カルド 第1節 カルド:「消費貸借」 第2節 恵与関係としてのカルド 第3節 「使用貸借」としてのカルド 第4節 「利益を生ぜしめるカルド」について──カルドにおけるリバー 第5節 カルドの本質 第7章 エジプト民法典における利息概念 第1節 エジプト民法典の歴史 第2節 エジプト民法典概観 第3節 エジプト民法典における消費貸借契約および利息 終章 結論 第1節 リバー概念の意味 第2節 イスラーム法の「変形」──エジプト民法典の危険負担制度とイスラーム法の滅失理論 第3節 法的諸概念のコンステレーション 後記 索引 ▼プロフィール 両角吉晃(もろずみ よしあき) 1968年 長野県生まれ 1990年 東京大学法学部卒業 1996年 東京大学法学部助教授 2010年 東京大学法学部教授
MORE -
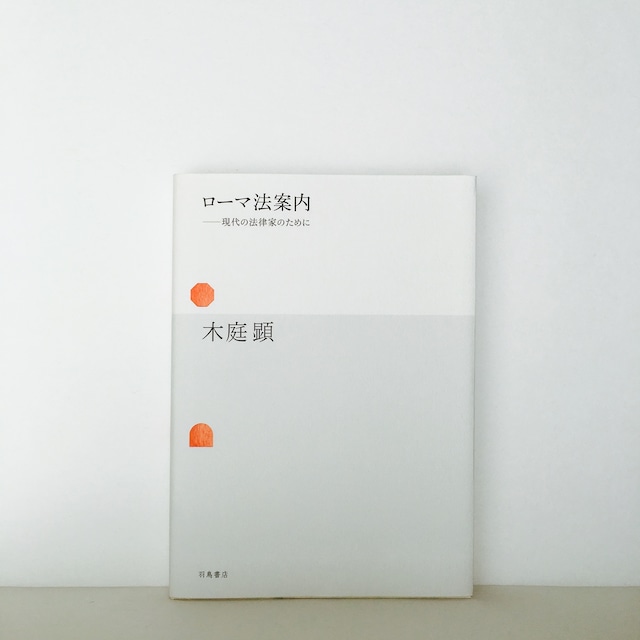
木庭顕『ローマ法案内──現代の法律家のために』
¥5,720
SOLD OUT
*申し訳ありませんが、品切れです。 A5判 上製 256頁 本体価格 5,200円+税 ISBN 978-4-904702-17-8 C3032 2010年12月刊行 装幀 原 研哉+中村晋平 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼概要 現代法を読み解く鍵──法律を学ぶすべての人へ 近代法の淵源ローマ法を、歴史学の成果をふまえて捉え直す。『政治の成立』(1997年)、『デモクラシーの古典的基礎』(2003年)、『法存立の歴史的基盤』(2009年、いずれも東京大学出版会)の三部作の成果を元に、現代の法律家に向けて「新鮮なローマ法」を提示。現代の法について考え研究するすべての人に贈る知的営為の書。 [目次] 0 序 1 歴史的前提 1−0 [ロ−マ社会について知ることは大変に困難である,ということをまず強く念頭に置くこと] 1−1[第一の歴史的前提は政治であること,ただし政治の概念に注意を要すること] 1−2[ローマでは,どのようにして,政治を備えた体制ができあがったか] 1−3[できあがった政治はどのような仕組を有したか──政治制度の骨格] 1−4[裁判は最も重要な政治制度の一つである] 1−5[都市が無ければ政治は無く,したがって法も無い] 1−6[その都市はどうやって実現されたのか?] 2 民事法の原点 2−1[法の原理を把握するためには,まずデモクラシーの原理を把握しておく必要がある] 2−2[ローマでも,特有の仕方ではあったが,デモクラシーへと人々は辿り着いた] 2−3[法の基本原理は占有である] 2−4[民事訴訟の基本原則は占有概念のコロラリーである] 2−5[取得時効の存在理由は人権概念につながる] 2−6[消費貸借の危険性およびそれへの対処法] 2−7 地役権,相隣関係,不法行為 2−8 相続財産 2−9 身分法 3 契約法の基本原則 3−0[契約や契約法をどのように捉えるべきか] 3−1 助走 3−2 契約法を生み出した社会 3−3 占有原理の適用 3−4 契約の根幹 3−5 契約責任 3−6 売買 3−7 契約の類型について 3−8 自由人の労働 3−9 委任 3−10 組合 3−11 寄託,銀行 3−12 bonorum possessio 3−13 嫁資 dos,ususfructus,fiducia,そしてusucapioの付加的要件 4 所有権概念の登場とその帰結 4−1 新しい現実 4−2 占有概念の転換 4−3 領域上の占有を売買する 4−4 過失(culpa) 4−5 契約責任の変貌 4−6 意思 voluntas 4−7 刑事訴訟の新展開 4−8 犯罪の新しい概念 4−9 元首政 5 所有権に基づく信用の諸形態 5−1 locatio conductio 5−2 質権 5−3 債権信用 5−4 condictio 周辺の新動向 5−5 保証 5−6 特有財産 peculium 5−7 民事訴訟の変容 5−8 争点決定 litis contestatio 5−9 身分法の変容 6 「ローマ法」伝播に関する簡単な注記 6−1 元首政期以降の状況 6−2 ユスティニアーヌスの事業 6−3「ロ−マ法」の再発見 6−4 人文主義法学 6−5 実証主義 6−6 現代 欧文索引/和文索引 ▼プロフィール 木庭 顕(こば あきら) 1951年生まれ。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。 『法存立の歴史的基盤』(東京大学出版会、2009年)で、日本学士院賞を受賞(2011年)。
MORE -
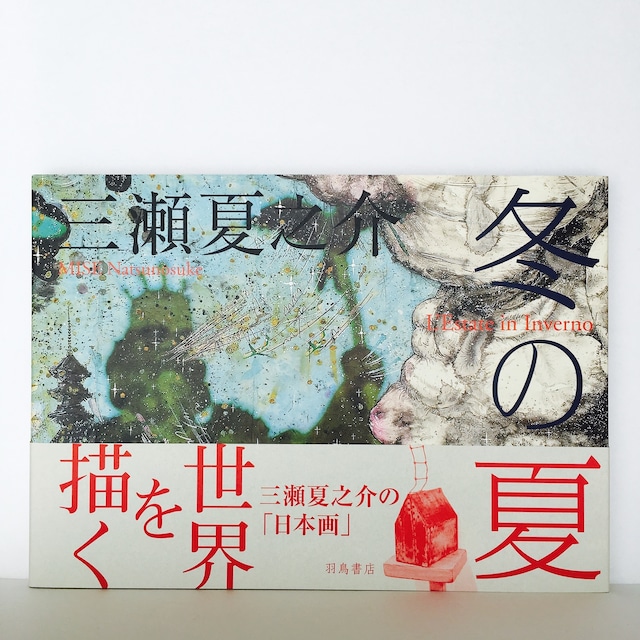
三瀬夏之介『冬の夏』
¥4,620
A4判横 上製 120頁 本体価格 4,200円+税 ISBN 978-4-904702-16-1 C1071 2010年11月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 サンエムカラー 製本 牧製本印刷 【日英併記】 ▼概要 世界を描く 三瀬夏之介の「日本画」 絵を描き、思考し、ひたすら描き続ける──2005年から2010年にわたる三瀬夏之介の軌跡 全長15メートルにおよぶ《だから僕はこの一瞬を永遠のものにしてみせる》をはじめ、《肘折幻想》《千歳》《J》《ハヨピラ》《ぼくの神さま》《君主論 -Il Principe-》《日本画滅亡論》《日本画復活論》《日本の絵》《奇景》などの主要作品を収録。展覧会風景とともにダイナミックに再現する。 [収録テキスト] 高階秀爾「創造する魂の軌跡」/宮本武典「〈肘折山水〉をめぐって」/三瀬夏之介「〈ひじおりの灯〉に寄せて」「《J》に寄せて」「北から」「描くこと」「日本画復活論」「日本画考」「日々」「家庭的であり宇宙的である」ほか、ブログ記事も多数。 ▼プロフィール 三瀬夏之介(みせ なつのすけ) 1973 奈良に生まれる 1997 京都市立芸術大学美術学部美術科日本画専攻卒業 1999 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了 2007-08 五島記念文化財団研修員としてフィレンツェにて研修 現 在 東北芸術工科大学准教授 第22回タカシマヤ美術賞(公益信託タカシマヤ文化基金主催)受賞 作家公式HP http://www.natsunosuke.com/ 東北画は可能か? 公式HP http://www.tohokuga.com/ ▼関連書籍 池田学+三瀬夏之介『現代アートの行方』
MORE -

長谷部恭男『憲法のimagination』
¥2,860
SOLD OUT
四六判 上製 248頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-15-4 C1032 2010年9月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『AERA』2010年10月18日AERIAL-BOOK 「いま最も旬な憲法学者のエッセー集だ。~」(ら) 『朝日新聞』2010年11月14日 「本書のカギはまさに「想像力」だ」 『出版ニュース』2010年11月中旬号 ブックガイドにて紹介 「法律学とは人間や世の中あっての学問という著者の思索、見識が、痛烈な皮肉やウイットの中に発揮され、憲法を学び、論じるための指南にも」 『日経プレミアPLUS』 vol.11「仕事に効く〈本〉」 木村草太先生が紹介してくださいました。「日本最高の憲法学者の1人である著者が、哲学、文学、映画など幅広い知見を生かして憲法にアプローチするエッセイ・書評集。軽妙な語り口に引き込まれるうちに、憲法や法律が身近に感じられるはず」。 ▼概要 思索する愉しみ 古今の哲学や文学、映画を緯糸に、 憲法学者が織り上げるエッセイ・書評集 日本を代表する憲法学者によるエッセイ集。 最新論文集『憲法の境界』、入門書決定版『憲法入門』につづく羽鳥書店刊行の第三弾。東京大学出版会『UP』誌での連載エッセイ「憲法のimagination」24回を中心に、2004年以降、著者が各紙・誌で発表してきた書評、コラムの計42編をまとめた。法律は縁遠いものと思っている人にとっても、「憲法学は、人はいかに行動すべきかを考える学問の一分野だということになります」という著者の一言には意外性を感じ、関心を持てるだろう。その小気味よい文章に引き込まれるうちに、憲法について興味深く学び、考えることができる。より幅広い人びとにとって読みやすいリベラルアーツ版憲法入門書といえる一冊。 [目次] はしがき 第1部 憲法のimagination 1 生きている 2 イェルサレムとアテネ 3 日本国民、カモーン! 4 自己目的化の陳腐さについて 5 アテネ学会日記 6 国民を使用人扱いするのか? 7 法哲学者の偉大さについて 8 「ガチョーン!」の適切さについて 9 続く? 10 ゲバラのように生きる 11 東京・横浜学会日記 12 とらわれて 13 謎はない 14 特殊な国、アメリカ 15 そうしたかったから 16 どこへ行くのか 17 法と戦略 18 へぇ、へぇ 19 認識を示す 20 そんな風には生きてない 21 厳密に言ってどうなのか 22 先例に従う 23 四人の子ども 24 スピノザの自由 第2部 ハムレットとドン・キホーテ 1 カール・シュミットのシェイクスピア カール・シュミット/初見基訳『ハムレットもしくはヘカベ』 2 ドン・キホーテの夢 ミラン・クンデラ/金井裕・浅野敏夫訳『小説の精神』 セルバンテス/牛島信明訳『ドン・キホーテ』(全六冊) 3 信じられない カズオ・イシグロ/土屋政雄訳『日の名残り』 4 法をおしえて E・H・カントロヴィッチ/甚野尚志訳『祖国のために死ぬこと』 5 人ではない J・L・ボルヘス/鼓直訳『伝奇集』 6 本の虫日記 7 憲法論争と九条問題 8 青春の一冊--おのれの守護神を信じた職業選択 マックス・ウェーバー/尾高邦雄訳『職業としての学問』 9 この人・この3冊 第3部 憲法学は何を考えるのか 1 憲法学は何を考えるのか 2 憲法改正論議の不思議 3 ソウル学会日記 4 がっかりなさいましたか? 5 地方自治と民主政治 6 平成「20年」 7 人民は代表されえない 8 ショートエッセー わたしとコピペ 9 評価 初出一覧 ▼プロフィール 長谷部恭男(はせべ やすお) 1956年広島生まれ。東京大学法学部卒業。早稲田大学法学学術院教授。 著書に 『比較不能な価値の迷路」』 『憲法の理性』 『憲法の境界』 『憲法入門』など。 ▼関連書籍 長谷部恭男『憲法の境界』 長谷部恭男『憲法入門』
MORE -
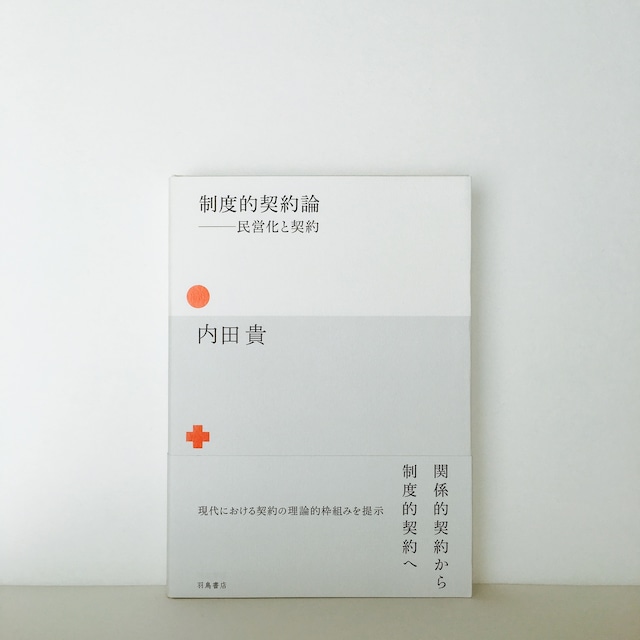
内田貴『制度的契約論──民営化と契約』
¥3,740
A5判 上製 240頁 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-14-7 C3032 2010年7月刊行 ブックデザイン 原 研哉+中村晋平 印刷 理想社 製本 牧製本印刷 ▼概要 関係的契約から制度的契約へ 現代における契約の理論的枠組みを提示。「債権法を中心とする民法典の改正」を進めている著者の専門領域の最新研究の成果。『契約の再生』(1990 年)で、関係的契約という契約概念を提唱した著者が、民営化時代の契約の理論枠組みとして新たに制度的契約という概念を提唱する。現代を理解するための法的パースペクティブ。 [目次] 第1部 民営化(privatization)と契約──制度的契約論の試み 第2部 制度的契約と関係的契約──企業年金契約を素材として 第3部 講演:制度的契約論の構想 第4部 資料:松下年金訴訟 鑑定意見書 ▼プロフィール 内田 貴(うちだ たかし) 1954 年大阪府生まれ。東京大学法学部教授、法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与を経て、現在東京大学名誉教授、早稲田大学特命教授。 [主要著書] 『抵当権と利用権』(有斐閣、1983) 『契約の再生』(弘文堂、1990) 『契約の時代──日本社会と契約法』(岩波書店、2000) 『債権法の新時代──「債権法改正の基本方針」の概要』(商事法務、2009) 『民法Ⅰ 総則・物権総論(第4版)』(東京大学出版会) 『民法Ⅱ 債権各論(第3版)』(東京大学出版会) 『民法Ⅲ 債権総論/担保物権(第3版)』(東京大学出版会) 『民法Ⅳ 親族・相続(補訂版)』(東京大学出版会)
MORE -

田中純『イメージの自然史──天使から貝殻まで』
¥3,960
SOLD OUT
A5判 並製 332頁 本体価格 体3,600円+税 ISBN 978-4-904702-11-6 C3010 2010年6月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 精興社 製本 矢嶋製本 ▼書評・記事 『日本経済新聞』2010年8月8日「歴史の深層から現在を思考」評・五十嵐太郎(建築評論家) 『東京新聞』2010年8月15日「かたちをめぐる自在な連想」評・柏木博(デザイン評論家) 『読売新聞』2010年10月10日 「変化するおもかげ追う」評・前田耕作(アジア文化史家) 『出版ニュース』2010年8月中旬号「ブックガイド」 『idea no.342』2010年9月号「ブック&インフォメーション」 ▼概要 記憶・生命の原型的イメージを手繰る ──都市表象分析をめぐる思索のエッセンス 「自然史」とは「ナチュラルヒストリー」を意味している。それは、「自然誌」「博物誌」「博物学」でもあり、分類学的な博物誌と系統学的自然史のあわいを揺れ動きながら、原型的イメージを図鑑のように編み、それが変容してゆく過程を歴史のなかにたどる。『UP』の好評連載「イメージの記憶」を中心に、『10+1』連載「都市表象分析」の最後の3回分も収録。本書には、前著『政治の美学』にいたるまでの著作のエッセンスが凝縮されており、田中純の思索を繙く最良の手引書となっている。 *田中純 公式ブログBlog (Before- & Afterimages) 2010年6月14日 「序」と「跋」の一部掲載 http://before-and-afterimages.jp/news2009/2010/06/post-89.html [主要目次] 序 Ⅰ 図像的転回の源流へ 第1章 イメージの系譜学──図像アトラス「ムネモシュネ」の方法 第2章 アートヒストリーとナチュラルヒストリー──種・様式・シークエンス Ⅱ 進化のイメージ 第1章 その馬を見よ──進化の肌理、歴史の知覚 第2章 ヒトの「おもかげ」──ヘッケル『人類の発生』と《泰治君の夢》 第3章 歪んだ創世記──『シュルツ全小説』に寄せて 第4章 天使をめぐって (1) 天使の博物誌──フェヒナー『天使の比較解剖学』 (2) 始祖鳥のメタモルフォーゼ──押井守『天使のたまご』 第5章 『リヴァイアサン』から『崖の上のポニョ』へ──ある象徴の系譜 第6章 楳図かずおの進化論──ムシとコドモ 第7章 幼形成熟の哀しみ──ビョークの人形愛 Ⅲ 情念のかたち 第1章 転生するニンフたち──ヴィヴィアン・ガールズの情念定型 第2章 鬼神たちの回帰──クロソウスキー『古代ローマの女たち』 第3章 表象の墓碑銘──ゴンブリッチ「棒馬考」考 第4章 メランコリーをめぐって (1) 弥勒とメランコリー──タルホからゴヤへ (2) 我ら、土星の子供たち──メランコリーの形式 第5章 イメージのサヴァイヴァル──ゴダール『映画史』 第6章 人形文字/文字という人形──多和田葉子「ゴットハルト鉄道」 第7章 まなざしの色彩──シェーンベルクのドローイング 第8章 書物のヒエログリフ化──『政治の美学』をめぐって Ⅳ 写真という多面体 第1章 細部の野蛮な自律性──矢代幸雄・ヴァールブルク・バタイユ 第2章 歪んだガラス──修整写真の欲望 第3章 写真の解剖学──歴史の証拠物件 第4章 時のアウラ──ロッシとタルコフスキーのポラロイド写真 第5章 石と化したスナップショット──ゲオルゲのイメージ戦略 第6章 見えない抹消線──高梨豊『地名論』 Ⅴ 都市の波打ち際 第1章 塔と貝殻──アルド・ロッシの詩学 第2章 多孔性の科学──生命の楼閣、都市の生命 第3章 波打ち際の知──『都市の詩学』への追記 第4章 都市表象分析とは何か──自註の試み (1) 「非都市の存在論」から「都市表象分析」へ (2) 発掘された幼年時代──「語り」のかたち 註/跋/初出一覧 書誌/図版一覧/人名索引/事項索引 ▼プロフィール 田中 純 (たなか じゅん) 1960年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授・表象文化論(思想史・イメージ分析)。 [主要著書] 『都市表象分析I』(INAX出版、2000) 『ミース・ファン・デル・ローエの戦場』(彰国社、2000) 『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』『死者たちの都市へ』(青土社、2001、2004、サントリー学芸賞受賞) 『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞) 『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008、毎日出版文化賞受賞) ▼関連書籍 田中純『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』 工藤庸子[編]『論集 蓮實重彦』
MORE -
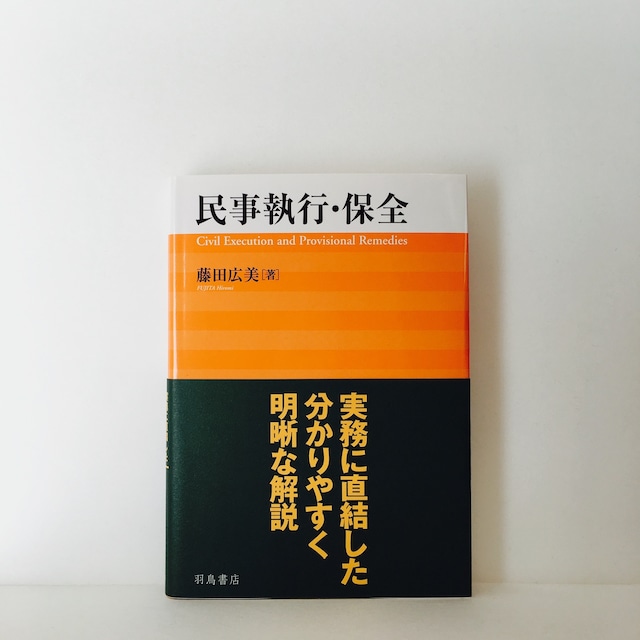
藤田広美『民事執行・保全』
¥4,400
A5判 上製 352頁 本体価格 4,000円+税 ISBN 978-4-904702-10-9 C3032 2010年4月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼概要 実務に直結した分かりやすく明晰な解説 豊富な実務経験(裁判官・弁護士)をもとに、難しいとされる民事執行・保全の実務における解釈・運用の理論的基礎を分かりやすく解説。自ら教鞭をとる法科大学院での実践的な教材を想定し、自習での理解をうながしつつ、民事訴訟実務の全体を学ぶ際に必要な総合力を養う。法科大学院生や司法修習生のほか、若手法曹や実務担当者にも必携の書。 ・豊富な実務経験(裁判官・弁護士)をもとに明晰な解説。 ・執行と保全の基本構造および機能的な特質を詳述。 ・個別の制度・手続についても基本的な視座を提供。 ・民法や民事訴訟法との連関を意識し、総合的理解へ。 ・実践的な教材として、独習者にも最適。 ・「です・ます」体の丁寧な記述で、図版や書式例も豊富。 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。今後、重版にともなう訂正および訂正予定を随時更新していきます。 民事執行・保全 訂正一覧 ★リンク準備中 [主要目次] まえがき 本書のコンセプト PART I 民事執行・保全の基本構造 Chapter 1 民事執行の基本構造 Chapter 2 民事保全の基本構造 PART II 強制執行通則 Chapter 1 執行機関 Chapter 2 執行当事者 Chapter 3 債務名義 Chapter 4 執行文 Chapter 5 強制執行開始要件 Chapter 6 強制執行の対象財産 Chapter 7 強制執行手続の停止・取消し Chapter 8 不当執行・違法執行からの救済 PART III 金銭債権の執行と保全 Chapter 1 対象財産の特定・選択 Chapter 2 不動産に対する強制執行 Chapter 3 動産に対する強制執行 Chapter 4 債権及びその他の財産権に対する強制執行 Chapter 5 金銭債権の執行保全[仮差押え] PART IV 非金銭債権の執行と保全&仮地位仮処分 Chapter 1 物の引渡請求権の執行 Chapter 2 作為・不作為請求権の執行 Chapter 3 意思表示請求権の執行 Chapter 4 非金銭執行の保全[係争物仮処分] Chapter 5 民事保全による暫定的救済[仮地位仮処分] PART V 担保執行 Chapter 1 担保執行の対象 Chapter 2 担保不動産執行 Chapter 3 動産競売 Chapter 4 債権その他の財産権についての担保執行 Chapter 5 形式的競売 PART VI 執行妨害とその対策 申立書等書式例/あとがき/事項索引/判例索引/法令索引 ▼プロフィール 藤田広美(ふじた ひろみ) 1962年生まれ。中央大学法学部卒。裁判官を経て、現在、琉球大学法科大学院教授・弁護士(沖縄弁護士会)。 [主要著書] 『講義 民事訴訟』 『解析 民事訴訟』 (共に東京大学出版会)、『破産・再生』(弘文堂、2012年)。
MORE -

齋藤希史『漢文スタイル』
¥2,860
四六判 上製 306頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-09-3 C1095 2010年4月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平 カバー写真 東野翠れん 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2010年6月13日「漢文の大水脈 日本文学の底に 評・田中貴子(甲南大学教授) 『読売新聞』2010年6月20日「多彩な味わいを伝える」 評・蜂飼耳(詩人) 『東京人』2010年8月号 Close up TOKYO Books「中国、空想旅行の場としての。」評・苅部 直(東京大学教授) 『新潮45』2010年9月号 書物の森「魅力的な漢文エッセイ」評・正津 勉(詩人) 『日本経済新聞』2010年10月17日「活字の海で」にて 「漢文を楽しくやさしく──奥深い世界伝える本、相次ぐ」 『東京大学教養学部報』533号(2010年11月4日)「軽やかに越境する」評・品田悦一(東京大学准教授) 『趣味の水墨画』2010年12月号(ユーキャン) 書物の森「いわゆる教科書的な漢詩に関する本のたぐいではない」 『読売新聞』夕刊2010年11月22日 本よみうり堂「漢文関連本の出版相次ぐ」「時空超えた対話が魅力」 『朝日新聞』2010年12月19日 書評委員お薦め「今年の3点」評者:田中貴子(甲南大学教授・日本文学) 『書道美術新聞』2011年2月1日号(美術新聞社)「話題の本」 『朝日新聞』2013年8月19日「天声人語」 「「緑陰読書」という言葉がある。夏休みの読書をそう称することが多い。中国文学者、斎藤希史さんの『漢文スタイル』によると、それほど古い言葉ではない。日本では、江戸後期の頼山陽の漢詩にその典拠らしい句が見られるという」。 ▼概要 隠者・詩人・旅人たちがめぐる読書の宇宙 不楽復何如!──こんな楽しみまたとない 中国古典文学と清末―明治期の言語・文学の研究者である齋藤希史氏によるエッセイ集。東京大学出版会の『UP』誌連載中の「漢文ノート」(1~12回)や『芸術新潮』2008年8月号・北京特集の「北京八景――記憶された町」など、計22編を収録。著者がひらく漢詩文の世界。国を超え、時代を超えて隠者・詩人・旅人たちがめぐる読書の宇宙へと読者は誘われ、ともにひとときを游ぶ……。いわゆる授業科目としての印象を持たれがちな「漢文」をあえてタイトルに掲げ、漢文脈の可能性と、漢詩文の世界の楽しみ方を伝える一冊。 平成22年度 第19回 やまなし文学賞 (研究・評論部門) 受賞 [目次] Ⅰ 詩想の力 1 隠者の読書、あるいは田園の宇宙 2 自然を楽しむ詩 3 詩人の運命 4 詩讖──詩と予言 5 天上の庭──「玄圃」 II 境域のことば 1 北京八景──記憶された町 密かな愛着 第一景 芥川龍之介『支那游記』 幸福な時間 第二景 袁宏道「秋日同梅子馬方子公飲北安門」 第三景 龔自珍「丙戌秋日独遊法源寺」 胡同の神さま 第四景 金受申『北京の伝説』 第五景 奥野信太郎『随筆北京』 町の音 第六景 老舎『駱駝祥子』 第七景 愛新覚羅溥儀『わが半生』 ふたりの希望 第八景 魯迅+許広平『両地書』 2 訓読の自由 3 来たるべき国語 4 思惟する主体 漢文脈の核心/漢籍の素読/韓愈の文章/教養と主体 5 旅人の自画像 旅行記の時代/漢学者の中国紀行/新聞記者の耳目/志士の渡航記/ 志士から留学生へ/鷗外の誇り/鏡の中の漱石/文化論の誘惑/街角の異邦人 III 漢文ノート 1 下宿の娘 2 詩のレッスン 3 恋する皇帝 4 緑陰読書 5 風立ちぬ 6 黄色い鶴 7 花に嘯く 8 不如帰 9 窈窕たる淑女 10 日下の唱和 11 天朗気清 12 赤壁の月 あとがき/初出一覧/人名索引 ▼ プロフィール 齋藤希史(さいとう まれし) 1963年千葉県生まれ 京都大学大学院文学研究科博士課程中退 京都大学人文科学研究所助手、奈良女子大学文学部助教授 国文学研究資料館文献資料部助教授 東京大学大学院総合文化研究科准教授、教授を経て 現在 同大学大学院人文社会系研究科 教授
MORE -

大村敦志+東大ロースクール大村ゼミ『18歳の自律──東大生が考える高校生の「自律プロジェクト」』
¥2,420
四六判 並製 264頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-08-6 C0037 2010年4月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『教育新聞』(教育新聞社)2010年5月13日「法の基本思想を学ぶ」 『進学レーダー』(みくに出版) 2010年6月号 「大人になるための条件とは?」(評者・河上進) 『学研 進学情報』2010年11月号「小論文ブックポート 52」(評者・福永文子) ▼概要 何歳から大人? ──法律家の卵、東大ロースクール生が5つのハイスクールを取材 民法学の第一線研究者である大村敦志氏が、教え子の東京大学ロースクールゼミ生に「高校生の自律をテーマに本を作ろう」と呼びかけたのが本書の始まり。成人年齢の引き下げの議論がなされるなか、「何歳から大人?」「成年とは何か?」という問いを抱え、ゼミ生たちは計5つの高校を訪ねる。彼らが「自律プロジェクト」としてとらえた高校での生徒会、運動会、文化祭、修学旅行などの特別活動を通して、高校生たちは何を学び、どのように「自律」していくのか、また、学校が担える役割は何か──インタビューを重ね、議論しながら、法律家の卵であるゼミ生たちがその答えを探る一冊。 [目次] 第 1 章 「大人」になることの意味 Ⅰ 法における「自律」 Ⅱ 日常生活で使われる「自律」の多義性 Ⅲ 学校の存在 第 2 章 「自律プロジェクト」としての特別活動 Ⅰ 生徒会 Ⅱ 運動会 Ⅲ 文化祭 Ⅳ 修学旅行 第 3 章 具体例に見る「自律プロジェクト」の実践 Ⅰ 私立麻布高等学校 Ⅱ 私立大妻高等学校 Ⅲ 都立新宿高等学校 Ⅳ 県立千葉高等学校 Ⅴ 県立兵庫高等学校 第 4 章 自律を考える Ⅰ 「自律」とは何か Ⅱ 学校の果たす役割 Ⅲ 未成年の「自律」と成人年齢引き下げ 解説編 この本がめざすもの……大村敦志 Ⅰ 「年少者」の「自律」とは Ⅱ 「ロースクール生」とは Ⅲ 「法教育」とは メイキング編 この本ができるまで……竹内弘枝 Ⅰ ゼミの進み方 Ⅱ ゼミを振り返って ▼プロフィール 東大ロースクール大村ゼミ(2009年度) 竹内 弘枝 (たけうち ひろえ) 1982年 東京大学教育学部卒業 2006年 放送大学大学院修士課程卒業 現 在 (社)商事法務研究会研究員[法務教育担当] 大村 敦志 (おおむら あつし) 1958年 千葉県に生まれる 1982年 東京大学法学部卒業 現 在 東京大学法学部教授
MORE -
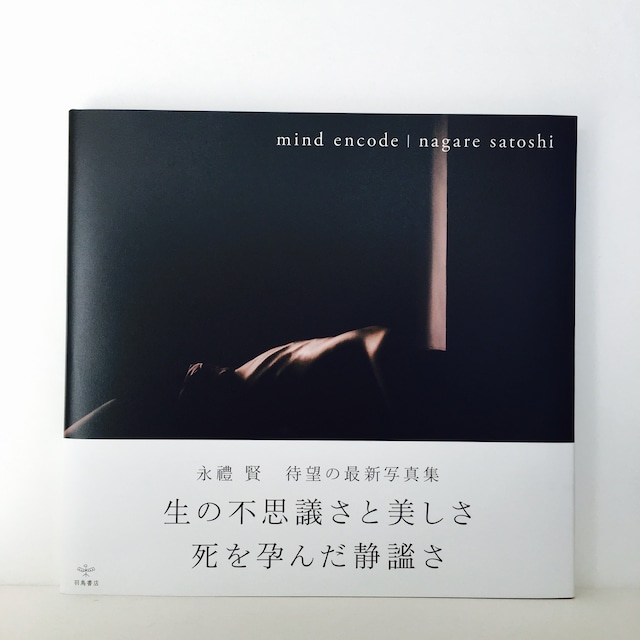
永禮賢『mind encode』
¥4,180
B4判変型 上製 72頁 本体価格 3,800円+税 ISBN 978-4-904702-07-9 C0072 2010年3月刊行 ブックデザイン 大西隆介(direction Q) 印刷 サンエムカラー 製本 新生製本 ▼書評・記事 『産経新聞』2010年4月10日 13面「産経書房」 アサヒカメラ.net 新刊ブックガイド 『季刊プリンツ21』2010年春号 新刊紹介 Visual Books 4 『カメラ日和』2010年7月号 PRESENT! PHOTO GRAPHICA VOL.19 (MdN) 最新写真集評 選者・沖本尚志 『アサヒカメラ』2010年6月号「世界観を写す圧縮された記号」(インタビュー:赤坂英人) 『メンズノンノ』 2010年7月号「旅々カメラ vol.43」 ▼概要 生の不思議さと美しさ 死を孕んだ静謐さ 永禮 賢 待望の最新写真集──好評を博した『birds of silence』に続く第2作。 世界の小さな断片から編み続けられる、新たな世界。 ▼プロフィール 永禮 賢(ながれ さとし) 1975年 青森生まれ 1997年 日本写真芸術専門学校報道写真科卒業 1999年 東京綜合写真専門学校研究科修了 第1回富士フォトサロン新人賞奨励賞 2001年 写真展 ニコンサロンJuna 21 / 東京 2005年 写真集 『birds of silence』 第8回新風舎・平間至写真賞大賞受賞 LAUS award '05 Graphic Communication部門入賞 2006年 COMMANDE M/Aフォトグラファー賞準グランプリ 第32回木村伊兵衛写真賞最終ノミネート 2009年 写真事務所 株式会社Fuse設立 現在、作品制作を中心に雑誌や広告、CDジャケット等の撮影で幅広く活動 *個展 2011年4月29日(金・祝)~5月30日(月) Satellite サテライト(岡山市) 2012年3月9日(金)~3月31日(土) YOKOI FINE ART(港区東麻布)
MORE -
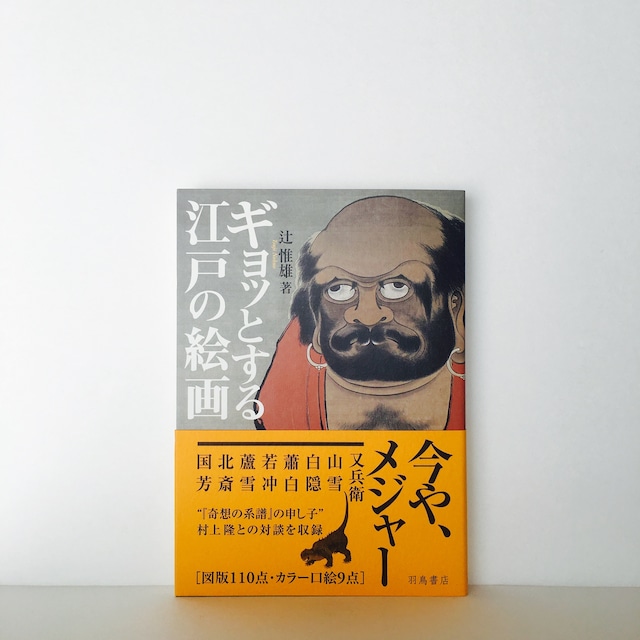
辻惟雄『ギョッとする江戸の絵画』
¥3,080
A5判 並製 240頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-06-2 C0071 2010年1月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『中国新聞』2010年3月14日 『熊本日日新聞』2010年3月14日 『信濃毎日新聞』2010年3月14日 『山梨日日新聞』2010年4月4日「新刊紹介」 『週刊文春』2010年2月18日号「文春図書館」新刊推薦文 『芸術新潮』2010年3月号「invitation」ギョッとしてナットク 奇想の画家列伝 『クロワッサン』2010年6月10日号 著者インタビュー「絵画は理屈ではなく、直感で見るのがいいです。若い男女が異性を見るように」 ▼概要 新・奇想の系譜! 底知れない江戸絵画の魅力を美術史の巨匠が縦横無尽に語る。 村上隆氏との対談収録。 2006年秋に放送されたNHKの番組「知るを楽しむ この人この世界」のテキストとして刊行された冊子『ギョッとする江戸の絵画』をベースに、アーティスト・村上隆氏との対談を加え、新たに書籍化する。6人の画家──又兵衛・山雪・蕭白・若冲・蘆雪・国芳を「再発見」した『奇想の系譜』から40年、白隠・北斎が新たに加わり、「新・奇想の系譜」とも呼べる内容で、平易な語り口で江戸絵画の愉しみを存分に伝える。 [目次] 芸術の効能は「ギョッ」にある 1 血染めの衝撃──岩佐又兵衛 「山中常盤」との出会い/又兵衛の数奇な生い立ち/「勝以画」の特徴とは/浮世又兵衛と又兵衛論争/「上瑠璃」と「堀江物語」/二人の又兵衛 2 身もだえする巨木──狩野山雪 断末魔の痙攣/エリートコースからの脱落/マニエリスムとの符合/山雪の新しさとは何か/文化の過渡期に生きた画家 3 「自己流」の迫力──白隠 達磨の大きさ、線の不思議/「奇想」の空白期間/禅僧としての白隠/技巧を捨てる/白隠が与えた影響 4 奇想天外の仙人たち──曾我蕭白 空前絶後の作品/発見された蕭白/わずかに判明した来歴/画風興隆期の作品/「本物」の証明 5 絵にしか描けない美しさ──伊藤若冲 若冲ブームの到来/八百屋の跡継ぎから画家の道へ/彩色画の若冲、水墨画の若冲/晩年の創作活動/絵画の伝統に革命をもたらした画家 6 猛獣戯画──長沢蘆雪 猫に見立てた虎/応挙という巨匠/江戸時代の鳥羽僧正/視覚遊戯を楽しむ/作品に見える蕭白と白隠 7 天才は爆発する──葛飾北斎 世界が認めたザ・グレート・ウェーヴ/挿絵画家・北斎と蘭書/絵手本にみる北斎のユーモア/七十歳を超えて迎えたピーク/北斎を継ぐもの 8 機知+滑稽・風刺の心──歌川国芳 武蔵の鯨退治/北斎と西洋画の影響/機知+滑稽=エンターテイナー/もう一つの潮流 対談 『奇想の系譜』から「スーパーフラット」へ 辻惟雄×村上隆 本書の成り立ち/辻惟雄と村上隆の出会い/君が研究しなさい/「スーパーフラット宣言」/『奇想の系譜』のDNA/若冲の民衆性/若冲「象と鯨図屏風」/宗教家・白隠=マンガ家・白隠/新発見/断片的とフラッシュ/『芸術新潮』連載/これからの「村上隆」 あとがき 関連画家年表/図版一覧 ▼プロフィール 辻 惟雄(つじ のぶお) 1932年 愛知県生まれ 1961年 東京大学大学院博士課程中退(美術史専攻) 東京国立文化財研究所美術部技官、東北大学文学部教授、東京大学文学部教授、国立国際日本文化研究センター教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長、MIHO MUSEUM館長などを歴任 現在 東京大学名誉教授、多摩美術大学名誉教授 [主要著書] 『奇想の系譜』(美術出版社、1970。新版、ぺりかん社、1988。ちくま学芸文庫、2005) 『奇想の図譜』(平凡社、1989。ちくま学芸文庫、2005) 『日本美術の表情』(角川書店、1986) 『岩波 日本美術の流れ7 日本美術の見方』(岩波書店、1992) 『遊戯する神仏たち』(角川書店、2000) 『日本美術の発見者たち』(共著、東京大学出版会、2003) 『浮世絵ギャラリー3 北斎の奇想』(小学館、2005) 『日本美術の歴史』(東京大学出版会、2005) 『岩佐又兵衛──浮世絵をつくった男の謎』(文春新書、2008) 『奇想の江戸挿絵』(集英社新書、2008)
MORE -
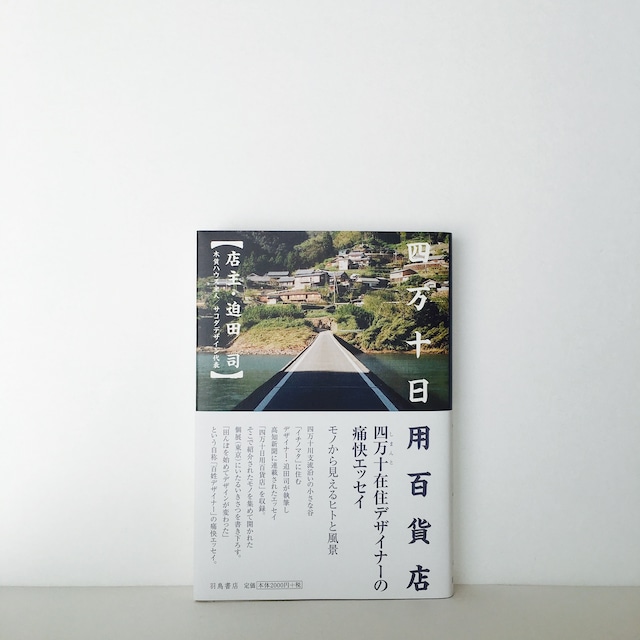
迫田司『四万十日用百貨店』
¥2,200
四六判 並製 232頁 本体価格 2,000円+税 ISBN 978-4-904702-04-8 C0036 2009年10月刊行 ブックデザイン 原 研哉+中村晋平 カバー写真: 吉原愛子 印刷 サンエムカラー 製本 清水製本所 ▼書評・記事 ▼概要 四万十在住デザイナーの痛快エッセイ モノから見えるヒトと風景 高知県・四万十川支流沿いの小さな谷「イチノマタ」に住むデザイナーの著者が、モノから見えるヒトと風景をつづったエッセイ「四万十日用百貨店」(2007年10~12月、高知新聞に56回にわたって連載)を全文掲載。約2年後の2009年夏、記事に紹介されたモノを集めた個展が東京で開催されることになったいきさつを書き下ろし、個展風景をカラー写真で収録する。田んぼを耕しながらデザインを生み出す著者ならではの視点をとおして、山あいの小さな谷からニホンを見晴らす。 [目次] プロローグ ぼくの谷 一ノ又 谷のしくみ/谷のしくみ図/ぼくの谷マップ 四万十日用百貨店(展) ★個展写真 谷から見える人と風景 [商品番号1 軽四トラック]運搬だけではない 市場になる のみ屋になる ステージになる [商品番号2 肥料袋]イガグリも歯が立たない強靭さ「四万十お裾分け袋」の大定番 [商品番号3 トタン波板]収穫を告げる「栗ドラム」米を守るチープな万里の長城 [商品番号4 たにご]なんでも洗える流れる洗い場 水と人の「暮らしの源流点」 [商品番号5 薪]自然の変換技術を体得すれば本物の「御馳走」にありつける [商品番号6 酒]唇湿ると滑る人間関係 酔わねば祝えない幡多方式 [商品番号7 沈下橋]じいさんの皺のような重厚感 最後の川の「最後の橋」を楽しむ! [商品番号8 くわ]背中で叩けばカエル探知 鰹のマイくわ・マイ藁焼き [商品番号9 藁]テクノロジー超えた万能結束力 人と神と自然を固く、緩く、結ぶ [商品番号10 石窯]素材も燃料も自ら調達 「ただ」という窯の中の「豊かさ」 [商品番号11 酵母]菌も証明 四万十の天然の力 職人御墨付きの「四万十酵母」 [商品番号12 鹿の角]生前の悪事を帳消しに 名刀は飾らない帽子掛け [商品番号13 害獣オリ]野生猪のリアルな動物園 命のやりとりを直視する [商品番号14 ふみきり]風が通る自由な「ふみきり」で 止まって何を見るべきか考える [商品番号15 漬物]手に漬けこまれた技術 風景全部をおいしく変換 [商品番号16 蜂防護服]キンチョールの二丁拳銃 獅子の城を制圧する戦闘服 [商品番号17 麦わら帽子]田畑という荒野を行く 百姓カウボーイのシンボル [商品番号18 うなぎばさみ]天然のヌルヌルは苦かった 安来節を封印する鬼の歯 [商品番号19 天然コンロ]男同士の意地が極めた 天然鮎専用の炭火コンロ [[商品番号20 黒パイプ]身体で覚え込んだ物理学 生きた水を扱う本能の力 [商品番号21 はがま]「自分の風景」とは何なのか その答えを証明してくれる釜 [商品番号22 おくどさん]水と土を太陽と人々に感謝 米に成仏してもらう最終装置 [商品番号23 氏神様]「森」という氏神様のお宅 身の上をじっくり相談 [商品番号24 まじない帖]自然のなりゆきに逆らうな 忘れた心を取り戻す帳面 [商品番号25 うたい]日本古来のミュージカルに学べ 節回しのよい「人生応援歌」 [商品番号26 炭]自分で生み出し、取り扱える 人に任せない「エネルギー」 [商品番号27 ホーロー風呂]環境へ「本当」にやさしい 五右衛門風呂に下心はない [商品番号28 薪ストーブ]光熱費を百分の一にカット 火の車を救う真っ赤な達磨 [商品番号29 煙突ブラシ]掃除しながら診断する 煙突医院の聴診器 [商品番号30 干し台]技術と知恵を受け継ぐ姿 「おてんとうさま」が見ているよ [商品番号31 番犬]吠え方で来客情報報告 さえる勘で家族を守る [商品番号32 おどし]鳥と人との知恵比べ 怖がらせ方は自由だ [商品番号33 巣箱]すみかなく「番人」減少 環境に能動的でありたい [商品番号34 ねずみとり]かわいさアピールで保釈!? ねずみに優しい生け捕り器 [商品番号35 ボーメ計]海を食べれば自分がわかる 人と自然を濃縮するはかり [商品番号36 しゃくり竿]水中で天然鮎と格闘技 しゃくり漁はスポーツだ! [商品番号37 石鹸]海と山つなぐ「しまんとエコ」 合言葉は「IKIIKI」 [商品番号38 防災無線]朝昼夕、十時と三時はお茶、四万十の暮らしのリズム [商品番号39 スレート瓦]「お金を使わない」仕事 絆深める「暮らしの修繕」 [商品番号40 枡]風景から生き方が見える 米を入れる米らしい入れ物 [商品番号41 田靴]アース耕す田んぼのブーツ アトム製はブレーク寸前!? [商品番号42 かなこ]牛でしか機能しない道具 田んぼのサーカス団を見たい [商品番号43 トロフィー] 夢を獲得した記憶を刻む 挑む力を手に入れた証し [商品番号44 子ども]「子どものシゴト」復権! メイド・イン・ちっチャイナ [商品番号45 もち]四万十人は「もち投げ」好き ネットでは検索できない催事 [商品番号46 ガードレール]静かに立つ尖った石たち 世の中に強い警告発して [商品番号47 チェーンソー]大怪我と背中合わせの作業 時代に振り回される山の価値 [商品番号48 腰なた]一家に一本「土州勝秀」山の経験をあぶり出す刃 [商品番号49 くすり]義と礼のやりとりを処方 四万十の腹くだりを治す [商品番号50 草]道草パワーの体験処方 「草」で「楽」になるのが「薬」 [商品番号51 葬具]別れるための「しきたり」 死んだときのために生きよ [商品番号52 竹]ありえない食べられる建材 仰天変貌で宇宙とつなぐ [商品番号53 空家]「空(から)」ではない学びの場 足跡からの生きるヒント [商品番号54 安全柵]土建屋さんの未来を示す 安全第一を意思表示する畑 [商品番号55 斧]薪を読みながら汗をかく 道具に身体が制御される [商品番号56 ポットン便所]「木賃ハウス哲学」の原点 ポットン! 落としてよい年を [番外編 川のこと] [番外編 木賃ハウスのこと] [番外編 田んぼのこと] [番外編 ユタカサのこと] [番外編 デザインのこと] 四万十日用百貨店(展) 麻布十番の「レーベルギャラリー」にて 誰も知らない四万十のデザイナーがなぜ東京で個展をするハメになったのか? 迫田司のデザイン/エピローグ ▼プロフィール 迫田 司(さこだ つかさ) 1966年熊本県生まれ。93年、高知県幡多郡西土佐村(現・四万十市)に移住し、2年後「サコダデザイン」を設立。休耕田だった棚田で米をつくりながらデザインに取り組む、自称「百姓デザイナー」。全国から仲間が集う現代の木賃宿「木賃(きちん)ハウス」を主宰。米袋では初となるグッドデザイン賞を受賞(2004年)。地元を愛し地元で活動する各地のデザイナーたちを結ぶネットワーク「地(ジ)デジ」(地・デザイン・ジャパン)を2011年11月に発足。2016年、ビートルズ来日50周年記念アップル・レコード公認オフィシャルロゴマーク作成。 ★2009年夏、本書のもととなる新聞記事をベースにした個展「四万十日用百貨店(展)」が、東京・港区三田で1か月に渡り開催された。 レーベルギャラリー *パネル展示 ジュンク堂池袋本店 2Fでパネルの展示を行ないました(2009年10月末まで)
MORE -

鴻池朋子『インタートラベラー──死者と遊ぶ人』
¥3,080
【在庫僅少】 美本はもうありませんが、できるだけ手入れしたものをお送りしています。 カバー・帯は替えがないため擦れ等が多少なりとも入っております。ご了承ください。 B5判横 上製 120頁 カラー 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-03-1 C1071 2009年9月刊行 ブックデザイン 中垣信夫・中垣呉(中垣デザイン事務所) 印刷 サンエムカラー 製本 新日本製本 ▼概要 読者はインタートラベラーという旅人に。 そして,地球の中心-6371kmへの旅が始まる。 ◎インタートラベラーInter-Traveller; 異なる世界を相互に往還し、境界をまたぐ人を意味する作家による造語。 スケールの大きな表現と技術の高さで、現在もっとも注目されるアーティスト・鴻池朋子の本格的作品集。本年7月より東京オペラシティアートギャラリーにて開催する「鴻池朋子展インタートラベラー」(同年10 月、霧島アートの森[鹿児島]にて共通テーマの個展を開催)にあわせて刊行される本書は、本展に出品される最新作やインスタレーションを中心にこれまでの代表作を網羅的に紹介することで、鴻池朋子の“ 現在” をあますところなく伝える。地中の世界を巡る生と死と再生の神話を、鴻池が言う「遊びとは魂を呼び還す技なり」という言葉のままに、読者は「地球の中心」へ旅をし遊ぶ「インタートラベラー」すなわち「死者と遊ぶ人」として、追体験する。 [目次] 生命讃歌の旅人……………高階秀爾 地殻 不連続面 マントル 外核 死者と遊ぶ人……………鴻池朋子 内核 これより地球の中心 アウトキャスト 地上へ 物語の解体から神話の起源へ……………飯田志保子 千のナイフと一匹の狼……………中沢新一 展覧会記録/作家略歴/作品リスト ▼プロフィール 鴻池朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。1985年に東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画デザインの仕事に長年携わり、1997年より作品制作を開始。2005年より4章から成る巨大絵画の物語シリーズを制作し、東京都現代美術館、森美術館、ミヅマアートギャラリー、大原美術館にて発表。更にはアニメーション、彫刻、キュレーションなどを行い常に話題を集める。 *「鴻池朋子展 インタートラベラー 神話と遊ぶ人」 東京オペラシティアートギャラリー 2009年7月18日(土)~9月27日(日) 鹿児島 霧島アートの森 2009年10月9日(金)~ 12月6日(日)
MORE -

長谷部恭男『憲法の境界』
¥3,520
A5判 上製 176頁 本体価格 3,200円+税 ISBN 978-4-904702-02-4 C3032 2009年7月刊行 装幀 鈴木堯+岩橋香月(タウハウス) 印刷 研究社印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2009年10月18日「道徳の思考に訴える“窓口”として」評者・苅部直(日本政治思想史) 『ジュリスト』2011/2/15(No.1416) 評者・中林暁生(東北大学准教授) ▼概要 未完のプロジェクト立憲主義の観点から考察 『比較不能な価値の迷路』『憲法の理性』(共に東京大学出版会)に続く長谷部憲法論文集第3弾。憲法のかかわる重要なテーマ──国境、国籍、主権、違憲審査等──について、憲法学の枠を踏み越えて、深く軽やかに考察する。 2007年と2008年の論考を中心に10本収録。憲法解釈をめぐる様々な議論が展開されるなかで、たえず議論をリードしている著者の最新論文集。 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。今後、重版にともなう訂正および訂正予定を随時更新していきます。 憲法の境界 訂正一覧 ★リンク準備中 [主要目次] はしがき 第Ⅰ部 時間 第1章 われら日本国民は,国会における代表者を通じて行動し,この憲法を確定する. 第Ⅱ部 空間 第2章 国境はなぜ,そして,いかに引かれるべきか? 第3章 人道的介入は道徳的義務か?──『憲法と平和を問いなおす』を問いなおす 第Ⅲ部 人間 第4章 国籍法違憲判決の思考様式 第5章 学問の自由と責務──レオ・シュトラウスの「書く技法」に関する覚書 第6章 法律学から見たリスク 第7章 私が決める 第Ⅳ部 裁判 第8章 民事訴訟手続の基本原則と憲法(長谷部由起子) 第9章 憲法から見た民事訴訟法 第10章 取材源秘匿と公正な裁判──憲法の視点から ▼プロフィール 長谷部恭男(はせべ やすお) 1956年 広島に生まれる 1979年 東京大学法学部卒業 東京大学教授をへて 現 在 早稲田大学法学学術院教授 [主要著書] 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991) 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』(弘文堂、1992) 『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999) 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』(東京大学出版会、2000) 『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004) 『憲法とは何か』(岩波新書、2006) 『Interactive 憲法』(有斐閣、2006) 『憲法の理性』(東京大学出版会、2006) 『憲法 第4版』(新世社、2008) ▼関連書籍 『憲法入門』(羽鳥書店、2010) 『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)
MORE -

高山宏『かたち三昧』
¥3,080
A5判 並製 204頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-01-7 C0070 2009年7月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 読売新聞 2009年10月11日 「人文学の新たなデザイン」 [評者]田中純(思想史家) 出版ニュース 2009年11月中旬号 ブックガイド *紹介ブログ 整腸亭日乗 ~ 高山宏と「羽鳥書店」 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる ~ グルーヴィな教養「かたち三昧」 中野香織オフィシャルブログ ~ 器用仕事 ▼概要 高山フィギュラリズムの極北 『UP』の好評連載「かたち三昧」全63回をまとめる。 さらに、フィギュラル・クリティシズムの実践編として漱石論4編も収録。 〈かたち〉を読み解く高山フィギュラリズムの秘術を公開する驚異の書。 [目次] 口上 フィギュラリズム 1 フィギュラティヴ・サークル 2 フィグーラ・セルペンティナータ 3 エキセントリック・ガーデン 4 うねくった漱石 5 彼岸へと過ぎる蛇 6 十九歳、何てパンクなマニエラ 7 薔薇の庭の音の蛇 8 詩神の音連れ 9 百学連環(1) 10 百学連環(2) グラン・メートル種村季弘(2004・8・29没)に 11 鯨の百科、鯨〈と〉百科 12 マーヤーは人のかたち 13 「く寝る」言葉の川走 14 サイモン・シャーマの歴史形態学 15 エーコ・インポッシビリア 16 ジュゼッペのヒト猫 17 我レ亦あるかであニ在リ 18 アナモーフィックな死 19 よく見ればオムニス 20 驚く、ヒューマニティーズ 21 葡萄のパラダイム 22 葡萄ルネサンス 23 シーレーノスの箱 24 これビン笑すまじきこと 25 ヒトはこれノミ 26 懼龍犇は寝ている──キャロル・フィギュラル1 27 切って分かった蛇馬魚鬼──キャロル・フィギュラル2 28 「体」現憧憬──キャロル・フィギュラル3 29 「クンストゲシヒテ」の星たち 30 哲学する「映像の力」 31 暗号はゼロのかたち(1) 32 「言葉と物」のペダゴジックス 33 言葉の永久機関 34 ちゃんと面白い英文学 35 はじめっから詐欺 36 暗号はゼロのかたち(2) 37 エヴリ・バディに謹賀新年 38 フォシヨンの家の馬鹿息子 39 ヤラセ引くヤセで裸 40 顔に目をつけた 41 未知の西鶴、道の才覚 42 きみの顔は正しい 43 お勉強やめてギルマン読もう 44 ブルーサティン、顔のマニエリスト 45 顔のマニエリスム(1) 46 顔のマニエリスム(2) 47 アポカリプスな顔 48 宙にあそぶ視線(1) 亡き若桑みどり先生に 49 宙にあそぶ視線(2)──His private eye 50 宙にあそぶ視線(3)──女たちは見る 51 絵面の見得 服部幸雄先生追善 52 語る目、語る指 53 アメリカン・マニエリスムの手 54 「知」塗られた手首の話(1) 55 「知」塗られた手首の話(2) 56 「知」塗られた手首の話(3) 57 「知」塗られた手首の話(4) 58 かたち好き垂涎の「大図典」 59 影のない翻訳 60 雲をつかむような話 61 こんなミーイズムなら大歓迎だ 62 矩形なのに、まどか 63 かたちばかりの修了試験 吾輩は死ぬ──『吾輩は猫である』 座頭を殺す──『夢十夜』第三夜 夢の幾何学──『夢十夜』第四夜 「擬(まが)いの西洋舘」のト(ロ)ポロジー──『明暗』冒頭のみ 文献索引/人名索引 ▼プロフィール 高山 宏(たかやま ひろし) 1947年 岩手県に生まれる 1974年 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了 現 在 大妻女子大学比較文化学部教授 [主要著書] 『アリス狩り』(青土社、1981、新版2008) 『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所、1992) 『ブック・カーニヴァル』(自由国民社、1995) 『カステロフィリア──記憶・建築・ピラネージ』(叢書メラヴィリア1、作品社、1996) 『エクスタシー──高山宏椀飯振舞I』(松柏社、2002) 『近代文化史入門──超英文学講義』(講談社学術文庫、2007)[『奇想天外・英文学講義』(講談社選書メチエ、2000)を改題] 『超人高山宏のつくりかた』(NTT出版、2007) [主要訳書] B・M・スタフォード『グッド・ルッキング──イメージング新世紀へ』(産業図書、2004) S・シャーマ『風景と記憶』(栂正行との共訳,河出書房新社、2005) B・M・スタフォード『ヴィジュアル・アナロジー──つなぐ技術としての人間意識』(産業図書、2006) B・M・スタフォード『ボディ・クリティシズム──啓蒙時代のアートと医学における見えざるもののイメージ化』 (国書刊行会、2006) B・M・スタフォード『実体への旅』(産業図書、2008)
MORE